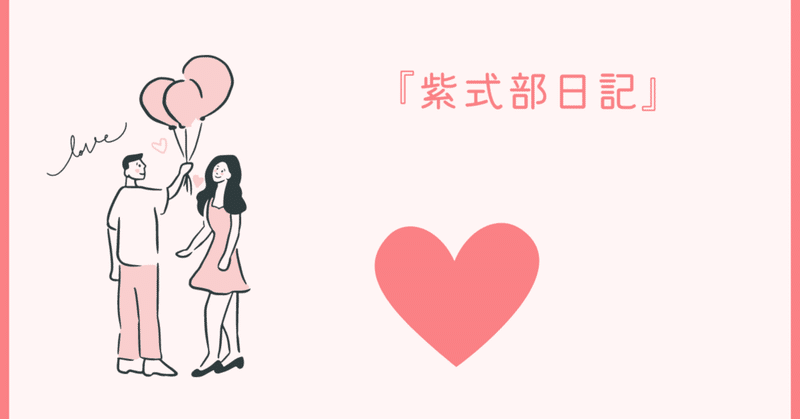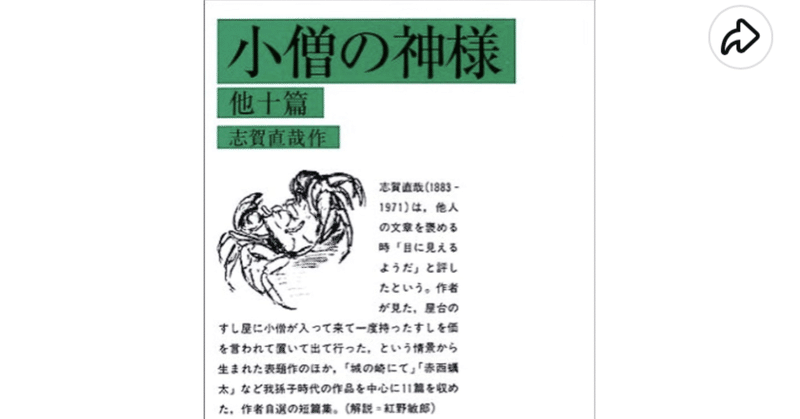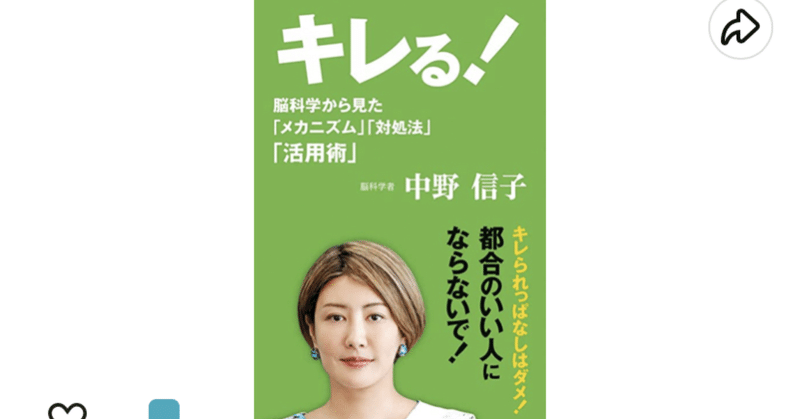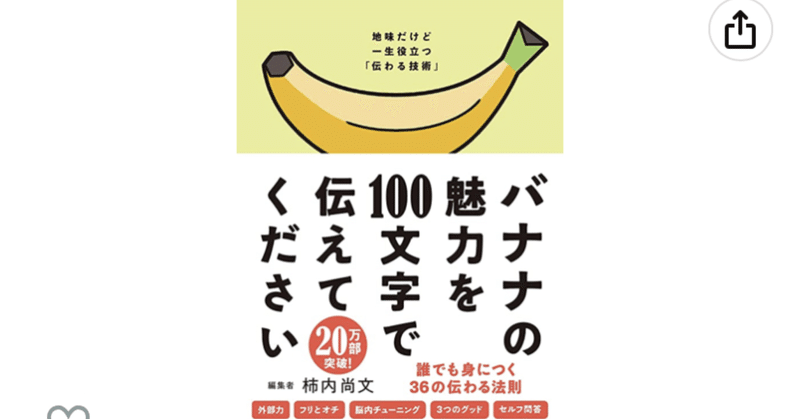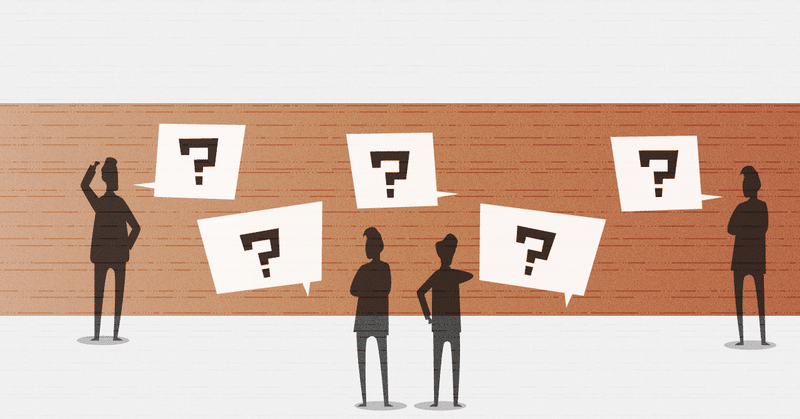#読書記録
【読書ノート】『新編 人生あはれなり 紫式部日記』
『新編 人生あはれなり 紫式部日記』
小迎裕美子 紫式部
紫式部日記をわかりやすく解説した本。華やかな日常を過ごしていと思いきや日々、将来の不安や人目を気にするストレス、目立ちたくないという願望など、現代の女性にも共感できる人間関係や仕事、嫉妬などが描かれている。
『源氏物語』の登場人物も取り上げていて、人物像を知る上で役にたつ。
平安中期の三大才女(紫式部・清少納言・和泉式部)の微妙な関係
医者と患者のコミュニケーション論
医者と患者のコミュニケーション論
里見清一著
著者は本名・國頭英夫。1961年鳥取県生まれ。1986年東京大学医学部卒業。国立がんセンター中央病院内科などを経て日本赤十字社医療センター化学療法科部長。
がんの「告知」は当たり前か?
現在は、患者本人へのがん告知は「当然のこと」となっているが、この慣習はそう古いものではないのです。医療先進国のアメリカでも、1961年の時点では、告知を「しない」が