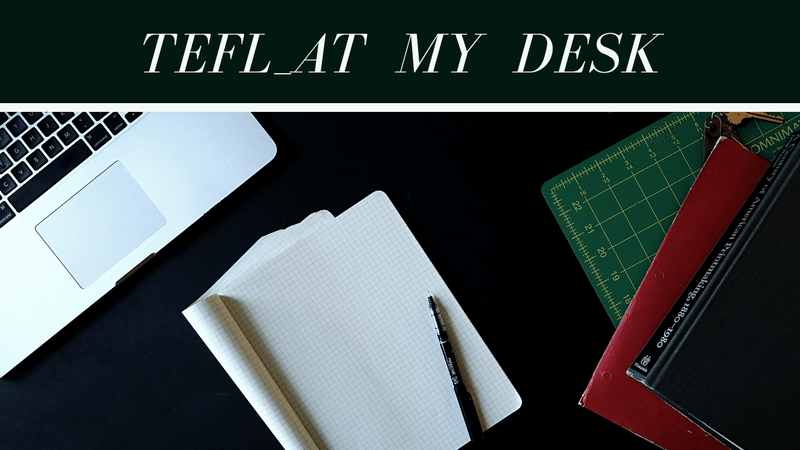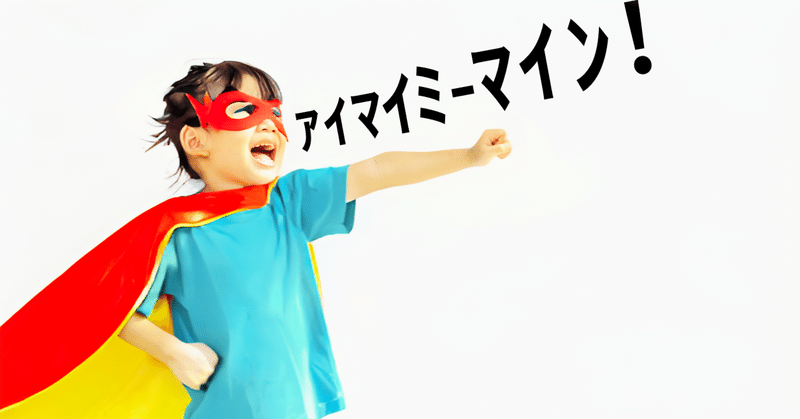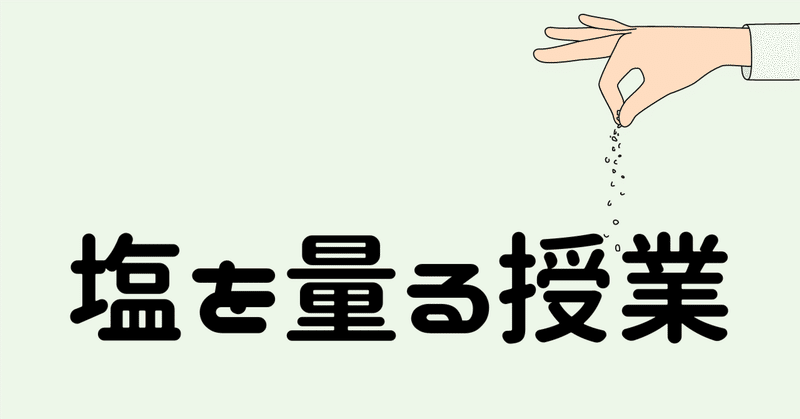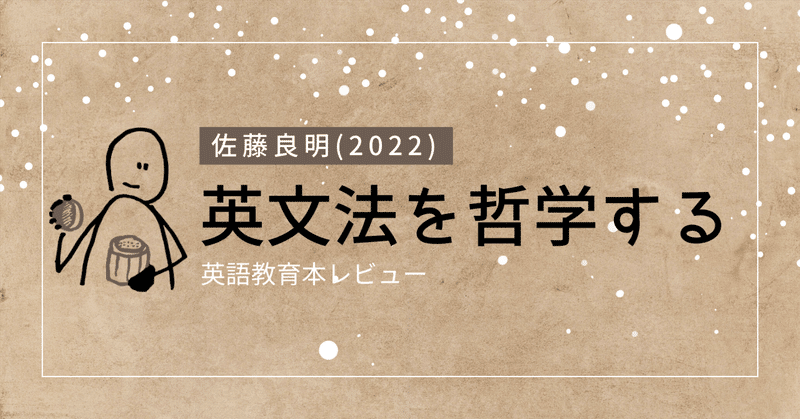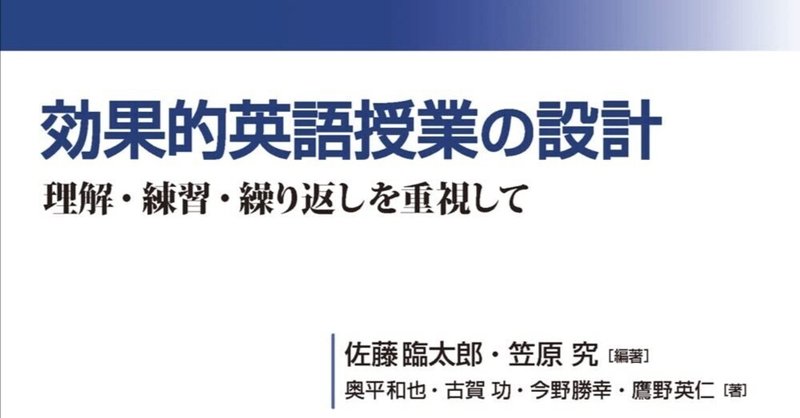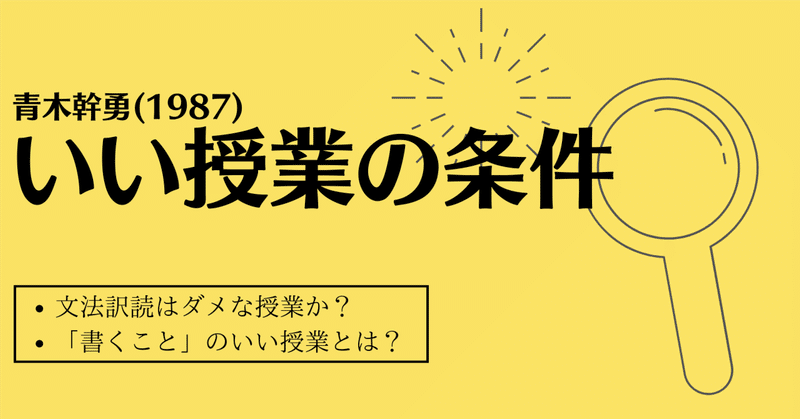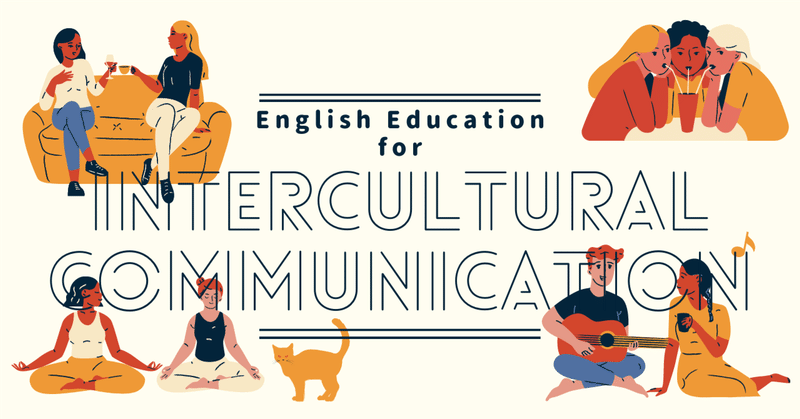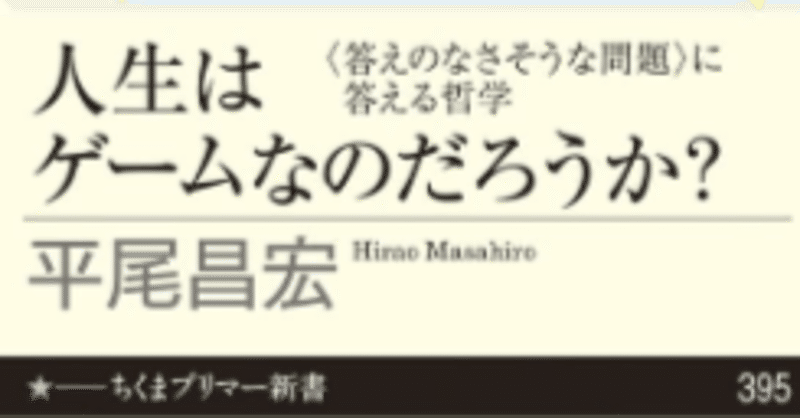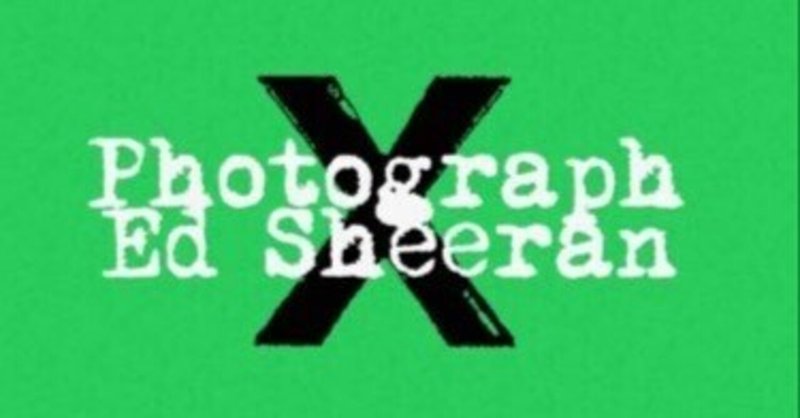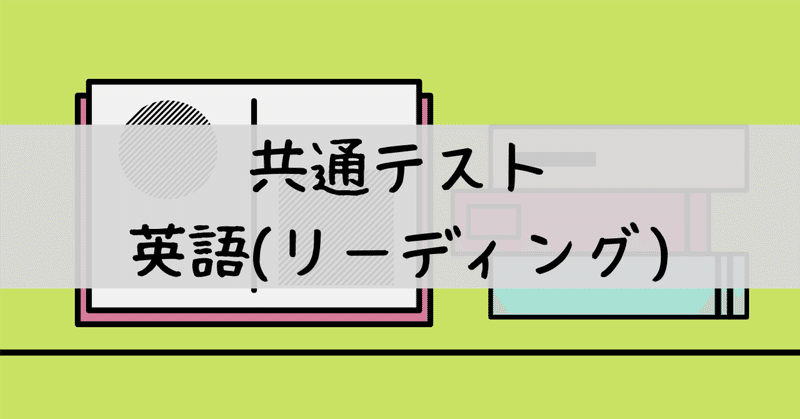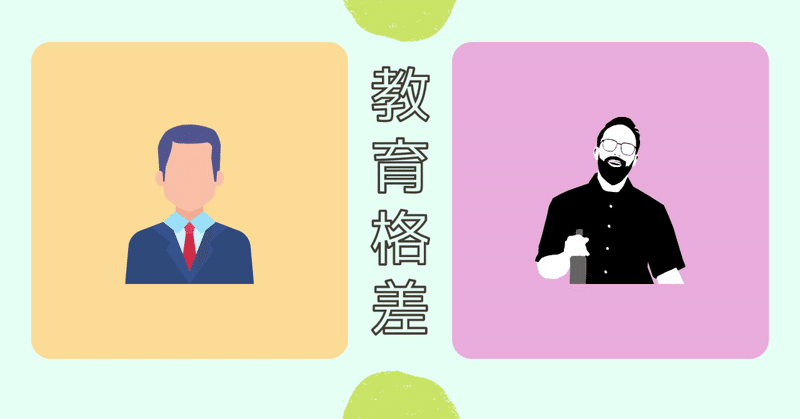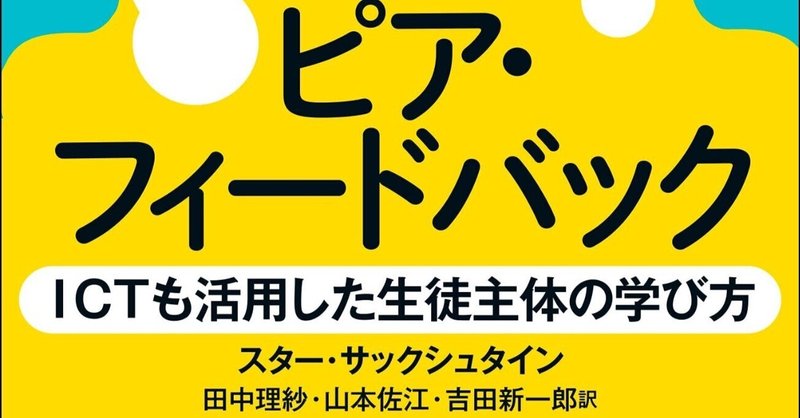記事一覧
『英文法を哲学する』
佐藤良明(2022)『英文法を哲学する』を拝読した。
今年読んだ英語関連本の中でもすこぶる面白かったので,もうすぐ出版から1年ほど経つようなタイミングではあるが簡単にまとめておきたい。
出来るだけ多くの英語教員に読んでもらいたい本なので,ギリギリ冬休みに間に合うように。
本書の基本スタンス-英語に乗る本書全体を通して佐藤は英語を日本語の枠組みから捉えることに否定的で,英語という言語に出会い,英
学生からの質問「授業中に内職してる学生ってどうしますか?」
教職の学生からふと雑談中に聞かれて、なんとなく自分の納得いく回答ができなかったなぁ、とモヤモヤしていたので改めてこの記事を書くことで自分の考えを整理してみようと思う。基本的に考えた順番に書き出していくので読みづらさはご勘弁いただきたい。
まず一つ、教職の学生たちが将来見ることになるであろう中高生と、私が今見ている大学生とでは、ちょっと考え方も変わってくるのかなというのは大前提にある気がする。
3
「異文化コミュニケーションの視点から考える英語教育」—鳥飼玖美子氏 特別講演
2021年度ELEC英語教育賞授与式に続いて行われた鳥飼玖美子氏の特別講演「異文化コミュニケーションの視点から考える英語教育」を視聴した。
全体を通して非常に聞きやすいし理解しやすい。これは鳥飼氏の著書等をそれなりにフォローしてきた上にかなり肯定的に捉えていることと無関係ではないだろうけど。
暗雲立ち込める「グローバリズム」「グローバル化」「グローバリズム」という言葉はもう聞き飽きるほど何年も
【授業で洋楽】 Photograph / Ed Sheeran
オミクロン株の感染急拡大に伴って,勤務校は少し前からオンライン授業に切り替わった。
私の英語の授業の一番の「売り」は,長い英文を見ても目を背けなくなる(と信じたい)読解の授業だと思っている。
それがオンラインでは,まぁ正直厳しい。オンライン授業で一人で家で黙って教科書3~4ページ分の英文に立ち向かえるのであれば,もうその生徒には私の授業は必要ないとも言える。
というわけで,思い切って授業を根本
共通テスト(英語・リーディング)について思うこと
テストの概要今年の共通テストは以下の6つの大問で構成された。
第1問 … 広告
第2問 … A. ビラ? B. 広告
第3問 … A. ブログ B. 雑誌
第4問 … ブログ
第5問 … 論説文とそれをまとめたノート
第6問 … A. 論説文とノート B. 記事とそこから作ったプレゼンの草稿
昨年と同じく発音や文法・語法などの知識を直接的に問う問題はなく,様々な媒体によって提示された文字情報を読