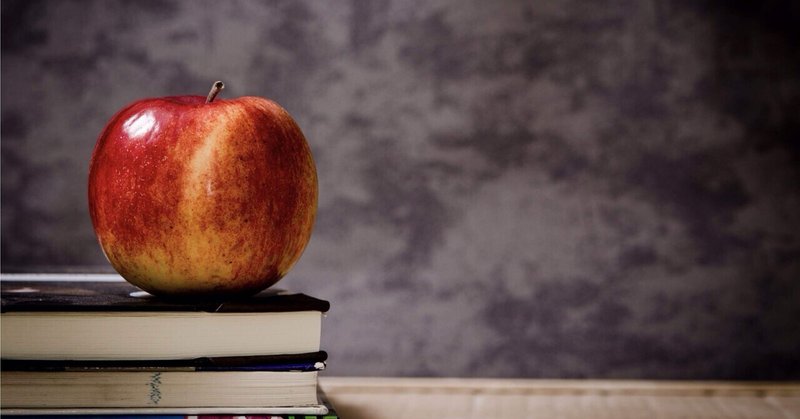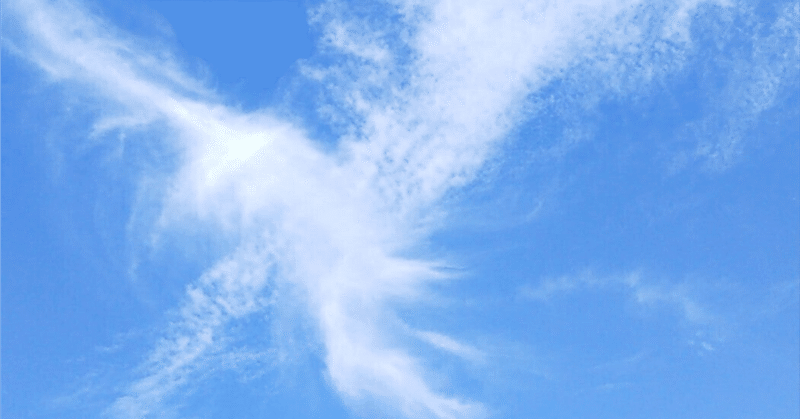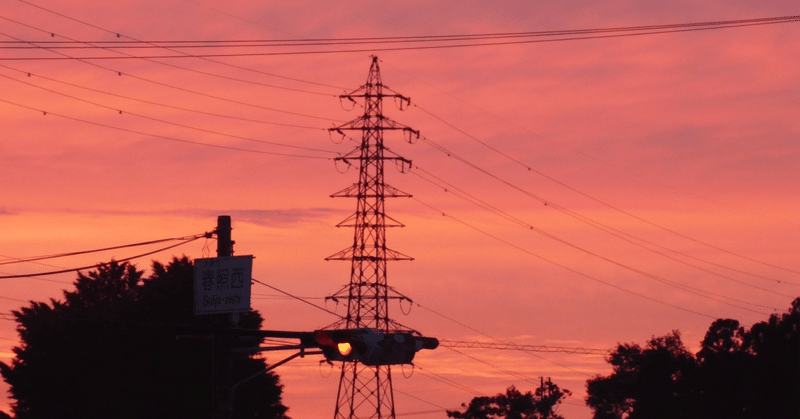- 運営しているクリエイター
#マネジメント
持続可能な組織マネジメントの実践と反省
第9回クリニカル・クラークシップに基づく作業療法臨床教育研究会研究大会が開催され、特別講演として「持続可能な組織マネジメントを目指したわれわれの実践と反省」についてお話をさせていただきました。
クリニカル・クラークシップに基づく作業療法臨床教育研究会は、以下の趣旨で設立された研究会です。
社会の要請に見合うOT有資格者の育成の課題は養成校のみではなく、われわれ臨床教育を行う側の課題でもあると感
なぜ、管理監督者と医療従事者は対立するのか
経営者および管理監督者と現場の医療従事者の対立の要因
わが国の医療業界は、少子高齢人口減少社会の影響により、病院経営はとても厳しくなると考えられています。組織が生き残るためには、外部環境に適応するだけでは不十分であり、経営者や管理監督者の視座は常に外部環境の進化の先にあることが重要と考えられています。つまり、経営者や管理監督者は、ビジョナリーであることが求められていると考えることができます。
スタッフに機会を与えるとき、マネジャーに必要な覚悟とは何か?
私は現在、全国病院経営管理学会リハ専門委員会の正幹事を務めています。リハ専門委員会では、リハ専門職で学会の個人会員の方を対象として今年度からオンラインサロンを始めました。オンラインサロンは、年3〜4回の頻度で、1回あたり1時間程度、さまざまな意見交換を行なっています。
昨夜のオンラインサロンでは、スタッフへの機会の与え方についてが話題となりました。育成を目的としてスタッフに機会を与えても、結局そ
3分でつかむ『心理的安全性』
1965年に登場した『心理的安全性』という言葉。最近では、あらゆる場面で見聞きするようになりました。ただし、時折、誤用されていたり誤解されているなと感じることがあります。
本noteでは、『心理的安全性』の要諦を端的に整理します。
もともとは、組織に使われていた『心理的安全性』。ハーバード大学教授のエドモンドソン氏が、「対人関係のリスクをとっても大丈夫という、チームメンバーに共有される信念のこ
マネジメントに係る先人のお言葉
自然科学と社会科学の両方に触れた私の感覚では、新しい知見は、自然科学においては「上書き保存」、社会科学においては「別名保存」される印象があります。つまり、自然科学では常に新しい知見が求められる一方、社会科学ではどちらも求められているような感覚があるのです。
今回は社会科学領域の一つであるマネジメントに焦点をあて、別名保存され続ける先人の言葉を整理します。多くの方々が活力を得られる記事になれば幸い
マネジメント教育をせずにプレイングマネジャーを課すのは大罪という仮説
医療従事者の監督職の多くは、プレイングマネジャーではないでしょうか。
2019年のリクルートワークス研究所の調査では、87.3%のマネジャーがプレイングマネジャーであったようです。
本noteでは、病院に勤務するマネジャーがなぜ忙しいのか。そして、その忙しさの緩和に必要な能力は何か。そして、プレイヤーとマネジャーの適切な割合はどのくらいかを短く整理します。
病院に勤務するマネジャーはなぜ忙し
なぜ、若いうちの苦労を避ける傾向に我々は嘆くのか?
最近、Twitterを流し読みしていると、若いうちに進んで苦労しようとする人がいないといった嘆きが目につくようになりました。実際のところ、どうなんでしょうか。
下の図は、日本生産性本部[1]による、働くことの意識調査結果のうち、「若いうちは進んで苦労すべきか」と言う問いに対する回答のトレンドです。平成23年度から急激に「苦労すべきだ」と回答した割合が減り、「好んで苦労すべきではない」と回答した
目でみるコーチングマネジメント
コーチングを取り上げたきっかけ 先日、他の保険医療機関の先輩から「コーチングの講師を紹介してほしい」と連絡を受けました。コーチングは組織のパフォーマンスを高める上でも注目されていますが、われわれリハ専門職にとっては、対象者の自律を支援する上で有効な手段であると私は考えています。つまり、対象者に対する「○○指導」という高圧的なものは論外ですが、「○○教育」よりもむしろ「コーチング」こそが対象者の自律
もっとみる仕事のできる人の時間の使い方
近年では、経営資源には人・モノ・カネ・情報・時間・知的財産の6つがあると言われています。この中で誰もが公平に有しているのは”時間”です。しかし、時間は有限で絶対に蓄えることができません。
一方、私の知る限り、仕事をしているほとんどの人は「時間がない」と感じています。しかし、「時間がない」と感じている同じ条件の中で、確実に成果をあげる人とそうでない人がいるのはなぜでしょうか?
それは、いかに時