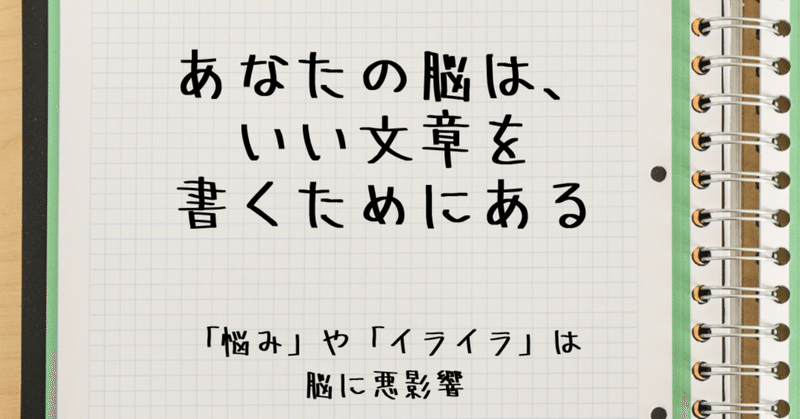
【執筆を無駄にしないために】悩みやストレスは、文章を思い浮かばせなくする
この度は、数ある中からご覧頂き、誠にありがとうございます。

【まえがき】
今回の記事内容はコチラ
1️⃣《こんなお悩みを持つ方にオススメ》
楽しく執筆したい
いい記事を書きたい
脳の仕組みを理解したい
2️⃣《学び》
悩みと執筆の関係が学べます
3️⃣《記事を読んだ後、どうなって欲しいか?》
悩みを吐き出し、執筆に集中して欲しい
以上を踏まえてご覧頂ければ幸いです。

【悩み】
悩みやストレスがあるときの
執筆
生きていれば、誰にでも悩みやストレスはあります。
その状態での執筆には、様々な影響が起こります。
今回は、『悩みやストレスと執筆の関係』についてお話致します。

【結論】伝えたいこと
✅【執筆前に悩みやストレスを吐き出す!
悩みは、気づかぬうちに脳のエネルギーを使ってしまう】

【理由その①】
執筆には、膨大なエネルギーを使う
まず、執筆にはとてつもない脳のエネルギーを使います。
頭の中の言葉を文字にしているので、当然といいえば当然です。
これを象徴するエピソードがあります。
私の日課はじつにわかりやすい。
午前中は執筆。午後は昼寝と手紙。 夜は読書と家族団欒、テレビでレッドソックスの試合、どうしても後まわしにできない改訂作業。
というわけで、原則として、執筆は午前中ということになる。
たとえば、これはあくまで僕の場合はということですが、書き下ろしの長編小説を書くには、一年以上(二年、あるいは時によっては三年) 書斎にこもり、机に向かって一人でこつこつと原稿を書き続けることになります。
朝早く起きて、毎日五時間か六時間、意識を集中して執筆します。それだけ必死になってものを考えると、脳が一種の加熱状態になり、(文字通り頭皮が熱くなることもあります)、 しばらくは頭がぼんやりしています。
だから午後は昼寝をしたり、音楽を聴いたり、害のない本を読んだりします。
そんな生活をしているとどうしても運動不足になりますから、毎日だいたい一時間は外に出て運動をします。
そして翌日の仕事に備えます。
来る日も来る日も、判で押したみたいに同じことを繰り返します。
2人がこの習慣になったのは、以下の理由が考えられます。
脳のゴールデンタイムを活かす
起床直後がゴールデンタイムになる理由
朝起きてから2~3時間は、なぜ、「ゴールデン」と呼ばれるほど、素晴らしい時間帯なのでしょうか。
まず、睡眠中に私たちの頭の中は整理整頓されます。
夢によって、「前日の出来事」の記憶が整理整頓され、朝起きた直後の脳は、「片づけられて何も載っていないまっさらな机」のような状態になります。
はじめは机の上に何も載っていなくても、仕事を進めるにつれて、書類や文房具が机の上にちらばりはじめます。
これと同じことが脳内でも起きているのです。
朝起きたときの脳の状態は、「何も載っていないまっさらな机」と同じ状態なので、 広々と作業スペースを使えて、仕事の効率も抜群にはかどります。
2016年に開発された、集中力を継続的に測定できる新型のメガネ「JINS MEME(ジンズミーム)」が、興味深いデータを提供しています。
「ジンズミーム」を使った500人の平均データによると、1日で最も集中力が高い脳のゴールデンタイム時間帯は、朝6~7時台です。
その後、9時以降、集中力は徐々に低下し、昼の2時に低くなり、その後、4~5時の終業時間に向けて、集中力が高まります。
このデータは、起床後2時間は、1日の山中で最も集中力が高い「脳のゴールデンタイム」であるということを見事に証明しています。
脳のゴールデンタイムでこなすべき仕事としては、クオリティの高い文章を書いたり、 理論的な仕事、語学学習、難しい書類を読んだり書いたりする、高度な注意力を必要とする書類作成など、「脳のスペック」や集中力を必要とする「集中仕事」が向いています。
朝に執筆するとクオリティの高い文章がスラスラ出てきますが、夜は文章が出てこないことがほとんどです。
そのことを誰よりも熟知していて、午前中に執筆しているのだと思います。
まずは、執筆にとてつもないエネルギーを使うことを理解しましょう。

【理由その②】
スマホで例えるとわかりやすい
悩みがある状態の執筆をイメージするには、スマホで例えるとわかりやすいです。
例えば、脳というスマホが64GBだとします。
そして、悩みが63GBあるとします。
つまり、悩みに大量のGBを使ってしまうので、動作が遅くなります。
なので、執筆前に悩みを吐き出して、脳のエネルギーを執筆に使えるようにするのが重要です。
【理由その③】
悩みやストレスは、脳に様々な影響を及ぼす
では、悩みやストレスと脳の関係を説明致します。
まず、コルチゾールの説明です。
■コルチゾール
副腎(腎臓の上部に座す) で生成されるストレスホルモンで、 心拍数や血圧を上昇させて警告を発し、「闘争か逃走か」の準備を促す。
コルチゾールが慢性的に分泌されると海馬が損傷を受けることがわかっている。
次に、海馬の説明です。
海馬は記憶の中枢といわれる
悩みやストレスが及ぼす悪影響は、
イライラで「海馬」が縮小、物覚えが悪くなる
〜中略〜
慢性的にコルチゾールが分泌されるとーそれが何か月も、あるいは何年も続くと、海馬は萎縮してしまうのだ。
〜中略〜
ストレス反応がいつまでも治まらないと、短時間の記憶が損なわれることが少なくない。
重いストレスを抱えた状態が長く続くと、言葉がうまく出てこなかったり、場所の認識ができなくなったりする。 海馬は空間認識にも関わっているため、自分の居場所や方向がわからなくなる可能性も高くなるのだ。
執筆では、たくさんの言葉を使うので、海馬がとても重要な役割を果たしていることが分かります。
次に、前頭葉です。
その前頭葉の前の部分「前頭前皮質」と呼ばれる領域は、高次認知機能をつかさどっている。
たとえば衝動を抑えたり、抽象的思考や分析的思考を行ったりする、文字どおり「高尚な場所」である。
前頭葉と「思考の継続」「思考の切り替え」が関与していることは、脳科学的には何十年も前から証明されています。
悩みやストレスが及ぼす悪影響は、
前頭葉も、やはりストレスによって萎縮する。そして実際に、極度の心配性の人は前頭葉の各部位が小さい。
そうなると、まさに踏んだり蹴ったりだ。ストレスが長引けば長引くほど脳はみずからを蝕み、歯止めはさらに利かなくなる。
慢性的なストレスの苦痛を抑えるために欠かせない海馬と前頭葉が、適切に機能しなくなるのだ。
つまり、
ストレスが増すと、つまりコルチゾールの血中濃度が高くなると、脳内で情報を伝達する機能が妨げられる
このように、脳の様々な部位に悪影響が及びます。
なので、思いっきり悩みやストレスを吐き出しましょう。


【方法】
書きだす習慣を持ち、文字を見るのが大事
では、悩みやストレスを吐き出す方法を2つご紹介致します。
①ネガティブを書きだせば、ストレスが減る
②視覚で見ることで、気付きを得る
まず、『①ネガティブを書きだせば、ストレスが減る』ですが、
「1日15分、 ネガティブな感情について書き出す」ことを4日間続けると、一時的にはネガティブな感情が強まるものの、長期的にはポジティブになることがわかったのです。
このように、日記を付けるなどして、ネガティブな気持ちを書き出しましょう。
2つ目の『②視覚で見ることで、気付きを得る』は、
客観視による気づき効果
社会心理学者でバージニア大学の教授を務めているティモシー・ウィルソンは、「書く」という行為には、考え方のネガティブサイクルをポジティブサイクルへと変化させる力があると述べています。
結婚したカップルに生活の悩みを書くように頼むと、悩みを書いた夫婦の方が書かなかった夫婦よりも「幸せだ」と感じる度合いが増加したという結果が出ました。
ただ悩みを書くことで、幸福感が高まったのです。書くことは思考サイクルを変えてくれる効果を生みます。
普段は目には見えない感情を「文字」で可視化することで、こんなことを思っていたのかと客観視することができます。
結果、自分の感情・思考と距離が生まれて、新しい見方・とらえ方が生まれてきます。
そして自分・相手を理解し、感謝が生まれ、小さなことに幸せを実感していきます。
これが書くことでポジティブサイクルになっていく秘訣です。
書くことで自ら気づくオートクライン効果
コーチングでは、自分で話した言葉で自ら気づくことをオートクラインといいます。
オートクラインとは医学用語で「自己分泌」を意味する言葉ですが、まさに書くことでも自分の内側から答えを分泌できるのです。
思っていること、感じていることを言語化することで、それまで感じなかった気持ちや、その深層にある理由に気づけます。
誰からアドバイスを受けるわけでもなく、たった1人で紙の上で言語化するだけですが、書くことが別の知性を駆動させるわけです。
紙の上で「あっ、そうか!」と気づくことこそオートクライン(自己分泌)効果です。
頭で考えるだけで終わりにするのではなく、書き出して文字を見て、自分の気持ちに気付くことが大切です。
ドラマなどで黒板に数式をいっぱいにして話す場面があるが、現実の数学者も同じことをしていると言える。
紙とペンがあれば、簡単に出来ます。
この機会に書き出す習慣を持ちましょう。
是非、試してみてはいかがでしょうか?


まとめ
1️⃣執筆には、膨大なエネルギーを使う。
2️⃣悩みを持っていると、スマホと同じく脳の動作を遅くする。
3️⃣書き出す習慣を持ち、文字で見ると気持ちが落ち着く。
🈁《悩みやストレスは抱えるのではなく、文字にしてみる。そうすれば、執筆で脳の力をフル活用出来る》
私の記事が、皆様の今後の成長に繋がることを心より願っております。
参考文献
↓↓↓
✳️マガジン一覧
過去記事をまとめたマガジンを掲載致します。
宜しければご覧ください。
✳️自己啓発ソムリエ 言葉で動くのコンセプト紹介
自己啓発ソムリエ 言葉で動くの
自己紹介になります。
宜しければご覧ください。
↓↓↓
「私が何故、自己啓発を記事にするのか?」その理由が書いてある記事となります。
宜しければご覧ください。
↓↓↓
「何故、本を読み続けるのか?」その理由が書いてある記事となります。
宜しければご覧ください。
↓↓↓
「私が知識にどういう思いをかけているのか?」を書きました。
宜しければご覧ください。
↓↓↓
以上になります。
最後までご覧頂き、誠にありがとうございました
皆様のサポートが、note活動の励みになります。 そんな気持ちにお返しが出来るように、記事に磨きを掛けるために使わせて頂きます。 宜しければサポートをお願い致します。
