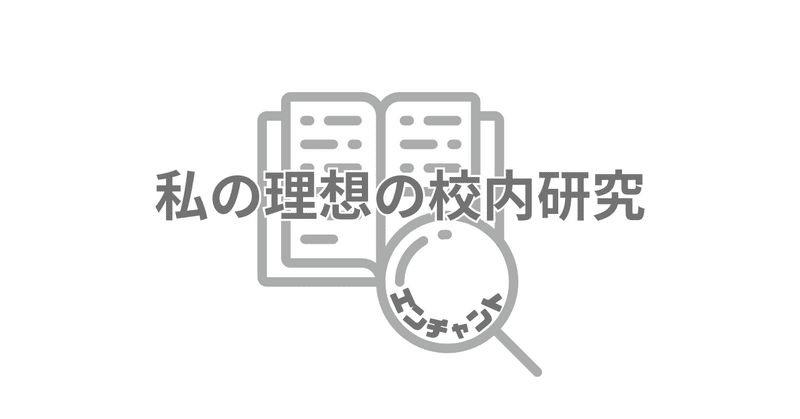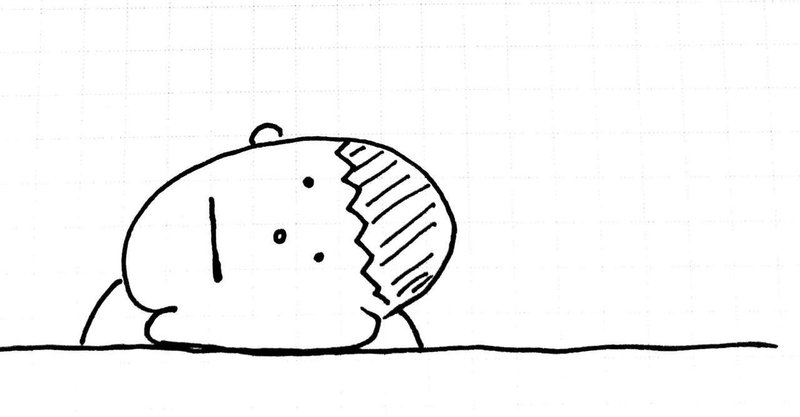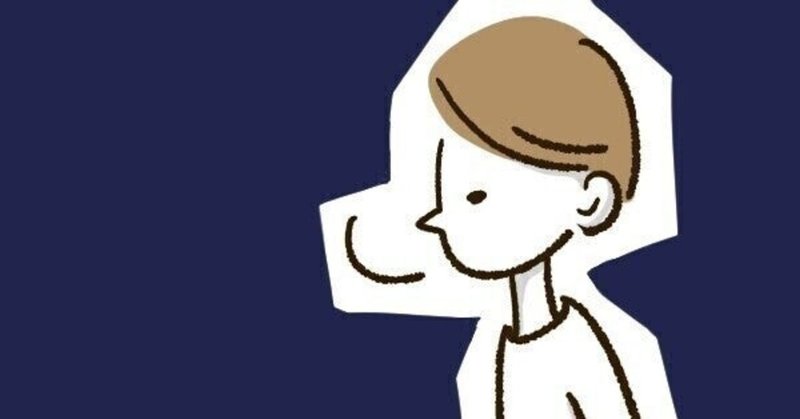#小学校の先生
授業でどう教えるかは手段だから、目的である子どもの成長を忘れないようにしたい
1293記事目
こんにちは、旅人先生Xです。
今日は「教える手段と子どもの成長という目的」について書いていきたいと思います。
良かったらぜひ、目を通していってみていただければ幸いです!
目次は、以下の通りです。
子どもの成長が学校の授業の目的だと思う
学校では、国語や算数といった様々な教科の授業があります。
子どもの頃から当たり前のように教科の授業を受けてきたし、教員になってからも当
【1分で読める~教育って「子どもを育てる」仕事だと思ってるあなたへ~】
※ 約1分で読めます
瓦をわるのに,瓦に意識があるうちは割れないそうです。
ではどうすると割れるのでしょうか?
こんにちは。がんTです。小学校教諭をしたり,2児の父親をしたり,一人の夫をしたりしています。
突然ですみません。
みなさんは教育って子ども(人)を育てる仕事だと思っていませんか?
もちろんそうなのですが,僕は
未来を育てる仕事じゃないかなと思っています。
ぼ