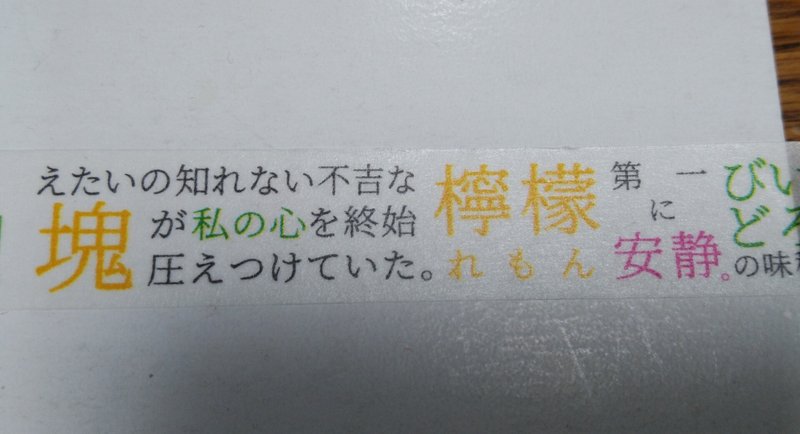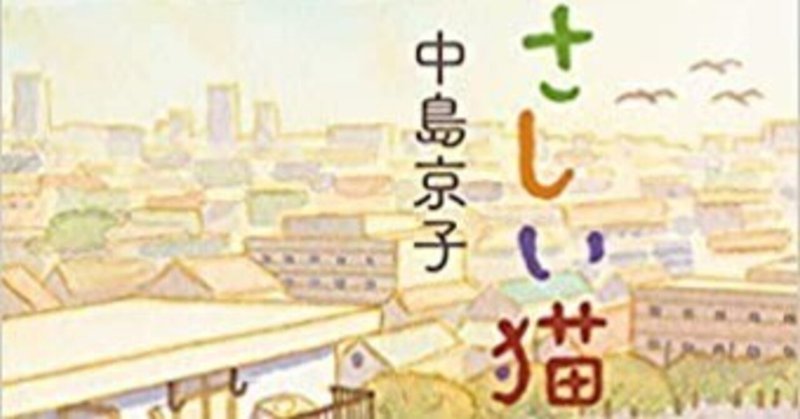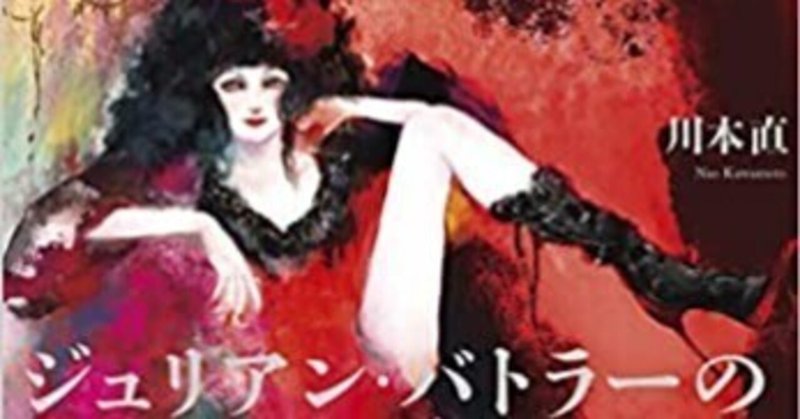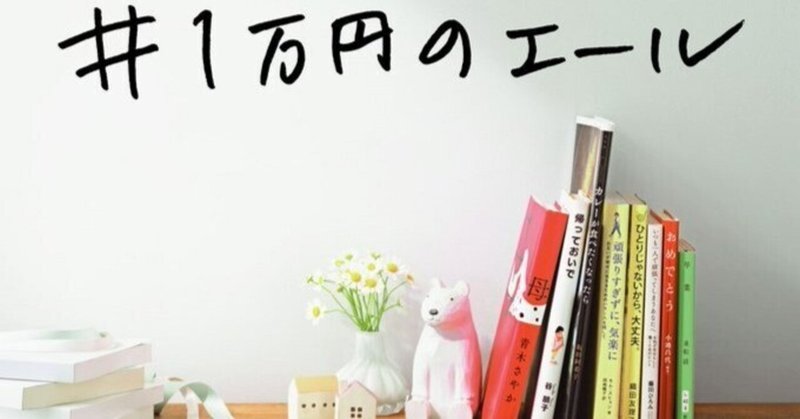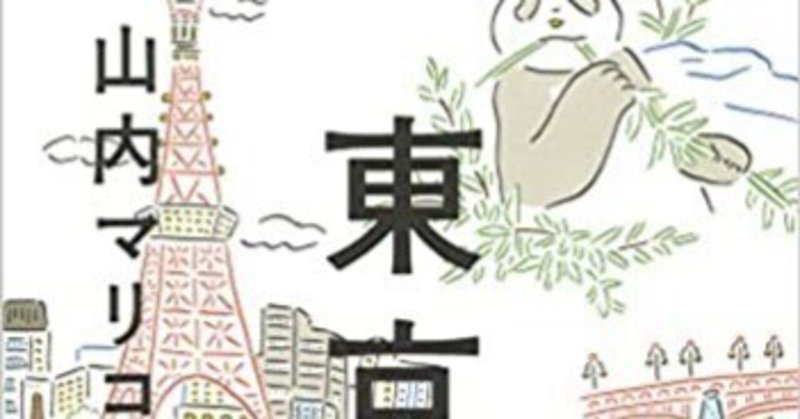2022年3月の記事一覧
わたしの本棚、自宅編(毎日読書メモ(282))
わたしの本棚、前回(ここ)は実家で塩漬けになっていた本の写真だったので、今日は自宅で、カバーかけてない本の多そうな場所を撮ってみました。
今の家に引っ越した時に本を並べて、それから入れ替えてない本が多いので、たぶん15年位このラインナップで頑張ってます。
傾向が大体見えて、
村上春樹 付随してレイモンド・カーヴァ―
ディック・ブルーナ
谷川俊太郎
サンリオ
岩波少年文庫
辺りが見えてきますね。
『やさしい猫』(中島京子)、わたしたちは何と多くのことを知らずに通り過ぎているのか(毎日読書メモ(281))
中島京子『やさしい猫』(中央公論新社)を読んだ。2020年から2021年にかけて読売新聞で連載されていた小説。不法滞在者とされ、入管(出入国在留管理庁)施設に収監されたスリランカ人男性と、彼を救おうとする日本人の妻、そしてその娘の物語であることはあらかじめ知って読み始めた。そして、2021年3月に、スリランカ人女性ウィシュマさん(ラトナヤケ・リヤナゲ・ウィシュマ・サンダマリさん)が名古屋の入管施設
もっとみるわたしの本棚(毎日読書メモ(277))
お題を見てやりたかった「わたしの本棚」、自宅の本棚がかなりカオスになっているのと、書店のカバーのかかっている本が多くて、写真を撮るとなるとカバー外して並べなおさないといけない状況で、そのまま撮影できない本棚を「わたしの本棚」と名乗っていいのか?、と葛藤して結局写真撮れず。
で、実家に来て、残っている本を見ていたら、写真撮れそうな感じに本が並んでいたので、撮ってみた。
30年近く塩漬けになっていた本
『ジュリアン・バトラーの真実の生涯』(川本直)、アメリカ文学史のはざまを読む(毎日読書メモ(279))
川本直『ジュリアン・バトラーの真実の生涯』(河出書房新社)を読んだ。この本を知ったきっかけは、朝日新聞の書評欄に著者インタビューが出ていたから(ここ)。
(本の紹介として、「日本では1文字も紹介されてこなかった」は雑だ。最後までこの本を読めば、日本での紹介の経緯もきちんと書かれている、まぁ、そこも虚構なんだけれど)
架空の作家を作り出して、実在のアメリカ文学史に切り込んでいるのか! どういう仕
図書カードが10万円分あったら何を買うか(毎日読書メモ(276))
昨日の、朝日新聞&図書カードNEXTのキャンペーン企画「#1万円のエール」について感じたこと(ここ)の続き。そこに、自由に使っていい図書カードがあったら何を買うか。
毎年4月に発表される本屋大賞、副賞は図書カードが10万円分である。
大賞受賞者がその10万円の図書カードで何を買ったかは、「本の雑誌」の記事で紹介される。
これまでの本屋大賞のページの中でも、過去の受賞者が何を買ったかが、紹介されて
#1万円のエール(毎日読書メモ(275))
昨日(2022/3/20)の朝日新聞に、朝日新聞の好書好日と図書カードNEXTの共同広告が出ていて、「進学や就職のプレゼントに、図書カードNEXT」をお勧めしている。節目のお祝いに1万円の図書カードを贈ったら、それはどんな本になるだろう、という期待をこめた広告。
で、広告に出ていた本(9,977円相当)が、自分だったら選ばないな―、というセレクションだったので、なんだか引っかかって、書いてみる。