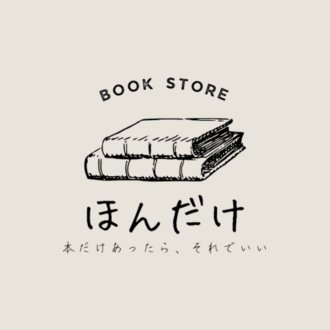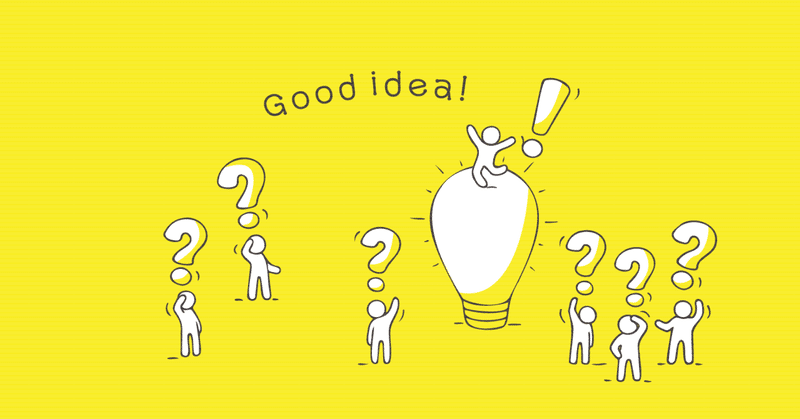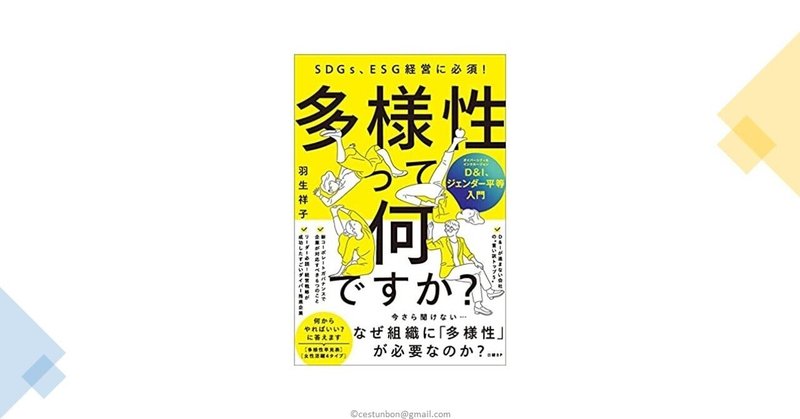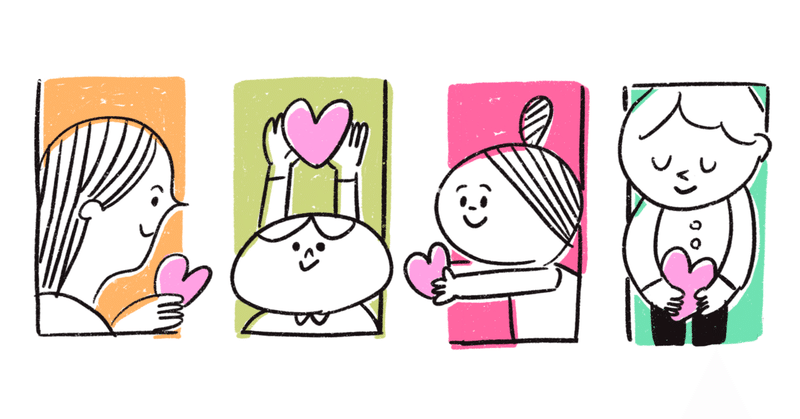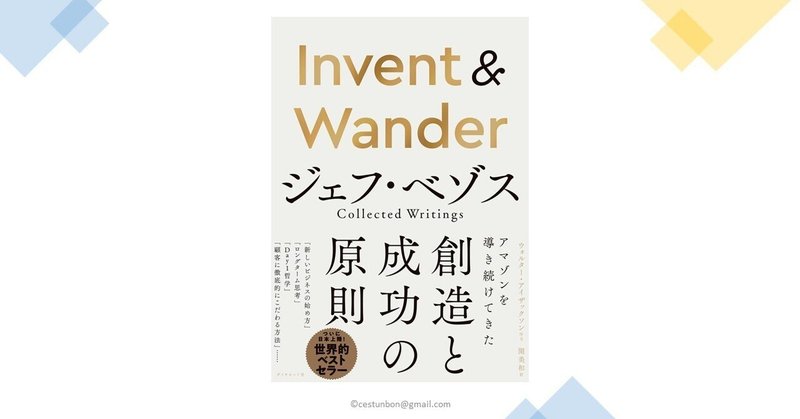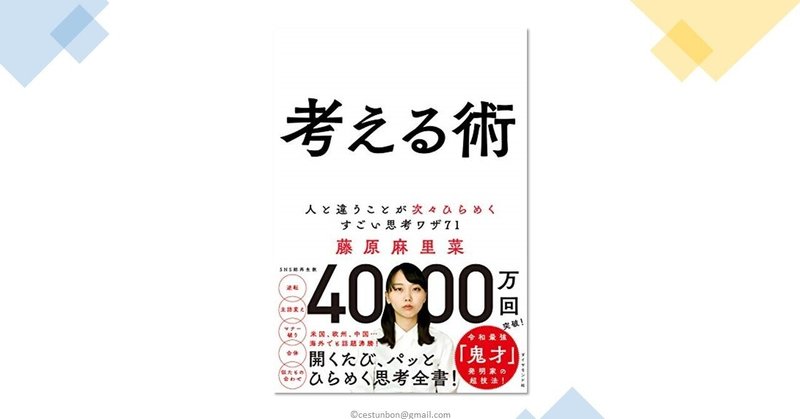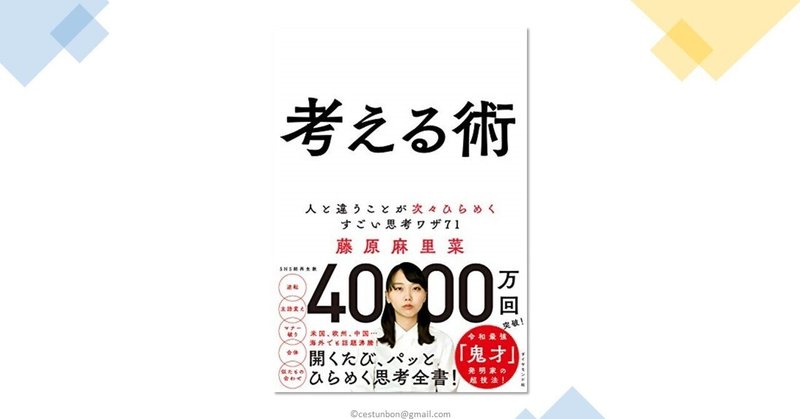#イノベーション
不幸はばらばら。幸福は同じ。アンナ・カレーニナの法則と新規事業成功の要点
どこかで耳にしたことがあるフレーズだけど、これが1877年のロシア人の小説から引用された言葉で、アンナ・カレーニナの法則と言われていることを『ブループリント(上巻)』をよんで知りました。
企業の新規事業担当としてはたらくわたしは、ついこう読み替えてしまう。
これは本当なのか。
もし本当なのだとしたら、どうしたらいいか。考えていきたいと思います。
企業とアンナ・カレーニナWikipediaにい
みんなが同じ方向をみるチーム。新規事業に必要なロール
新規事業のリーダーには多くの役割を求められます。顧客課題を発見して、その解決策をつくっていく製品開発(プロダクトマネジメント)。意思決定権をもつマネジメント層に企画を提案し、予算を獲得するための社内交渉。
とくに難しいのは、チームの方向性を揃えること。少人数で取り組んでいる間ですら、方向性のズレに悩まされ、「なにをやりたかったのか」わからなくなり迷走してしまう。「いまなにをすべきなのか」もわから
『Invent & Wander』ジェフ・ベゾスは新規事業の応援団長
ジェフ・ベゾスは、書籍をオンラインで販売するだけでなく、キンドルをつくり、アレクサやAWSをつくり、ブルー・オリジンではロケットまでつくっている。
「アマゾンらしさとは何なのか?」とか「シナジーはあるのか?」と考え続けることよりも、「お客様のためになることは何なのか?」に向き合い続けてきたからこそ、多岐にわたるイノベーションに挑戦してこれたアマゾン。
その企業哲学のエッセンスを、ジェフ・ベゾスが
無駄づくりがいっぱい詰まった『考える術』は、ムリなくしの書だった(後編)
こちらは前編のつづきです。
のるかそるか。というより、のってそる一時期タピオカが流行った。わたしもタピオカは大好きなのだが、多くの女子と一緒に並ぶのは気が引けるし、インスタでタピオカをみたいとは思わない。藤原さんも、インスタ映えを阻止する志を抱き、『インスタ映え台無しマシーン』を発明した。スイッチを押すだけで、カメラに指が重なるという仕組みだ。
トレンドを持ち出し「あるある」の共感を集めた後で