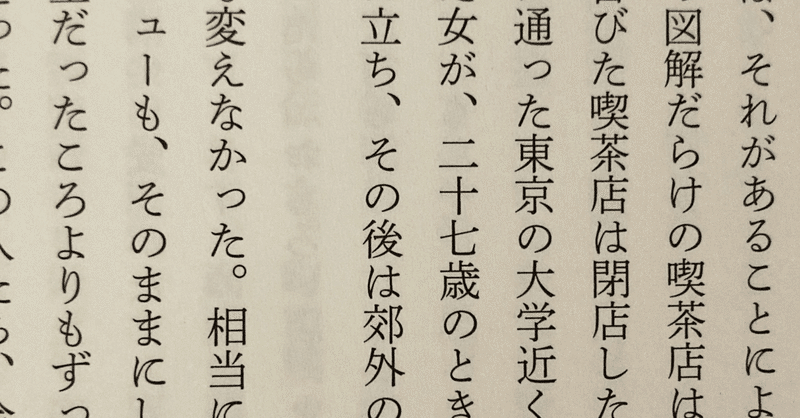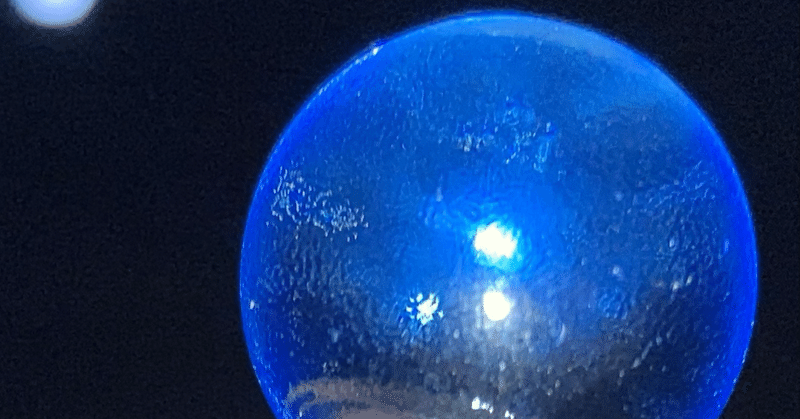#海外文学のススメ
『渚にて 人類最後の日』 ネヴィル・シュート
悲しく救いのない終末小説。しかし、ここまで救いがないにも関わらずこんなにも美しく、穏やかに凪いだ読後感を与える小説が、他にあるだろうか。
物語の舞台設定は1963年。この小説の初版は1957年なので、近未来というよりも同時代を描いたフィクションだ。
60年代初頭に起きた第三次世界大戦で核戦争が勃発し、核爆弾によって地球の北半球は壊滅状態になった。
今は南半球に位置する国だけで、かろうじて人間が生
『望楼館追想』 エドワード・ケアリー
円屋根のある古い大きな建物「望楼館」は、周囲が都会化する中で古色蒼然、陸の孤島だ。
「ぼく」ことフランシス・オームは、この望楼館に、両親と一緒に暮らしている。
望楼館の住人はフランシスを含めて7人。風変わりな彼らは、やがて自分が最後の住人になってしまうことを恐れながら、ひっそりと暮らしている。
フランシスの仕事は、町の中央にある台座の上に全身白ずくめで立ち、彫像のパントマイムをすること。
白ず
『雌犬』 ピラール・キンタナ
怖い小説だ。
コロンビアのワイルドな雨風と、闇深い女性の心が、怖い。
主人公ダマリスは、海辺の断崖の上に住んでいる、もうすぐ40歳になる女性。
村に出るには、急な階段を降りて入江を渡らなければならず、住んでいる小屋も古く不便な生活だ。
ダマリスと夫には子供がなく、不妊は夫婦仲も冷え切らせている。
淡々と感情を抑えた語りが、彼女の半生を語り、波乱に満ちた少女時代から、夫婦で崖の上の管理人小屋に住
『舞踏会へ向かう三人の農夫』 リチャード・パワーズ
ぬかるんだ田舎道に佇む三人の男。
二人は明らかに若く、一人は年齢不詳。
揃いのスーツと帽子姿の三人は、めかし込んでどこかへ向かう途中のようだ。
表紙の写真は、写真家アウグスト・ザンダーによるもの。
本書は、この一枚の写真を巡って想像力を羽ばたかせた、歴史の流れの物語である。
3つの物語が並行して交互に語られながら進行する。「めぐりあう時間たち」の構造だ。
簡単にキャプションをつけるならば、
『ささやかだけれど、役に立つこと』 レイモンド・カーヴァー
カーヴァーの作品は端正だ。
真昼の陽光が全ての像をくっきりと照らし出すように、彼の乾いた筆致は、名もなき人々の人生のそこはかとないおかしみや哀しみ、また悪夢をも描き出す。
その端正さゆえに、それが悪夢である時、彼の作品は衝撃的に残酷なものになる。
突然運命に牙をむかれ、なすすべもなく打ち砕かれる主人公たちは、同じくなすすべもなくそれを目撃するしかない読者の心に、衝撃的に焼き付くのである。
それぞ