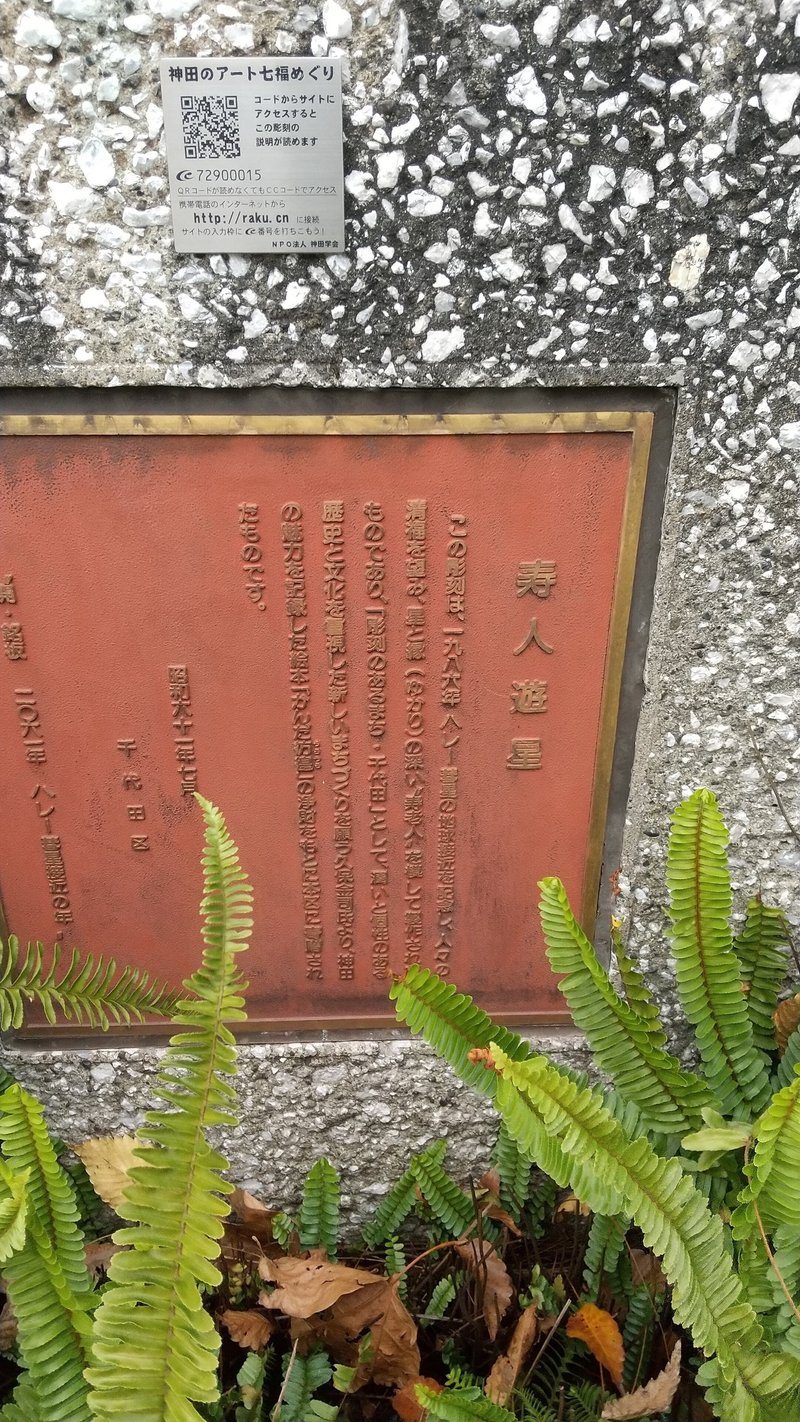#心理学
【読書録】フーコー『精神疾患とパーソナリティ』4(終) 驚くべき二つの「効果」と一つの「操作の結果」
フーコー節、とでもいうような、独特の語法があると、昔から思っていた。曰く、今はこれこれという観念が常識となっているが、それは通時的に自明なものではなく、○○年代に起こったこれこれの出来事の効果であった、など。
今回、『精神疾患とパーソナリティ』を読み直して、初読では気付かなかった、というか、今までその初読の、途中まで読んだ時に抱いたイメージをそのまま引きずっていたのでわからなかった点が二つあ
【読書録】フーコー『精神疾患とパーソナリティ』3 あっけなく行われるフロイト精神分析の要約と乗り越え
フーコーの『精神疾患とパーソナリティ』を、さらに読み進めている。
フロイト理論の要約と問題点の指摘が、スピーディに、的確に行われていることに驚く、これは、やはり、前に一読した時には気づかなかった点である。
フロイトの、初期の、と言っていいのか、分析の仕組みは、精神の構造の発展史的記述、人は生まれてから何期と何期があって、そして、それが一番外の膜で覆われてはいるが、実は見えないだけで今まで
【読書録】フーコー『精神疾患とパーソナリティ』1
また久々に読書録である。本当に、正味の読書録を書いていこう。今までは、気取り過ぎて、大変だった。
フーコーの伝記を読んで、初めに出て来た本の、『精神疾患とパーソナリティ』を手に取った。実は、この本は、半ば来歴は知っていながら、ずいぶん前に購入して、七割方読んだ本だった。七割読んで、すっかり奥に仕舞われていた。が、伝記を読んだので、改めてバックボーンを知ることが出来たので、また味わいも変わるだ
【読書録】豆腐色戦記(白)
封筒は茶色、豆腐色は白を塗布しろと。
ふうろいとに憑りつかれておる。もともとは、ドゥルーズの『千のプラトー』を読んでいて、狼男の章を読んだ時に、元ネタを読んでおくべきだと考えて開いたフロイト全集だったが、そこから逸れるようにして開いた西谷修の『不死のワンダーランド』にも、「〈不安〉から〈不気味なもの〉へ」と題して、またしてもフロイトを読めと促される。フロイトならもう読んだよ、と、「夢判断」を
【読書録】フロイトから逃れたつもりがフロイトに戻ってくる
気分転換というか、少し気ままに本が読みたくなって、あるいは、つい今しがた本の整理をしたからという物理的な動機もかかわってくるのかもしれない、とにかく西谷修の『不死のワンダーランド』を読み始めた。いや、前に半分以上読みかけていて、放っていた。こんな本はたくさんある。あまり途切れ途切れに本を読むのはよくないと決め込んでいたけれども、割合悪くもないかもしれない。本の種類による。ある種の散漫な意識に貫か
もっとみる【読書録】フロイト全集14 2 フロイト節
フロイトの書いているものを、内容を理解し、感じる為に飲み込まなければいけない、フロイト節のようなものがある。
一つは、無駄にではないだろうが、回りくどいこと。いや、半ばは無駄なんじゃないかと思う。「私はもしかしたら読者の疑念を招いてしまうかもしれない、それは……」という感じの、エクスキューズが多く、厳密でありすぎることに読んでいると疲れを覚えてくる。
もう一つは、多く感じるところかもしれない
【読書録】フロイト全集14 晩年の信仰
フロイト全集14巻、有名な『狼男』分析を読むつもりで読み始めたけれども、とりあえず月報を読んでいる。
あまりよく知らない、いろんなジャンルの偉い先生方の、論評がつづく。
その中、月報の最後の文章、濱田秀伯という人の、「ジャネとフロイト」という文章の中で、知っている人は知っている、『ヒステリー研究』という、フロイト初期の出世作みたいな研究本を共同制作した人について触れていて、この人、フロイトと