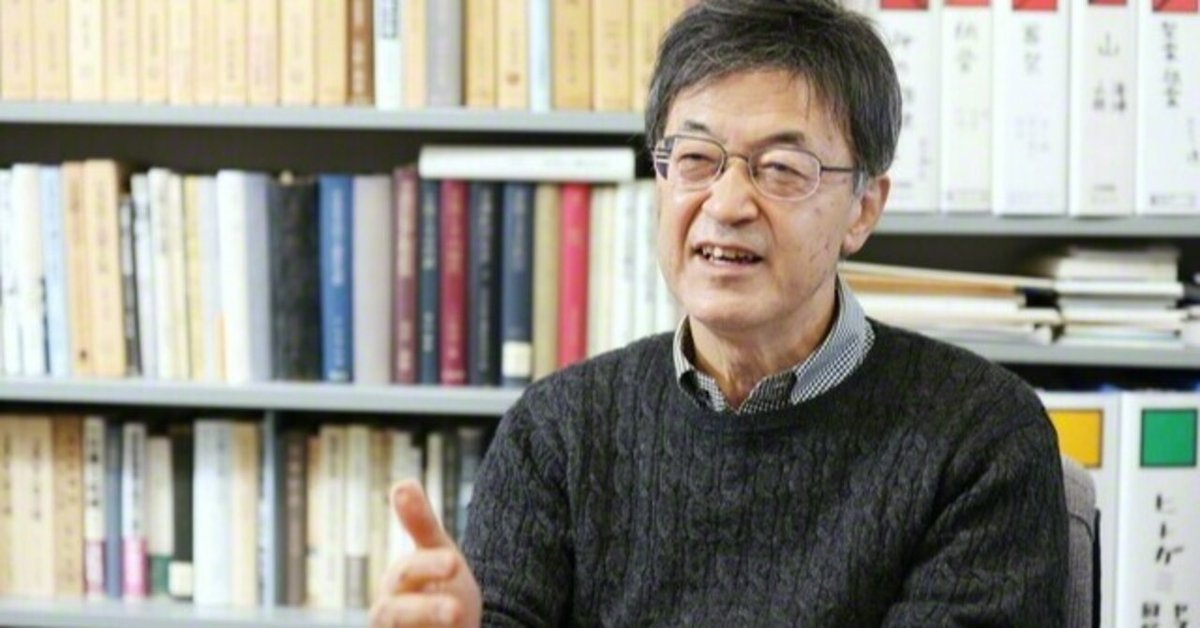
佐藤弘夫 『日本人と神』 : 〈心理的ファクト〉としてのコスモロジー
書評:佐藤弘夫『日本人と神』(講談社現代新書)
まさに目からウロコの落ちる、抜群に面白い清新な「宗教学」書。
私は、趣味で「宗教」の研究を始めた、正攻法の「無神論者」である。そんな私は、「宗教」というものを考える上で、まずは最もメジャーな「キリスト教」を研究対象とすることにし、聖書の通読は無論、聖書学、教会史、神学などの本を片っ端から読んでいって、最近では、大学で神学を学んだ神父さんや牧師さんくらいとなら、神学論的な議論ができる程度の「知解」を身につけることができるようになった。
そこで、そろそろ本命である「日本の宗教」として、「神道」や「仏教」に手を出し始めたのが、ここ数年のことだ。
なぜ「日本の宗教」が本命なのかと言えば、それは私が日本人だからであり、かつ、「アメリカによるイラク戦争」を支持した創価学会・公明党を批判して脱会した、元「創価学会」員であったからだ。

ただし、子供の頃に親と一緒に創価学会に入った私は、当時も「信仰的確信」(キリスト教で言えば「回心」)を得ることができず「いつかはそれが得られるだろうか…」と思いながら、つまり半信半疑で「学会活動」を続けていたような人間だった。だから「創価学会の戦争支持」というあからさまな「言行不一致」による「背信」を見せつけられて、比較的あっさりと論理的に「この信仰は間違っている。また、そもそも宗教なんて、すべて幻想ではないのか」と考え、信仰を捨てることができたのだと思う。

(公明党・冬柴幹事長)
そんなわけで、私の「宗教研究」の本命は「日本の宗教」であり、特に「仏教」だったわけだが、「仏教」と言っても山ほどの宗派・教団が国内外にあって、「仏教」全体をひととおり押さえた上でその本質を捉えるといったやり方が、容易でないのは自明だった。だから、典型的な世界宗教であり、宗教的な「輪郭」が比較的はっきりしている(と思えた)キリスト教との対比で、「仏教」(の輪郭)を捉えることができるのではないかと、まずはキリスト教への迂回路を採ったのである。そして、これはおおむね正解であったようだ。
では、「仏教」だけではなく、なぜ「神道」なども含む「日本の宗教」なのかと言えば、それは私の興味が、「天皇制」という「宗教がかった政治制度」と「戦争を含む、日本の政治史」という「アクチュアルなもの」にもあったからである。
つまり「イラク戦争」「アメリカ同時多発テロ」といった、目の前で展開された政治の問題が、「創価学会」や「信仰」との関連において他人事ではなかったし、それは「オウム真理教事件」も同じであった。だから「天皇制国家としての日本」を考えるためには、どうしても「仏教」だけではなく、「神道」を含む「日本の宗教」の全体的理解が必要だと、そう感じられたのである。

そして、私のこうした興味の、最も根底にあるのは「どうして、宗教などという非現実的なものを、本気で信じることができるのだろうか」という疑問だった。
もちろん「頭の悪い人が信じる」で済めば話は簡単だが、きわめて頭のいい学者や知識人でさえ信仰を持っている人は少なくないのだから、信仰の有無が「頭の良し悪し」に還元できないのは明らかなので、「では、なぜ」と根元的な疑問を持ったのである。

(オウム真理教の教祖・麻原彰晃こと松本智津夫)
○ ○ ○
『 この地球上に、いまだかつて神をもたない民族はなかった。なぜ人は神を求めるのであろうか。こうした疑問から、神の問題を人文学の重要課題と捉えるに至ったわたしは、それを研究者としての自分が追求すべき最終的なテーマと考えるようになった。』(P257)
本書著者は「あとがき」で、このように語っている。

これは、私の「どうして、宗教などという非現実的なものを、本気で信じることができるのだろうか」という疑問と、似ていると言える反面、違ったところもある。
似ているところとは、どちらも「神(や仏)の実在」など、毛ほども信じてはいない、という点である。
一方、違う点は、私の関心は「個人の内面(心理)」にあり、佐藤の関心は「人間一般の内面(心理)的動向」に向いてる点であろう。
そのため、私の場合は、「宗教」が「多くの(ほとんどの)人」に必要なもの、言い換えれば「人間社会」に必要なもの(必要悪的な幻想)だと認めても、そうした「社会的必要性からの宗教の活用」ということには、本書著者である佐藤のような興味はない。
つまり、私としては(役に立つものだったとしても)「宗教は幻想である」ということがハッキリすれば、他の人がそれに頼るのは「必要悪」として容認しないではないものの、そうした「信仰」を「人間理性の限界」として、あまり好ましくは思えないのである。
で、このように「宗教に対して潔癖」な私(潔癖だからこそ、道具としての宗教利用が好きではない私)としては、優れた「宗教学」書を読んで裨益されるところが多かったとしても、どこかで隔靴掻痒的な「違和感」がついて回った。
えてして「宗教学」というのは、(信仰を持った宗教学者を別にしても)「宗教を(学者個人は)信じてはいないけれど、宗教の社会的価値は認める」という「どちらにも良い顔」をするようなところがあって、「無神論」のように「宗教とは、願望充足的幻想でしかない。人間は、もっと強くなって、現実を直視すべきである」みたいな、身も蓋もないことを言わないから、その奥歯にものの挟まったような物言いが、どこか「物足りない」し「信用しきれない」と感じられたのだと思う。
このように「宗教の価値を認める」という点では、本書もまた通例の「宗教学」の範疇にはあるものの、普通のそれよりは、よほど「無神論」的に「論理的」である。「道徳」や「人生哲学」や「宇宙論」的なものではなく、「社会心理学」的に「信仰する人々」を見ているのが感じられて、論理的に気持ちがいいのだ、ベタついていないのである。それは、著者の次のような言葉にも明らかだろう。
『 わたしは前近代に帰れ、といっているのではない。過去に理想社会が実在した、などといっているのでもない。どの時代を切り取っても、苦悩と怨嗟の声はあった。いまわたしたちが生きる世界を見直すために、近代を遥かに超える長い射程のなかで、現代社会の歪みを照射していくことの重要性を論じているのである。』(P255)
つまり「正しい信仰」があるのではなく、否応なく「人間の信仰的な営みがあった」という現実を客観的に理解した上で、私たちの社会と個人と信仰のあり方を考えなければならない、と言っているのである。
○ ○ ○
さて、こんな「理性的」な著者は、本書で何を訴えているのであろうか。
それは「日本の宗教学は、このままでいいのか」という問いであり、「このままで良いわけがない」ということである。
「日本の宗教学」のどこがダメなのかと言えば、それが「学界的慣習」として「日本の宗教」というものを「歴史的ファクト」においてしか考えようとしない点である。
平たく言えば「事実関係」が重要であり「事実が先にあって、考え方(宗教宗派の流行り廃りや変化)が生まれる」という発想だ。具体的に合えば「最初にアニミズム的な感覚があり、それがシャーマニズムに発展し、それから豪族が力をつけて氏族神話を発展させ、それが神道となり、そこへ仏教が入ってきて」といった「事実の連なり」として「日本の宗教」を理解する仕方である。

これに対して、本書著者の佐藤は、言うなれば「心理的ファクト」としての「人々の宇宙観(コスモロジー)」(の変化)を重視し、「歴史的ファクト」の前に、「心理的ファクト」としての「人々の宇宙観(コスモロジー)」(の変化)があった、それがあったからこそ、いくつかの「歴史的ファクト」の中から一つだか二つだかの「歴史的ファクト」が選択的に採用されて、それが(必然的に見える)「歴史(的事実)」を構成するようになった、というような考え方である。
つまり、一般的な「宗教学」は「歴史的ファクト」ばかりを問題にして、あまりにも「心理的ファクト」を無視しすぎているというのが、本書著者の主張なのだ。
しかし、言うまでもなく、「歴史的ファクト」と「心理的ファクト」は、どちらか一方が正しいというようなものではない。そう考えてしまうと「卵が先か鶏が先か」の堂々巡りに陥ってしまうだけであり、重要なのは、常に「両にらみで考える」ということなのだろうと思う。
そうした意味で、本書著者の「宗教学」に対する「問題提起」は、非常に重要なものだし、まったく正しいと、私は高く評価したい。
しかしまた、そうした学問的価値とは別に、私にとって本書が抜群に面白かったのは、「心理的ファクト」を重視する著者のスタンスが、もともと「社会」よりも「心(個人の内面)」に惹かれる私の趣味に合致したからであろうと思う。

たしかに「心理的ファクト」だとか「心の問題」というのは、実証的なものではなく、多分に「解釈学」的なものだから、「歴史学」な感性の持ち主が多いであろうの「宗教学」の世界では(「それは評論であって、学問ではない」といった感じで)正当に評価されにくいのかもしれないが、著者も言うとおり、「世界」に通用する「日本の宗教学」であるためには、「特殊日本的思考形式に縛られた方法論」だけに頼っていては、いわゆる「ガラパゴス的」な学問になってしまうだろう。
無論、これまで鍛え上げられてきた学問的方法論を蔑ろにしてはいけないが、「社会学」や「宗教学」においても「解釈」の問題は決して避けられないのだから、常に「外部の目」を取り込むことで自己を相対化する作業を怠っては、日本の宗教学の発展はないのではないだろうか。
私としては、佐藤弘夫の方法論を発展させる「宗教学」者の出で来たることを期待したいと思う。
初出:2021年5月4日「Amazonレビュー」
(2021年10月15日、管理者により削除)
再録:2021年5月14日「アレクセイの花園」
(2022年8月1日、閉鎖により閲覧不能)
○ ○ ○
○ ○ ○
○ ○ ○
○ ○ ○
○ ○ ○
○ ○ ○
