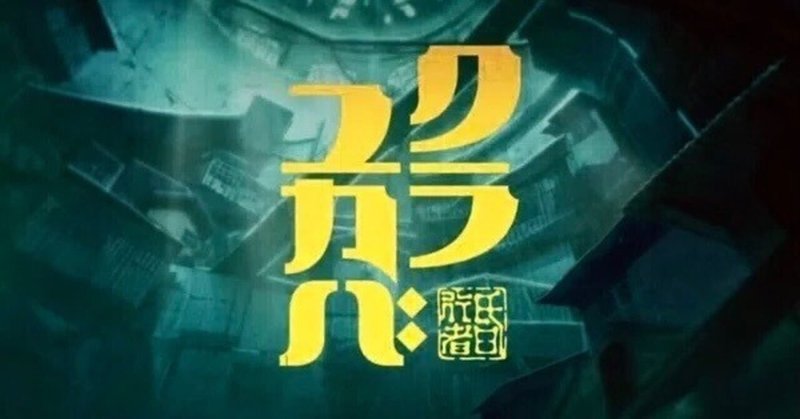
塚原重義監督 『クラユカバ』 『クラメルカガリ』 : 暗示と憑き物落とし
映画評:塚原重義監督『クラユカバ』『クラメルカガリ』(2023年・2024年)
塚原重義監督による『クラユカバ』と『クラメルカガリ』の2本は、どちらも「60分ほどの劇場用中編アニメーション作品」である。
『クラユカバ』は、塚原監督の完全オリジナル作品であり、『クラメルカガリ』の方は、作家・成田良悟による同作のスピンオフ小説を原案に、塚原がアニメ化した作品という位置づけになる。
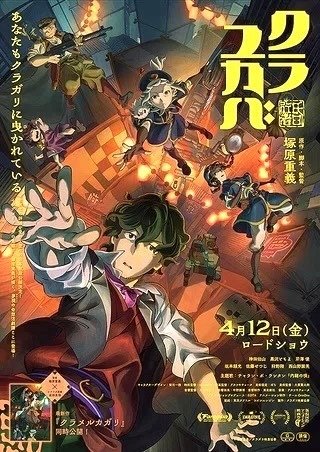

塚原重義監督は、いわゆる「Web系アニメーター」で、『クラユカバ』までは「商業アニメーション制作」に関わったことはなく、学生時代からオリジナルアニメーションを制作してきた、「アニメーター」というよりは「アニメ作家」と呼ぶべき人だろう。
『2001年(平成13年)8月にWebサイト「弥栄堂」を開設。2003年(平成15年)よりフラッシュアニメーションを制作』(wiki)、2チャンネルでフラッシュアニメを公開し始めて、そこで評判を取り、
『2018年(平成30年)に初の長編アニメーション「クラユカバ」の制作を発表、同年12月にパイロットフィルムのクラウドファンディングがおこなわれた。2020年(令和2年)にパイロット版が完成。同年5月に本編序章の制作が発表された。「序章」は翌2021年(令和3年)8月にシネ・リーブル池袋で公開され、同時に企画をツインエンジンが、アニメーション制作を同社グループのパンケーキが担当して映画全編の制作が決定したことが発表された。完成した作品は2023年(令和5年)にワールドプレミアとなった第27回ファンタジア国際映画祭で長編アニメーション部門の「観客賞・金賞」を受賞した。』
(Wikipedia「塚原重義」)
というのが、劇場用中編『クラユカバ』の、日本での公開までの大まかな経緯だ。
さて、『クラユカバ』『クラメルカガリ』の2本についての、私の評価を先に書いておくと、「よく出来ているが、作品として小さくまとまった佳品」というものだ。
こう書くと「いや、むしろ壮大な物語世界の一部を描いた作品と評するべきだろう」と反論したくなる人もあるだろう。たしかにそれはそのとおりなのだが、にも関わらず、実際には、その「壮大感」を出せていないところが、この作品の「物足りない」部分なのだ。


上の「Wikipedia」から引用にもあるとおり、『クラユカバ』は、クラウドファンディングで「パイロット版」が作成され、そこからさらに「序章」版が作られて公開され、これが今回の、言うなれば「完全版」へと発展したわけなのだが、この「完全版」が、そもそも「壮大な世界設定」の「一部」でくり広げられる「小さな物語」であり、陳腐な言い方で言えば「クラユカバ・サーガ」の「序章」に過ぎない。
その証拠に、次作『クラメルカガリ』は、『クラユカバ』と世界観を同じくする「スピンオフ作品」であり、言うなれば、この作品もまた「クラユカバ・サーガ」の「一部」という位置づけなのだ。
したがって、『クラユカバ』は、「パイロット」版が発展して、「序章」版が作られ、それがさらに発展した本作「完全版」でさえ、やはり「壮大な物語世界の一部」を描いたに過ぎない、いわば「序章」に止まっていて、語の本来の意味での「完全版」にはなっていない。要は、作品として「完結していない」のだ。
長々と引っぱったあげく、そのラストは、「謎」の「完全解明(解決)」にはなっていない。
たしかに、一連の「誘拐事件」の犯人は特定され、被害者は救出されるのだが、その犯行を行なった犯人なり犯行組織が、捕まるなり壊滅させられるまでには至らないし、その犯行組織と主人公の探偵「荘太郎」との、親の代からの因縁も、「何かあった」ということまでは「思わせぶりに明かされる」のだが、具体的に描かれるまでには至らない。

なにしろ、公式には「長編」と銘打って、長編料金で公開された作品ではあれ、実際には「60分ほど」の「中編」なのだから、「壮大な世界設定」そのままの「壮大な物語」を描くことなど、もとより出来ない相談で、だから、全体の入り口となる「ごく一部」を切り取るというやり方自体は、決して間違いではないとも言えるだろう。
しかしだ、この『クラユカバ』は、「小さな物語を、きっちり描ききった作品」にはなっておらず、その大半は「この物語は、壮大な物語の序章(入り口)に過ぎないのですよ」と語ることに費やされた、言うなれば「壮大な予告編」でしかない。
無論、それを「序章」と呼んでもいいのだが、いずれにしろ「物語作品」としては「完全」でもなければ「完成」してもいないのである。
言い換えれば、「序章としては、なかなかよく出来ている」とか「予告編としては、よく出来ている」という感じの、「思わせぶりなだけの作品」なのだ。
したがって、この「予告編としての序章」の背後に(入り口の奥に)「壮大な物語」(奥深い世界)を見る(幻視する)ことで、本作を「過大評価」する人も少なくはなかろうが、それは「予告編」と「本編」の違いを錯覚させられている人の、誤った評価だと言えるだろう。
「予告編ではあれほど面白そうだったのに、実際に本編を見てみると、それほどのものではなかったのでガッカリした」なんてことは、よくある話なのだから、本編『クラユカバ』という作品の「基本性格」を正しく見抜いた者には、本作は「よく出来た予告編」の域を出ない「こじんまりとした作品」でしかあり得ない。最初から「壮大な物語」など語る気のない、あくまでも、思わせぶりに観客の気を惹くための、「予告編(思わせぶり)」に過ぎないのである。

その証拠に、次作『クラメルカガリ』も、「スピンオフ作品」でしかないし、この先、この「シリーズ」作品が作られたとしても、このような「断片世界」を描いたものばかりで、「壮大な世界設定そのものと対峙するような、壮大な作品」が作られることはないと、そう断じて良いだろう。
観客としての「群盲」は、永遠に「象」の一部を撫でさすって、妄想を膨らまさせてもらえるだけで、実態(全体像をそのまま)に見せられることはないのである。

言うなれば、壮大な迷路の中央に高く聳える、謎めいた「黒い塔」を遠望しながら、観客たちは、いつまでも、その裾野の「迷路」をぐるぐると歩かされるばかりで、いっかな、その世界の中心たるべき「塔」に到達することもなければ、その「迷宮世界」の謎を解いて「決着をつける」こともできない。
観客たちは、「いつかあの塔にたどり着け、そこでは、思いもかけない真相が明らかにされるのだろう」という「期待」を抱かされたまま、いつまでも「塔の裾野の迷路」をぐるぐると歩き回らされたあげく、そのうち「この迷路自体が楽しいのだから、それでいいじゃないか」というふうに「勘違い(自己洗脳)」させられてしまうのである。
そうした「本作の本質」を象徴する言葉が、荘太郎が失踪した父の残した言葉として思い出す『クラガリに曳かれるな』という、警告の言葉である。


「クラガリ」とは、この作品世界のキモをなす「底なしの地下世界」のことだ。
そこではあらゆる「正体不明の悪」が蠢いていて、その「クラガリの謎」を解き明かそうとした者は、逆にクラガリに引き込まれて、身を滅ぼしてしまう。ちょうど、先代の「探偵」であった「荘太郎の父」が、妻子を残して失踪してしまったように。

だが、ここまでの記述でもおわかりだろうが、私は、この謎めいた世界の「全貌」が、塚原監督によって明示的に描かれることは、永遠にない、とそう見ている。
「思わせぶり」は、どこまでも「思わせぶり」だから「面白そう」なのであって、ネタを割ってしまったら、その途端にその「夢は覚めてしまう」ものだからだ。
その意味で、「クラガリに曳かれるな」という言葉は、「両義的」なのだ。
この言葉は、「その危険な暗がりの奥にこそ、すべての真相が隠されているのだ」ということを、「物語内」的には「暗示」しているのだが、実際には、つまり「物語外」的には「暗がりの中には何もない。だから、暗がりに惹かれても、馬鹿を見るだけだよ」という、人を食った、真逆な警告のメッセージが込められてもいる。
「クラガリの奥は空っぽ」であり、「この迷路は、あの塔へとは続いていない」。
「クラガリの奥に、真相がある」とか「この迷路は、終着点であるあの黒い塔に続いている」などと期待した人は、カフカの『城』の主人公である「K」と同様、いつまでたっても、そこへはたどり着けず、その手前でウロウロさせられることになる。

また、仮に、荘太郎なり「K」なりが、「目的地」に辿り着いたとすれば、それはきっと「失望させられる現実」でしかないだろう。
また、それを知っているからこそ、塚原監督は「クラガリに曳かれるな」というメッセージをくり返し発しつつ、決して「クラガリ」の奥に光を当てて、そのすべてを描くようなことはしないはずなのだ。それをしてしまえば、「幽霊の正体見たり枯れ尾花」同様の、「失望」を招くことにしかならないことを、重々承知しているからである。

○ ○ ○
そんなわけで、実際の『クラユカバ』と『クラメルカガリ』が、どのような作品なのかというと、それは「ビジュアル的には優れた佳作」だとまでは言えるだろう。
そして、その特徴的な作風は、「レトロフューチャー」や「スチームパンク」を基盤としたものだというのも、「Wikipedia」の紹介を待つまでもなく、一見して明らかである。
「スチームパンク」というジャンルをある程度ご存じの方ならお分かりだろうが、このジャンルは「世界観のオリジナル性」よりも「ビジュアルイメージ」優先の「オシャレな未来世界」を描いたもの(像)である。
「蒸気機関がすべての動力となり、それによって稼働するコンピュータや人工知能などによって運営された未来世界」とでも言えようか。
つまり、「古いものと新しいものの奇形的一体化によって生まれた、懐かしいが新しい世界」を描いているのである。

だから、「スチームパンク」というのは、その自覚の有無に関わりなく「レトロフューチャー」の一種なのだ。
「スチームパンク」や「レトロフューチャー」は、SF作品が従来描いてきた「無機質な未来」の「非情性」を排した、どこか「懐かしい」世界を描いているのである。
したがって、塚原監督のオリジナル作品である『クラユカバ』の主人公である荘太郎の職業が、「探偵」だというのも、そうした文脈から生まれてきたものであり、要は「レトロ・オシャレ」なイメージの産物なのである。

ただ、ここで、「ミステリファン」である私が、是非とも指摘しておかなければならないのは、スピンアウト作品である『クラメルカガリ』には無くて、塚原監督の完全オリジナル作品である『クラユカバ』にはある「探偵趣味」とは、明らかに「京極夏彦」の影響下にあるものであり、さらに限定すれば、京極夏彦のデビュー作である『姑獲鳥の夏』の影響を色濃く受けた作品だ、という点である。

ネタバラシになるので、詳しくは書かないが、探偵小説である『姑獲鳥の夏』という作品のキモは、「自己暗示」によって「記憶が隠蔽」され「目の前にあるものまで見えなくなってしまう」という状況にある。
要は、その人物は「そのおぞましい現実を見たくない」のである。
だからこそ、記憶を改変して「見たものを見なかったことにし、目の前にあるものを見えていないことにする」のだ。その現実が、自分にとって、あまりにも受け入れがたいものであるからこそ、心理学的な「防衛規制」によって、その「暗い現実」に直面することから、自身の心を守るのだ。曰く、一一心の暗がりに惹かれるな。
○ ○ ○
しかしながら、こうした本来ならば「重くて暗い」題材を扱いながら、『クラユカバ』の場合、所詮はこれも「オシャレな道具立てのひとつ」にしかなっていない。
『姑獲鳥の夏』のような、最終的な「過酷な現実の突きつけ」にいたる「不穏さ」は、ほとんど無いに等しい。あっても「オシャレ(な香水)として匂わせる」程度のものなのである。
『姑獲鳥の夏』は「心の暗がりの謎を暴く」作品だったけれど、『クラユカバ』は「知の暗がりに迷って、疑心暗鬼を見る楽しみを与える」作品にすぎない。だから「ぬるい」。
言い換えれば、塚原監督は、観客たちに対して「暗示」をかけているのである。
「クラガリの奥には、とんでもない真相が潜んでいますよ。だから、覚悟のない者は、決してクラガリに踏み込んではいけない。クラガリに曳かれ(惹かれ・引かれ)てはならない」。
一一「クラガリに曳かれるな」とは、そういう意味であり、真相を明かす(暴く)という「その気があるのか無いのかよくわからない」思わせぶりであり、言うなれば(落ちる気があるのかないのかわからない、思わせぶりな)「悪女の手管」のたぐいなのである(例えば、『ルパン三世』の峰不二子の、それみたいなもの)。

そんなわけで、この『クラユカバ』の世界というのは、いかにも「日本的」な「空虚な中心(中空)をめぐる、壮大な世界設定」の世界であり、「天皇家の先祖をたどっていけば、フィクションとしての神話の世界に行き着いてしまう」というような「底の抜けた(根拠不在の)世界」なのである。
だからこそ、「クラガリ」は、その「全体像」が描かれることはないし、描くつもりもない。「クラガリ」の奥には、「恐るべき真相」があるのではなく、「底の抜けた空虚」があるだけだからだ。
○ ○ ○
しかし、こうした「実のなさ」は、塚原監督の「趣味」にも、あらかじめ明らかだ。
「スチームパンク」や「レトロフューチャー」が、しばしば「オシャレな表面(奥行きを持たない看板)」でしかなかったというだけではなく、塚原監督自身、自分の好きな「作風」を次のように語っているのである。
『幼少期より古い空想科学映画、主に昭和ゴジラシリーズ(具体的な作品名としては「キングコング対ゴジラ」や「ゴジラ・エビラ・モスラ 南海の大決闘」、「ゴジラ対ヘドラ」を挙げている)など東宝特撮映画を見ていた。その流れの中で無責任シリーズ、若大将シリーズ、社長シリーズなどの「映画なんだけど大作感のない、ぬるい感じ」の作品が好きになったと語っている。
影響を受けた人物に古澤憲吾、福田純、坪島孝、そして岡本喜八といった昭和30~40年代に東宝で活躍した映画監督を挙げている。岡本喜八監督作品については学生の頃に「独立愚連隊」シリーズに関心を持ち「いつかこういう映画を作りたい」と思ったなど特に影響を受けている。』
(Wikipedia「塚原重義」)
つまり、塚原監督は、基本的には「痛快な娯楽作品」が好きなのであって、「テーマ性の強い重厚な作品」を好む人ではない。言い換えれば、「クラガリの奥に潜む、暗い真相」みたいなものを描きたい人ではないのだ。

では、どうして京極夏彦の『姑獲鳥の夏』を参照したのかといえば、それが「オシャレ」だと思ったからであって、その内容的な「重厚さ」にまで惹かれたわけではなかったのである。
『姑獲鳥の夏』に始まる「京極堂シリーズ(妖怪シリーズ・百鬼夜行シリーズ)」の主人公・中禅寺秋彦は、古本屋「京極堂」の主で神主でもある、作品内の位置づけとしては「名探偵」である。
そして、その彼の決め台詞は、
『この世に、不思議なものなの何もないのだよ』
つまり、このシリーズが「妖怪シリーズ」と呼ばれるのは、その個々の作品で描かれる「事件」が、まるで「妖怪」に憑かれた者による犯行のように見えるからだ。
言い換えれば、その犯人の「心の歪み」を説明するのに「妖怪の比喩」を用いるのが有効であり、その捉えがたい「心の歪み」に「名前」を与えることで、その「心の歪み」を「名前」という依代ごと払い落とすのだ。
つまり、ここでの「妖怪」とは、あくまでも「比喩」であって、「妖怪が実在する」という話ではないのである。
当然、中禅寺秋彦の言う『この世に、不思議なものなの何もないのだよ』とは、「この世に、妖怪などというものは存在しない。そればかりではなく、宗教も含めて、それらはすべて、理性の言葉で説明できるものでしかないんだよ」ということなのだ。
したがって、名探偵である中禅寺秋彦が、物語の最後で行う「謎解き」が、「憑き物落とし」と呼ばれるのも、人間の陥りやすい「錯誤」とそれへの「妄執」を、解体し、祓い落とす作業だからである。
つまり、本作『クラユカバ』が観客に行ったのは、京極夏彦が「京極堂シリーズ」で行った「憑き物落とし=暗示はずし=洗脳はずし」とは真逆の、「暗示=催眠」そのものなのである。
「クラガリに曳かれるな」という言葉によって、逆に、クラガリの奥に「何か途方もないものが隠されている」という暗示をかけることで、「幻覚」を見せるためになされた、それは「心理誘導」なのだ。

○ ○ ○
だから、本作『クラユカバ』や、そこで「予告」された「クラユカバ・サーガ的な壮大な世界」が「暗闇の奥に存在する」と思った人は、その暗示にかかって、まんまと「疑心暗鬼」を見せられた、ということでしかない。
言い換えれば、『クラユカバ』の奥に「特別なもの」など、なにも潜んではいない。
そこに「妖怪」の存在を見てしまうのは、「君が、猿アタマだからだよ」ということにしかならないのだ。
猿くん、そろそろ目を覚ましたまえ。
(2024年5月24日)
○ ○ ○
● ● ●
○ ○ ○
○ ○ ○
○ ○ ○
・
○ ○ ○
・
○ ○ ○
