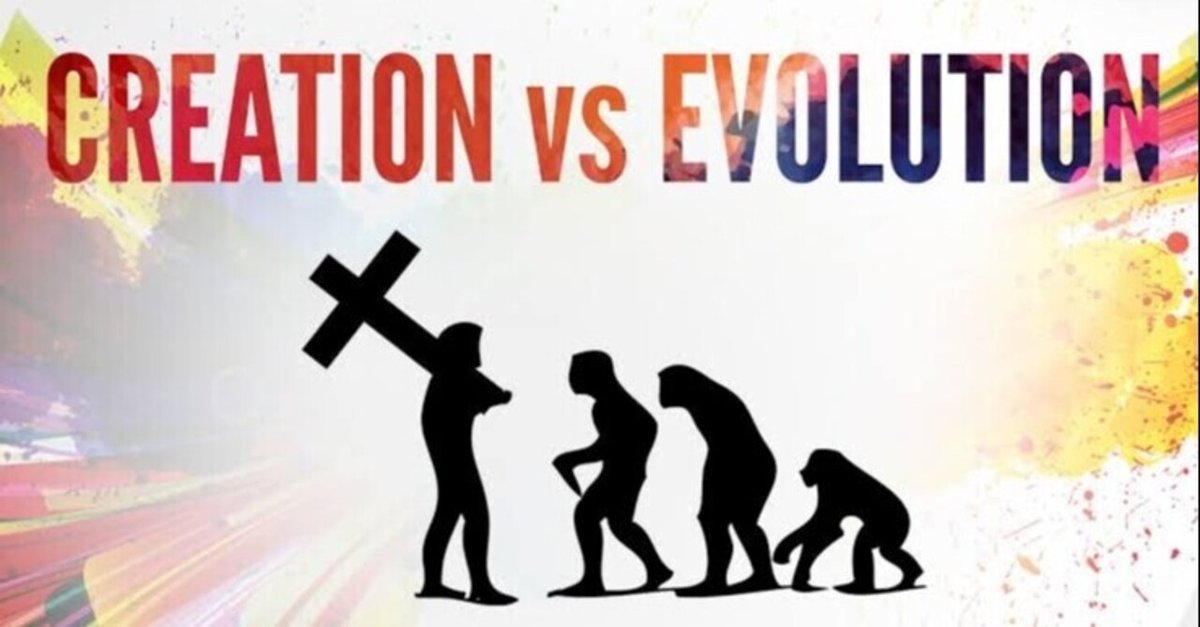
三井誠 『ルポ 人は科学が苦手 アメリカ 「科学不信」の現場から 』 : ノブレス・ オブリージュ
書評:三井誠『ルポ 人は科学が苦手 アメリカ「科学不信」の現場から 』(光文社新書)
本書のテーマは、〈科学〉と〈政治〉と〈宗教〉の問題である。
さらに言うと、〈科学〉が、〈政治〉や〈宗教〉と、うまくいっていない現状の問題である。
本書は、科学先進国であるアメリカにおいて、意外にも科学が大衆的な信用を十二分に得られていない現実があり、それがトランプ政権の保守的政策によって、さらに悪化しているという現状への危機感を出発点として、「なぜ人は科学を軽んじることができるのか」と問い、さらに「科学を信用しない人たちに、科学を正しく理解してもらうには、どうしたら良いのか」といった解決策の模索にいたるまでの内容を蔵していて、そのスタンスは思弁的・抽象的なものではなく、徹底したリアリズムに立脚したものだと言えよう。

○ ○ ○
〈科学〉と〈政治〉と〈宗教〉のからみあった問題というのは、まさしく私が近年とりくんでいるテーマであった。
当初は、別々の問題意識から興味を持ったテーマだが、それが近年において、深く繋がってきたのだ。
「宗教」への関心は、私が幼い頃、家族とともに創価学会に入信し、やがて公明党・創価学会がアメリカの「イラク戦争」を支持したことにより、私が創価学会を批判し辞めたという経緯に発する。
つまり、もともと宗教に興味があったのではなく、なんとなくやっていたのが、「宗教と戦争」というリアルな矛盾に直面して、初めて「宗教とは何なのか」というテーマにぶち当たったのだ。
しかし、それでも、その時はまだ「政治」については、さして興味がなかった。だが、「9.11」(アメリカ同時多発テロ事件)を同時代に目の当たりにして衝撃を受け、それについて書かれたノーム・チョムスキーの『アメリカに報復する資格はない! 9・11』を読むにいたって、「政治」というものが無視できない現実として、私個人にも迫ってきたのである。
その後、地味に持続していた宗教への興味を、強く喚起したのが、あの「オウム真理教事件」だった。
「やはり、宗教は好き嫌いで済ませられない、重大な何かである」という意識を強め、さらに近年、さる切っ掛けから、宗教問題を独学する上でのテーマを「キリスト教」にしぼったことで、私の宗教研究は輪郭をハッキリさせたのである。
キリスト教を宗教研究のテーマに選んだのは、キリスト教2000年の歴史のなかで、多くの超一流知識人がキリスト教に帰依していたという事実と、その彼らが「神の実在」という、およそ信じられないことについて、営々と理論を紡いできたという事実があったからである。
つまり、彼らは、庶民のように漠然と「ありがたい」と信仰していたのではない。彼らは知識人故に、無神論的な批判に対抗する理論構築をしてきたはずなのだから、それを知れば、彼らの理屈も理解できるし、反論も可能となる。つまり、論理的な宗教批判が可能となるのではないかと考えたから、キリスト教を研究対象として選んだのだ(だから、比喩的で哲学的な、抜け道の多い、仏教ではダメなのだ)。
そしてさらに、宗教に対立するものとしての「科学」も、おのずと私の視野に入ってきた。
科学に積極的な興味があったのではなく、あくまでも宗教を批判する立場の代表として、科学の考え方を明確にする必要があったのだ。
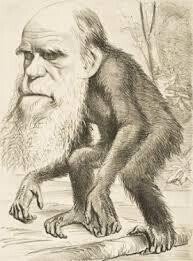
(※ 聖書に書かれた創造説を否定するものとして、米国ではいまだに、ダーウィンの「進化論」を認めない保守派キリスト教徒が少なくない)
以上、こうした経緯から、近年の私の中では〈宗教〉〈政治〉〈科学〉という三大要素が、からみあったかたちでテーマ化されることになった。どのテーマを考える場合でも、どこかで必ず他の要素がからんできて、それらが「なにか本質的なところでつながっている」という事実を、私は実感せずにはいられなかった。
では、〈科学と政治と宗教の結節点〉とは何か。
それは〈心=理性と感情〉である。
私の、宗教に対する最初の興味は「なぜ人は、宗教などというものを信じられるのか(神や仏の存在を、本気で信じられるのか)?」というものだった。
例えばそれは「教養のない庶民ならばいざ知らず、歴史に名を残すような超一流の知識人が、どうしてキリスト教の信者でいられたのか?」という疑問であった。

(※ 1925年、テネシー州デイトンで行われた、進化論教育の是非を問う「スコープス裁判」をめぐる風景)
しかし、そうした「非理性性」への疑問は、近年、なにも「宗教」の問題に限定されるものではなくなってきた。
例えば「在特会の会員たちは、どうして、あんな見苦しいヘイトスピーチを平然と吐きちらせるのか?」「どうして、どこの国にも『我が国が世界一すばらしい』と単細胞にも思いこめる愛国主義者がいるのか?」「なぜ、皇室はアマテラスという神に始まる万世一系の家系だなどという、おとぎ話を信じられる人がいるのか?」「なぜ、キリスト教徒は、イエスが処刑後三日目に肉体を持って復活し、やがてその肉体を持って天に昇ったとか、(カトリックは)聖母マリアは例外的に原罪を免れて生まれ、処女懐胎してイエスを産み、肉体を持ったまま昇天したなどという、ご都合主義的な与太話を信じられるのか?」「なぜ、アメリカ人の多くが、トランプみたいな、見るからにデタラメで卑しい男を支持できるのか?」「なぜ日本国民の多くは、加計学園問題を始めとした、政治家の横暴と欺瞞を黙認し得るのか?」等々、信じられないような「非理性的な態度」というのは、なにも宗教信者に限られたものではないというのが、近年ますますハッキリとしてきたのである。

(トランプ米国大統領)
○ ○ ○
こうした「謎」に対し「人はなぜ、科学的思考を拒絶したりするのか?」という観点から真相に迫ったのが本書であり、本書の回答は、きわめて科学的な「人の脳は、人類史の最近の数秒にしかあたらない科学的思考にいまだ馴染まず、石器人的な本能的で直観的思考に縛られたままだからである」という「脳進化心理学」的なものとなっている。
この回答自体は、脳科学の初歩をかじった私には、特別目新しいものではなかった。すでに「脳科学」は「宗教を脅かす最新科学」として、宗教界からも注目されていたので、私もチェックしていたからだ。
しかし、本書のオリジナリティーは、こうした「謎解き」に満足することなく、それでは、そうした「科学を信用しない人たちに、科学を正しく理解してもらうには、どうしたら良いのか」というところにまで踏み込んで、その具体策まで検討している点だと言えるだろう。
さて、正直に言えば、これまで私は、そこまで考えることはしなかった。
私の興味は、あくまでも哲学的で知的な「謎解き」にあって、「問題の解決」にはなかったからである。
「謎解き」は自分の頭のなかで出来るけれども、「問題の解決」はイヤでも「他者への働きかけ」をしなくてはならない。だが、そんな面倒なことは、真っ平ごめんだ。どうしようもない馬鹿どもを説得するなんて徒労に、大切な自分の時間を注ぎ込みたくはない。この先世界がどうなろうと、ひとまず私はあと30年ほどで死んでいなくなるんだし、子供を遺すわけでもないので、あとは子孫に責任を持たねばならない人たちにお任せする、というのが偽らざるホンネだったからである。
しかし、本書最終章の末尾に示された、著者の正論には、さすがの私も少なからず心動かされ反省させられた。
『 会場から、「政治的な二極化が進むなか、お互いの理解を助けるコミュニケーションはどうあるべきなのか」と質問されると、アルダさんはちょっと考え込むように一呼吸置いてから話しはじめた。「私は答えを知りません。ただ、自分の経験から言えることは、相手を愚かだとさげすんだり、無知だと責めたりするようなやり方はよくないということです」。そして、最後に付け加えた。
「お互いに敬意を持たなければ、私たちはいったい、どこに行けるというのですか」
お互いに敬意を持つことから始めて、少しでもお互いの理解が広がれば、と願いたい。科学が苦手な私たち(※ 人間)が科学と付き合う時にも、そこにかかわる人たちへの敬意がまず一歩になるのだろう。
反対している人たちは何を心配しているのか。
自分たちはただ事実を押し付けるだけになっていないか。
お互いの心を結び付ける何かを見つけ出せないか。
科学を巡るコミュニケーションでも、気持ちを大事にすることで誤解を解きほぐす道が開けるのかもしれない。簡単ではないが、そこに希望を託し、本書の締めくくりとしたい。』(P230〜231)
著者も言うとおり、これは『簡単ではない』。
奇麗事ではなく、ホンネで言うならば「そんなことは不可能だ」と言いたくなるだろう。
ことに「ネトウヨ」などとの議論を試みたことのなる者なら、あるいは「貴方がその汚い言葉を吐きかけられる側の立場だったら、どう感じるだろうか」と問いかけ、説得を試みたことのある人なら、彼らのような凝り固まった「妄信者」たちを説得することが、いかに困難かということを、嫌というほど知っているだろう。だからこそ、彼らに対する多くの人は、諦めの気持ちから、彼らを憎悪し対抗心を滾らせるだけになってしまってもいるのだし、それはある意味で仕方のないことなのだ。
しかし、もしも我々が、知的にも人間的にも「彼らより優れており、ものも見えている」という自負を持つのであれば、手を差し伸べる役割は、我々の方に与えられた使命だとも言えるのではないだろうか。
もちろん、これは「上から目線の物言い」であることは認めよう。
だが、それは「選ばれた者の義務」つまり「ノブレス・オブリージュ」だとは言えまいか。
すくなくとも私自身はそう思うので、簡単なことではないし、腹の立つことばかりだろうが、それでも「彼ら」に手を差し伸べる努力をしたいと思ったのである。
「彼ら」は『何を心配』して、あのようにいきり立っているのかと考え、その不安に寄り添う努力が必要だと思ったのだ。
よく言うことだが「相手のレベルまで下がってはいけない」。
そうではなく、誇りある者ならば、こちらから「目線」を下げてやらなければならないのだと、反省させられた。
これを「傲慢」だと言う人も多いだろう。だが、諦めてしまい、ただ憎むことを自分に許すよりは、よほどマシなのではないかと、私にはそう思えるのである。
初出:2019年6月14日「Amazonレビュー」
(2021年10月15日、管理者により削除)
再録:2019年6月15日「アレクセイの花園」
(2022年8月1日、閉鎖により閲覧不能)
○ ○ ○
○ ○ ○
・
○ ○ ○
○ ○ ○
・
○ ○ ○
・
○ ○ ○
・
・
○ ○ ○
・
・
