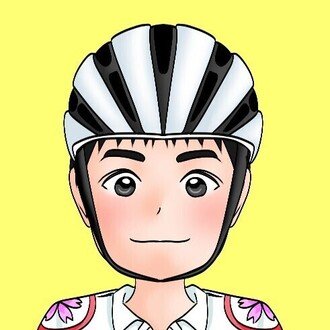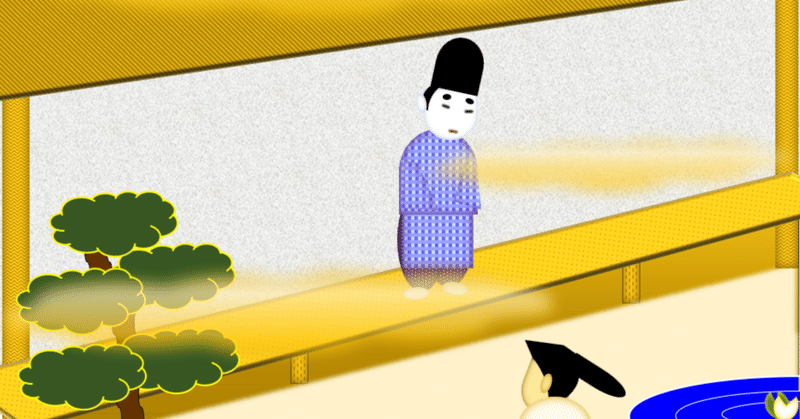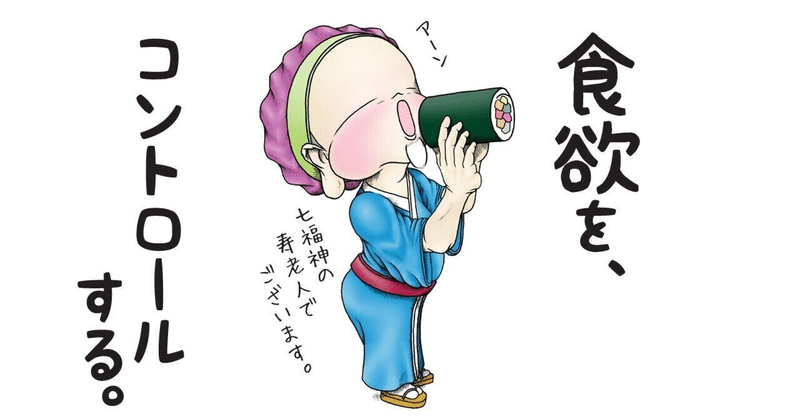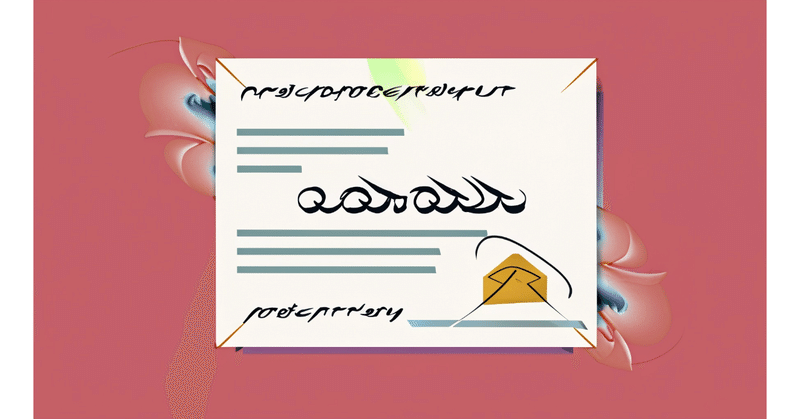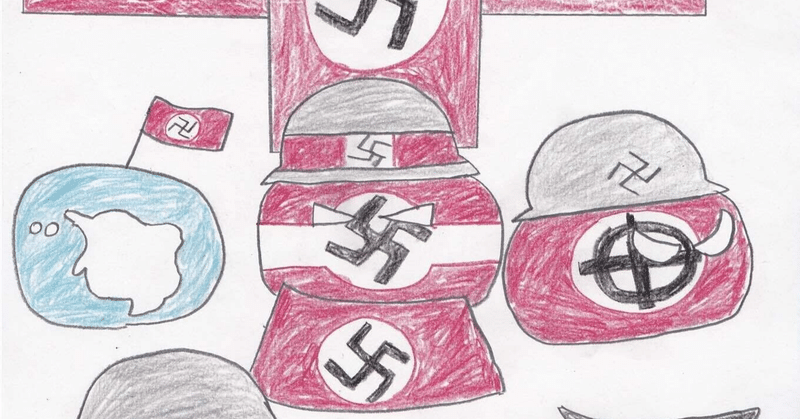#創作大賞2024
DXの思考法を読んで|DXをするための具体的アプローチIX
先日、「コロナショックサバイバル」と「コーポレートトランスフォーメーション」の2冊の本を読んだ。DXを理解しようとして読んだ本なのだが、この2冊には話が飛躍している部分があって、理解が難しいところがあるようなのだ。
その間を埋めるのが本書の「DXの思考法」なのだそうです。本書は1度目は理解できなかった。一つは難解なのと、もう一つはオーディブルで読んだけど、図表がPDF等でまとめられておらず、本を
「コロナショックサバイバル」と「コーポレートトランスフォーメンション 日本の社会を作り変える」の2冊を読んで
最近2冊の本を読みました。以下の本たちです。最近DXが良く言われていて、本当のところはどうなんだろう。それを調べるために読みました。
1冊目:「コロナショックサバイバル」
2冊目:「コーポレートトランスフォーメーション」
この2冊の本は、コロナが発生して世界が大混乱の中で書かれた本です。
1冊目はコロナショックが来てすぐ発売された本のようで、2020年の3月か4月くらいに急いで出版された本
「成瀬は天下を取りにいく」を読んで|西武大津店を舞台にした好奇心旺盛な中学生の地域密着物語
※アイキャッチ画像は、建築パース様より引用させていただきました
小説を読みました。題名は「成瀬は天下を取りにいく」です。作者は宮島未菜さんという方で現在40歳の主婦をされている方のようだ。
宮島さんは、今から3年前に新潮社が主催する女による女のためのR-18文学賞において2021年の大賞・読者賞・友近賞を受賞したころからデビューとなった。
R-18文学賞|R指定なの?個人的に女による女のため
「ザイム真理教ーそれは信者8000万人の巨大カルト」を読んで|目に見えるものは氷山の一角でありオトリとも言える
1冊本を読みました。タイトルは「ザイム真理教」です。もしかしたら言葉だけでも聞いたことがあるかもしれません。大ヒットした本ですので内容まで知っている方も多いかもしれません。
作者はご存じ森永卓郎さんです。最初は森永卓郎さんの「書いてはいけないー日本経済墜落の真相」という本がおススメにでてきたんですね。
その中では、絶対書くことができないタブーが日本には3つあると書かれていました。そのひとつが本