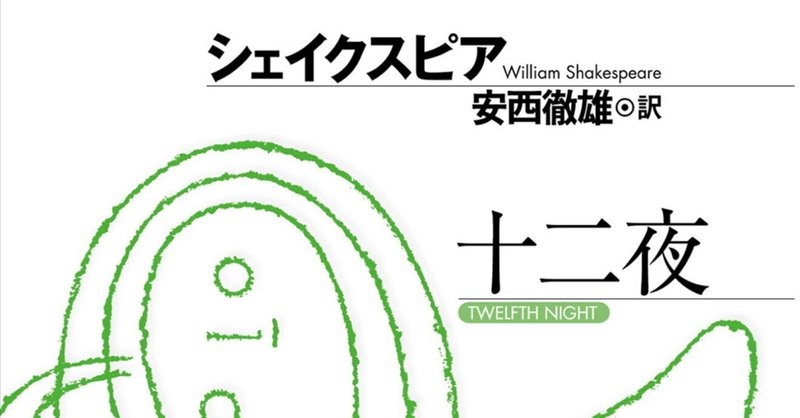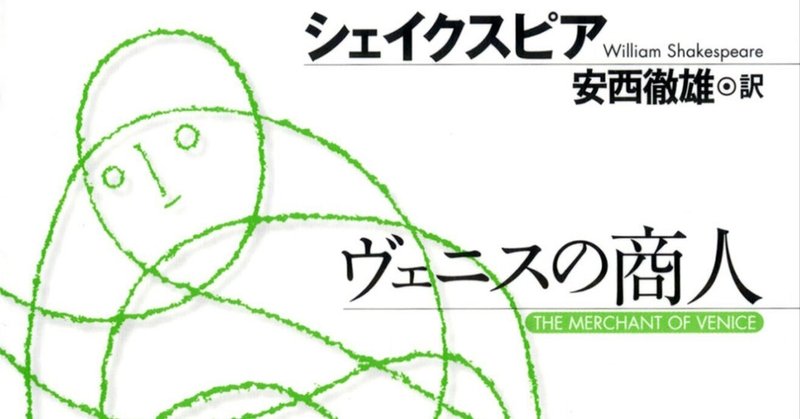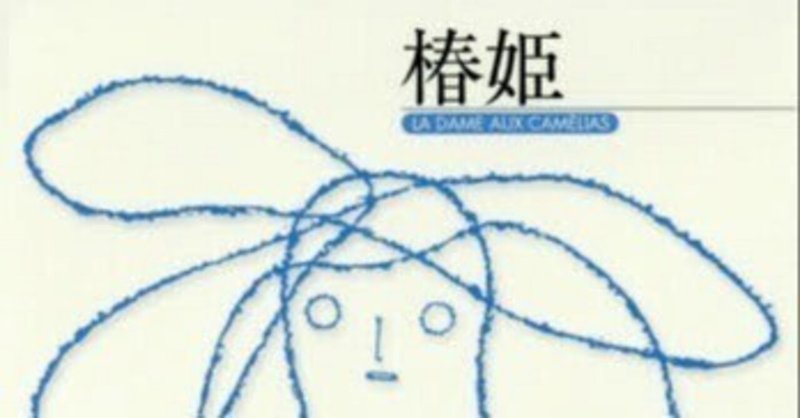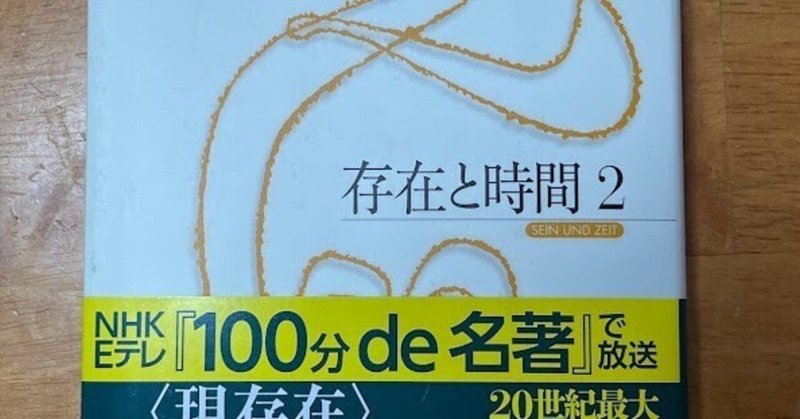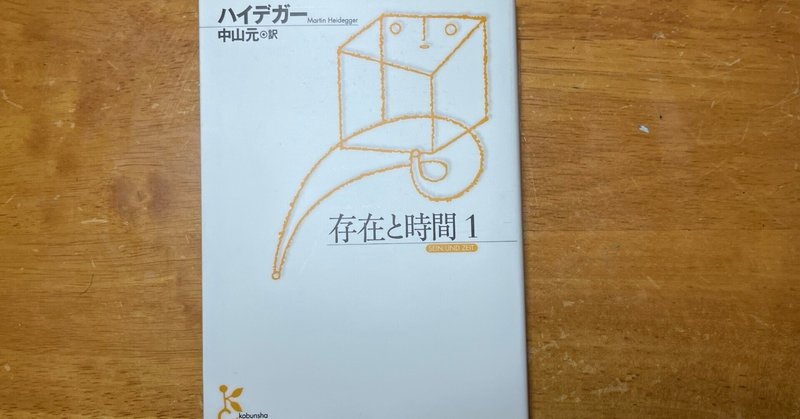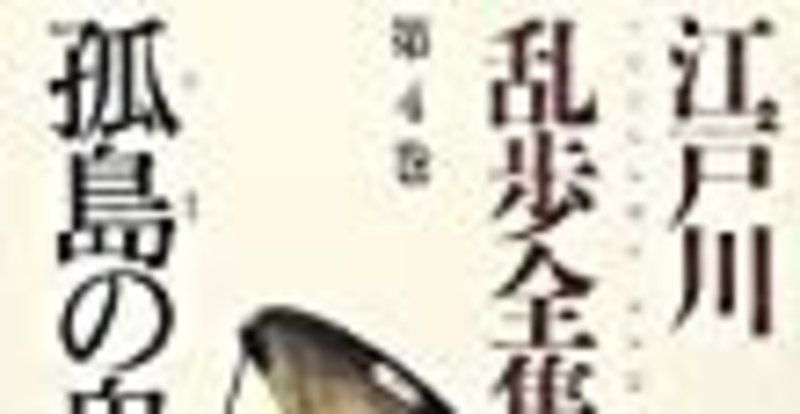#光文社
ハイデガー「存在と時間5」(1927年)
人間は普段、日常生活において現実世界に頽落してしまっている。つまり、人間本来の姿ではなくなってしまっている。
それが、不安によって、本来の自分が見えるというのがハイデガー( 1889年9月26日 - 1976年5月26日)の主張。
フロイト(1856年5月6日 - 1939年9月23日)も、不安という現象が人間の精神を深いところで刻印していると考えていた。同時代の人がこういうことを考えるのは面白い
シェイクスピア「十二夜」(1601年から1602年)
「十二夜」という言葉の意味については調べてみたがよくわからなかった。たぶんそんなに難しくはないと思うが、なじみがない。
主人公はヴァイオラという女性。船が難破して双子の兄セバスチャンと生き別れる。お互いに、兄妹が死んだと嘆くが、実は両方とも生き延びている。
そんなことは知らずに、ヴァイオラはとにかく陸に戻り、男装して、オーシーノ伯爵に仕える。伯爵はオリヴィアという女性に恋しているのだが、色よい回
ハイデガー「存在と時間4」(1927年)
人間の根源について考察する本書について、根源よりも、哲学の基本がわかっていない自分が読む。
読んでいて、なんとなくわかった気になる部分もあるけれど、大半の部分は思い返そうすると、理解していなかったことに気づく。
「気分」「世間話」「好奇心」「まなざし」。慣れ親しんだ用語も、哲学において語られると敷居が高くなる。
それでも懇切丁寧な解説の助けを借りて、なんとなく、ざっくりと、理解した気になる。
シェイクスピア「ヴェニスの商人」(1594年から1597年)
本編の面白さもさることながら、解説も含めて読むと、シェイクスピア作品がどうして現代にいたるまでの400年という時の流れで生き残ってきたのか、というのがなんとなく理解できた気がしてよかった。
タイトルになっている「ヴェニスの商人」はアントニオという男のこと。
彼は、友人のバサーニオのために借金をする。金を貸してくれたのは、ユダヤ人の金貸しであるシャイロック。借金をする際に、返せなかったら、自分の肉
ハイデガー「存在と時間3」(1927年)
「存在と時間」をようやく3巻まで読み終えた。
哲学に関してはちびちび読んではいるけれど、ズブの素人なので、というエクスキューズをしないと読書感想文も書けないくらい難しい。
という前提のもとで自分の理解(もしくは誤解)を書く。
3巻を読んでいて印象に残ったのは、過去の哲学者たちの考えていたことが、ハイデガーとしては納得のいかないものであったということ。特に3巻においては、デカルトの哲学に対する批判
「存在と時間1」(1927年)
非常に難解だが、おさえておくべき本だと感じた。
正直、よくわからないので、もやっとした感想になる。
ハイデガーが問うているのは、現存在とはなにか、ということのようだ。
現存在とは我々人間のことだ。ギリシア時代の哲学者たち。ソクラテス・プラトン・アリストテレスはこの現存在について考えていたようだが、時代が流れるにつれて忘却、もしくは自明のものとされてしまい、形骸化していた。デカルトとカントはこの問