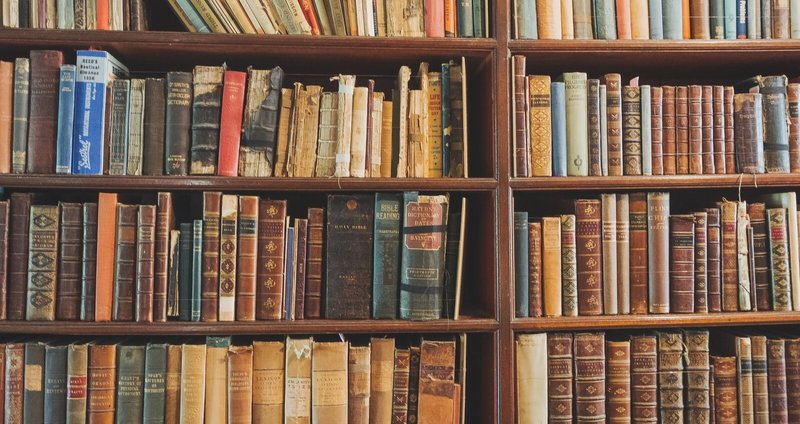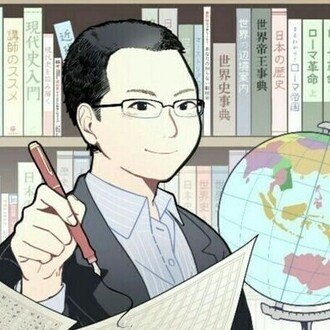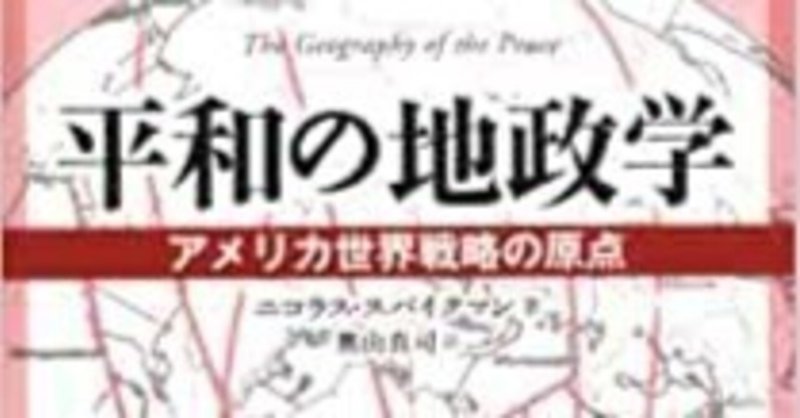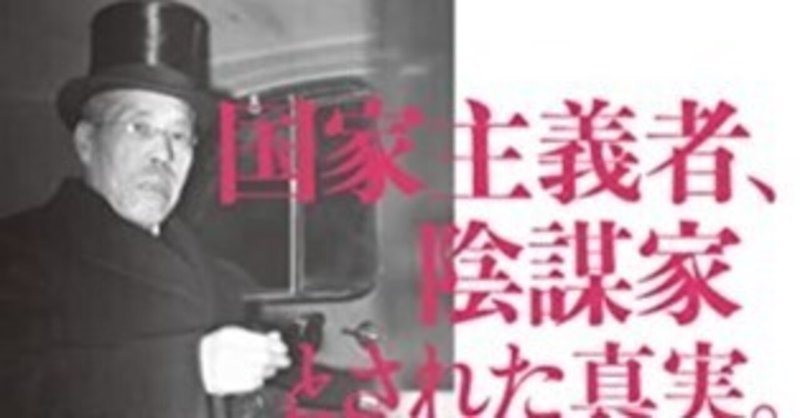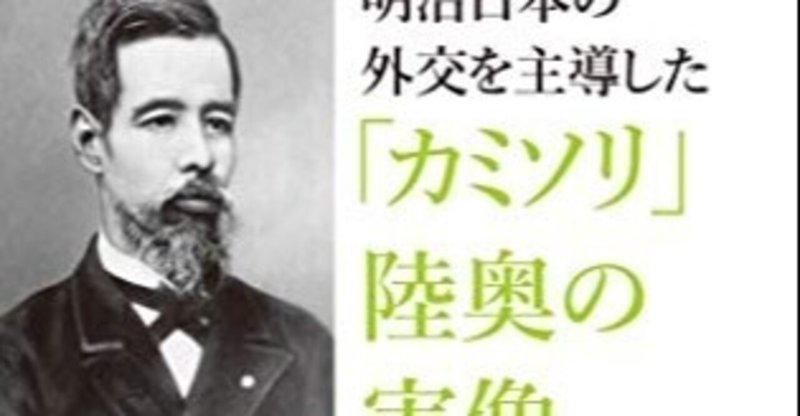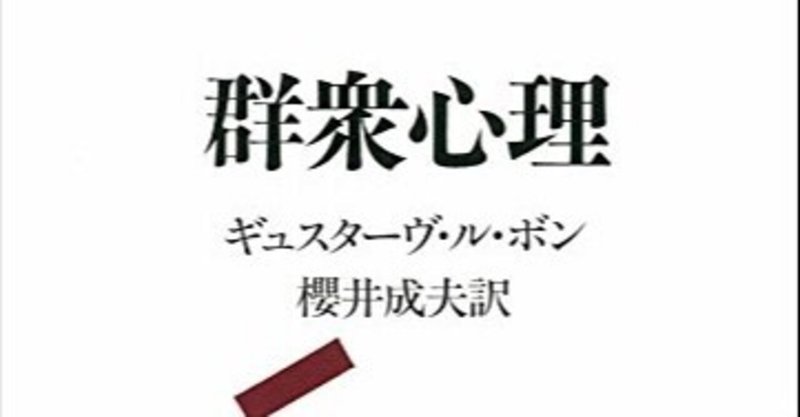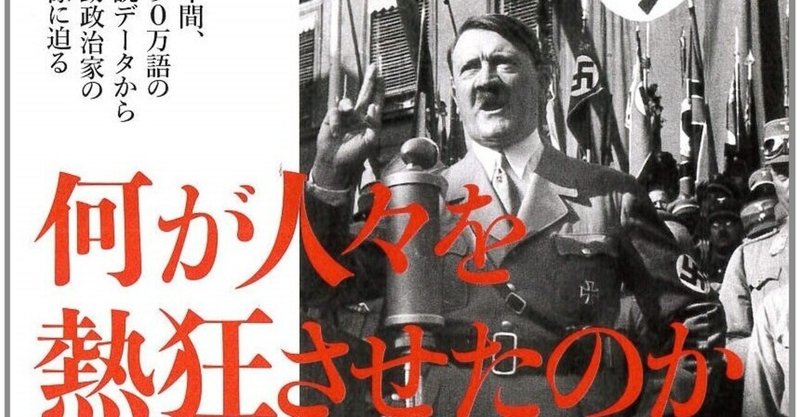#近現代史
文学からパレスチナ問題を知る④~「ハイファに戻って」
前回はこちら。
パレスチナを代表する作家ガッサーン・カナファーニーを紹介する本連載は、今回が最後です。最終回は、1969年発表の「ハイファに戻って」を取り上げます。
作品を紹介する前に、前提となる知識を説明しておきましょう。
「ハイファに戻って」の背景知識 ハイファは、現在のイスラエル北部、地中海に面する港町です。アラブ人(パレスチナ人)の土地でしたが、1948年にイスラエル領となりました
【書評】ニコラス・スパイクマン「平和の地政学」(芙蓉書房出版)
今世紀に入ってブームとなった感のある地政学。今や、書店には「地政学」を冠した本が数多くあります。私も最近、下記の本に関わりました。
手に取りやすい本で入門するのはいいことですが、やはり古典的な書物を読んだ方が本当の教養につながるでしょう。
とはいえ、地政学の祖とされるマハンやマッキンダーの著作は、一般にはハードルが高いように思われます。マハンの文章は非常に難解ですし、マッキンダーの著書は