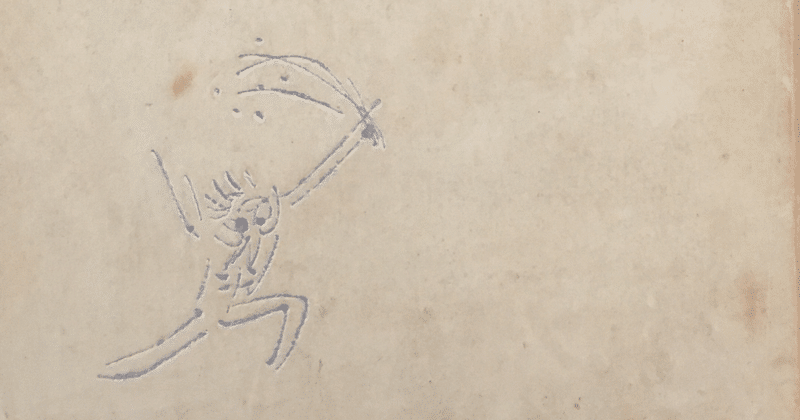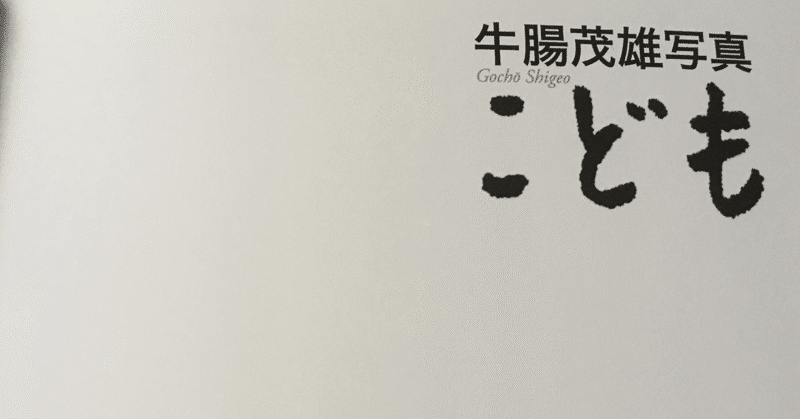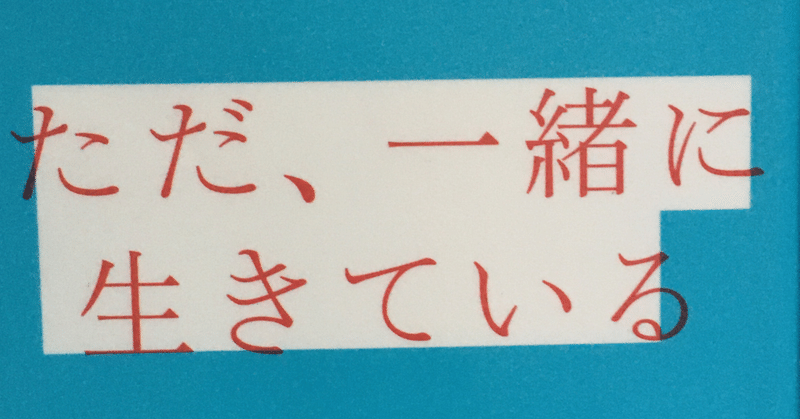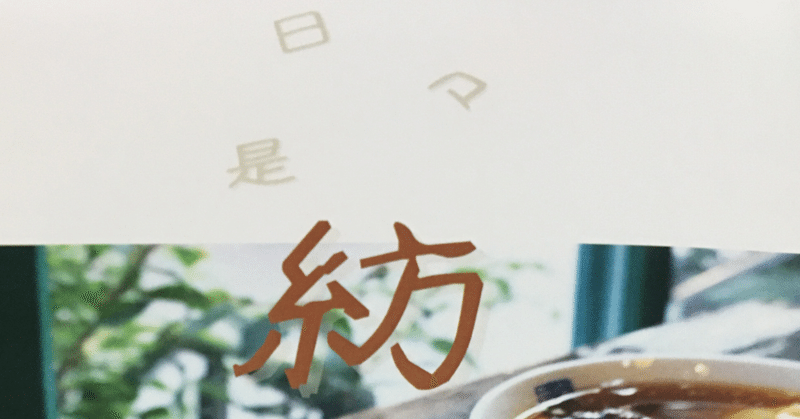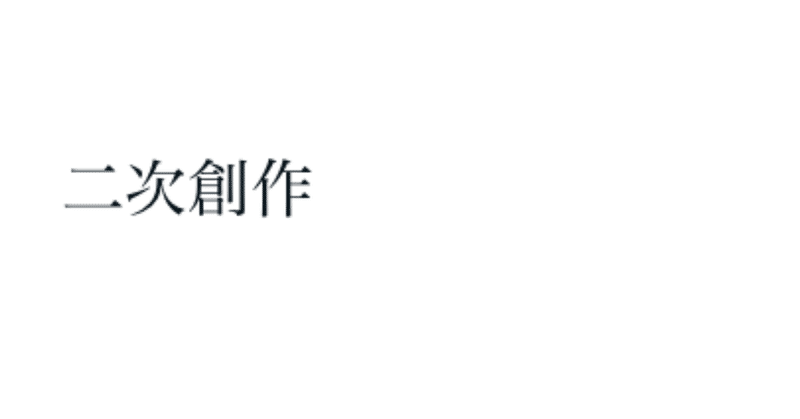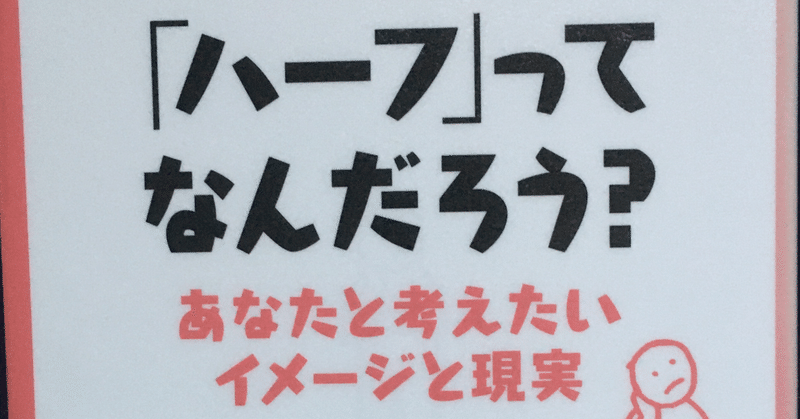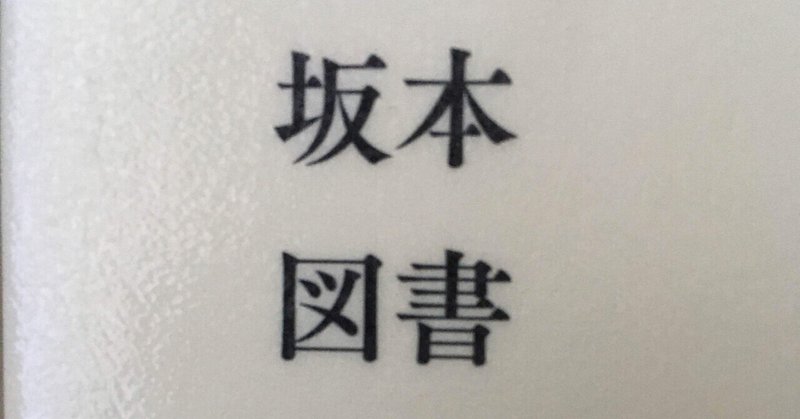2024年1月の記事一覧
ただ、一緒に生きている(坂本美雨) 読書感想文
ただ、一緒に生きている(著:坂本美雨、光文社、2022)
ミュージシャンの坂本美雨さんによる娘さんについての子育てエッセイである。
美雨さんの娘さんは、
そんな娘さんのことを美雨さんは、
と語る。
それにしても子どもはすごい。
例えば、偏見も疑いもなくオープンハートでどんな人も笑顔にしてしまう。
例えば、言葉を知る時の根源的なうれしさを、大人が言語を会得するのとは違う興味そのもので知る
世界と繋がり合えるなら(羽田光夏) 読書感想文
詩集 世界と繋がり合えるなら(著:羽田光夏、読書日和、2020)
この『詩集 世界と繋がり合えるなら』は全盲の詩人でnoterさんの羽田光夏さんの詩集である。
全体的に優しい詩篇で構成されており、あたたかな包み込まれる印象を受けた。どれも日常の一篇を書かれており、親しみやすい詩集であった。
今回は詩集から七篇詩を選んで感想を書いてみたいと思う。
欠片
なんともミステリアスな詩だと思った
読書感想文: Mimínozさんの作品を読んで
注:今回ご紹介するMimínozさんの作品はどれも原作ありきの二次創作のため、その点ご了承ください。
『A3!』(エースリー)という「イケメン役者育成ゲーム」で、リベル・エンタテインメントが提供しているスマホ向けのアプリゲームがあります。
ちなみにこのゲームはアニメ、ノベライズ、コミカライズ、舞台化もしています。
今回、Mimínozさんによる二次創作、このゲーム内に登場する立花いずみ主宰兼総
坂本図書 読書感想文
坂本図書(選書・語り:坂本龍一、バリューブックス・パブリッシング、2023)
音楽家・坂本龍一が高谷史郎と制作していたオペラ『TIME』のことから時間についての記述が多い本である。
坂本が自身の好きな本を紹介していくというコンセプトだが、前述した通り、時間についての本が多い。
例えば夏目漱石では『夢十夜』、九鬼周造では『時間論 他二篇』、アンドレイ・タルコフスキー『Sculpting in