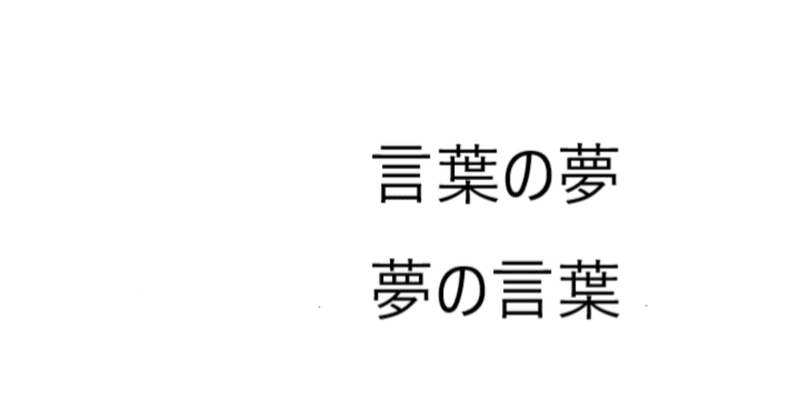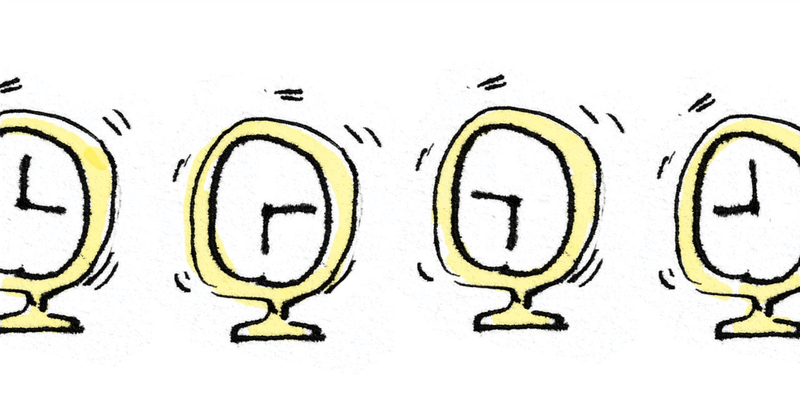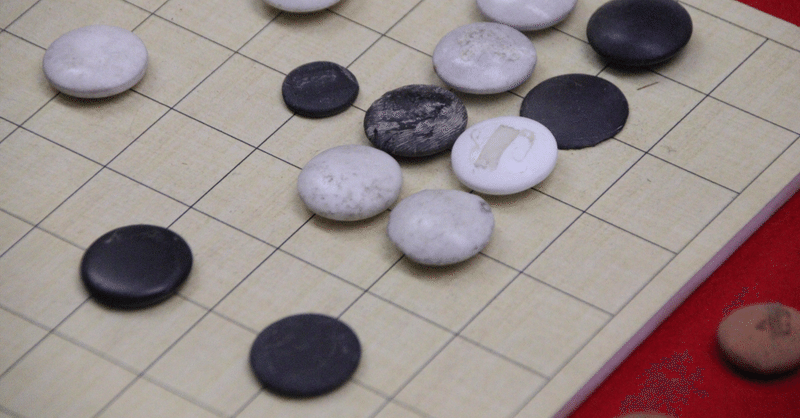2024年2月の記事一覧
わける、はかる、わかる
本記事に収録した「同一視する「自由」、同一視する「不自由」」と「「鏡・時計・文字」という迷路」は、それぞれ加筆をして「鏡、時計、文字」というタイトルで新たな記事にしました。この二つの文章は以下のリンク先でお読みください。ご面倒をおかけします。申し訳ありません。(2024/02/27記)
*
今回の記事は、十部構成です。それぞれの文章は独立したものです。
どの文章も愛着のあるも
長いトンネルを抜けると記号の国であった。(連想で読む・02)
「「国境の長いトンネルを抜けると雪国であった。」(連想で読む・01)」の続きです。
連想を綴る この三文は私にいろいろな連想をさせ、さまざまな記憶を呼びさましてくれます。
・「国境の長いトンネルを抜けると雪国であった。」
約物である句点も入れると二十一文字のセンテンスをめぐっての連想を、前回は書き綴りました。
今回は、「国境の長いトンネルを抜けると雪国であった。夜の底が白くなった。信号