
森有正 『ドストエーフスキー覚書』 : 「神」を担いだ ラスコーリニコフ
書評:森有正『ドストエーフスキー覚書』(ちくま学芸文庫)
今となっては、すっかり読まれなくなった作家の一人であろう。
森有正は「1911年11月30日生」の「1976年10月18日没」の人で、森の名前にあるていど馴染みのある読書家というのは、私よりも年長者になるのではないかと思う。
『 人物
東京府豊多摩郡淀橋町角筈(現在の東京都新宿区西新宿)生まれ。明治時代の政治家森有礼の孫に当たる。父の森明は有礼の三男で、有馬頼寧の異父弟、キリスト教学者、牧師。母は伯爵徳川篤守の娘。祖母寛子は岩倉具視の五女。妹は世界平和アピール七人委員会の委員を務めた関屋綾子。
経歴
生後間もない1913年に洗礼を受けてクリスチャンとなり、6歳からフランス人教師のもとでフランス語、後にラテン語を学んだ。暁星小学校・暁星中学校から東京高等学校 (旧制)を経て1938年に東京帝国大学文学部哲学科を卒業(卒論は『パスカル研究』)、同大学院を経て東京帝国大学の特研生、副手、助手を歴任。傍ら東京女子大学や慶應義塾大学予科などで講師を務め、フランス思想・哲学史を講義した。旧制一高教授を経て、1948年東京大学文学部仏文科助教授に就任する。
第二次世界大戦後、海外留学が再開され、その第一陣として1950年フランスに留学する。デカルト、パスカルの研究をするが、そのままパリに留まり、1952年に東京大学を退職しパリ大学東洋語学校で日本語、日本文化を教えた。教え子に歴史学者のクリスチャン・ポラックなどがいる。
1962年にフランス人女性と再婚するも1972年に離婚。
デカルト、パスカルやリルケ『フィレンツェだより』、哲学者アランなどを訳し、パイプオルガンを演奏しレコードも出している。晩年に哲学的なエッセイを多数執筆し注目を浴び、1968年に『遥かなノートル・ダム』で芸術選奨文部大臣賞を受賞しそれらにより一時日本に帰国し講演・対談や短期の集中講義なども行っている。日本に永住帰国を決め、国際基督教大学に教職が内定していたが、血栓症がもととなり1976年にパリで客死した。墓所は多磨霊園にある。』
(Wikipedia「森有正」)
見てのとおりの「超サラブレッド」で、一般にも「森有正」と言えば、まず「森有礼の孫」であり「クリスチャン作家」であり「フランス在住のエッセイスト」として知られていた。
「哲学者」というのは、フランスで哲学を学んで、大学でそれを講じていた、いわば「職業」のことであり、そちらで専門的な業績を残した「学者」というのとは違う。
あくまでも、「哲学教授」という肩書きは、大学で「哲学を教えている先生(哲学研究家)」が「哲学者」と呼ばれる、その意味での「哲学者」だと言って良いだろう。
また、森が専門的に学び講じたのはデカルトとパスカルだが、森自身の本領は、あえて言うなら「キリスト教思想」であって、デカルトとパスカルは、むしろそれを支えるための「基礎教養」にすぎなかったのではないか。
だからこそ、デカルトやパスカルに関する専門的著作は、初期に1冊ずつあるだけで、その後はもっぱら、キリスト教とパリに関わる「エッセイ」的な「読み物」著作ばかりなのである。

ちなみに、森有正は「プロテスタント」であったが、『プロテスタントの牧師を父に持つ森有正は、中学卒業までの11年間、カトリックの曙星(※ 小学校と中学校)に通わされたそうで』、若くして「プロテスタントを続けるか、カトリックに乗り換えるか」の選択を迫られて、「プロテスタント」を選んだ人であるらしい。
このあたり、詳しいことは知らないが、森有正の父・森明の教育方針も興味深ければ、たぶん森有正が持たざるを得なかった「信仰的葛藤」あるいは「屈折」も興味深いところである。
言い換えれば、彼は「超サラブレッド」として、「きわめて恵まれた(生育・教育)環境」に育ったがゆえに、ちやほやされもしただろうが、他人から「おまえがその地位にあるのは、もっぱら生まれのおかげだ」と陰口されているだろうことくらいは容易に察していただろうし、その点での「コンプレックス」を少なからず抱えていただろう。
そのうえ、「絶対的真理」であるはずの「キリスト教」が、実際には「ひとつではない」という事実にも、おのずと「葛藤(不安定性)」を感じずにはいられなかったはずである。
つまり、彼の場合は、「生まれながらのクリスチャン」だとは言っても、それは「キリスト教国」に生まれた、当たり前に、生まれながらの「プロテスタント」や「カトリック」といった人たちとは違い、おのれの信仰についての「自明性」を、持てなかった人だろう、ということだ。
だからこそ、彼はフランスへ移住して、そこに自身の「安住の地」を求めることになったのだろうし、「プロテスタント」信仰の絶対性を、我が事として求めざるを得なかったのではないだろうか。
○ ○ ○
本書は、『デカルトの人間像』(1948年)、『パスカル 方法の問題を中心として』(1949年)に続く、森の第3著作であり、1950年という早い時期に刊行されている。
なお、本書収録のドストエフスキーについての「覚書」、ひらたく言えば、「学術論文」ではなく「批評的エッセイ」が書かれたのは、同書刊行の前年(1949年)で、あちこちの雑誌(『文藝』『国土』『世界文学』『基督教文化』『人間美学』『新文学』『婦人之友』)に掲載されたものをまとめたのが、本書『ドストエーフスキー覚書』である。

1949年と言えば、森は38歳。
したがって『1938年に東京帝国大学文学部哲学科を卒業(卒論は『パスカル研究』)、同大学院を経て東京帝国大学の特研生、副手、助手を歴任。傍ら東京女子大学や慶應義塾大学予科などで講師を務め、フランス思想・哲学史を講義した。旧制一高教授を経て、1948年東京大学文学部仏文科助教授に就任』した途端の、集中砲火的な「原稿依頼」だったと言えるだろう。
つまり、森有正の作家デビューは「東大教授デビュー」とほぼ同時という、実にわかりやすい「権威主義」的な評価によるものと見てよく、当然、その時に注目されたのは、森の「超サラブレット」性である断じても良いだろう。
森は、きわめて耳目を惹きやすく、わかりやすい「経歴」の持ち主だった。作家デビュー時、すでに「超有名人」だったのである。
だが、こういう「否応なく出自に恵まれ、そのために売れっ子」になった人というのは、それこそ否応なく「コンプレックス」を抱えざるを得ないというのは、見えやすいところである。
彼は、「祖父の七光り」だけではなく、その縁戚関係において「何重もの後光」を背負わされたのであり、人が、彼自身を「評価している」などとは、森自身にも思えなかったはずだ。
彼自身は、当初、戦後のフランス留学を終えた後は、日本で生活するつもりであったらしいが、結果として彼は、自ら望んでフランスに留まることになる。これは彼が、日本では「森有礼の孫の超サラブレッド」としか見てもらえないことによるものであったのではないだろうか。
だから、そんな彼が、専門であるデカルトやパスカルに関する著作を刊行した後、自ら好んでドストエフスキーについての著作を刊行したというのは、とても興味深く、象徴的な「チョイス」だとは言えないだろうか。
ドストエフスキーの信仰は、「プロテスタント」でも「カトリック」でもなく、「ロシア正教」である。
キリスト教に詳しくない人のためにざっと説明しておくと、「ロシア正教」を含んで「ギリシャ正教」とか「東方教会」などと呼ばれる「正教会」とは、もともとは一つであったキリスト教の「教会」組織から、(「プロテスタント」が派生する以前に)「教会」の主流派であった「ローマ教会(現在の、カトリック教会・西方教会)」と縁を切った、地理的に東寄りの「教会」群のことである。
しかし、「カトリック教会」からしても、それらはまだ、復縁合同されるべき「教会の一員」であって、「プロテスタント」のように「異端」認定し(て排除し)たりはしていない、言うなれば「身内の、意見を異にする、別派閥」というような位置づけになる。
「教会」の中での、「政治的主導権争いと神学的見解の相違」によって「東西」に分かれてしまったけれども、「異端」認定して、完全に縁を切ってしまうには、「正教会」は、あまりにも大きい存在だったというわけだ。
そのようなわけで、ドストエススキーというのは、「カトリック」と「プロテスタント」の双方から「キリスト教」作家として顕彰される「偉大な作家」ではあったけれども、じつのところ、微妙な存在だったとも言えるのである。
本書で、ドストエススキーをめぐって、参照され言及される作家や哲学者は、世間一般的に著名な哲学者や作家を除けば、基本的に「プロテスタント」関係者だと思って良い。つまり、「カトリック」べったりで「プロテスタント」を認めないような有名関係者は参照されていないに等しい。
この場合、ドストエフスキーは、「カトリックではない」という点において、「プロテスタント」である森有正にも、言葉は悪いが、「利用価値のある、有名作家」であったと、そう言えるのである。
言い換えれば、ドストエフスキーが、「正教会」信者であり、おのずと「カトリック」に一定の距離をおいているとは言っても、仮に、「プロテスタント」について明確に否定的な見解を語っていた人であったなら、いかにすごい作家だろうと、森はドストエフスキーを論じたりはしなかったであろう、ということだ。
もちろん、森がドストエススキーを論じたのは、日本人がドストエススキー好きであり、また小林秀雄に主導された「ドストエフスキーブーム」の続いていた時期だったからだ、とも言えるだろう。
日本で、キリスト教のすごさを論じるのに、ドストエフスキーくらい便利な作家など、他にいなかったというのは確かだし、終戦4年後の1949年と言えば、日本がまだ進駐軍の影響による「キリスト教ブーム」にあった時期だから、そのおかげもあって、著作家としては無名の等しかった森有正が、「クリスチャン作家」として、引っ張りだこにもなり得たのであろう。
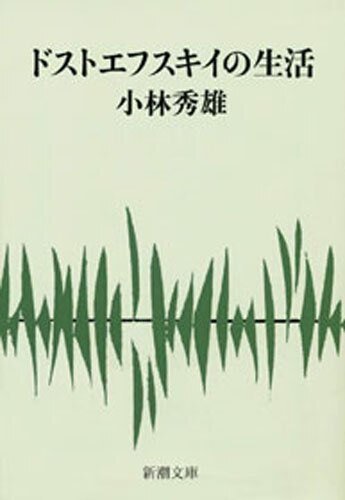
森の場合、1950年の第3著書である本書から、次の第4著書である『流れのほとりにて パリの書簡』(1959年)までには9年の間隔があるし、それ以降に刊行されるのは「パリ在住」であることを生かしたエッセイなどが中心で、彼が作家として認知されたのも、そうした「異国情緒あふれる哲学的(=キリスト教思想的)なエッセイ」によってであったと言えるだろう。
まだまだ外国が、あるいは「憧れのパリー」が遠い時代にあって、日本語でパリのことを書いてくれる日本人作家は、他にはいない等しかったから、泥臭い「日本の戦後文学」に飽き足りない人たちが、森を読むことで、ある種の「エリート意識」をくすぐられたというのも、想像に難くないところなのではないだろうか。

だが、言い換えるならば、森有正が「ロシアの大地信仰に根ざした庶民派」のドストエススキーに強くこだわったのは、その経歴の「初期」に限定されるのではないか。
もちろん、ドストエフスキーへの興味は、ある程度継続しただろうし、言及することもあっただろう。しかし、ドストエススキーは「パリの人」ではなかったし、「パリもの」ばかりを書いた晩年の「森有正らしい森有正」に読者が期待したのは、「ドストエフスキー的なもの」でなかったというのは、明らかなのである。
したがって、本書『ドストエーフスキー覚書』は、森有正の著作の中では、「異色作」であり、のちの「森有正」の著作とは、少々おもむきを異にしたものであったと見るべきであろう。
私は、森の著作を読むのは、本書が初めてだから、確たることは言えないのだけれども、森の経歴と著書名をざっと瞥見しただけでも、このくらいのことは、おおよそのところ見当がつく、ということである。
○ ○ ○
さて、本書『ドストエーフスキー覚書』だが、私が見たところ、本書の特徴として興味深いのは、同書を構成する10本のエッセイのうち、大雑把に言って、前半のものは「ドストエフスキーを引き合いに出しての、キリスト教的な反近代主義の正しさ喧伝したもの」であり(その点ではむしろ「カトリック的」なのだが)、それが本書半ばを過ぎると、なぜか急にそうした「アピール」が薄れて、作品そのものからドストエフスキーの特性を読み取るという、比較的「当たり前なところに落ち着いた」作家論になっているという、いささか奇妙な「分裂」であり「転調」である。
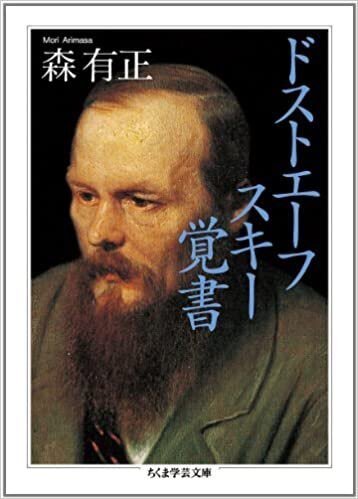
前述のとおり、本書収録の「覚書」は、いずれも「1949年」中に、いろんな雑誌に掲載されたものであり、それが掲載順に収録されたものである。
だから、これらの「覚書」では、しばしば「この問題については、別のところで論じたから、ここでは割愛する」みたいな言葉が目に付き、内容的には、おおむね一貫していると言える。
だが、問題は、それなのにどうして、その半ばで一種の「転調」がなされたのか、ということであり、なぜそれは、「徐々に高まる」といった当たり前のものではなく、途中で「憑き物が落ちる」といったような態の「イレギュラーな転調」であったのかが、たいへん気になるところなのだ。
だが、現時点での私には、その謎についての解答は提示し得ない。
もしかすると、この「謎解き」は、すでにどこかでなされており、解決済みの事項なのかもしれないが、そのような可能性があるからといって、この「奇妙な謎」は無視して良いものではないと思うし、本書を通読しても、この「転調」に気づかない読者は、きっと少なくないだろうから、解答までは提示できなくとも、やはり指摘しておくべきだと、斯様に考えたのである(なお、Amazonのカスタマーレビューなどでは、誰もそんなところまでは気にしていない)。
さて、このように指摘した上で、本書で、最も注目すべき文章は「第4章」として収録されている「コーリャ・クラソートキン 一一「カラマーゾフの兄弟」の中の一挿話」であろう。
この章での森の語りは「異様に激しい」のである。
コーリャ・クラソートキンというのは、『カラマーゾフの兄弟』の中心的主人公であるアレクセイ・カラマーゾフ(愛称・アリョーシャ)を尊敬する、母子家庭の少年だが、この、いかにも子供っぽいコーリャに対する森の視線が、異様に厳しく「敵対的」なのである。
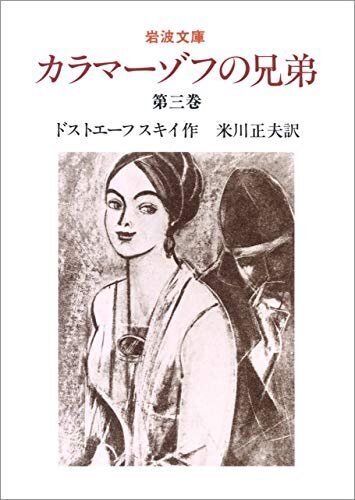
たしかに、コーリャは、自意識が強く「近代主義的」な少年で、その意味では、少々「生意気」な部分がないわけではないとは言え、しかしそれは「背伸びしたがる少年」の姿としては、むしろ「微笑ましい」ものでしかない。
それなのに、そんなまだまだ未熟なコーリャをして、将来の(観念的殺人者である)ラスコーリニコフ(『罪と罰』)だとか、「徹底的な虚無主義者」であるスタヴローギン(『悪霊』)、あるいは「神を告発する、理知的な人間主義者」であるイワン・カラマーゾフ(※ 森は「イヴン」と表記)と「同型の人間」であると言い募り、ことさらに「悪役」に仕立て上げようとするかのような、森の「おとな気ない」語りには、あきらかにバランスを失った、何やら「異様なもの=暗い情念的なもの」を感じざるを得ないのである。
以上の「印象」の証拠として、少々長くはなるが、「コーリャ・クラソートキンの像」と見出しのつけられた文章の前半部分を、そのまま引用紹介しておきたい。
『 クラソートキン(※ コーリャ)は不断に自己に対する関心を忘れることのできない少年である。ドストエーフスキーはクラソートキン自身のアリョーシャに対する自己省察を通してかれを次のように描出している。
「……今はかれにとってすこぶる重大な瞬間であった。第一に自分の面目を損なうことなしに、独立した対等の人間だということを相手〔アリョーシャ〕に示めさなければならない。「でないと、ぼくは十三の小僧っ子だと思って、あんな連中と同じに見るかもしれない。アリョーシャはいったいあの子どもらをなんと思ってるだろう。今度ちかづきになったらひとつ訊いてみてやろう。だが、どうも都合が悪いのは、ぼくの背が低いことだ。トゥジコフはぼくより年が下だが、背はぼくより二三寸高い。でも、ぼくの顔は利口そうだ。もちろんきれいじゃない、ぼくは自分の顔の拙いことを知っている。が、利口そうなことは利口そうだ。それからまたあまりべらべら喋らないようにしなくちゃならない。でないと、アリョーシャはすぐ抱きついたりなんかして、ひとを子どもあつかいにするかもしれない……ちぇ、子供あつかいなんぞされたら、とんでもない恥っ曝しだ………」」。この簡単な描写のなかに、クラソートキンは実に鮮やかに浮き上がってくる。それはかれの外観だけではなく、その精神像をも明示している。かれは本質的に他との関係を自ら意識しながら生きている人間である。かれはすべてを自分を中心として考え、自己が見事に動く姿を点出する。他のすべての人物は自己の活動を引きたてる背景としての意味しかもたない。われわれはここに幾多の差異があるにもかかわらず、『悪霊』の主人公ニコライ・ スタヴローギンの姿を思い浮かべざるをえない。かれ(※ スタヴローギン)はきわめて美しい少年であり、優れた知性を有していた。そしてかれもまたすべてを自分を中心にして考える少年であった。外観がやや相違するにもかかわらず、かれら二人の精神像は、驚くべき類似を呈する。これにはかれらふたりの相似の教育環境があずかって力があった。ふたりとも母親ひとりの希望の的であり、母親はこれらの子どもたち(しかもひとりっ子)にあらゆる生甲斐をかけていた。すなわち母親は息子に求めるところがあったのである。このことは子どもたちをたちまち本質的な暴君にしたててしまう格好の地盤である。しかもスタヴローギンの場合、その師父の役目を引き受けたスチェパン氏は、この子どもに自分の感情のはけ口を見出した。すなわち彼もまたスタヴローギンに、精神的に求めるところがあったのである。しかるにコーリャの場合、かれに接近したアリョーシャはあくまでかれに求めるところがなく、しかも子どもの心を啓発してやまなかった。クラソートキンはついにアリョーシャを軽蔑することができなかったのである。かれはアリョーシャにおいて友にして真の師に出遭ったのである。このことはついにクラソートキンの進路を一変する。この転換こそドストエーエフスキーが他の人物において描こうとして描くことのできなかった点、あるいはそれは描いても種々の条件のために歪められたものであったが、かれはこの子どもの無垢の心においてそれを凝集した形の下に描出しえたのであった。それはともかくとして、クラソートキンは小柄で利口な、しかもそれを不断に対他的な関心の対象として意識する、自尊心の高い子どもであった。ドストエーフスキーは以上のクラソートキンの自意識に映されたかれの像に加えて、次のような註解的叙述を行っている。「コーリャは胸を躍らしながら、一生懸命に独立不羈の態度を保とうと努めていた。なによりかれを苦しめたのは、背の低いことであった、顔の「拙い」よりも、背の低いことであった。かれの家の片隅の壁には、もう去年から鉛筆の線が引かれていたが、それはかれの背の高さをしるしづけたもので、それ以来かれは二カ月めごとにどのくらい伸びたかと胸を躍らせながらその壁へ丈くらべに行くのであった。が、残念ながら、ほんの僅かしか伸びなかった。これがためにかれは時によると、もうすっかり絶望してしまうことがあった。顔はけっして「拙い方」ではなく、少し蒼ざめていて、そばかすはあるが、非常に色の白い愛らしい顔だちであった。灰色の眼はあまり大きくはないが、生き生きと大胆な表情をしていて、よく強い感情も燃えたった。頬骨はいくらか広かった。唇は小さくてあまり厚くはなかったが、非常に赤い色をしていた。鼻は小さくて、そして、思いっきり上を向いていた。「まったく獅子っ鼻だ、まったく獅子っ鼻!」とコーリャは鏡に向かったとき、口のなかでこう呟いた。そしていつも憤然と鏡の傍を去るのであった。「顔つきだってあまり利口そうでもないようだ」。かれはどうかすると、そんなことまで疑うのであった。しかし顔や背丈の心配が、かれの全心を奪い去ったと思ってはならない。むしろその反対で、鏡の前に立った瞬間、どれほど毒々しい気持になっても、後からすぐ忘れてしまって(長く忘れていることもあった)、かれが自ら将来の目的として定めた通り、「思想問題と実際問題にぜんぜん没頭して」いたのである」(第三巻)、これらの描写によってクラソートキンの精神像はまったく明らかになる。かれの全情念の様態は自己省察を媒介として不断に転回する。かれの情念は直接対象と連関して燃えあがるのではなく、常に対象に対する自己のあり方に向って働く。かれは本質的には自己の内側に閉鎖した存在である。ここに地下生活者、ラスコーリニコフ、スタヴローギン、イヴン、の系譜が素朴に姿を現している。かれは鉄道の線路の間に俯伏しに臥て、汽車が全速力で上を通過し去るまでじっとしていた。これは一つの好奇心の表現ではなく、「十五になる子どもたちがコーリャに対して、おそろしく傲慢な態度をとって、「ちっぽけな」小僧っ子として友だちあつかいもしてくれなかったのが、堪らなく口惜しかったのである」(第三巻)。すなわち年上の子どもたちに対して独立の自分を意識し、誇示するためだったのである。かれの希望、残念の情、絶望、満足の情はことごとく自己に向かって集中した。この自意識の念は、内容的に分析すると、自己の他に対する優越と自己支配との実現を意識することを焦点とするものであった。かれは自己を常に閉鎖しなんぴとも自己の心内に干渉することを許さなかった。これがその友人たちに対してかれを自由にすることのできぬ存在として、尊敬と不可解の服従との対象としたのである。われわれはここにスタヴローギンの姿の重要な一面を見ることができるであろう。』
(P127〜131)
ドストエフスキー自身は、コーリャ・クラソートキンについて、明らかに「好意的な描写」をしている。
なのに、森による、この異様に歪んだ「強弁的解釈」は、いったい何に由来するものなのであろうか。
『われわれはここに幾多の差異があるにもかかわらず、『悪霊』の主人公ニコライ・ スタヴローギンの姿を思い浮かべざるをえない。』などと、誘導的な『われわれ』呼ばわりなどして欲しくないが、この「傲慢なまでの断言」は、彼の「超サラブレッドの東大教授」という根拠以外、いったい何処に求められよう?
そして、少なくともこの時の森有正は、「ドストエフスキーの権威」を悪用して、生意気な「近代主義者(無神論者)」であるコーリャに対し、「異端審問」での有罪判決を言い渡している。
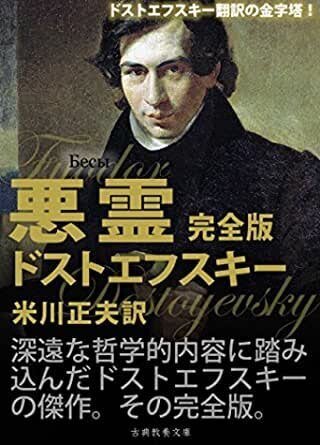
そして、そこでは明らかにドストエフスキーその人が「不在」であったのと同様、彼の信仰もまた、彼の歪みを正すものどころか、それを正当化する「道具」にしかなっていない。
要は、森有正の「神」である「イエス・キリスト」は、少なくとも、この「異端審問」の法廷においては、「不在」でしかなかった、ということである。
一方、森は、スメルジャコフに唆されたとは言え、よく吠える番犬のヂューチカに、針を仕込んだ柔らかいパンを食べさせ、ヂューチカが「きりきり舞いして、きゃんきゃん鳴きながら走り去っていく」姿を見て、ハタと自分の罪の重さに気づき、死ぬほど苦しむ少年イリューシャに対しては、きわめて同情的であり、少年の「本質」は「愛」だとまで言い募っている。
また、そんなイリューシャについて、「これでイリューシャも反省するだろう」と、いささか呑気にかまえていたコーリャ・クラソートキンに対しては、例のごとき「憎悪」を込めて、過剰に酷評するのである。
本書解説では、『ドストエススキー』という著作もある文芸評論家・山城むつみが、森有正の「傷ついたイリューシャに対する、過剰なまでの好意的なこだわり」について、次のように評している。
『 たとえ(※ 犬の)ジューチカ(※ ママ)が死んでも「駆けながら鳴いているヂューチカ」は消滅しない。いや、それだけではない。たとえイリューシャ(※ 本人)が死んでも、「「駆けながら鳴いているヂューチカ」を見た」イリューシャは消滅しない。この光景に引き裂かれる彼の苦しみは、彼が死んでも分裂し停止したまま存在し続けるのだ。森はそうはっきりとノート(※ 覚書)している。
何と奇妙な、そして不気味な断言だろう。賭けてもいい。森がこう断言するのは、森自身にも「ヂューチカ」がいたからだ。それが彼にとって何だったかのかは知らない。知る必要もない。しかし、彼が何かをやったはずである。そして、彼は彼の「ヂューチカ」が消えないこと、森自身が死んでも消えないし、それを見た森自身も分裂したまま存在し続けるということに根源的な怯えを感じていたはずである。それが彼の言葉をノートの言葉にし、その断言を異様に尖らせている。そんな言葉だからこそ、読む我々にも思い出させるのではないか、自分にも自分の「ヂューチカ」がいることを。それが、研究でも批評でもない(※ つまり、分析して明示的に説明したりはしない)ノートの言葉なのである。』
(P435〜436、山城むつみ「解説」より)
つまり、森有正には、後悔してもしきれないような「罪の記憶」が「呪い」として貼り付いており、それは自分が死んでさえ消えて無くならずに残り、自分をその死後まで告発し続けるものだ、というふうに、言うなれば「強迫神経症」的に思い込んでいるのである。
だからこそ、イリューシャの悲劇について「可哀想ではあれ、自業自得だ」と冷めた突き放し方などは到底できず、思い切り感情移入して「むしろそれは、イリューシャの愛ゆえだ」と、代理的に「自己正当化」してしまうのである。そして、ここにあるのは、森有正の「自己憐憫」に他ならない。
山城むつみは、本書の解説者として、本書著者の森有正を「責めて」済ませるわけにはいかないから、「しかしこれは誰にも思い当たるところのあることであり、それを深く苦しみぬいた森は、並外れて繊細な人であった」といったニュアンスの「綺麗事(の絵図)」に落とし込んでいる。

しかし、ここで、山城が、森の「イリューシャに対する共感」には言及しても、「クラソートキンに対する過剰な憎悪」の方には触れないのは、森の「クラソートキンに対する過剰な憎悪」は、言い訳の余地のない「八つ当たり」であることが、あまりにも明白だったからに他ならない。
つまり、そっちの方は「みんな同じだよね」といった「綺麗事」に落とし込めるようなシロモノではなかったのだ。だから山城むつみは、そちらについては、無難に敬遠回避したのである。
○ ○ ○
以上のようなことからわかるのは、森の「評価」や「断言」は、まったく信用ならないものであり、「コンプレックス」なり「トラウマ」なりによって「目の眩んだ妄言」であるおそれが十二分にある、という事実である。
彼には、何らかの「強烈なコンプレックス」や「トラウマ」があって、それゆえに「何かにすがり」「何かを敵視し」「何かから自身を正当化」していると言えるのではないか。
端的に言ってしまえば、森は、「憎むべきクラソートキン」にも似た「自意識過剰による無神経さ」によって、他でもなく自身が、誰かを決定的に傷つけたという「消えぬ負い目」を抱えているからこそ、あれほどにコーリャ・クラソートキンを憎まないではいられなかったのではないか。
またその反面、そんな自分は「罪を悔いて苦しみ抜いている、愛の人」だと思いたいから、イリューシャに対しては、きわめて同情的なのであろう。
そして、こうした感情を正当化するための「目隠し」であり「武器」となっているのが、「キリスト教信仰」であり、その「罪と罰と愛」といった「権威主義的な概念」であると言っても良いだろう。
キリスト教に無知な人たちなら、そういう重々しげな「レトリック」に飾られた言葉に、実際以上の「深い意味」を見てしまい、現実をそのまま見ることができないように「幻惑」されてしまうのである。
そして、このような「明白な証拠」から推して、森が「日本から出奔しなければならなかった=日本では安らげなかった」というのは、彼が「超サラブレッド」としての「傲慢と無神経」で、誰かを決定的に傷つけてしまったからであり、その「負い目」があって、彼を「超サラブレッド」扱いにする日本(要するに、そっとしておいてくれない日本)では安らげなかったから、「パリに逃避した」ということではなかったろうか。

山城むつみが指摘しているとおり、森が『研究でも批評でもない(※ つまり、分析して明示的に説明したりはしない)ノートの言葉』、あるいは、その一種である「エッセイ」の類いしか書けなかったのは、彼にはそういう「恣意性(恣意的なレトリック)」が許されるかたちでしか、自身を語ることができなかったからではないだろうか。
「パリの話」「キリスト教の(愛と救いの)話」と言えば、耳障りがよく、ロマンティックでもあろう。
だが、彼が「論を立てなかった=論を捨てた」のは、本書『ドストエーフスキー覚書』に見られるような、自身の若さ(未熟さ)による無自覚(誤魔化し=心理的な自己隠蔽)に気づいて、そこから逃れようとしたからではないか。
つまり森有正は、年をとって「自身の自己欺瞞」に気づいたのだけれど、しかし、それを自身で剔抉する「強さ」を持つまでには至らなかったから、「パリに逃れ」さらには「エッセイに逃れ」ざるを得なかったのではないだろうか。
(2023年5月14日)
○ ○ ○
○ ○ ○
・
○ ○ ○
・
○ ○ ○
・
・
○ ○ ○
・
・
