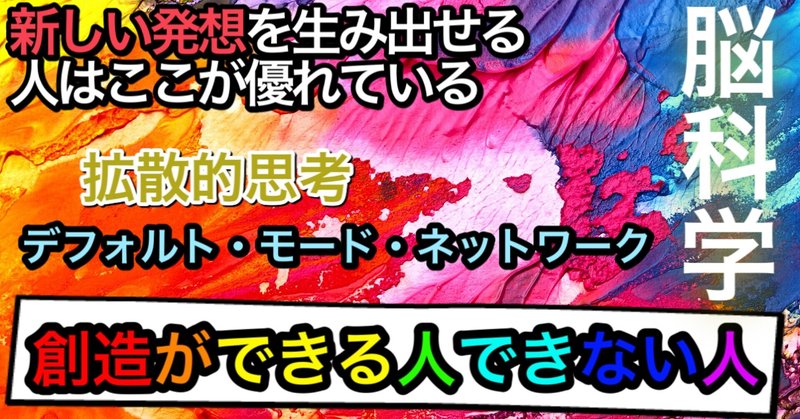
【脳科学】創造ができる人とできない人の違い
と言うことで本日もたわえもない雑談をしていこうと思うのですが、皆さんって新しい発想ができる人とできない人ってどんな違いがあると思いますか?
社会に出て必要な能力は”解決”と”創造”の2つであると、僕は考えています。
「今抱えているこの問題はどうすれば良いのか。」
「この目的を達成するためにはどんな方法があるのだろうか。」
「コミュニケーション能力をつけるにはどうすれば良いか。」
「この問題を解決するのに必要なデータは何か。」
「今自分は何をするべきか。」
社会に出るとこういう「答え」がある程度決まっていたり、全く決まっていない問題を僕達は解くわけで、完全に答えが決まっている問題はありません。
”創造”と”解決”の脳の仕組みを知っていこうシリーズpart1↓
ただこの記事↑でもお話ししたのが、創造ができる人って拡散的思考ができると言うことで、脳のデフォルト・モード・ネットワークという脳の思考ネットワークの働きが強いってことでしたよね。
どういうことかと言うと、例えば「この新しい技術を使って何ができるようになるのか」というアイディアを短時間で沢山出す能力が優れていると言うことです。
これが新しい発想ができる人はこの働きが強いし、できない人はこの働きが弱い。これができる人とできない人の差なんですよね。
新しい発想ができない原因
じゃあその違いってなんやろなって考えていくと、まず最初に拡散的思考への不確実(不安感)が挙げられます。
どういうことかと言うと、論理的な収束的思考をすると
「この問題はこれがこうなってああなるから、この解き方で解くのが良いのか」
って論理的に正しい意見を考えられるので、論理性という自分で納得するための材料があるわけで、なぜこの方法は正しいのか間違えているのかってことを1つづつ確認しながら安心して自分の考えをアウトプットできるのです。
ただ拡散的思考をしていくと
「あ、このアイディア良いかも。あこれも良いかも。あ、この角度からも行ってみようか」
みたいに思いついたことを直感で言って、論理的に正しい間違えている関係なく色々アイディアを考えるわけですよね。
だから拡散的思考をする人は論理的な意見を言われた時に論理的な反論が出来ないケースがあり、それを不安だと恐れるケースがあるんですよね。
要するに拡散的思考ができない人って
「この方法とかどう?!面白そうじゃね?」
「僕はこういう根拠があってこの方法が良いと思っているんだけど、それはどのように効率的なの?」
「うっ…」
みたいに非難されるのを恐れているんですよね。
しかし新しい発想ができたり、拡散的思考ができる人ってこうやって不確実で不安なことをも超越する何かがあるのです。
人って当たり前ですが基本的に自分にとって損になることってしないのでね、この拡散的思考の原動力になっている”何か”があるのです。
じゃあその”何か”って何?って話ですよね。
創造の原動力になる”何か”とは
結果から言えば、その”何か”の正体とは報酬と意欲の事を指します。
例えば皆さん学生時代に学校で教えられた勉強ってつまらなかったですよね。
だからいきなり「この数学の問題集、小学生でも簡単に解けるような計算問題がめっちゃあるから解いてみない?」
とか言われても
「いや(面倒くさいし)ええわ。」
ってなるじゃないですか。そりゃそうですよね、興味ないし面倒臭そうだし解いたところで自分に何のメリットもないですもんね。計算なんて携帯でできるんですから。
ただ例えばこれが
「この問題集、結構頭をひねって考えないと解けない問題があるんだけど解いてみるかい?」
とか
「この問題集を全部解いたら何でも好きなものを1つ買ってあげるよ。」
とか言われると
「あ、じゃあちょっと面白そうだし解いてみようかな」
「なんでも買ってもらえるならやるか。」
ってやる気出す人が出てくるのはなんとなく読者の皆さんも想像できると思うのですが、こうやって自分がその問題を解決することによって得られるメリットがあるから人って”創造”したり”解決”したりするんですよね。
これが”何か”の正体でじゃあこれが何なのかと言うと、先ほどもお話ししましたように”報酬”であり、この報酬に向かって問題を解決しようとするのが”意欲”です。
これは前回の記事でもお話ししたことなのですが、人って世界にある全ての問題を解くことができないので、ある程度自分が解決するべきorしたい問題を理由や興味によって決めるわけですよね。
例えば
「これを知れば恋愛の仕組みが理解できます↓」
「なぜ高学歴の無能や低学歴の有能がいるのか↓」
っていう風に記事を紹介されると
「あ、この記事面白いんで読んでください。」
って言われるよりかは、読む理由が明確にわかったり、それを読むことによって自分が得られるメリットが見えやすくなるので興味がそそられたりしますよね?
もっと言えば恋愛とか仕事の話って多くの人が興味があるので、割と多くの方から関心を向けていただくことができるのです。
という感じで、この世界には沢山未だに誰も解いたことがないor自分がその答えを知らない問題が沢山あるのですが、人はそれらを全て解くわけではなく、自分が興味があったり解くべき理由がある問題をその中から選別している、というお話です。
だからこの興味や理由が大きくなれば意欲も大きくなり、そうなれば報酬も大きくなるという関係になっているのです。
そしてイタリア・スイスのダレモレ人工知能研究所のユルゲン・シュミットフーバー教授によると、この報酬や意欲、興味などには2つの拮抗する2つの側面があるといわれています。
要するに人が新しい発想や創造をしたり、解決したりする原動力となっているものには2つのせめぎ合う性質があるということです。
それが内発的意欲と外発的意欲。
というところで、明日はこの内発的意欲と外発的意欲についてお話ししていこうと思いますので、興味がある方はぜひご覧ください。
それでは、最後まで読んでくださりありがとうございました。
参考文献↓
もらったら社会貢献のためにユニセフに募金します。 ※こいつは嘘をついています。募金せずに帰り道でコンビニに寄ってたばこ買うに違いありません。
