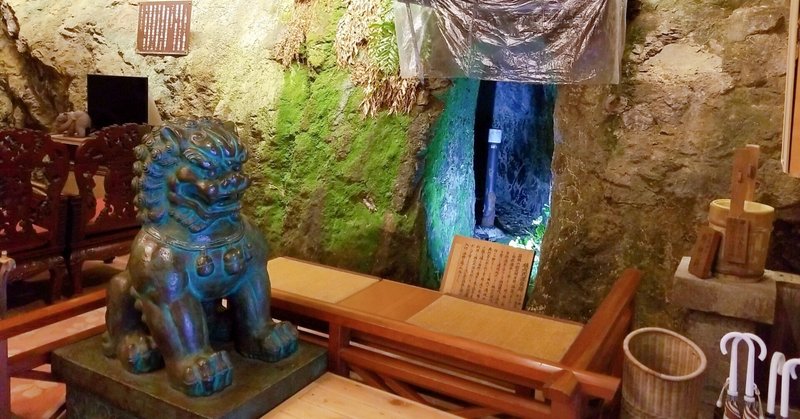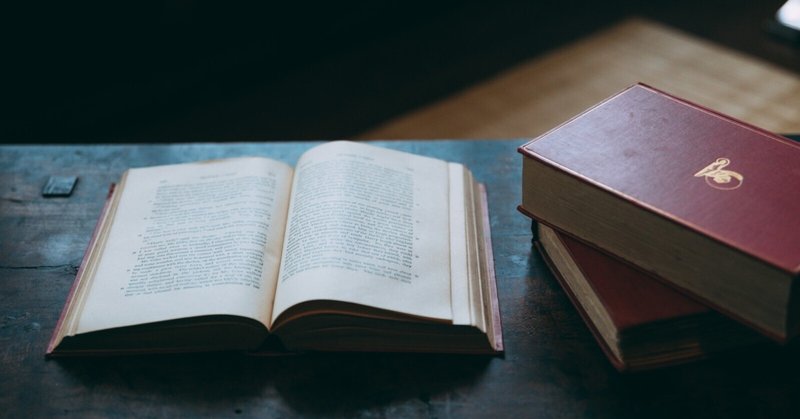記事一覧
浅野智彦『「若者」とは誰か 増補新版』要約と感想
社会学者、浅野智彦の著作『「若者」とは誰か 増補新版』を読んだ。以下は本の要約と感想です。
要約1 消費行動からコミュニケーション論へ 「若者論」は切り口がその時代によって異なる。
1980年代においては、日本の消費社会化が進むのと同時並行に、その消費行動によって若者は語られていた。
しかし、1990年代に入ると、若者論の中心は「消費行動」から「コミュニケーション論」へと性質を変えていっ
社会問題が解決できることを提示した本 『社会問題のつくり方』著:荻上チキ 書評
社会を変える具体的な方法 『社会問題のつくり方』と銘打ったこの本、社会問題を社会問題として提起し、それを解決するまでの方法と道筋が紹介されている。
・同じ問題意識を共有した仲間とチームを作る。
・その問題が一体どういう状態にあるのか調査をする。
・広く人に知ってもらうために記者会見をする。
・政治家と繋がる。
・その問題を解決するための法案を成立させる。
そこまでの一連のノウハウが、10代な
変わりゆく街の風景と「資本主義の精神」 ブックオフ論争を問い直す
■消えゆく街の個人経営店 街からちょうどいい定食屋さんが消えてしまったような気がします。今日は夕飯を外で済まそうかな、と思ったときに、気軽に入れるお店。かつては個人経営のお店でそういうお店がたくさんあったのですが、今はそれが牛丼屋やチェーンのラーメン店に取って代わられてしまいました。
定食屋だけではなく、かつては個人経営の喫茶店、古本屋などが街に1つや2つありました。それが今では喫茶店はドトー
私たちは言語の中に閉じ込められ、そして開かれる 『文学理論』と映画『ドライブ・マイ・カー』
日本語によって規定される思考
私たちは普段、言語によって物事を認識し、その思考の枠組みは、言語によって規定されます。
例えば日本語では「敬語」があることによって、相手と自分の立場のどちらが上か下かを表さなければいけないようになっています。
また日本語は英語と違って、主語を明確に打ち出す必要がない言語だと言われています。その分主体が曖昧になりやすい傾向があると言えるでしょう。
このよう
政治を知り、自分を知るための入門書 西田亮介『ぶっちゃけ、誰が国を動かしているのか教えてください』書評
政治とメディアへの素朴な疑問に答えてくれる この本は、社会学者西田亮介さんが、政治に対してどう関わればいいか、その基本的なスタンスについての問いに応えてくれる本だ。
例えば、「政治なんて難しいし、面倒だし、関わらなくてはいいのでは?」という問いに対しては、
→「政治に参加するのはコストだが、政治家がきちんと政治を行っているか見張っていないと、なにかあったときの対価は自分に返ってくる」という立場
『呪いの言葉の解きかた』書評 自分自身を縛る言葉に抗うために 著:上西充子
普段の生活の中で、人から言われたことや自分の中で、自身の思考や行動を縛る言葉がある。
例えば、「普通でなければならない」「理不尽に耐えるのが大人」「社会と他人は変えられない」「弱音や愚痴を吐いてはいけない」などなど。
自分が感じたことや思ったことを、押さえつけ、抑圧する。
聞いた瞬間に息苦しさやダメージを感じてしまう、そんな言葉たち。
なにかがおかしいと思っても、どこがどうおかしいのかうまく