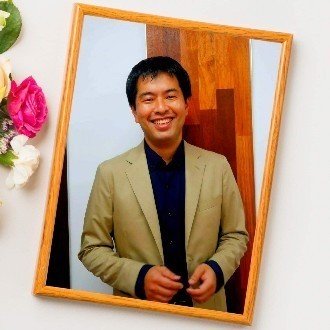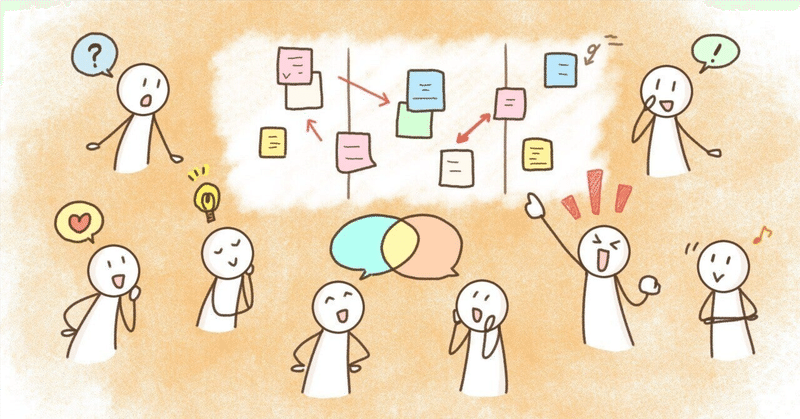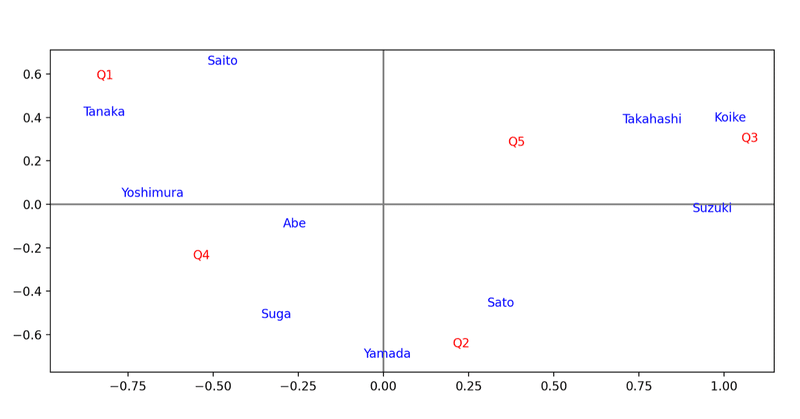記事一覧
子供の「分かんない」をファシリテーションでなんとかする
「分かんない」
そう言って子供が思考停止することってありませんか?
子育てで、よくあるそんな状況へ、ファシリテーションを活用した例です。
今回、子供が学校でスピーチをする機会があるけど、何を話したらいいか分からない、と相談を受けました。その時の経験を書きたいと思います。
スピーチに関する詳細は書きませんが、「自分のやりたいこと」がテーマでした。これに対し、「何を言えばいいかわからない」と相
技術者・研究者が持つ力を引き出すためのワークショップデザイン
※本記事は、「研究開発リーダー」2021年9月号に掲載したものをベースとし、一部加筆したものです。
1.はじめに ワークショップとは、主体的に参加したメンバーが共働体験を通じて創造と学習を生み出す場[1]であり、研究開発の現場でも、イノベーションを目的としたワークショップに関わる機会が増えている。また、革新的イノベーションの創出に向けた対話ツール [2]などのように、ワークショップ運営に関する知
”ファシリテーション” は 陰キャの生存戦略である
問い:陰キャは、組織の中でどうすれば生き残れるのか?
答え:ファシリテーターになろう。
ということについて書いてみます。
1.そもそも陰キャってどんな人?こちらの記事によると、
というのが特徴とのこと。
これを踏まえると、私は陰キャだな。。。
2.ファシリテーターってどんな人?こちらはWikipediaにありました。キラキラしているイメージ。
陰キャがなるのは無理なのでは?と思えちゃい
ブレストでの問いの立てかた
ブレインストーミングのファシリテーションを依頼されることが度々あります。
先日、依頼者から
「普段、どのように問いを立てているのか?」
と聞かれたので、ちょっと整理しました。
本記事の対象私がブレストを実施するのは、多くの場合は研究者・技術者相手です。そのような方が参加する場での問いを対象にします。
前提ブレストを通じて得たいアイデアは、既存の事業や技術に関連したものとします。未経験の領域な
コレスポンデンス分析を使ったチーム分け
ワークショップで出たアイデアの整理に、統計的手法を使う方法について、下記にて紹介しました。
このように、分析をワークショップに活かす使い方について模索している内容を、備忘録もかねて記載したいと思います。
なぜやろうと思ったのか?今回使ってみる手法はコレスポンデンス分析です。これは、先の記事で述べた数量化3類と基本的には同じ内容です。pythonを勉強する中でこの記事を見つけたので、何かやってみ
話下手? いいえ、聴き上手です!
懇親会などのお酒の席で、会話に入るタイミングって難しくないですか?
乾杯の挨拶って突然振られると焦りませんか?
そんな私ですが、ファシリテーターをしています。ファシリテーションでは、参加者のお話をまずは聴くことが重要です。
対話の機会があった方から、私は傾聴力が高いと言われたことがあります。ファシリテーションをしていたから、自然と傾聴力が高くなったと思っていました。しかし、原因は話下手だったか
なぜ教科書が読めないのだろう?
新井先生の講演を聞きました。
新井先生は、東ロボ君プロジェクトを推進されていた方です。
講演内容は、下記の書籍がベースになっています。
https://www.amazon.co.jp/dp/4492762396/
講演の中で、下記のようなお話がありました。
2で割りきれる数を偶数、それ以外の数を奇数と言います。
下記から、偶数を全て選びなさい。
① 8
②110
③65
④0
※選択
オンライン会議の欠点を逆に活かすための3つのコツ
最近、ZoomやSkype等のWeb会議システムの活用が注目されていますが、リアルとは違う面が、不満を生んでいます。
そんなWeb会議を良いものにするコツは3つあります。
コツ① 無理に進めようとせず、不馴れな参加者を思いやり、受け入れる。
コツ② 話し出せない人に声をかける。
コツ③ 話した内容を整理して伝える。
以下では、これらのコツがなぜ必要かの理由を記載します。リアルが好きな方に
天才と秀才と凡人がいるチーム
天才を殺す凡人、という本を読みました。
https://www.amazon.co.jp/dp/4532322537
天才は創造性、秀才は再現性、凡人は共感性を軸としていて、お互いが理解できない、というものです。
はじめの方だけを読むと、人をある種のタイプに分類し、人間関係をどのようにするか、を記載してあるのかと思いました。
ですが、本書の後半では、誰もが三つの軸を持っていて、その顕現度合
バリューグラフによるアイデア創成
何か新しいことを考えようとしたとき、考えるきっかけが必要です。
このきっかけとしては、多くのことが考えられますが、今ある何かを起点とすることが多いと思います。
一番多いのは、今、課題があって、それを解決する新しいことを考えること。しかし、多くのケースでは、自分が気づいている課題には、他の多くの人も気づいています。
そのため、わかっている課題に対しては、多くの場合、すでに他の人がアイデアを考え
オンラインWSで出たアイデアを親和図にまとめる
◼️発散と収束優れたアイデアやインサイトを得るためには、「発散」と「収束」のプロセスを盛り込んだワークが有効です。
発散の代表例がブレインストーミング。
これは、参加者同士がワイワイと意見を出し合って、誰かのアイデアに乗っかってアイデアを広げていくものです。
収束の代表例が親和図。
これは、出されたアイデアを見ながら、参加者同士が似たアイデアをまとめたり、気になるアイデアをくっつけたりしながら
テキストコミュニケーションでの心理的安全性
インターネットではこれまではテキストコミュニケーションが主体でした。
好みの掲示板、スレッドがあり、そこに書き込むのも内容を読むのも楽しい。顔が見えなくても。
そこには ここに集まっているのは仲間 という意識があったと思います。
一方で、最近増えているビジネスチャットツール。
仕事の仲間でやっているはずなのに、投稿されずに使われなくなることも多々あります。
これはなぜでしょうか?
私は