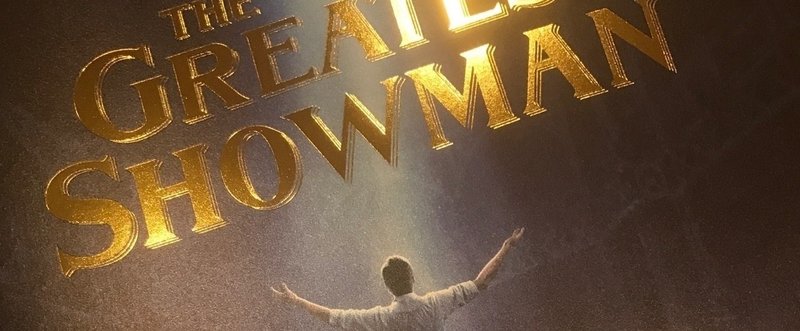2018年3月の記事一覧
「思い立てる」のはありがたい
「フットワークが軽いよね」といわれることが増えた。そうなのか、と思う。
わたし自身、あまりフットワークが軽い方だとは思っていない。むしろ、本質は出不精だ。放っておけばひとりで何時間でも引きこもれる。むしろ、「ひとりならば」引きこもれる。
わたしが外に出るのは、誰かに会うためがほとんどだ。誰かの話を聴きたくて、誰かと話がしたくて、わたしはいつでも外に出る。
***
ライター仲間の大城あしかさ
それは「ネタ」か、それとも「ヒト」か
ものを書く人間には、「あ、これはネタになるな」と思うことが多々あるだろう。自分の失敗談をはじめ、「こういう人がいた」「こんな会話を聞いた」など、アンテナを張り巡らしている人は少なくないだろうと思う。
これは創作でも同じだ。「こんな変わった仕事があるんだ」「こんな変わった人がいるんだ」という出会いは、発想力や執筆モチベーションの原動力になる。こうした気持ちは、当たり前のものでもある。
しかし、そ