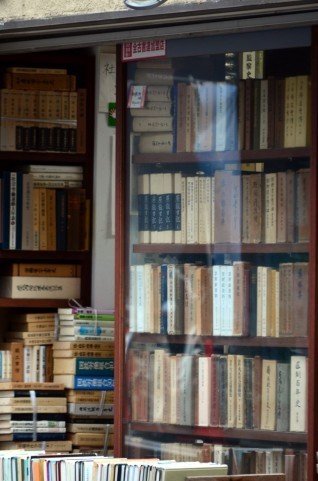
- 運営しているクリエイター
2023年3月の記事一覧
割り算の答えとはなにか、子どもにきちんと説明する必要がある、信濃の民話「池に浮かんだ琵琶」と福音書、あまりこういう事は考えたくない他
未来社刊「日本の民話」シリーズ第1巻「信濃の民話」に出てくる「池に浮かんだ琵琶」は、悲しいお話です。
琵琶法師の琵琶の音が美しいと褒めてくれた池の主の龍は、「明日、いざよいの夜には、この池を荒らして大洪水を起こす。早くこの地を立ち去るがよい。しかし、この事を他に洩らせばお前の命はないぞ」と、秘密を明かします。
琵琶法師は、洪水が起きれば村が押し流されると知って、
「もしワシがあの秘密を教えず
「紙」マルチによるニンジン栽培のテスト。地代は原価+手間賃で決まる価格とは別の原理で成り立っている件など
アダム・スミスは国富論の中で、賃銀と利潤は価格の原因だが地代は結果だとしています。
「地代」について、制度や政策と言うことを離れて考えてみると、確かに「労働」によって実現される価値とは違う性格を持っていることは確かです。
価格や価値と「労働」の関係ですが、アダム・スミスは「労働価値説」、つまり、労働があらゆる価値の源泉だとしています。
たとえば、僕が大根を育てて、1本100円である飲食店に卸
ニンジンの発芽直後の雑草との関係について、お釈迦様は修行中、野獣と一緒にいた件と福音書との比較他
「原典訳 原始仏典(中村元編)」にウルヴェーラー近くの森でお釈迦様が修行していた時のお話として、「そこにいるわたくしに獣は近づき、孔雀は木の枝を落とし、風は落葉を吹き動かした」とあります。
新約聖書のマルコ福音書には、「それから、霊はイエスを荒野に送り出した。イエスは40日間そこに留まり、悪魔の誘惑を受けられた。その間、野獣と一緒におられたが、天使たちが使えていた」
とあります。
つまり、お
「同調圧力」的行動は世界的に見られるものですが、日本の場合、稲作受容以前の時代に遡る歴史的事情による「特徴」があるのかもしれません。
日本は同調圧力が高い社会だと言われる事が多いようです。
「みんな」と同じにしなくてはいけない、違うことをすると「出る杭は打たれる」と言う諺どおり、叩かれる・・・
果たして、「同調圧力」型の社会と言うのは、日本独自のものなのでしょうか?
ヨハネ福音書8章に「姦通の現場で捕らえられた女」について、イエス・キリストが「あなたがたのうちで罪を犯した事がない者が、まず、この女に石を投げなさい」と言う場
泰平モード⇒消費文化の登場⇒八百屋と言う職業の成立⇒野菜の品種改良の進展と言う順番かもしれない、地域経済にとって農業の比重は高い地域があると言うこと
井原西鶴の「好色一代男」巻六「身は火にくばるとも」に「魚屋の長兵衛にも手を握らせ、八百屋五郎八までも言葉を喜ばせ」と言う描写が出てきます。
好色一代男の執筆時期は、1682年ですが、この時代、既に「八百屋」と言う職業、つまり、「野菜小売業」が成立していたとすると興味深いと思います。
島原の乱が終わったのが1638年、寛永の大飢饉が1640-43年にかけてです。この後、農民への過酷な収奪を和らげ生産
新興国が世界経済の中心となる時代の農業、草刈り作業と「優占種」雑草の変化を捉えた農作業、ニラやネギを地下茎タイプの草と捉える菜園デザイン等
1990年代、日本は中東和平多国間協議の環境問題作業部会議長国でした。僕は中東によく環境調査にでかけました。
当時話題になっていたのは、日本がヨルダンに作った肥料工場です。
JA全農は、1996年、日本ヨルダン肥料株式会社を設立し、現地の工場を作りました。JA全農は、2011年にヨルダンから撤退、その後、中国のリン工場の株式を取得したとの事です。
リン肥料の原料となるリン鉱石は世界的に偏在し
国富論にみる徒弟奉公と半農生活の農家を生み出すための仕組み、温暖化には「上限」がある?など
アダム・スミスの国富論にギルドの徒弟修業のお話が出てきます。
「全ヨーロッパを通じて昔は7年と言うのが同業組合化された職業の大部分における徒弟修業の期間であったようだ。そういう団体は昔はみなユニバーシティと呼ばれた」
ユニバーシティは、今では大学を意味する言葉ですが、この点について、スミスは
「しかるべき資格のあるマスターのもとで7年間勉強したと言うことが、リベラル・アーツの場合も、マスター
一次産品の奪い合いから重化学工業の産物が流通する時代、そして、これから・・・
鉄の古代史(奥野正男)では、弥生時代の遺跡から人体に打ち込まれた可能性がある鉄鏃が出土していることを述べています。
「(弥生時代)前期末の時点には農耕を基盤とした社会が定着し、生産力の急速な増大によって、余剰生産物が生み出され、その結果として人口も更に増大し、新たな可耕地への進出が強く要求された。」
「この間の土地開発は低丘陵、あるいは当時の可耕地と考えられるあらゆるところに遺跡が立地している
畑の雑草観察、保温の状況によりで生えている雑草の種類が違うので種類ごとに発芽・生育適温があるのだろうと思う、備中鍬による畝立て法の工夫、西鶴文学に出てくる野菜の漬物のことなど。
井原西鶴の好色一代男に「いま日が暮れて間もなき夜食、まづ蓋をあければ小豆食、『これはおもしろい、鯖きざみて穂蓼置き合わすこそ心にくし』と思えば、湯を飲むまで香の物を出さず」と言う描写が出てきます。
日が暮れてすぐの夜食の蓋をあけると小豆飯だった。これは面白い、鯖を刻んで穂蓼(タデの穂)が付け合わせてあるのはよいと思ったところ、湯を飲むまで香の物が出てこなかった
いくつか思うのは、雑穀を炊き合わ















