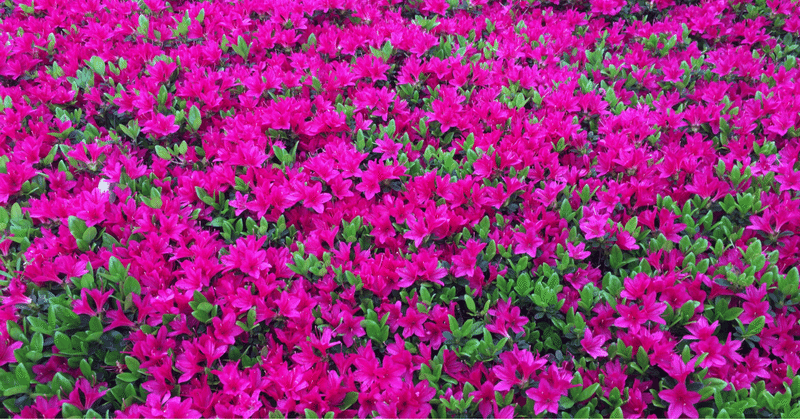#日本文化
日本文化 ラッシュアワー
通訳ガイドのぶんちょうです。外国人観光客と一緒に行動を共にするのがガイドである私の仕事ですが、ラッシュ時の東京の電車に乗らざるを得ないことがあります。普段あまり電車に乗らない、特に欧米の方々は見知らぬ人と身体が接触するのを嫌がるのでラッシュはなるべく避けるのですが、その日は「それは是非乗ってみたい!」という反応でした。
そもそも、ラッシュ時の他人との接触はすごいレベルですよね。身内でもほとんどな
伝統文化① なぜ歌舞伎役者は男だけなの?
こんにちは。通訳ガイドのぶんちょうです。
ガイド中に歌舞伎座の建物が目に入ると、必ず外国人観光客に説明するのが歌舞伎についてです。現存の建物は銀座・大阪、共に建築家、隈研吾氏の手がけたものでインパクトがあります。
歌舞伎ファンの方は結構たくさんいらっしゃる一方で、一度も歌舞伎を見たことがない方も多いと思います。外国人に聞かれるかもしれない歌舞伎のこと。一度は見ておくことをおすすめします。
歌
伝統文化② 歌舞伎メイク 隈取り
こんにちは。通訳ガイドのぶんちょうです。
今日も私の視点で、初心者さん向けに歌舞伎について紹介します。前回の記事はこちらで、歌舞伎がどのように生まれたのかについて書いてあります。
皆さんは歌舞伎の演目に、どちらのイメージをお持ちですか?
1 二枚目の役者さんがなよっとした感じで演じる
2 すごい形相で顔に模様のついた役者さんが「てやんでぇ」風に演じる
1に近いイメージの方は「和事」2の場合は「
伝統文化③ 江戸時代の歌舞伎の楽しみ方
通訳ガイドのぶんちょうです。今日も私の視点で歌舞伎を知らない方に向けて書いていきます。前回は「見得」という独特の演出方法について触れました。
見得はクライマックス、感情が最高潮に達したときに役者が首を少し回してからにらみを効かせるのですが、この瞬間に合わせて、舞台の右手に置いたツケ板が拍子木で勢いよく打たれます。この音で場に緊張感が走り、観客は今まで以上に役者の表情に釘付けになります。
また、
伝統文化④歌舞伎 今を生きる江戸庶民
通訳ガイドのぶんちょうです。
今日も初心者向け、歌舞伎について私の視点で紹介していきます。
テレビも映画もなかった江戸の庶民は、歌舞伎が最高の娯楽だったわけですが、なぜそんなにハマっちゃたのでしょうか。
きのうの記事に書いたように、舞台演出の面白さがあります。でも、それだけではありませんでした。
歌舞伎のストーリーは大雑把に分けると以下の二つがあります。
時代物 (江戸時代から見た歴史物で
折り紙ができるのは実はすごい
通訳ガイドのぶんちょうです。
外国人観光客に折り紙を教えることがあります。新幹線の中ですることが多いです。車やバスの中では酔っちゃいますからね。
折り紙と言えば「鶴」が定番で、これなら私も自信を持って折れる唯一の折り紙です。でも、初めて折り紙をする外国人には難易度が高すぎるのです。つきっきりで教えてもできる人は一握りです。
中には上手にできる人もいますが、「四角い折紙を三角形になるように半分
ガイド開店休業中の生活
通訳ガイドのぶんちょうです。
外国人観光客の案内をする仕事なので、この仕事は開店休業状態が続いています。2020年の3月以来、数えたらもうすぐ20ヶ月。長い!
幸い夫がまだ現役サラリーマンなので生活に困ることはないのですが、大変ながらも充実していた日々が忽然と消えてしまい、初めの半年くらいは、何をして過ごせばいいのやらわかりませんでした。ガイド仲間から何してる?と聞かれると、「鍋底磨いてる」と答
WASHOKUが賞賛される理由
通訳ガイドのぶんちょうです。今日は、ガイド目線で和食について書いていきます。和食はWASHOKUとして2013年にユネスコによって無形文化遺産に登録されました。農林水産省のホームページの記載はこのようになっています。
南北に長く、四季が明確な日本には多様で豊かな自然があり、そこで生まれた食文化もまた、これに寄り添うように育まれてきました。
このような、「自然を尊ぶ」という日本人の気質に基づいた
子どものひとり電車通学にびっくりする外国人観光客
通訳ガイドのぶんちょうです。訪日外国人は、日本が安全な国だということは認識しています。それでも、都内の電車や地下鉄に小学生が一人で、あるいは友達同士で乗っていると、安全さの度合いが自分が思っていた以上だと知らされるようで信じられないような表情をします。
「あの子はなぜ一人なの?」と聞かれたことがあります。なぜと言われても...。一瞬返答に困ります。電車通学の小学生なんて日本人には見慣れた風景です