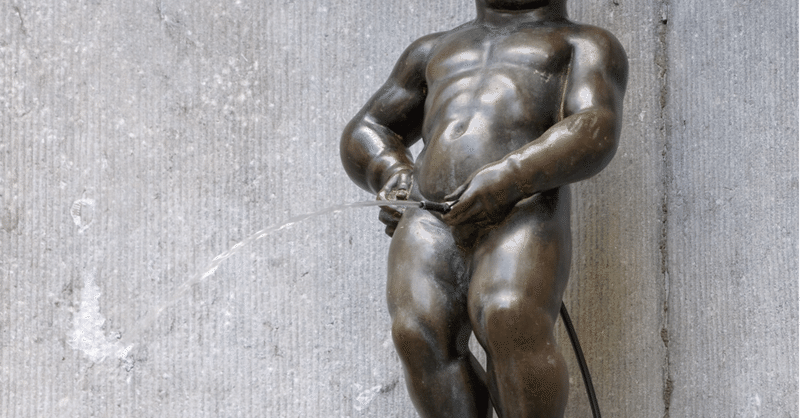
- 運営しているクリエイター
#読書
好作家需具备同化他人经验的能力
(優れた作家には、他者の経験を吸収する能力が必要だ)
※3/5/2024、文汇报
https://dzb.whb.cn/2024-03-05/7/detail-843331.html
「こんなひどい政治に見切りをつけて自分たちで勝手にやろう」
※マガジン9「雨宮処凛がゆく!第668回」
https://maga9.jp/240221-2/
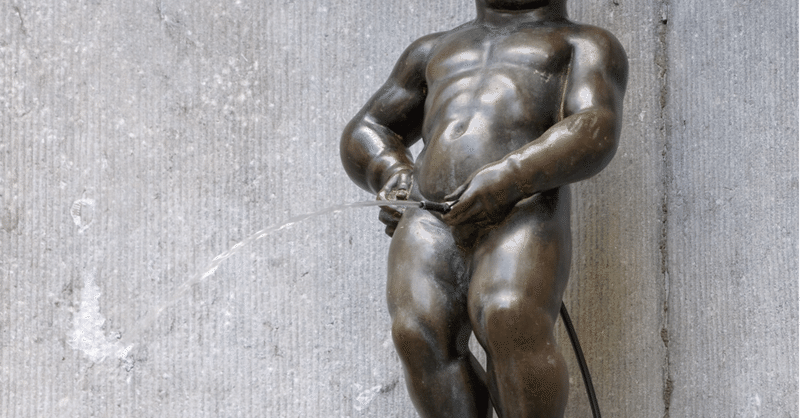
好作家需具备同化他人经验的能力
(優れた作家には、他者の経験を吸収する能力が必要だ)
※3/5/2024、文汇报
https://dzb.whb.cn/2024-03-05/7/detail-843331.html
「こんなひどい政治に見切りをつけて自分たちで勝手にやろう」
※マガジン9「雨宮処凛がゆく!第668回」
https://maga9.jp/240221-2/