
【勉強は再生】勉強とは、〇〇を作り直すこと
この度は、数ある中からご覧頂き、誠にありがとうございます。

【まえがき】
今回の記事内容はコチラ
1️⃣《対象者》
学生。
社会人。
資格取得を目指している人。
2️⃣《学び》
勉強する意味が学べます
3️⃣《記事を読んだ後、どうなって欲しいか?》
勉強して、とあるものをどんどん作り直してほしい
以上を踏まえてご覧頂ければ幸いです。
(関連記事)
こちらもご覧頂くと、より楽しむことが出来ます。

【前提】勉強は、ただ知識を覚えるだけではない
机にかじりつきながら出された問題を解き、暗記する。
これが、一般的な勉強のイメージですが、勉強への意味が少し違います。
勉強とは、ただ知識を覚えるだけではありません。
『とあるもの』を作り直すためにします。
今回は、「勉強」についてお話致します。

【結論】伝えたいこと
✅【勉強とは、自分の脳と心を作り直すことである】

【理由】
脳と心を作り直すので、それ相応の負荷が掛かるのは当然
まず、勉強とは自分の脳と心を作り直すことです。
こんな話があります。
「さっぱりわからない」
「同じところを何度も間違える」
「なかなか結果が安定しない」
勉強をはじめたときに誰もが通る体験です。
とてもストレスがかかります。
つい投げ出してサボったり、 別の勉強法を試してみたくなります。
安心してください。 そのような痛みを感じていることこそが、 正しい学びをしている証拠なのです。
2013年、 コーネル大学の神経科学者ネイサン・スプレングらは、学習による脳の変化を調べました。
38件の研究で撮影された学習前後の脳画像データを分析し たところ、 重要なパターンが見つかりました。
誰もが学びはじめは何回もつまずき、やり直します。 1つひとつ意味をなぞる地道な努力が必要です。
この段階で活性化していたのが 「背側部前帯状皮質」という脳領域です。
この部位は、何かを間違えないように注意を払う役割があります。
しかし学びが進むと、こうした脳領域の活動は低下していきます。
その結果、とくに気をつけなくても正しい手順で素早くこなせるようになります。
この段階で活性化するのが後帯状皮質や左後下頭頂小葉といった脳領域です。
ここはボーッとしている状態での脳活動を司る部位です。
ここが活性化しているときは、手先はスピーディに動きながらも前のことを思い出したり、 先のことを想像できる余裕が生まれます。
いわゆる「スジがいい人」とは、 注意を払い続ける状態からいち早く抜け出せた人を示すと言えます。
私たちは、勉強を通して自分の脳をつくり変えています。
あきらめず繰り返すことで、 脳に新しい回路ができて、最初は高度に思えたことも、必ず鼻歌まじりでできるようになります。
それを信じて、勉強の最初の進みが遅い時期を切り抜けましょう。
勉強の最初がつらいのは、誰だって一緒なのですから。
自分の力で自分という人間の心を成長させていくのです。
実はこれが勉強する「本当の目的」なのです。
たかが点数や順位をいくらか上げることが 「一世一代の目標」 であるかのようにおろおろしていては、エネルギーを発揮できるわけがありませ ん。
私もそれで疲れて、立ち往生してしまったのです。
それよりも勉強を通して「心を成長させ、自分を完成させること」に気を向けた方が、はるかに得るものが多いのです。
実際、私はやがて人生の舞台に上がる自分を「磨く」ことから目をそらしていました。
何が本当に重要なのかが分からなかったのです。 点数に執着することをやめて 「自分」に気持ちを集中すると、ストレスは減っていき、勉強がだんだん面白くなっていきました。
それにつれて、点数や順位もぐんぐん上がっていきました。
いまからでも「点数」から 「心」へと、勉強の焦点を変えてみましょう。
勉強するいまくらい「自分の心を削り、くっつけ、整えること」に全力で集中できる機会はめったにありません。
年を取るほど、その場その場でやるべき仕事がたくさん出てくるからです。
大人の多くが、10代のころに作り上げた心のままで一生 を過ごします。
いまこの瞬間が、自分の中をよいもので満たし、 悪いものを払い落とすチャンスです。 勉強を通して自分に気持ちを集中させ、自分をよりよい人間に作り変えることができるのです。
人生の勝敗は、その人が持つ「心の力」の強さによって決まります。
自分の中をよいもので満たし、 悪いものを払い落とすチャンス、「魂を鍛え上げる絶好のチャンス」を逃さないようにしましょう。

脳と心を作り直すので、それ相応の負荷が掛かるのは当然です。
だからこそ、どんな勉強も最初は辛く感じます。
そして、辛くなってしまうので、『ラボリの法則』が働きます。
これは、
人は、困難な状況に直面すると、脳が防御メカニズムを作動させて、その状況に抵抗し、ストレスの少ないほかのことを見つけようとする。
この反射は何十万年にもわたって構築されてきたもので、生存本能の一部だ。
サーベルタイガーに食われないようにしたり、甘い果物を食べようとしたりするのと本質的に同じだ。
この現象は、困難な状況を回避して、代わりに楽しい状況を探すという人間の傾向を研究したフランスの神経科医の名前にちなみ「ラボリの法則」と呼ばれている。
甘いフルーツジュースを飲んだり、ピスタチオ味のアイスクリームを食べたり、インスタグラムの写真で「いいね」を受け取ったりと、楽しいことを経験すると、脳は、喜びを、 生み出す化学物質ドーパミンを出すことで、私たちに報酬を与える。
脳は、ご褒美のホルモンを多く手に入れるために、時間がかかるものよりもすぐに満足感を与えてくれる行動を優先しようとするのだ。
勉強が辛くなって、スマホやゲームをしてしまう理由になります。
スマホやゲームは始めるのは簡単ですが、停止ボタンを押すのが難しいです。
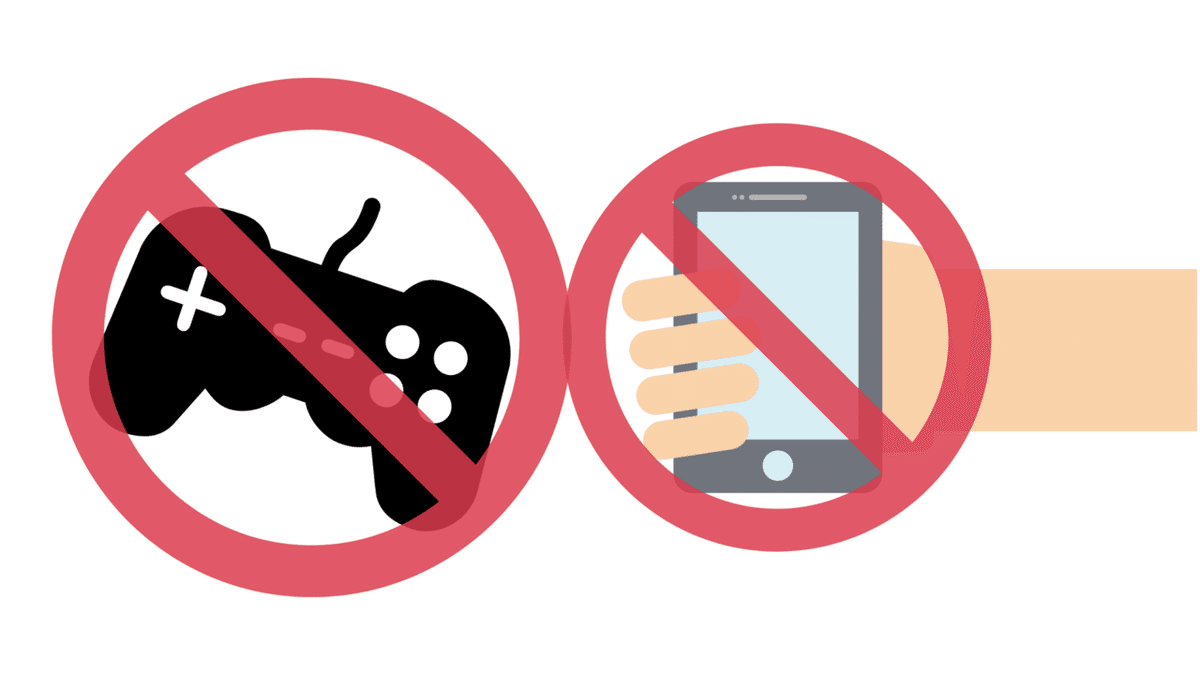
この影響もあるのか、
実は、日本人は大人になってからの勉強量が先進国の中でもワースト1位といわれています。
また、
2022年8月31日に総務省統計局が発表した令和3年社会生活基本調査(生活時間及び生活行動に関する結果)によると、有業者の「学習・自己啓発・訓練」は週全体で平均7分という結果でした(研修などの時間は除く)
🅿️つまり、週8分以上勉強すれば、脳と心は作り直されて、簡単に周りよりも常に一歩先に行くことが可能になります。

【方法】
勉強には一工夫が必要
では、ここでオススメの勉強法を2つご紹介致します。
①楽しく勉強するために、漫画やイラストの多いものを選ぶ。
②メンタルマップを活用する
順番に説明していきます。
まず、『①楽しく勉強するために、漫画やイラストの多いものを選ぶ』ですが、これには理由があります。
絵や図を描くなど、「視覚」を使って説明すると、理解しやすく、また何倍も記憶に残りやすくなります。
ある事柄を説明して、72時間後にどれだけ覚えていたかを調べた実験があります。
「口頭で説明」した場合は、10%しか記憶していなかったのに対し、「絵を使いながら説明」した場合は、65%も覚えていました。
視覚を使うと、口頭で説明するよりも倍以上記憶に残るのです。
別の研究では、 2500枚以上の絵を10秒ほど提示したところ、それらの絵は90%以上の精度で数日間記憶されました。
さらに1年後に再検査したところ、なんと63%も記憶されていたのです。
文字よりも、絵は圧倒的に記憶に残りやすい。
インプットが視覚的的であればあるほど認識されやすく、 思い出す可能性が高くなる。
心理学ではこれを「画像優位性効果」と呼びます。
ビジネス書でもマンガ版があります。
分かりやすく記憶に残るのでオススメです。
そして、『②メンタルマップを活用する』です。
こちらは、
本を読む前の準備として、最もシンプルで効果的な方法が「メンタルマップ」を作ることです。
メンタルマップとは、自分の人生の目標や行動を箇条書きにして視覚化したもの。
その効果は文字通り、読書中に迷子にならないよう「地図(マップ)」を示してくれることです。
人間は行動を起こすとき、何らかのやるべき理由と自分へのメリットを感じています。
ところが、日常生活を送る間に、「なぜ、自分がその行動を始めたのか」を見失ってしまう傾向があります。
取り組んでいることに意義が見出せなくなり、 行動に迷いが生じ、挫折してしまうのです。
こうした人の心の動きに着目し、挫折を避ける方法としてハーバード大学の心理学者であるショーン・エイカーが提唱しているのが、メンタルマップです。
何か行動を起こすとき、その理由、もたらされるメリット、期待していることなどを3つ箇条書きでメモに書き出します。
そして、何らかの迷いが生じたとき、そのメモを見直します。
すると、脳が自分の行動の意義を再認識し、やる気を取り戻すことができるという仕組みです。
これで、勉強する意味とモチベーションを保つことが出来ます。
『コミュニケーションの勉強をする』と仮定した場合、こんな風に書きます。
①何故この勉強をするのか?
「人間関係を良好にしたい」
②何を学びたいか?
「コミュニケーションが苦手なので、誰とでも気軽に話せる会話術」
③勉強した後、どうなっていたいか?
「今まで話したことがない人ともコミュニケーションが取れるようになりたい」
A4用紙や手書きのメモ帳に書いたりすることをオススメ致します。
スマホに書いてしまうと、つい動画やSNSを見てしまう可能性があります。
なので、紙に書くようにしましょう。
この2つを組み合わせて、勉強してみてください。


まとめ
1️⃣勉強とは、自分の脳と心を作り直すこと
2️⃣自分の脳と心を作り変えるので負荷が掛かって辛く感じるのは当然。
なので、勉強のやり方に工夫が必要である。
3️⃣マンガやイラストの多い教材を使ったり、メンタルマップを活用して勉強してみよう。
🈁《勉強とは、今まで知らなかった自分に出会うこと。
脳と心は一生作り変えられる。
さぁ!勉強でもっともっと自分を成長させていきましょう!》
私の記事が、今後の皆様の成長に繋がることを、心より願っております。
参考文献
↓↓↓
(関連記事)
こちらもご覧頂くと、より楽しむことが出来ます。
✳️マガジン一覧
過去記事をまとめたマガジンを掲載致します。
宜しければご覧ください。
✳️自己啓発ソムリエ 言葉で動くのコンセプト紹介
自己啓発ソムリエ 言葉で動くの
自己紹介になります。
宜しければご覧ください。
↓↓↓
「私が何故、自己啓発を記事にするのか?」その理由が書いてある記事となります。
宜しければご覧ください。
↓↓↓
「何故、本を読み続けるのか?」その理由が書いてある記事となります。
宜しければご覧ください。
↓↓↓
「私が知識にどういう思いをかけているのか?」を書きました。
宜しければご覧ください。
↓↓↓
以上になります。
最後までご覧頂き、誠にありがとうございましたさ
皆様のサポートが、note活動の励みになります。 そんな気持ちにお返しが出来るように、記事に磨きを掛けるために使わせて頂きます。 宜しければサポートをお願い致します。
