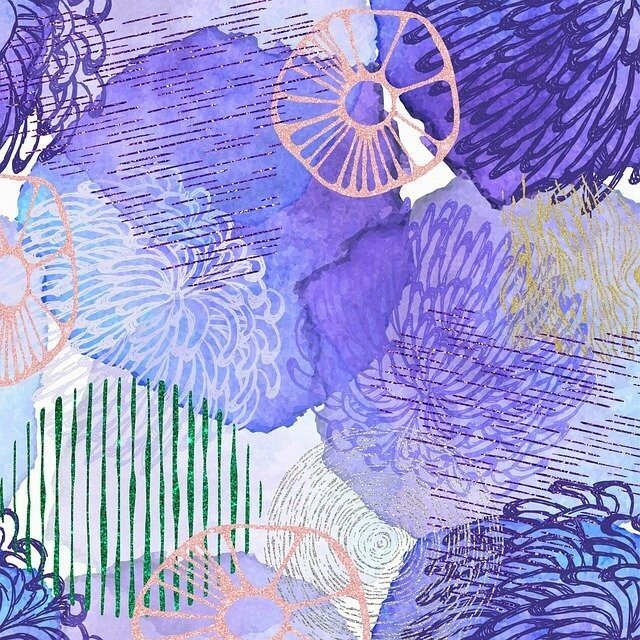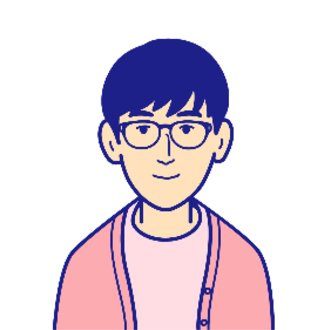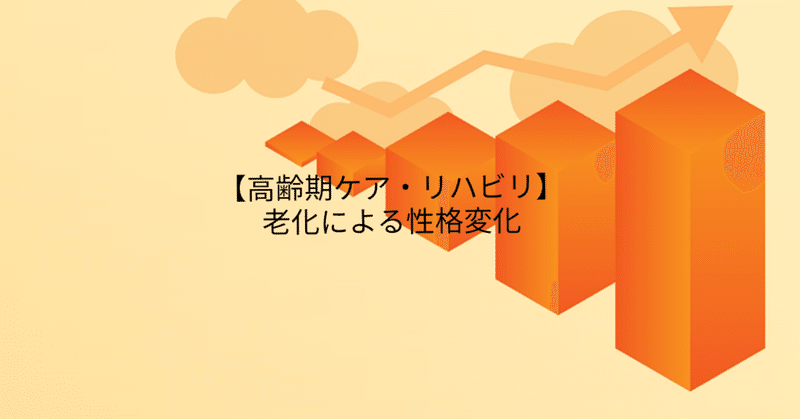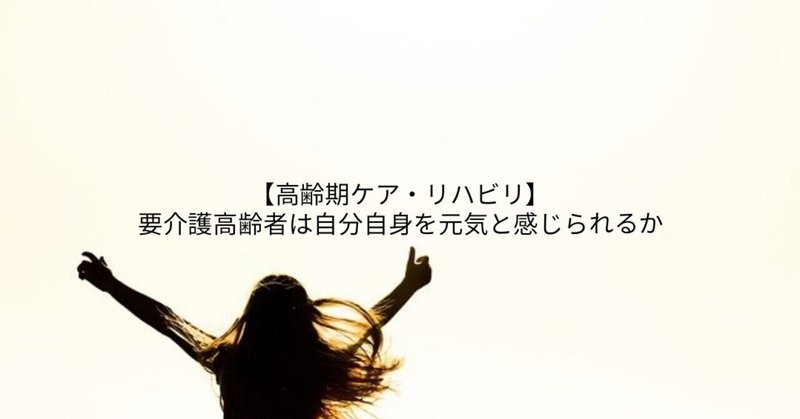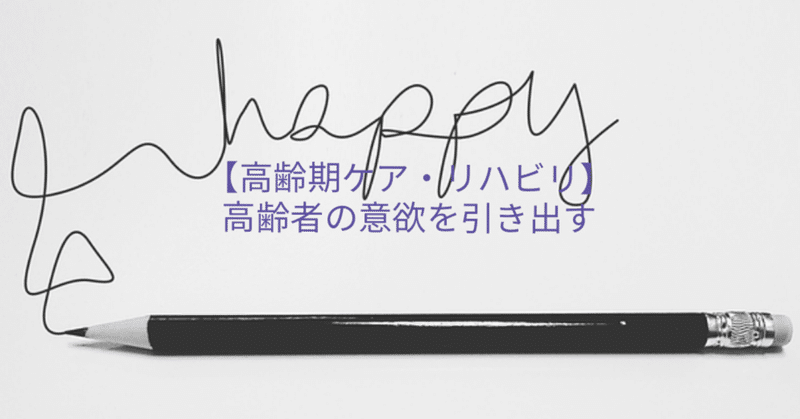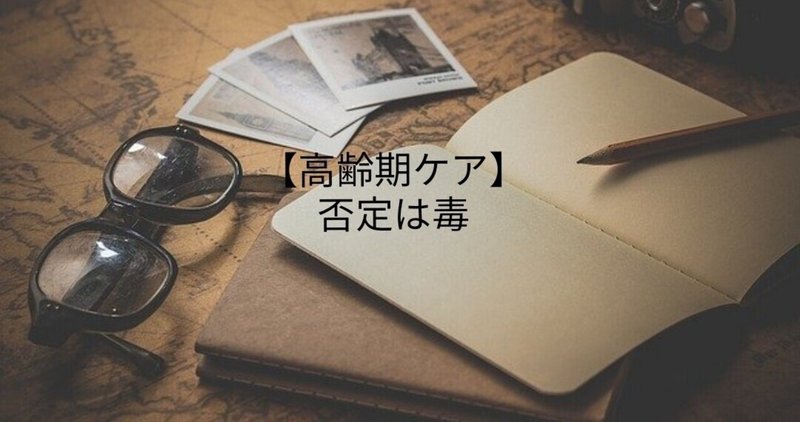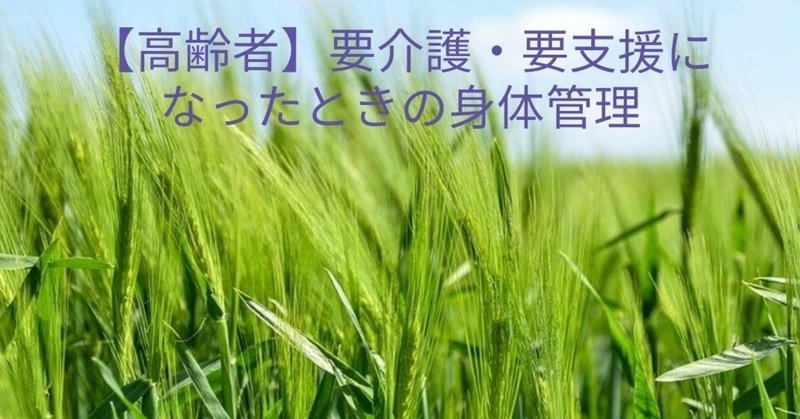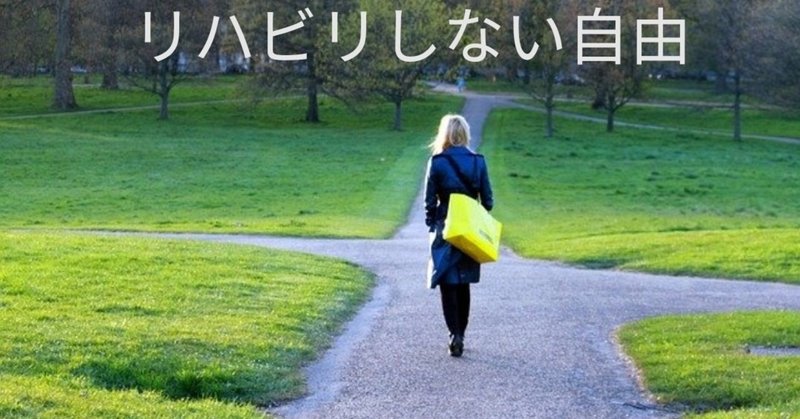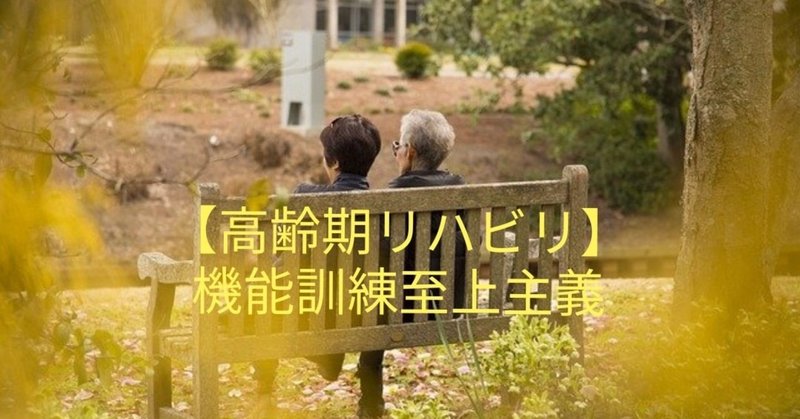#要介護
出版しました「要介護でも健康に暮らす方法」
手前味噌ですが(・。・;
「要介護でも健康に暮らす方法」
(Amazonから購入できます)
という本を出しました。
こんな方に読んでいただきたいです。
〇団塊の世代の方・家族介護されている方
〇介護保険サービスに携わっている専門職の方
〇作業療法士
内容自分や家族が
要介護・要支援になったときの
介護やリハビリの考え方やノウハウ
です。
詳しくは
①高齢者は機能訓練を過度に
【高齢期リハビリ】機能訓練至上主義
「機能訓練至上主義」、ツイッターでこんな言葉を見かけまして記事を書いてみました。
介護保険サービスの現場ではリハビリの仕事に携わってますと介護保険サービスでは身体機能の回復にどうしても注目が集まります。
たとえば
ケアマネさん「下肢筋力が弱ってきたのでリハビリできるデイ(通所サービス)を利用しませんか?」
家族「少しでも身体が元気になれば…。」
本人「また機能訓練すれば、元のようになれる