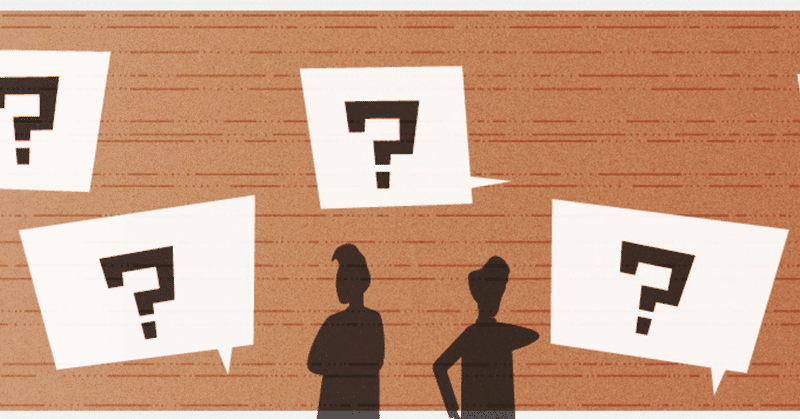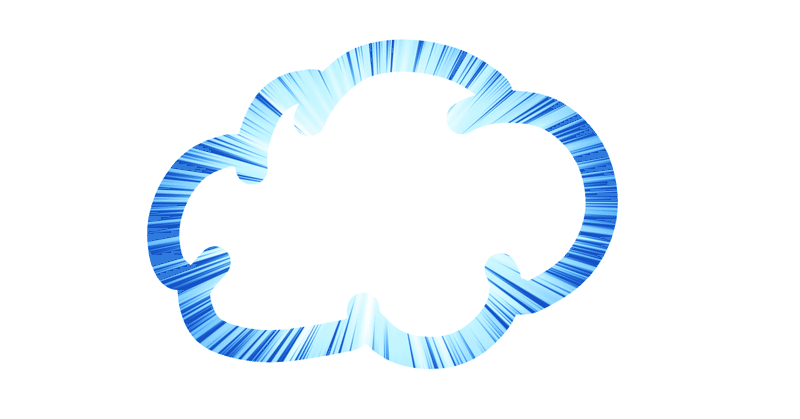2021年4月の記事一覧
ゴールを設定したときに、そこには誰がいますか?
仕事をしていると、「ゴールは何か?」を問われることは少なくありません。
プロジェクトのゴールであったり、1時間の打ち合わせのゴールであったり。確かにゴールがないと迷子になって、何をやっているかわからなくなります。ゴールを設定するのは重要なことだと思います。
私は製造業で事業企画をしています。今は事業部のマクロ事業計画を担当していますが、その立案過程において、方針としてゴールを示すのが非常に重要
部下に話してもらえるための聴き方とは。
私の会社では、定期的に匿名でアンケートを取っています。
それは各部署の上司に対するアンケートです。匿名ではあるものの、課単位、部単位で点数が集計され、それがマネジメント層にフィードバックされます。
数字の絶対値が悪かったり、前回に対し悪化傾向があれば、会社や労働組合から名指しで改善指示がきます。悪目立ちしたくないマネジメント層はこの結果を戦々恐々待っているわけです。
ちょうど1年前、その数字が
行動する人のミッションに合わせてアイデアを出そう。
前回、私の仕事である事業企画業務で、関係部署に目標達成に向けたお願いをするときのマインドセットについて書かせていただきました。
振り返ると、自分の立場で言いたいことをいうのではなく、
「相手の話を聞き」「共感=肯定し」「相手のやりたいことを提案する」
というのが重要です。
「相手のやりたいことを提案する」はもう少し分解できて、
・相手にとって有益なことと会社に必要なことをすり合わせる
・そ
共感して提案するおもてなし精神で仕事に取り組んで成果を導く。
私は製造業で事務職として事業企画に携わっています。
業績を出すためには、当然設計者や、なによりも工場サイドの活動が不可欠です。
そんな中で私たちのような事業企画をするメンバーは業績や目標を数値目標として示し、「やらねばいけないこと」を説いていくわけです。
例えば経費目標や、原価目標といったものです。「このくらいの予算に納めないと目標利益が出ない」という話をするわけですが、それ自体は必要な情報で
Kintoneで創造力を刺激し、自発的なDX活用を促す。
昨今DXが叫ばれますが、DXは人材育成の格好の機会です。
私の仕事は事業計画なので、毎月の売上集計などルーティンが多く、DXという言葉のない時から様々な方法で効率化をしてきました。
よくあるのがMicrosoft Accessです。
売上明細のようなデータを分析できるように、アルファベットの社内コードになっているところに顧客名をつけたり、品番しかないところにパラメータを使って製品名をつけたり。
育てているようで、育てられる。チームマネジメントも子育ても同じ。
私は今年から課長となり、部下を抱えています。
でも、これがチームを率いる初めての経験かというとそうではありません。
私が32歳、係長になった時に、2名の後輩とチームを組みました。一人は4年後輩、もう一人は9年後輩です。
係長になったときに、上司からは「自分一人で成果を出すのではなく、二人の後輩をうまく使って成果を出せるようになってほしい」と言われ、その通りだと思い、気合が入りました。
自己紹
自分の価値基準と相手の価値基準の摺りあうポイントを見つけるのが管理職の役割。
私の所属している組織では、今度人事異動があり、それに伴い、チーム内でも業務担当の変更を行うことになりました。
課長以上で話し合って業務分担を決め、それをメンバーに説明していくのですが、納得してもらうのに苦労をしています。
みんな正論はわかっているので、どうしてそのような担当になったのか、説明すれば一定の理解を示してくれます。しかし、どこか納得できない気持ちがある。全員が全員同じ価値基準ではあり