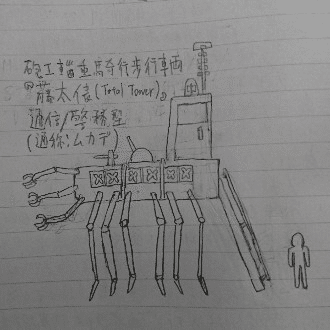随筆(2021/3/6):魔法と科学の対比を、もうちょっと広く考えてみる(1.前提としての「目的物→行為者→手段→法則」または「財→専門家→技術→学問」モデル)

1.「魔法と科学はどう違うか」というテーマ
1.SFとファンタジーに関する創作に関して、時々出て来る、「魔法と科学はどう違うか」というテーマ
SFとファンタジーに関する創作に関して、時々出て来るテーマに、
「魔法と科学はどう違う(と考えるとしっくり来る)か」
というものがある。
先日、これの、自分なりの切り口を思いついた。
単純に「魔法と科学」という切り口ではなく、他のものも含めた、やや大きめの構図になった。
自分では「あー、これはこれで切り口としてはありうるやつだ。しっくりと来る」と思っているのだが、まあ説明を試みてみます。
1.2.ざっくりとしたイメージ
まず、「魔法と科学」の指しているものを厳密に定めるというより、そこからざっくりとイメージされるものを考えたところ、
「そもそもこれは、もうちょっと大きな枠組みで、「神の領域」「魔の領域」「人の領域」として考えた方がいいのではないか」
「神の領域のものを扱うために、魔の領域のものが生じて、どんどん神の領域から間接的になっていったのではないか」
「魔の領域から、さらに零落した人の領域のものが、零落したままで、神の領域に直接的に近づこうとしたのではないか」
「ただし、そうやって得られたものは、降って湧いてくるものではなく、自分で手に入れるものなので、その時点で神の領域そのものにはなり得ないし、有り難みのない人の領域にとどまるのではないか」
というざっくりとしたイメージが浮かび上がった。
とはいえ、これでは何の話か分からないと思うので、もうちょっと説明を試みます。
1.3.前提としての、「あると嬉しいものが今正にそこにあるのか、それとも何層かのクッションが要るか」という問題意識
一般性を出来るだけ保ちながら、それでも具体的にいうと、まずは
「あると嬉しいものが今正にそこにあるのか」
「ボタンを押すと出てくる程度にはワンクッション要るものなのか」
「それともなんかクソ面倒臭い技術のツークッションが要るのか」
「クソ面倒臭さの極みである深遠な学問を学ばねばならないスリークッション制なのか」
という話があります。
***
「あると嬉しいもの」とは、経済学用語でいうところの財(goods)と概ね同じようなものを指しているので、今後はそう呼びます。
で、上の話をもうちょっと整理すると、
「あると嬉しいもの、『財』が、既にここにある」
「財、つまり、あると嬉しいものがないから、『専門家』がなんかして、あるようにする」
「なんかうまくいかないので、うまくいくための『技術』が要る(この場合、『専門家』は『技術者』でもある)」
「技術がうまくいかないので、うまくいくための『学者』による『学問』が要る」
という、「財→専門家≒技術者≒達人→技術→学者≒学問」といった目的手段関係ないし問題解決関係がある訳です。
財があるのが一番有り難い。そして、学問まで降りて来なければならないとなると、これは有り難みに乏しい。
(平たく言うと、会社の人事担当者が「大学はとにかく即戦力となる学生を育てろ」と言い出す話ですね。
ごもっともですが、とある理由で、不毛な話です。
それについての説明は後でします)
***
さらに抽象的にいうと、
「『目的』となるもの、『目的物』が、既にここにある」
「目的物がないから、あるようにするために、『行為者』が『行為』せねばならない」
「行為がうまくいかないので、うまくいくための『手段』が要る」
「手段がうまくいかないので、うまくいくための『法則』が要る」
という、「目的物≒目的→行為者≒行為→手段→法則」といった目的手段関係ないし問題解決関係がある訳です。
目的物があるのが一番有り難い。そして、法則まで降りて来なければならないとなると、これは有り難みに乏しい。
これが、今から言う話全般の、主軸になります。(だいたい連載三回くらいで終わればいいですね)
1.3.直ちに『目的物』(財)が得られるなら、一番有り難い
目的物が既にここにあるなら、それは恩恵とか奇跡とか幸運とかそういう神の領域のもので、一番有り難みがある。
あったらいいなと思った時に、人が努力せずに、降って湧いて来ている。というのがポイントだ。
ここが全ての出発点だ。
1.4.目的物(財)を得るために要請される『行為者』(専門家≒技術者≒達人)
目的物がないから得るためには、行為者が行為をしなければならない。(シビアな話だ)
ヒトの社会はしばしば分業制で、行為者はそのうち専門化していって、専門家が出て来る。
こうなると、依頼者は専門家に頼めばいい。と言うことになる。非常にシンプルだ(依頼者にとっては)。
「能動的にボタンを押したら出て来る」とまでは簡単ではないだろうが、それに近い。
もちろん、この時点で「既にここにある」という、神の領域のような圧倒的有り難みはなくなってしまっている。
だが、「欲しいときに欲しいように得られる」のは、それはそれで、アド(利点)だ。
(もちろんこれは、ちゃんと得られたら、の話であるが)
***
たいてい、誰しも、「人の手に余ること」を専門家に任せたくなる。
が、こういう専門家は、大昔はしばしば、シャーマンなどの広義の魔術師と重なることになった。
やりたいことだが、人の手に余る、よく分からない、ちょっと面倒なこと。
こういうのは、平たく言って、魔の領域だ。
それをやる人たちが広義の魔術師として、魔の領域の存在という扱いをされるのも、自然な流れであろう。
(この話はたぶん次々回にします)
1.5.行為者(専門家≒技術者≒達人)に要請される『手段』(技術)
当のなんかの行為者としては、自分のなすべき行為において、準備や手順は「ある」ものであり、それはひっくるめて、技術として、押さえておかねばならない。
だって、準備も手順も技術もなくていいなら、基本誰でも使えるし、人に頼まずに自分でさっさとやってるからな。
準備も手順も技術も要請される場合は、専門家≒技術者がやるのだ。
で、なんかの技術者でも「この場合、こうすれば、こうなる」程度の、準備なり手順なり技術なりのことだけわかっていればいい場合は、ふつうのなんかの技術者をやっていけるし、それで老練の達人にもなれる。
これで十分に現場が回る場合は多々ある。だったら、それでいいんだよな。俺だってこのカテゴリだし。
1.6.手段(技術)に要請される『法則』(学者≒学問)
だが、いずれ、
「これをやればこれが出来るが、求められているものとはやや違う。どうすればいいのだ?」
という工夫の話が出て来るかもしれない。
というか、しばしば出て来る。
「どんな場合、どうすれば、どうなる」の事例研究(口伝や、文字があった場合、それはいずれ資料として記録され、編纂される)がなされ、整理が出来たら、なんかの技術者はこれを再利用して、いろんなことができるようになる。
こうなると、なんかの技術者は、そういう一連の営みを求めるようになる。
そして、事例研究や記録や編纂や整理や再利用等を一連の営みとする『学問』が、『学者』が出てくる。
(もちろん学問には他にも意義がたくさんあり、ジャンルによっても異なるが。
これについては次回、科学との絡みで、少し触れます)
なんかの技術者は、しばしば、老練の達人に訊いて、新たな技術を体得するものだ。
その達人が、たまたま教え上手で、しかも学者肌だった場合、技術の承継は非常にスムーズになる。
もちろん、学問そのものも、そうやって承継される。
1.7.法則(学問)は、目的物(財)とは、間接的にしか関わっていない
逆に言えば、そういう技術(や学問そのもの)に効く形でこそ、学問は役に立つのであって、学問が直ちに財をもたらしてくれる訳ではない。
この間接性はそのままでは埋まらないし、財がもっと欲しい依頼者がしばしば「学問なんか何の役に立つんだ」論法を使う、大きな理由にもなる。
「じゃあ、法則に裏付けられていない手段で、デタラメに行為して、目的を達成してみたらどうなるか、分かっておられるのか。
しばしばやれないし、もしやれても、質や量はスゲエ無残なことになるぞ」
という回答をしたくなる。
だが、こうした説明が通るとも限らない。
やはり、目的物が目の前にあるかないかが一番大事で、ないならそれは
「いずれ大量かつ高品質のものが得られるかも知れないので、見守っていて欲しい」
という説明をことごとく吹っ飛ばすほどの不利益だ。
ここで何もかもを吹っ飛ばすと、たいてい全員が長期的には損をするのだが、今損をしている人に
「長期的に損をしないために、今短期的に損をしてほしい。その過程で、あなたが潰れても、私は知ったことではない」
という説明が、通じる訳がないんだよな。
潰れたら、長期的な得もへったくれもないに決まってるやんけ。
そんなことを説得側が考えすらしてないのに、説得なんか、出来る訳、あるか?
1.8.そこで科学です
で。
実は、学問を少しでも目的物に寄せようとすると、科学になるんです。
そんな訳で、次回は科学の話をします。
特に、
「科学の軸を考慮すると、事情が違って来る。
まず、「財→専門家→技術→学問」から「科学技術的成果←科学技術者←科学技術←科学」に矢印がひっくり返る」
という話をします。
乞うご期待。
(続く)
いいなと思ったら応援しよう!