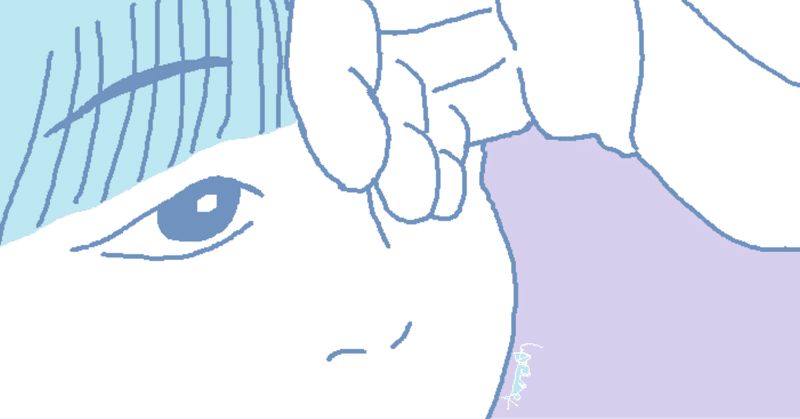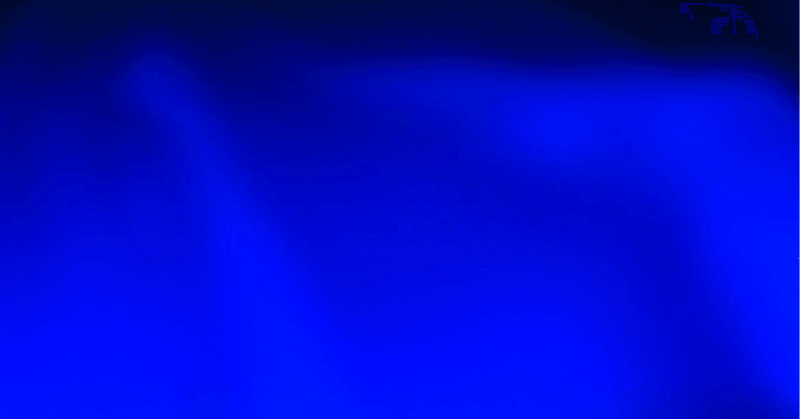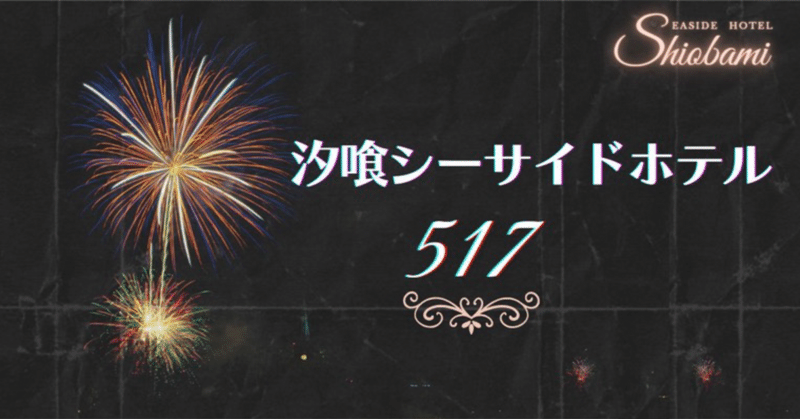記事一覧
プロローグ/夜のない星
彼女の視神経について書こうとしている。羞明と呼ばれる症状だ。光に極度に反応して、些細な光量であっても眩しく感じる。彼女の症状はその最たるもので、夜であっても眩しいという。夜を見たことがないという。
鳴宮聡子。
彼女が知っているのは、光と色が混沌とした夜だ。雷鳴、そして驟雨——網膜にできた夥しい光の傷が、彼女の視界に降りそそいでいる。
「笑い話があるんだけど」と彼女は、路地裏で燻っている焼死体
【詩】真夏のやけっぱち
無色の火柱があちらこちらで燃えさかる
500ml
あまりの非力さにむしゃくしゃしながら
シャッターだらけの裏道でゴミ箱をけとばした
だれかの吐瀉物がわたしの靴をよごしたけれど
吐瀉物よりどろどろな自身の臭いに鼻がゆがんだ
どろどろは包み隠すほどに光り輝き
正当化する被害者意識、争いのはじまり
それは本意ではない、誠に遺憾であります
ばらまかれた快楽
優しい言葉、きれいな言葉の裏側にはりつく焦り
救
【映画感想文】そのセックスが嫌だったと気がつくまでには時間がかかる - 『HOW TO HAVE SEX』監督: モリー・マニング・ウォーカー
たしかに同意はしたけれど、本当は嫌だったということは往々にしてある。
面倒くさい仕事だったり、友だちや親族からのややこしいお願いだったり、つい、空気を読んで「いいよ」と言ってしまったばかりに悶々としてしまう。
「そうだよ。わたしはたしかに同意した。でも、それはNOを言えない雰囲気に負けてしまっただけ。本当はちっともやりたくないんだってば!」
心の中ではそんな風に叫びたい。でも、どうせ誰
小説/汐喰シーサイドホテル704号室
「お願いだよ、この通り。な、な?」
父さんは 汐喰シーサイドホテルのフロントカウンターで両手を合わせる。
僕はカウンターに飾られた金色に光る〔Good-bye 2023〕の文字を見つめてる。
「海の見える部屋だって本当はひとつくらい空いてるだろ。な」
「申し訳ございません。あいにく満室でございます」
ホテルの人は同じ言葉を繰り返す。
「年越しの花火を子どもたちに見せたいんだよ。分かるよな。な?」