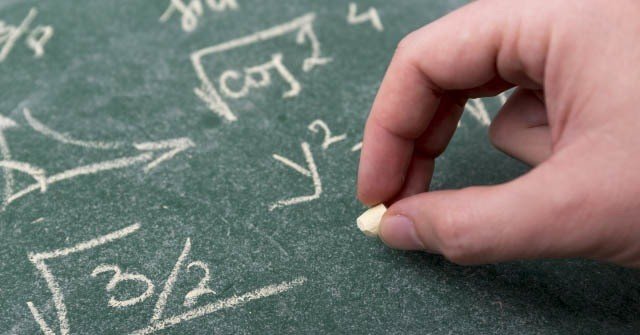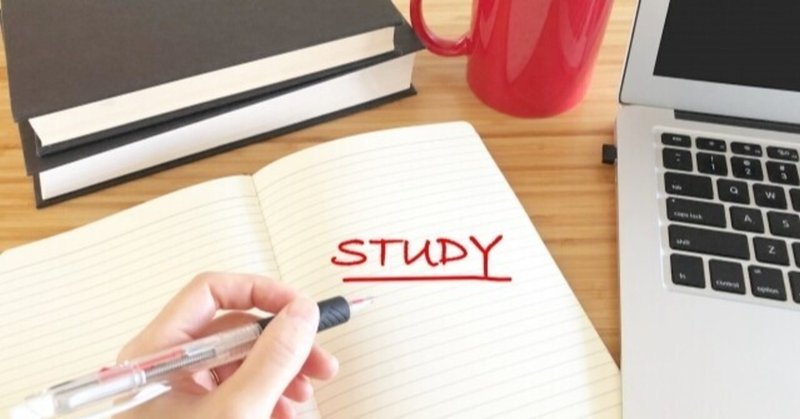#オンライン授業
時代は超効率重視?近大の調査から見えてきた、新たな学生の学びスタイルをどう受け止めるかについて考える。
コロナ・パンデミックがはじまって2年半が過ぎました。アフターコロナの社会はどうなるのか?みたいなことが話題にはあがるものの、コロナがどこかのタイミングできれいに収束して、コロナのない世界がはじまる、というのは、おそらくないように感じます。
グラデーション的に変化しつつ、気がつけばコロナがあまり気にならない、コロナと共存した社会になっていた……、そういうのが現実的なのではないでしょうか。であれば、
”対面の価値“の最大化は、大学キャンパスだけではなし得ない。近大が取り組む、大学街活性化策の意義を考える。
新年度に入って、学生たちがキャンパスに戻ってきました。活気のある大学の風景やざわめきはやっぱりいいもので、構内を歩いているだけで元気をもらえます。その一方で過去2年間のキャンパスがとてもイレギュラーな状況だったのだと、あらためて感じさせてもくれます。
このイレギュラーの状況は大学だけでなく、その周辺、つまり大学街にも大きな影響を与えました。今回、見つけた近畿大学の取り組みは、活気がもどった大学が
オンライン授業に必要なのは監視か、信頼か。テレワークとは異なる、オンライン授業ならではの難しさ。
オンライン授業が、コロナ後の大学教育にどんな影響を与えるのかは、大学関係者でなくても興味のあるトピックです。今回、取り上げる早稲田大学のニュースは、そんな大学のオンライン授業の今後を考えるうえで、しっかり議論した方がいいもののように感じました。こういったニュースを、大学そして社会がどう受け止め、どうやって未来への肥やしにしていくかが、大学教育を豊かにしていくうえで必須なような気がします。
ニュー
今後、一気に増えてくる?海外大学と結ぶオンライン教育の協定は、日本の大学に何をもたらすのかを考える。
大学の学びにオンラインをどのように活かしていくべきかは、コロナ禍になって以降ずっと注目されているテーマなように思います。今回、見つけたプレスリリースも、そんなアフターコロナのオンライン教育を意識した意欲的な一手だと言えます。これまでになかったような大学の学びがでてくるのを目の当たりにすると、やっぱりワクワクしてきますね。
リリースの内容は、追手門学院大学がペンシルバニア大学と「Online Le
オンライン授業を深めるヒントは授業外にあり?関西外大のオンラインクイズイベントに見る、抜け落ちていた視点。
大学がコロナ禍で得たものとして、最もといっていいほど大きいのはオンライン授業への理解、ノウハウ、また対応できる環境(学生側も含めて)ではないでしょうか。おそらく、オンライン授業は何らかのかたちで、アフターコロナにも残っていくのは間違いないでしょう。今回、見つけたのは、こういったオンライン授業のグッドプラクティス……ではなく、オンライン授業をより豊かにするかもしれない、そんなヒントになりそうな取り組
もっとみるよくよく考えると実は尖っていた立教大学のコロナ対策が教えてくれる、大学の姿勢を行動で示すことの大切さ。
GW前に立教大学がコロナ感染症対策のために3.7億円を投じたという記事を見つけました。積極的に対応しているなぁと思いながらも、そのときは読み飛ばしたのですが、よくよく考えてみると、実はけっこう尖った使い方なのかなと思いなおしたので、今回これについて取り上げてみることにしました。
まずは記事をご覧ください。じゃじゃん。
短い記事なのですが、さらに端的にまとめてしまうと対面授業の割合を大幅に増やす
甲南女子大学の公開講座の打ち出し方をヒントに考える、オンライン学習に慣れた世代との新たな関係性のつくり方。
新型コロナが流行ってから、公開講座をオンラインでやる大学が増えてきたというか、それがニューノーマルな開講方法として定着しつつあるように思います。公開講座の担当者からは、オンライン化したことで受講生が増えたという声もちらほら聞いており、少なくともこの種の取り組みに関していうと新型コロナは追い風だったのではないでしょうか。
今回、見つけた甲南女子大学のリリースも、そんな公開講座の変化を感じさせるもの
これから支持される学びは、いち大学では成立しない?学びのオンライン化がもたらす、新たな学びの評価軸を考える。
魅力的なオンラインの学びにある2つの共通点オンライン授業という学び方が大学教育に本格的に取り入れられるようになり、なんだかんだでもうすぐ1年が経とうとしています。当初は対面授業の代替として、対面でやってきたことを何とかしてオンラインに置き換えようとする取り組みだったように思います。でも、時間が経ち、学びのコツや特徴がわかるようになってきて、じわじわと内容が変化してきているようです。今回はそんな新し
もっとみる今だからこそ意味がある?成蹊大の「オンライン授業の取り組み」特設サイトがシンプルながら考えさせられる。
以前、成蹊大学とサイバー大学の連携についてnoteに書いたことがありますが、今回も成蹊大学のオンライン授業関連の取り組みについて紹介したいと思います。この大学はオンライン授業の受け取り方が、とてもポジティブで見ていて気持ちがいいです。
成蹊大学「オンライン授業の取り組み」特設ウェブサイト
どんっ。取り上げるのは、「『オンライン授業の取り組み』特設ウェブサイト」。名前ですぐわかるように、成蹊大の
急速なオンライン化のなかで置き去りにされそうな、言語化されにくいけど大切な授業以外の大学の価値、を考える。
大学=勉強をするところ、というと、正しくはありますが、ほとんどの学生は少し不満気な顔をするのではないでしょうか。クラブやサークル活動であったり、友達との会話であったり、それにゼミの飲み会や大学祭、さまざまな出来事があってこそ、学生たちが期待する“大学”になるからです。
今回のコロナパンデミックで「学びを止めるな」と方々から声が挙がり、大学を含む教育機関の関係者たちが尋常ではない努力をし、その姿が