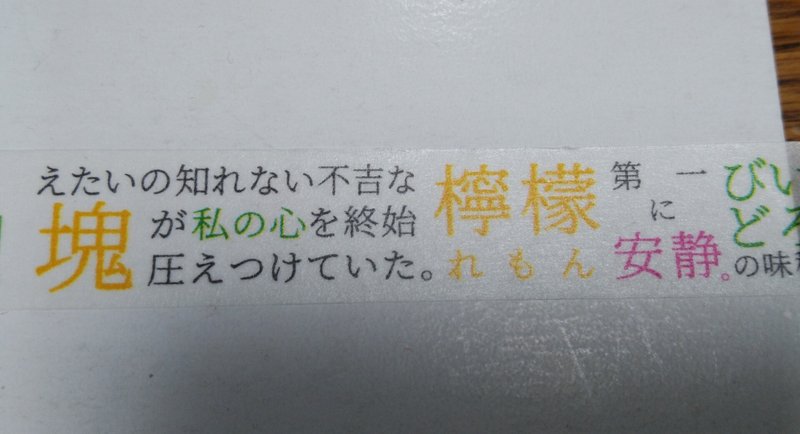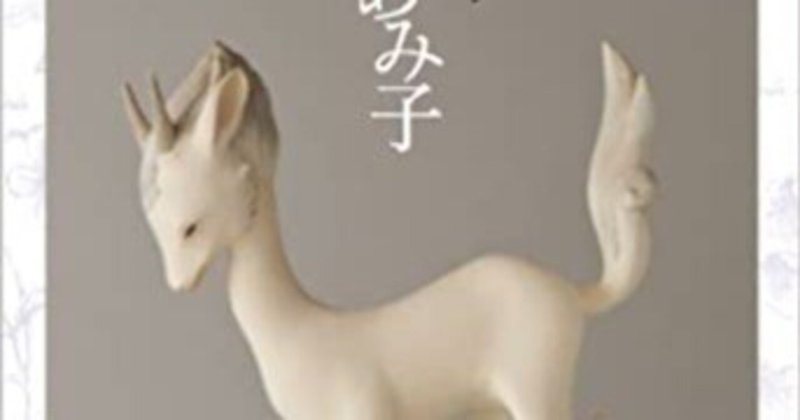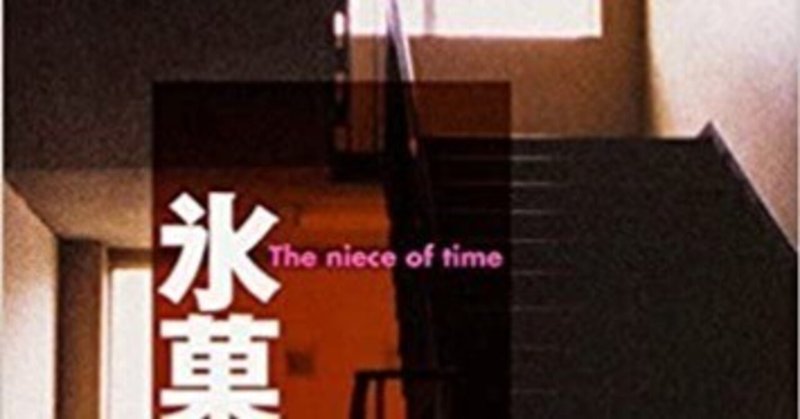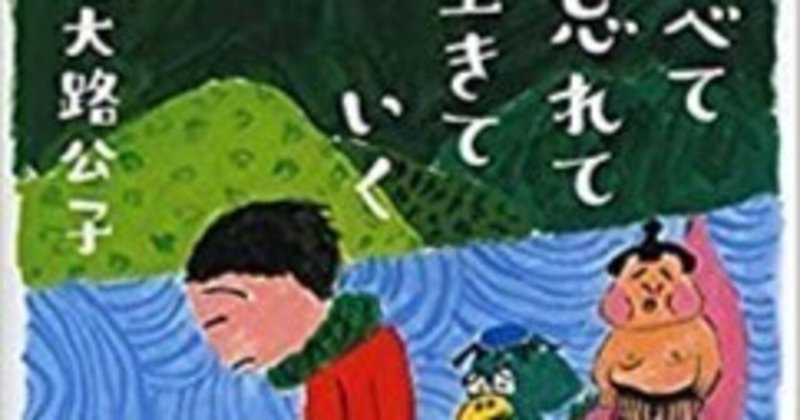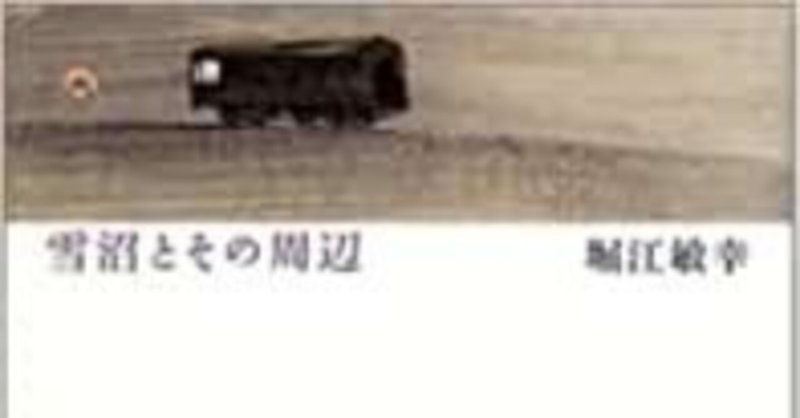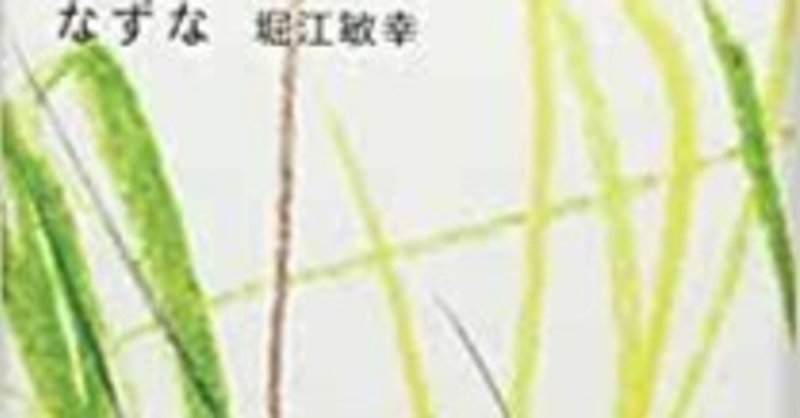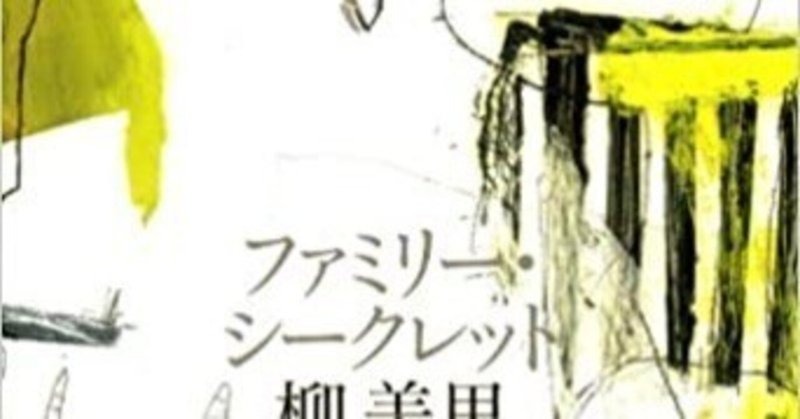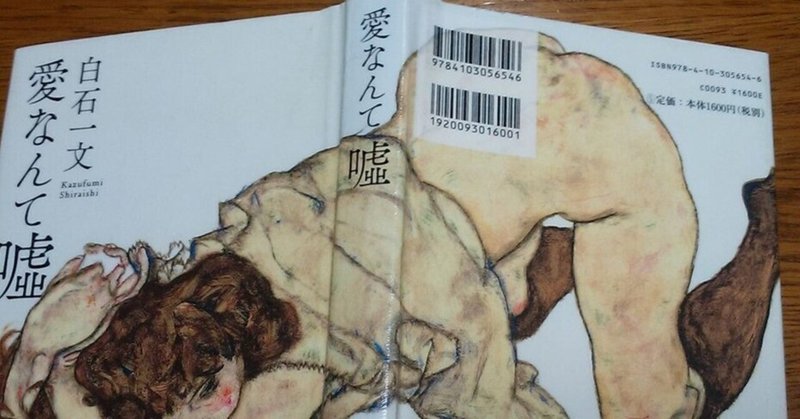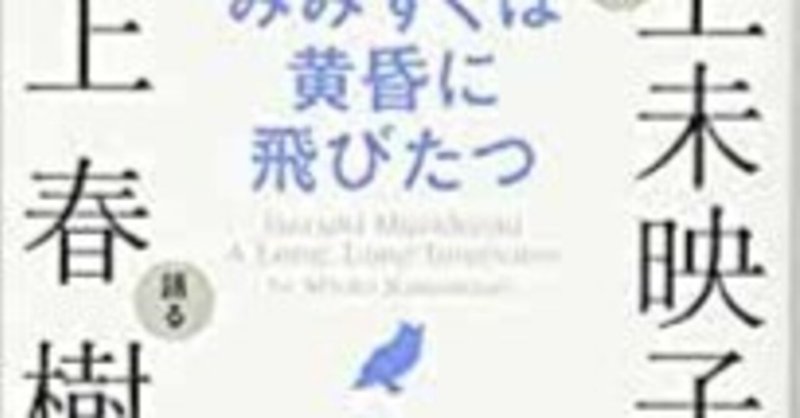2022年5月の記事一覧
今村夏子『こちらあみ子』(毎日読書メモ(330))
今村夏子『こちらあみ子』(筑摩書房、後ちくま文庫)。これがデビュー作。三島賞受賞。その後『むらさきのスカートの女』(朝日新聞出版)で芥川賞。寡作だが質の高い作品を送り続けている作家。
表紙が土屋仁応『麒麟』。土屋仁応の彫刻作品については先に読書メモを書いている。
『こちらあみ子』の読書メモはこちら:
あみ子から見える世界は、他の人が見ている世界とはちょっと違うようだが、そのことをあみ子はあまり
米澤穂信「古典部」シリーズ(毎日読書メモ(329))
最初に読んだ米澤穂信は『クドリャフカの順番』だった。順番違うやろ! 既に構築されている物語世界を十全には理解出来ないまま、高校の文化祭の熱気と謎解きに溺れた。
それから『氷菓』(角川文庫)に戻り、順番に読む。当時は『遠まわりする雛』までしか出ていなかったので4冊。ちょっとあけて『ふたりの距離の概算』、ずっとあけて『いまさら翼といわれても』まで6冊。2015年に飛騨高山に行ったので、神山高校のモデル
80年代SF傑作選(上)(毎日読書メモ(328))
この間、ハワード・ウォルドロップ「みっともないニワトリ」について語った時に(ここ)図書館で借りてきた『80年代SF傑作選(上)』(小川隆・山岸真編、ハヤカワ文庫SF)、他の作品も全部読んだ。昔の文庫本は活字が細かい…活字の大きさの境界点はどこにあるんだろう? 現在のR眼だと、へたにコンタクトレンズとかで矯正しちゃうと、逆に、古い文庫本は読むのが結構辛いのであった。
わたしはそんなに良いSF読みでは
北大路公子『すべて忘れて生きていく』(毎日読書メモ(327))
北大路公子『すべて忘れて生きていく』(PHP文芸文庫)を読んだ。ここまで着々と積み上げてきた北大路公子本の履歴を総ざらえして、これまで触れることのなかった新しい境地も見せて貰えたお得本。作者本人が全然整理管理していなかった過去の原稿をお友達のハマユウさんと編集者の愛と執念で1冊にまとめ上げた力作、作者だけ脱力した、文庫オリジナル本。刊行されたのは2018年5月で、古いもので2008年、最新は201
もっとみる堀江敏幸『雪沼とその周辺』その他いろいろ(毎日読書メモ(326))
3回連続堀江敏幸。たまたま図書館で手に取った『雪沼とその周辺』(新潮社、新潮文庫)に圧倒され、その後むさぼるように読んだ時期の記録。
『雪沼とその周辺』:いきなり堀江敏幸に圧倒される。なんで今までこの人の作品を読んでこなかったんだ! どの短編もしっくり腑に落ちて来ました。最初に読んだせいか、「スタンス・ドット」が特に印象的。(2008年8月)
『熊の敷石』(講談社文庫):芥川賞受賞時に読みそび
堀江敏幸『ゼラニウム』『未見坂』他(毎日読書メモ(325))
1つ前に続けて堀江敏幸の読書メモ。『ゼラニウム』(中公文庫)の感想。
エッセイのような、と思って読み始めたら、まごうことなく小説でした。相変わらずの博覧強記はあまり前面に出ず、フランスであがくように生きている作者を投影した登場人物が色々な意味の一期一会を体験してきたことを丁寧に描いている。切なくもあり、おかしくもある。堀江敏幸の世界をあますところなく伝える秀作でした。(2011年4月の読書メモよ
柳美里『ファミリー・シークレット』(毎日読書メモ(323))
柳美里の構築力の強さに心惹かれ、何冊も読んでいた時代の記録。『ラミリー・シークレット』(講談社。のち講談社文庫)の感想。
やや下世話な興味で読む。自分の育ち、自分が子どもに行ってきた虐待的行為、虐待の結果子どもと引き離された母親との対話、畠山鈴香や酒井法子についての考察、そうした断片の間に、カウンセラーとの複数回のセッション、カウンセラー臨席での父との再会の記録が入っているが、読んで感じたのは、
わたしの「ドードーをめぐる堂々めぐり」(毎日読書メモ(322))
川端裕人『ドードーをめぐる堂々めぐり 正保四年に消えた絶滅鳥を追って』(岩波書店)を読んで1ヶ月くらいたってしまった(感想はこちら)(トップ画像は川端さんの本からお借りした)。多くの人が、300年以上前に遠い海の向こうで絶滅したドードーという鳥の名前を知っている、そのきっかけとして、『不思議の国のアリス』と映画版ドラえもんを挙げたが、わたし自身にとってのドードーの思い出は、「SFマガジン」で読んだ
もっとみる中島京子『ムーンライト・イン』(毎日読書メモ(321))
中島京子『ムーンライト・イン』(角川書店)読了。先日、『やさしい猫』(感想ここ)を読んだ後で、近作を一つ読み飛ばしていたのに気づいたので、あらあら、と思いながら読む。中島京子は一作ずつテーマも作風もすごく違うので、別に引きずられることもなく、独立した作品として読む。中島京子の本は、どの作品も、登場人物たちの弱さとか情けなさとかに正面から向かって描いていて、それに勝るやさしさがじんわりと伝わってくる
もっとみる村上春樹・川上未映子『みみずくは黄昏に飛びたつ』(毎日読書メモ(319))
川上未映子 訊く/村上春樹 語る『みみずくは黄昏に飛びたつ』(新潮社、現在は新潮文庫)についての簡単なメモ。帯に書かれた「ただのインタビューではあらない」が好き。
川上未映子による村上春樹インタビュー読了。『騎士団長殺し』のネタバレばりばりなので、未読の人は注意。
わたし、時々村上春樹のどんなところが好き?、と尋ねられ、うまく答えられない。小説の感想とかも言えない、書けないのだが、ただ、ひたすら
『ふしぎ駄菓子屋銭天堂5』(廣嶋玲子・jyajya)(毎日読書メモ(318))
廣嶋玲子『ふしぎ駄菓子屋銭天堂』シリーズ(jyajya絵、偕成社)、他の本を読むのに忙しくしている間に、最新刊17巻が発売され、また、第3回“こどもの本”総選挙で第1位に選出されて(ちなみに第1回は9位、第2回は4位だったので、どんどん評判が上がっているということだね)、図書館の棚から消えてしまって、また、予約して少し待たされる状態に。
今回は、銭天堂の扱い商品である飲み物やカプセルトイが盗難に