
ロマン・ポランスキー監督 『ローズマリーの赤ちゃん』 : 悪魔は、ここにいる。
映画評:ロマン・ポランスキー監督『ローズマリーの赤ちゃん』(1968年・アメリカ映画)
本作『ローズマリーの赤ちゃん』は、ミステリー小説ファンには『死の接吻』で、SF小説ファンには『ブラジルから来た少年』によって知られる、奇才アイラ・レヴィンのホラー小説を、ロマン・ポランスキー監督が映像化した作品である。
ごく大雑把に言えば、本作は「悪魔崇拝にとらわれた隣人たちから、生まれてくる赤ちゃんを守ろうとする妊娠女性の話」だと、そう言えるだろう。
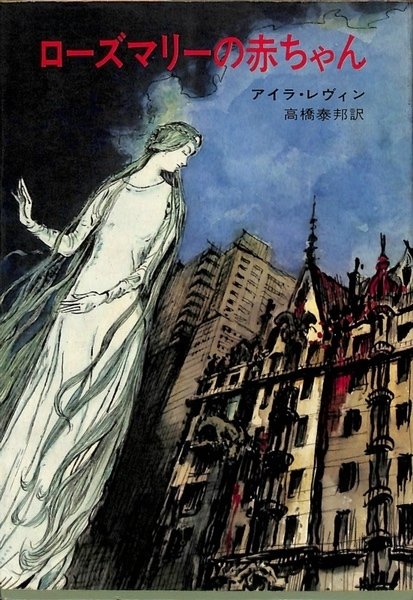
だが、本作については、すでに優れた紹介文が書かれている。
映画評論家・松崎まことが「洋画チャンネルサイト ザ・シネマ」に寄せた「漂泊者ポランスキーの「呪われた映画」『ローズマリーの赤ちゃん』」が、それだ。
この紹介文で語られているのは、次のような諸点だ。
(1)映画『ローズマリーの赤ちゃん』の「ストーリー」。
(2)同作が、ポランスキーによって撮られることになった経緯。
(3)本作に現れたポランスキーらしさと、そこに反映されたのであろう、ポランスキーの経歴と個性。
(4)本作の成功と、その後、本作が「呪われた作品」と呼ばれるに至った、「シャロン・テート事件」をはじめとした、現実の事件のあれこれ。
(5)ポランスキーという監督の「根無草(デラシネ)」的な個性を反映した、その後の(作家)人生。
つまり、映画『ローズマリーの赤ちゃん』をめぐるポランスキー監督についての、ひととおりの理解は、松崎によるこの紹介文を読めば、もう他のものを読む必要はないとそう言えるほど、秀逸でよくまとまった文章となっている。
だからまずは、是非とも、こちらの文章を読んでほしいと、強くお薦めしておきたい。
そしてその上で、本稿での私は、松崎の書いた「中心的な部分」を避けて、「周延的な問題」から本作を論じてみたいと思う。
その「周延的な問題」とは、本作が、「今どきのホラー映画」とは「いかに異なっているか」であり、「その違いは奈辺に由来するものなのか」という問題である。
○ ○ ○
「今どきのホラー映画」とは、それが「娯楽性の高い(B級と呼ばれる)作品」であるか、あるいは「芸術的表現を意識した作品」(例えば、A24が、制作・配給するような作品)であるかを問わず、ひとまず「観客を怖がらせる」という目的においては、完全に一致していると、そう言ってもいいだろう。
ただ、前者の「怖がらせ方」は、「お化け屋敷」や「びっくり箱」的な、言うなれば「即物的な怖がらせ方」、ほとんど「脅かし、驚かせる」に近いような「怖がらせ方」、端的なものとしては「ショッカー」などと呼ばれることもある、言うなれば「ショックを与える」作品、その「衝撃性」において「怖い」と「驚いた」が一体となったような「怖さ」を提供する作品が多いと、そう言えるのではないだろうか。
では、後者である『「芸術的表現を意識した作品」(例えば、A24が、制作・配給するような作品)』とはどのようなものなのかというと、こちらは、もっと「心理的に惹起される怖さ」を意図したもので、「映像的」な側面を強く意識しつつ、その「物語の段取り」において、観客を、限りなく「不安」へと追い込んでいくような作品のことである。
ただ、この「今どきのホラー映画」を代表する両者(両傾向)には、共通点もある。
それは、どちらも「超常的なもの」あるいは「異常なもの」を描くという点において、いわゆる「人間を描く」という方向性は採らない、という点である。
つまり、「超自然的なもの」を描くにしろ、社会的規範を完全に逸脱したような「精神異常的なもの」を描くにしろ、それらは「当たり前(普通)ではない」という点では共通しており、その「当たり前ではない」点を、もっともらしく描くことにおいて、見る者を「非日常的な恐怖の世界」へ連れ出すことを目的としているのである。
だが、本作『ローズマリーの赤ちゃん』の場合、見てもらえば分かるとおり、そうした「ホラー映画」とは、一味も二味も違う。
さすがはポランスキーとでも言うべきか、「ホラー映画」を撮っていると言うよりは、「ホラー」という題材を扱いながら、しかし実は、いつもどおりに、「人間心理」映画を撮っている、という印象なのだ。

平たく言うなら、本作は、「ホラー映画」として「観客を怖がらせよう」という意識から撮られたものではなく、あくまでも「主人公の、極限的に追い詰められていく心理」を描いた「人間心理」映画なのだ。
そして、その意味において、言うなれば「普通の映画」だからこそ、「ホラー映画らしくない」のである。
では、なぜ、ポランスキーは、このような「撮り方」をしたのだろうか?
無論それは、この作品の制作された時代の問題であり、また彼が「流行」に流されないで、自分の流儀で作品を撮れる立場にあったということがあり、自分の流儀で撮っても、「ホラー映画」として成立する作品を撮れるだけの力量を持った作家だったからであろう。
そして、そんな本作で特徴的なのは、本作の中で描かれる「悪魔崇拝者(サタニスト)」たちの姿だ。
もちろん彼らは、日頃は「普通の市民」を装っており、本作の主人公であるローズマリーにも「親切な隣人」として接してくるのだが、しかし、その描き方が「今どきのホラー映画」とは、ちょっと趣きが違う。
「今どきのホラー映画」であれば、そうした「なりすましの善人」というのは、その「正体」が明かされるまでは、普通以上に「良い人(善人かつ、感じの良い人)」であり、(伏線的な描写はあるにしろ)その正体が明かされた途端「豹変」して、その「異常者ぶり」を表すというパターンが多い。つまり、そのギャップによって「怖さ」を演出するのである。

ところが、本作の場合は、その「隣人の夫婦」というのが、最初から「ちょっと変わり者」であり、親切は親切なのだが、少々迷惑なほどの他人の私生活に踏み込んでくる「無神経で面倒くさい人」という、「嫌な印象を与える人」たちなのだ。つまり、「悪魔崇拝者」か否か以前に、「普通の人」の範疇にはあっても、「関わり合いにはなりたくないタイプの人」として描かれるのである。
だから、物語の前半は、「ホラー的に怖い」というよりも、「こんなのが隣人だったら、嫌だな」という、言うなれば、当たり前の「嫌悪感」の方が強く惹起されるような描写になっているのだ。
そして、このことは「今どきのホラー映画」の紋切り型の作劇法とは、むしろ真逆だとさえ言えるのである。
「今どきのホラー映画」だったら、「普通だと思っていた人が、実は異常者だった」から、その「ギャップ」によって「怖い」となるのだが、本作『ローズマリーの赤ちゃん』の場合は、当初の「人間的な嫌さ(不愉快さ)」が、そのままシームレスに「悪魔崇拝者の異常性」へと接続されていて、そこに「ギャップなど無い」ことこそが「気味わるい」。その人柄においては、正体を明かす前と後とに、ほとんど変わりがないのだ。

つまり、ポランスキーの描く「怖さ」は、「異常性」という「非日常性」の中にあるのではなく、むしろ「異常性」が「日常性」の中に潜んでいるものであるからこその「怖さ」なのだ。
言い換えれば、ポランスキーの描く「怖さ」とは、映画館の中でだけ楽しめ、映画館を一歩出れば忘れることの許される「娯楽としての怖さ」ではなく、映画館の外にも存在する「怖さ」であり、映画館を出たからといって消えてなくなってくれるような「怖さ」ではないのである。
だから、本作の「怖さ」は、いわゆる「ホラー映画」的な「娯楽としたの怖さ」ではなく、むしろ、普遍的な人間存在に秘められた「嫌らしさ」の「怖さ」だとも言えるし、そうしたことから、本作は、「怖い」と言うよりも、「嫌な」映画になっている。
映画を見終わって、「ああ怖かった(けれど、面白かった)」というような「娯楽作品」ではなく、何か「嫌なもの(現実)」を見せつけられたような、独特の「嫌な余韻」を残す、ホラー映画では、他にあまり類を見ない作品となっているのである。
で、こうした「独特の味わい」が、どういうところから出てきたものなのか、という点についての説明は、ほとんど、先に紹介した「松崎レビュー」の補足的なものとなってしまう。
と言うのも、松崎も指摘していたように、ユダヤ人であるポランスキーは、幼くして「ナチスドイツ」からの逃亡生活を経験をしており、言うなれば、本作の主人公ローズマリーや、別作品『戦場のピアニスト』の主人公などと同様の、「孤立無援で逃げまわる」というトラウマ的な経験しているのだ。
そのことにより、誰も信用できないという、根深い「人間不信」とその「恐怖」が、その心に抜き難く刻印され、それが本作における主人公の心理描写を、リアルなしたのではないか、ということなるからだ。
ポランスキーの描く「恐怖」は、「ホラー好き」に由来する「安心な恐怖」などではなく、骨の髄まで染み入った、「リアルな恐怖」なのである。
だが、それだけでは済まない。
ことの真相は、定かではないとしても、じつはポランスキー自身の行動に関わる皮肉な現実も、そこに加わるのである。
『 さて(※ 愛妻)シャロンを(※ マンソン・ファミリーによる虐殺事件で)失って、憔悴しきったポランスキーであったが、やがてその悪夢を振り払うかのように、次々と新作に取り掛かるようになる。しかし(※ 映画監督、アンジェイ・)ワイダが言うところの、(※ ポランスキーの)“コスモポリタン”ぶりに拍車が掛かったようで、その舞台はイギリス、イタリア、フランスなどに渡る。
結局ポランスキーが、『ローズマリー…』の他にハリウッドで手掛けた作品は、『チャイナタウン』(74)のみ。そしてその主演だったジャック・ニコルソンの邸宅で、ポランスキーは、13歳の少女モデルの強姦という、“事件”を起こしてしまう。
ポランスキーは、己の原体験を、スクリーンに映し出すことを、特徴とする映画作家である。例えばイギリスで撮った『袋小路』に登場する主人公夫婦は、ポランスキーがシャロンの前に結婚していた、バルバラ・ラスとの関係をモデルにしたとされる。またアカデミー賞監督賞に輝いた『戦場のピアニスト』(02)は、実在のユダヤ系ポーランド人ピアニストの体験記を原作としながら、主人公のナチス・ドイツからの逃亡劇には、ポランスキー自らの体験を、多々盛り込んでいる。
しかしながら、ポランスキーが77年に起こした、少女の強姦事件は、まるでその真逆である。シャンパンと麻薬的な効果のある鎮静剤を飲ませて、性交に及んだと言われているが、これはその9年前に撮った『ローズマリー…』に於ける、悪魔主義者たちの手口をトレースしているかのようだ。
ポランスキーは拘留後、一旦釈放された際に、再びの収監から逃れて、アメリカ国外へと脱出した。以降アメリカへの入国は不可能となり、アカデミー賞が贈られた際も、セレモニーへの出席は、叶わなかった。
アメリカ脱出後、ポランスキーはパリを拠点とし、そこで新たなる家庭も持った。2009年に映画祭で訪れたスイスで身柄拘束されたことはあるも、翌年には釈放されて、フランスに戻っている。
とはいえ、その出自に加えて、アメリカで巻き込まれた悲劇と、自ら起こした事件によって、ポランスキーは、“コスモポリタン”というよりは、“デラシネ=根無し草”としての映画人生を、歩み続けているようにも映る。』
(松崎まこと「漂泊者ポランスキーの「呪われた映画」『ローズマリーの赤ちゃん』」より)
つまり、「悪魔」は、周囲の「普通の人たちの中」どころか、じつは「自分の中」にさえ潜んでいた、ということなのだ。
もちろん、ポランスキーにかけられた嫌疑は、いわゆる「冤罪」なのかもしれない。
しかし、私がここで問題としたいのは、ポランスキー個人の問題ではなく、「私たち」一般のことなのだ。自分を「普通の人間」だと、そう思い込んでいる「私たち自身」のことなのである。
これは、さほど難しい話ではない。
仮に私たちが、ポランスキーのような「世界的な映画監督」であり、多くの若い女優たちが擦り寄ってきた場合、それに、うっかり手を出してしまったりはしないか、という話なのだ。
無論これは、性別を入れ替えてもいいし、年齢を下げて、未成年の「美少年・美少女」だとしてもいい(ポランスキーの場合、薬を盛って強姦したか否かを疑われるほど、多数な女性と関係しただろうし、その中には未成年がいた可能性も十分にあるだろう、ということだ)。
男であれ女であれ、そうした「悪魔の甘い誘惑」に、私たちは、いつでも必ず抗いきることができるだろうか。それを想像してほしいのだ。

自分の中の「悪魔」が「まあ、いいじゃないか」と囁くことは決して無いと、そう言えるだろうか。また、これまで一度もなかっただろうか。一一そういうことなのである。
例えば、私たちは、車の通行の絶えた深夜の道路において、それでも歩行者用の信号の「止まれ」を守って、一人で信号が青に変わるのを待つことができるような「一点の曇りもない人間」だろうか?
「別に、誰に迷惑をかけるわけではないのだから、こんな場所でこんな時間に、馬鹿正直に信号を守る必要はない」と、そんな「悪魔の囁き」に身を委ねたことは、一度もないだろうか? 「ダメなものはダメ」だと、すべてにおいて、それを自身に強いて生きてきたと、そう胸を張って言えるだろうか?
そこまでは「言えない」としたら、ポランスキーがどうという問題ではなく、私たち自身が、「普通の人」であると同時に、時と場合によっては「悪魔崇拝者」に変貌することだってある、「リアルな人間」なのではないだろうか?
本作『ローズマリーの赤ちゃん』が、「怖い映画」と言うよりは「嫌な映画」という印象を与え、その結果としてのみ「怖い映画」だと評し得るのは、本作が「私たちの中にもある、見たくないもの」を、誇張して突きつけてくるような作品だったからではないだろうか?
私たちは、ナチスを支持し、ユダヤ人への迫害を加担した「普通の人たち」と同じように、「悪魔崇拝者」としても顔を、無自覚なままに隠し持っている「当たり前の人間」なのだと、そう言っても過言ではないのではないか。
私にとって、何よりも怖いのは、私の中の「私の知らない私の顔」の存在なのではないだろうか。

(2024年6月8日)
○ ○ ○
● ● ●
○ ○ ○
○ ○ ○
○ ○ ○
○ ○ ○
○ ○ ○
