
〈自尊心〉病者の手記:萩原俊治『ドストエフスキーのエレベーター』
書評:萩原俊治『ドストエフスキーのエレベーター 自尊心の病について』(イーグレープ)
「私たちは、自尊心の病という檻に囚われており、そこからは逃れられない」ということを知っているという点において、私は、自尊心の病という檻から逃れ得ている、優れて例外的な存在である。
一一本書の内容を、簡単にまとめると、こうなる。
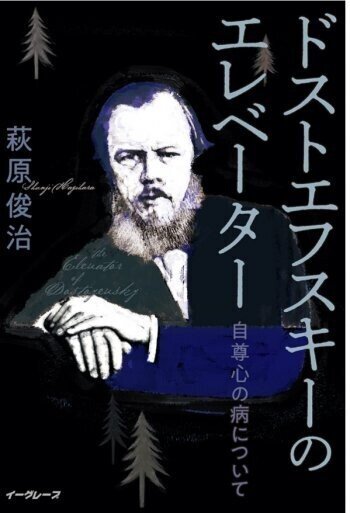
「外に出られないということを知っている点で、私は外に出ている」という理屈は、ありふれた誤謬論理でしかないが、本書著者は、まんまとそうした「自尊心の病という檻」の錯誤に囚われているのだ。
「私を客観視している私」というのは「私を客観視している私(という主観)」ということでしかないから、これは原理的に成立不能である。
しかし、だからと言って「客観視しようと、しないでいい」ということにはならない。
完璧にはできないまでも、やろうと努力するからこそ、完璧ではないにしても「それなりの成果」は得られるからで、「完璧じゃなければ、やる意味がない」というのは、病的な「完璧主義の傲慢」でしかない。
では「私を客観視する私を客観視する私を客観視する私を…」という、「無限後退」的な認識努力で良いのか言えば、それで良い。
なぜならば、もともと人間とは「有限」な存在なのから、「無限」な認識努力に取り組んだところで、個々人の能力的限界に従って、その努力は、否応なく、どこかの地点でストップしてしまうものだからである。
そして、そこまでやれば、それはもう立派なものだし、それ以上のことは原理的にできないのだから、それ以上を求める必要もない。あとはせいぜい、もっと基礎体力をつけて、再チャレンジをし、より遠くまで踏み出せるようにするしかないのだ。
本書著者は、冒頭の「要約」と「似たようなこと」を書いているのだが、しかし、ご当人が誰よりも「自尊心の病」の重病患者であるからこそ、口では「人は、自尊心の病からは逃れられない」と言いつつ、その自覚なしに「外に出られないということを知っている点で、私は外に出ている」と思ってしまっている。
一一それが本書を、堪らなく「イタい」ものにしてしまっているのだ。
端的に言えば、本書は「自慢話」の書にしかなっていないのである。
著者は、自分が「自尊心の病」を自覚できるようになったのは、『ぺちゃんこ』になる体験をしたからだと、一見、自身のかつての「愚かさ」を反省しているかのごとく語っているが、実際のところ、この言葉は、自身を「特権化」するためのものでしかない。要は「私はかつて、極限体験をしたから、自尊心の病を自覚できたけど、のほほんと生きてきた皆さんでは、当然そんな自覚は不可能でしょうね」ということなのだ。
著者は「あとがき」に、次のように書いている。
『 いや、それはわたしたち個々の人生に限ることではない。自尊心の病の分からない人々はこの世界を地獄にしてしまうだろう。と言うより、わたしの目には、世界はすでにそのような人々によって、ムンクがその『叫び』という絵で描いたような世界になっているように見える。だから、わたしたちはどうしても自分の自尊心の病に気づかなければならないと思う。
しかし、そういうわたし自身、長い間、自分の自尊心の病に気づくことができず、そのため、わたしのまわりにいる人々の生活を地獄のようなものにしてきた。わたしは本書をそのような人々に対する贖罪として書いた。本書はドストエフスキー論という体裁をとってはいるが、わたしの罪の「告白」に他ならない。』(P190〜192)
このように、「贖罪」「罪の告白」の書だと言いながら、『ぺちゃんこ』体験が詳しく語られることはないし、その一方、自身が「自尊心の病に気づいている」というのを、自明の事実のごとく語っている。
だが、「自尊心の病」に罹っていた頃は、当然、自分が「自尊心の病」に罹っているとは自覚できていなかったはずで、では、なぜ「今はもう、自尊心の病に罹ってはいない」と、そう言えるのだろうか。一一無論、そんなこと、言えるわけがない。
よく言われることだが、「本物の狂人は、自分が狂人であることに気づけない」というのと、まったく同じことなのである。
しかし、著者自身も、「私は、自尊心の病の外にいる(=すでに健康である)」という「自己診断」による自己主張に無理があるということには、おおむね気づいている。
そこで著者は、「私を客観視する私を客観視する私を客観視する私を…」という、原理的に際限のない無限後退を「切断する」ために、「神という絶対権威」を持ち出してくる。一一これが、著者の言う「回心」(P95〜)である。
つまり、「神」という「絶対的な外部」を持ち出してきて、その「外部の権威」で、自分では原理的に切断することのできない「私を客観視する私を客観視する私を客観視する私を…」という無限後退を、切断してみせるのだ。
『 昔、わたしはドストエフスキーが分からなくて苦しんでいた頃、ロシア語の聖書を教えてもらっていた大阪ハリストス教会の故牛丸神父から、「信仰がなければ、ドストエフスキーの小説はゴミと同じです」と言われ、驚いたことがある。牛丸神父はトルストイを罵倒し、同時にドストエフスキーを賞賛しながら、そう言われた。今から思えば、牛丸神父のいう「信仰」とは、イエス・キリストという存在の意味がわかるようになるということ、つまり、わたしの言葉で言えば、「自尊心の病」が分かるようになるということだった。要するに、牛丸神父のその言葉をわたしの言葉で言い直せば、トルストイには自尊心の病が分からず、ドストエフスキーにはわかった、ということだ。』(P191)

だが、ここで「回心」などというものを持ち出すのは、「ズル(反則)」でしかない。
なぜなら、「神という絶対権威」が「絶対権威」である得るのは、「神という絶対権威」の存在を認める人の間でだけであり、そうでない人には通用しない、所詮は「ムラの論理(ローカル・ルール)」でしかないからだ。
だからこそ、著者は、次のように言う。
『 しかし、本書でも述べたように、わたし自身は、自尊心の病がわかるということは、キリスト教の枠を超えた、わたしたちの誰もが経験しなければならないことだと考えている。そして、その経験がなければ、わたしたちの人生は生きるに値しないものになる、と、わたしは思っている。』(P191)
つまり、「神の絶対権威」を持ち出して「神への回心」が無ければ「自尊心の病」を癒すことはできないとしておきながら、「洗礼を受けてクリスチャンにならなければ、人は自尊心の病から、救われることはない」とまでは、言わないのである。一一これは、「二股膏薬」とでも呼ぶべきもので、端的に言って「ズルい」。
しかし、なぜ著者が「洗礼を受けてクリスチャンになり、神の絶対権威の前に謙遜にならなければ、人は自尊心の病から救われることはない」と言えないのかといえば、そう言ってしまっては、それはもう「文学」でも「哲学」でもなく、「宗教」の話になってしまい、著者が、いまだに止まりたいと思っている「文学」や「哲学」の世界から逸脱して、「文学」村や「哲学」村の人たちからは「ああ、萩原さんは、宗教村に安住しちゃいましたね」と、もはや評価の対象ですらなくなってしまうからだ。
だが、「ドストエフスキー研究家」という自負をいまだに抱えている著者には、それは我慢ならないことであり、「自尊心」が許さない事態なのだ。だから、「わたしはクリスチャンとして神を信じ、その権威に従って、人としての自尊心という傲慢から自由になります」とまでは言い切れないのである。
つまり、「神」が絶対権威であり得るのは、「クリスチャン村」の仲間内だけであり、彼は、自身をその仲間に「ちょっと交ぜてもらう」ことで、自身が「自尊心の病」を癒したという「裏付け」にしようとした。
しかし、完全に「クリスチャン村」の住人になってしまうと「あの人は、信仰を持つことで、自尊心の病を癒したのかもしれないけれど、しかし、私たちから見れば彼は、自尊心という病に、盲信という病を上書きしたようにしか見えないんだよね」と言われることにしかならない。
自らを「信仰の檻」に閉じ込めるならば、「自尊心の病(=檻)」から解放されたと認めてもらえるが、そこに閉じこもれば、「信仰の檻」の「外の人たち」からは、もう満足な「承認を得ること」ができなくなってしまう。
そこで本書著者は、「信仰の檻」に半歩だけ踏み込んで、半開きのドアのところで「内と外に二股をかける」ということに、ならざるを得なかったのである。
しかし、この「中途半端」なスタンスというのは、まぎれもなく著者が、いまだに「自尊心の病」に囚われ、その「檻の中」にいる証拠であろう。
著者は、本書の中(P118〜124)で、ペトロが、イエスの予言どおりに三度うらぎった、という聖書のエピソードを紹介して、自身もペテロと同様の人間だったが、同様に「(自尊心の病を克服して、最後は)変われた」というふうに語っている。
しかし、正確に言うなら、本書著者は、その後も変わらず「自尊心の病」の中にあってイエスを裏切り続けており、むしろ、イエスとペトロの権威を、利用しているだけなのだ。

なぜ、こんなことになってしまうのか。
それは、彼が「信仰の檻」に自身を閉じ込めて安心立命を求めようとしても、檻の格子の隙間からは「誘惑に満ちた、外の風景」が、彼の目にも映るからで、完全に「外界」から切り離されることはないからである。
つまり、「自尊心の病」は、生きているかぎり、完全に消し去ることなどできないし、それはキリスト教の司祭や篤信者ですら、人間的欲望に流されることが多々あるのと同じなのだ。
ましてや、本書著者の場合は「外の世界」に多大な未練を残しており、だからこそ「信仰の檻」の扉を完全に閉じて、覚悟を決めて、その中で安らうことができない。
あわよくば「外の世界」が、自分を呼び戻しに来てはくれないものか、つまり「高く評価してくれないものか」という、世俗的な「欲望=未練」を捨てきれないのである。
だから彼は、檻の中に半身を隠して、なかば檻に守られながら、檻の外に向かって、悪罵を投げつけ続けずにはいられない。「そんなことでは、救われないぞ!」と。
しかし、それはもう「自尊心の病」を克服した者の姿ではなく、「私は正しい」という、凡庸な「自尊心の檻」の中に止まった者の姿でしかない、という現実を、逆証明するものでしかないのである。
『 わたしたちは『地下室の手記』を最後まで読んで初めて、これが自尊心の病について書かれた作品だと分かったら、また、最初に戻ってこの冒頭の奇妙な文章から読み始める。なぜなら、わたしたちには、そのとき初めて『地下室の手記』は自尊心の病だけについて書かれた、最後と最初がつながった終わりのない円環状の物語であると分かるからだ。』(P139)
最後と最初がつながって円環をなす、リアル『地下室の手記』。
一一それが本書であると言っては、手厳しすぎようか。
(2022年6月15日)
——————————————————————————————————
【補記】
この自費出版に近いだろうマイナーな本を、なぜ、私が読むことになったのか、その経緯について、書いておこう。
直接のきっかけは、四五日前、私のこの「note」アカウントを、本書著者と同名の「萩原俊治」という人がフォローしてくれたからである。
そこで、どんな人なのだろうかと、そのアカウントを覗いてみると、フォロー数が3で、まだフォロワーもいなければ、記事もない人であった。つまり、「note」アカウントを取得したばかりの人のようだったのだ。
だが、そこにブログへのリンクが貼られていたので、そちら(ブログ「こころなきみにも」)を覗いたところ、そのトップに「このブログを始めた理由」という自己紹介記事が掲げられており、その冒頭で『なぜこのブログを始めたのか。その理由についてはすでに2013年10月2日の記事で説明している。しかし、今では他の記事に埋もれて読みにくくなっているので、それを複写し、ブログの最初の部分に掲げておこう。最近は日記帳や忘備録みたいになっているこのブログだが、最初は目的があって書いていたのだ。』となっていて、「2013年10月2日の記事」である「匿名について」が引用されていた。
で、そちらを読むと、どうやら萩原氏は、著名なロシア文学者の亀山郁夫を批判している人のようで、ここで初めて、萩原氏がなぜ私をフォローしたのかに思い当たった。

というのも、その数日前に、私が記事を読み、興味を持ってフォローし、コメントを書き込んだりして何度かやり取りしている「ヤマダヒフミ」氏の、亀山批判に関する記事「亀山郁夫と悪夢世界」を読んでいたからだ。
そこには『ネットを見ていたら、ロシア文学専攻の賢い人を見つけました。ドストエフスキーの研究者らしいのですが、その人のブログを読んでいました。/そうすると、そこで亀山郁夫の批判が長々と行われていました。』云々とあったので、きっと、ヤマダ氏経由で、私にたどり着いたのだなと思い、お名前でネット検索してみると、大阪府立大学でロシア文学を講じ、10年前に退官なさった方だとわかった。
そこで、著作はあるだろうかとネット検索したところ、本書がヒットし、しかも、ヤマダ氏がAmazonレビュー「感謝」で、本書を絶賛なさっていたので、この本の著者に間違いないと思い、本書を読んでみることにした、という経緯である。
そんなわけで、私としては、きっと面白い本だろうと期待して購読したのだが、見てのとおり、完全に期待はずれだった。しかも、その期待の外し方が、どうにも好ましくないものだったので、正直にそのあたりを論じたところ、上のようなレビューになったという次第である。もちろん、萩原氏本人も、本稿を読んでくださるはずだ。
なお、『ドストエフスキーのエレベーター 自尊心の病について』の版元「イーグレープ」は、キリスト教関係の書籍を多く手がけ、自費出版も行なっている出版社である。
(2022年6月15日)
○ ○ ○
○ ○ ○
○ ○ ○
・
○ ○ ○
・
○ ○ ○
・
・
○ ○ ○
・
・
