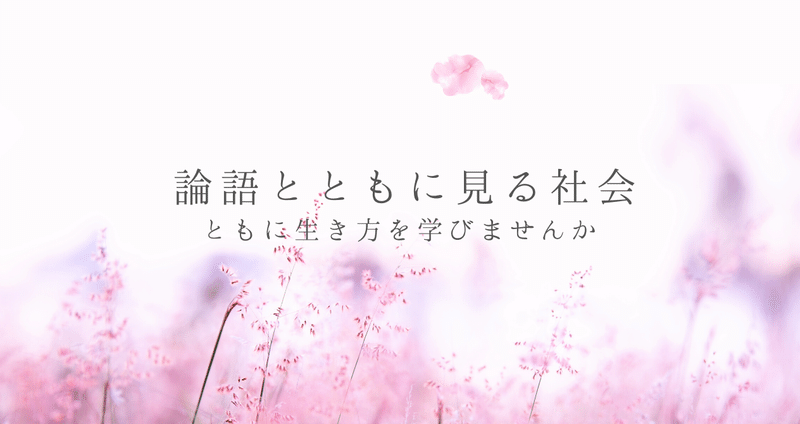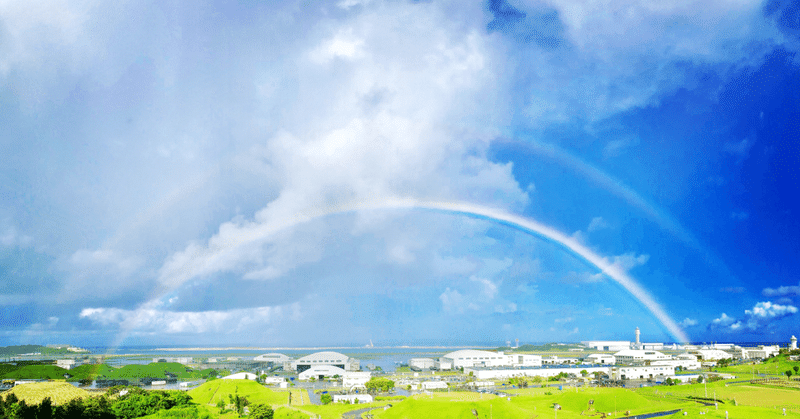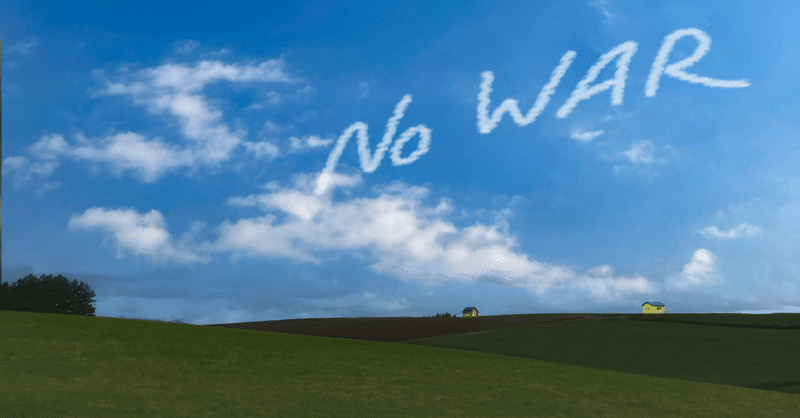#世界平和
忠恕一貫...まごころ(忠)からなるおもいやり(恕)
子曰(のたま)わく、參(しん)や、
吾が道は一(いつ)以(もっ)て之(これ)を貫く。
曽子(そうし)曰わく、唯(い)。
子(し)出ず。門人問うて曰わく、何の謂(いい)ぞや。
曽子曰わく、夫子(ふうし)の道は忠恕(ちゅうじょ)のみ。
(里仁第四、仮名論語四三頁)
先師(孔子)が言われた。
「参(曾子の名)よ、私の道は一つの原理で貫いている」
曾子が「はい」と歯切れよく答えられた。
先師は満足げに出
志仁無悪...憎む心をもたない。それは、悪い事をしないことよりも難しい。
「子曰(のたま)わく、苟(いやし)くも仁(じん)に志(こころざ)せば、惡(にく)むこと無きなり。」
(里仁第四・仮名論語三八頁)
「かりそめにも仁に志したならば、人を嫌ったり、人を拒んだりすることはない。」
この章句を「苟(まこと)に仁に志せば、惡(あく)無きなり」と読み下すのが、一般的である。
真に仁を志したならば、過ちを犯すことがあっても、悪事をはたらくことはない、と言う解釈である。
不教民戦...「充分に教育もしてない民を戦わせるのは、それこそ民をすてるというものだ」
子曰(のたま)わく、敎(おし)えざるの民を以(もっ)て戰う、是(こ)れ之(これ)を棄(す)つと謂(い)う。
(子路第十三、仮名論語一九九・二〇〇頁)
先師(孔子)が言われた。
「充分に教育もしてない民を戦わせるのは、それこそ民をすてるというものだ」
気に入った一枚の写真がある。
漆黒の闇に青と白が斑(まだら)なす小さな地球と微かな月が浮かんでいる。
宇宙航空研究開発機構(JAXA)の探査機「は
教民即戎...「君子とまではいかない善人でも、民に七年間教えたら、民を戦争に行かせることができる」
子曰わく、善人、民を敎(おし)うること七年、亦(また)以(もっ)て戎(じゅう)に即(つ)かしむべし。
(子路第十三、仮名論語一九九頁)
先師は言われた。
「君子とまではいかない善人でも、民に七年間教えたら、
民を戦争に行かせることができる」
「己の欲せざる所、人に施(ほどこ)すこと勿(なか)れ」(顔淵篇、衛霊公篇)と言われた孔子であっても、民を教え、祖国のため、同胞のため、家族のために死ぬことを