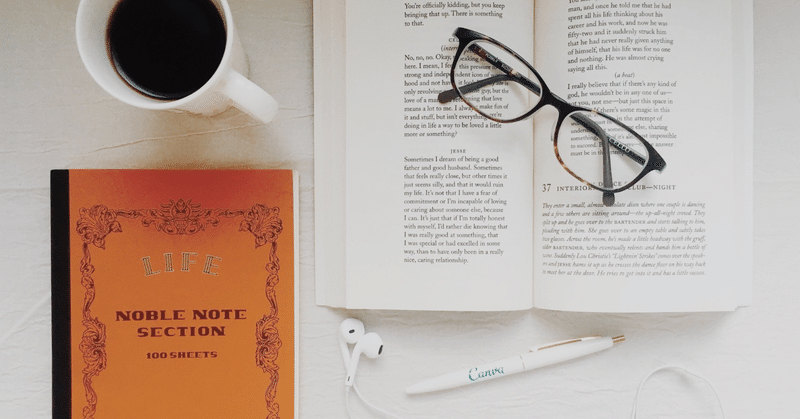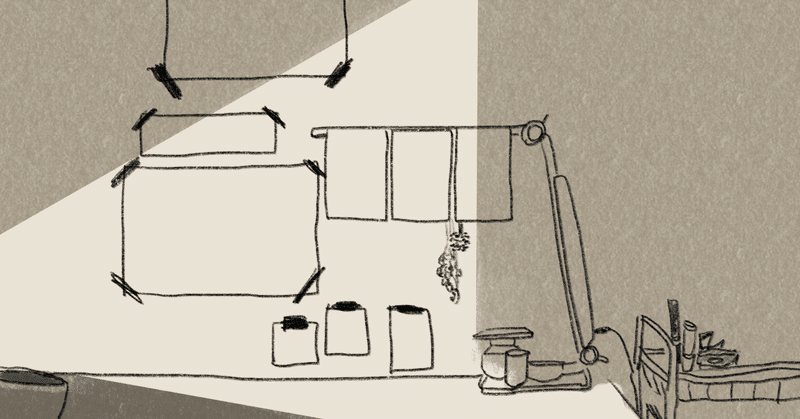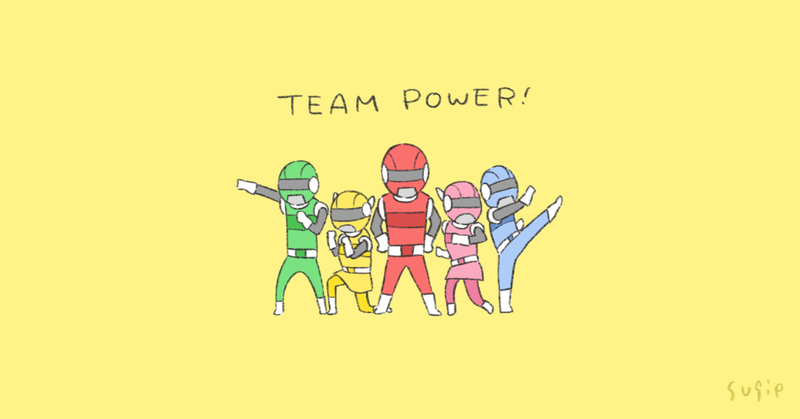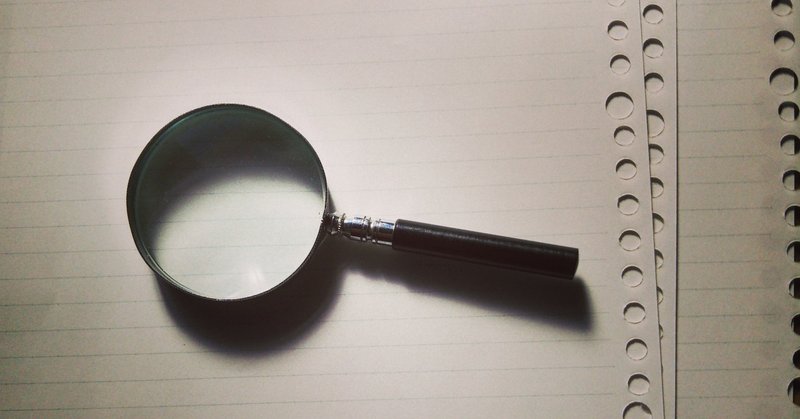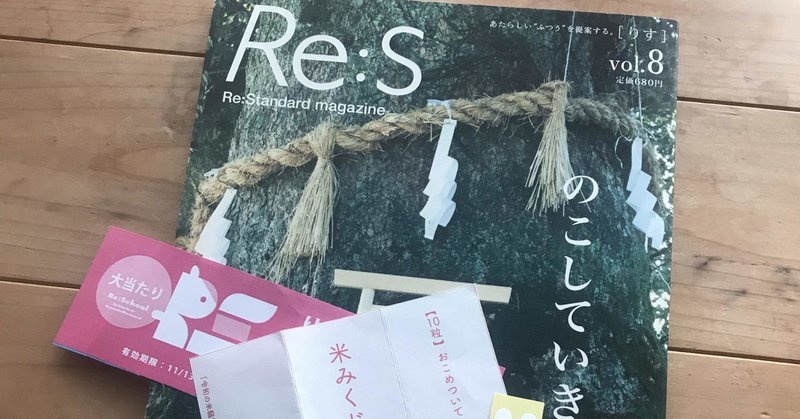#エッセイ
他者をジャッジしないという能力
本当にたくさんの人と関わりながら仕事をしている友人がいる。議員さんから、社長、アーティスト、関わる人の職種も多様だ。
たくさんの人と関わりながら仕事をするには、体力がいる。お互いの長所や短所を理解し、意思を尊重しながら成果には妥協しない、そんな精神的なタフさも求められる。
さらに言えば、「この人はこういう人だ」と、一方的にジャッジせず、真摯に向き合う姿勢が必要だ。
自分に近い意見を持っている
発信力より、受信力を高めたい
「発信力が注目されてますけど、コミュニケーションって、受信力も大事なんですよね。」
「ドキュメンタリーって、あんまり編集されていないから、感想は見る人によるんだよね」
「自分が考えていることや発言することに、ほとんど価値はないんだと思います。」
ここ最近、別々の場所で、別々の人から、受信力の大切さについて考えさせられるきっかけをもらった。
フォロワーを増やす・・・
集客力を高める・・・
想
楽しいと安心のあいだを埋める
市の家庭教育委員として活動している。先日、そのメンバーとのミーティングで、自分たちの活動の目的を改めて考える機会があった。
「楽しいことは他のところがやっているから、自分たちは困っている人をサポートしていくことが大事だよね。」
と、1人のメンバーが話してくれたのだけれど、この言葉を聞いて、自分自身も楽しいことより、「安心」を感じられることに興味があるなと改めて気づいた。
安心は買えるとは限ら