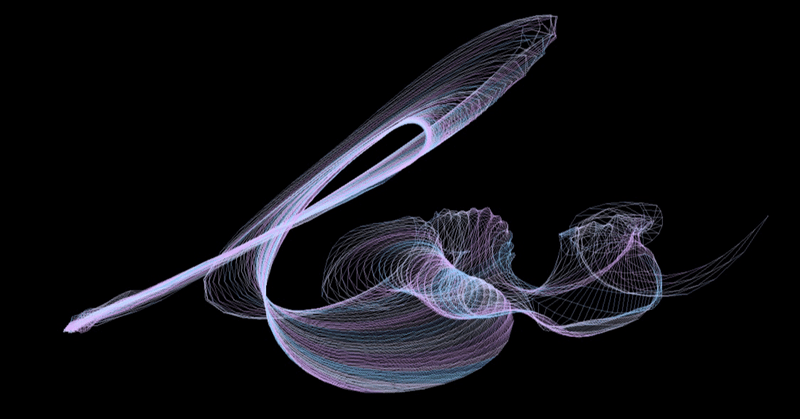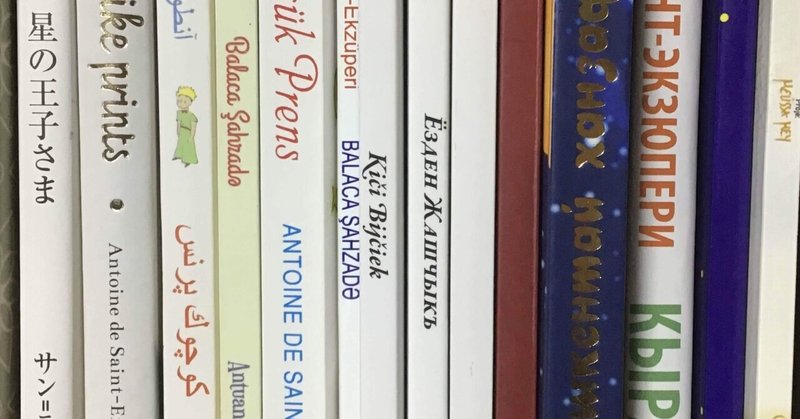記事一覧
ジョゼ・サラマーゴ『だれも死なない日』
これは例外の話だ。例外状態。
これまで読んだサラマーゴの作品は、どれもそうだった。『白の闇』も『見ること』も。特殊な状況に置かれた人々の話。本作では、ある国で、ある日を境に、人がだれも死ななくなる。
人はみんな死ぬ。死なない人はいない。いない筈だから、例外である。それが突然、常態になる。人々がその変化にどう反応するか。それが描かれる。
葬儀屋や保険屋が困る。人が死なないと商売あがったりである
レヴィ=ストロース『構造・神話・労働』
声のある本だった。本書は講演・対談集だ。もとが声で語られたものを文字に起こした形式である。だから、音声的に感じられても不思議はない。
ただ、わたしが感じたのは、音ではなく、声なのだ。身体器官としての声。文体や筆跡と似たような、レヴィ=ストロースの個人情報をそなえたものしての、声。
*
「構造」と「神話」と「労働」について語っている。タイトルの通りだ。しかし、「構造についての話」や「神話につい
ニック・チェイター『心はこうして創られる』
タイトルからわかる通り、本書によれば、「心」は「創られる」ものだという。それは臓器のように、人の内部に「在る」ものではなく、表情や声のように、その都度「創造される」類のものだというのだ。
英語の原題は the mind is flat 、日本語にすれば「心は平ら」。本文中では「心には表面しかない」等と訳されている。その意味は、心には「深層」とか「奥行き」のようなものはない、ということだ。
*
アミン・マアルーフ『アイデンティティが人を殺す』
読むのが難しい本だった。と、いって、内容が高度で難儀した、というのではない。
どちらかといえば、易しい本だと思う。どの本も、深く理解しようとすれば「簡単」ということはない。それはこの本も同じだ。
でも、難しさの程度というか、とっつきやすさには本によって一冊一冊に個性がある。晦渋な言い回しや、複雑な概念操作のために難読、という本もある。そして本書は全然そういうタイプの本ではない。
*
「アイ