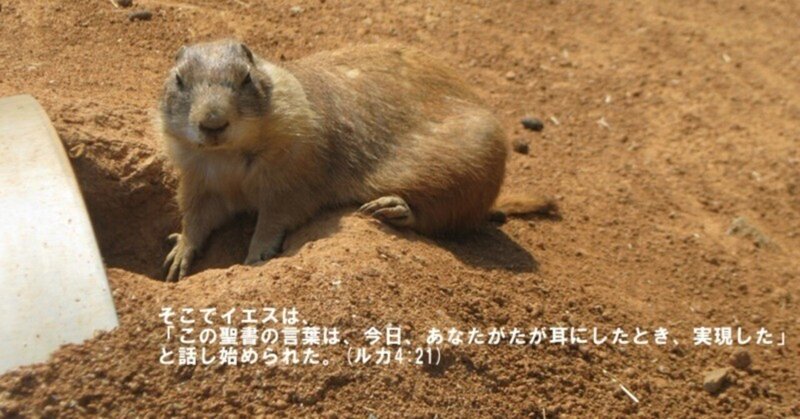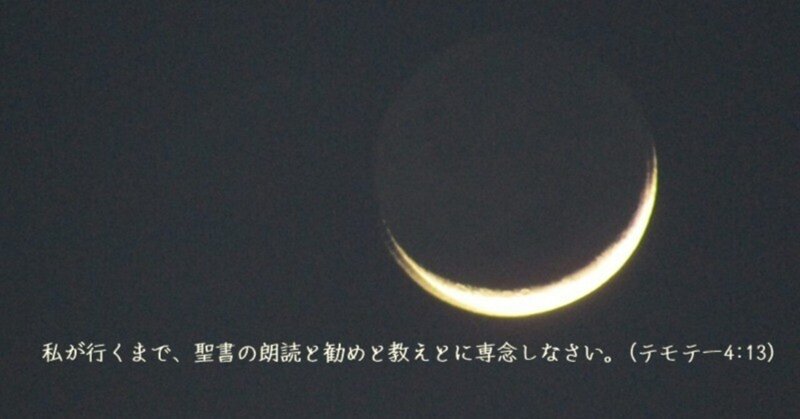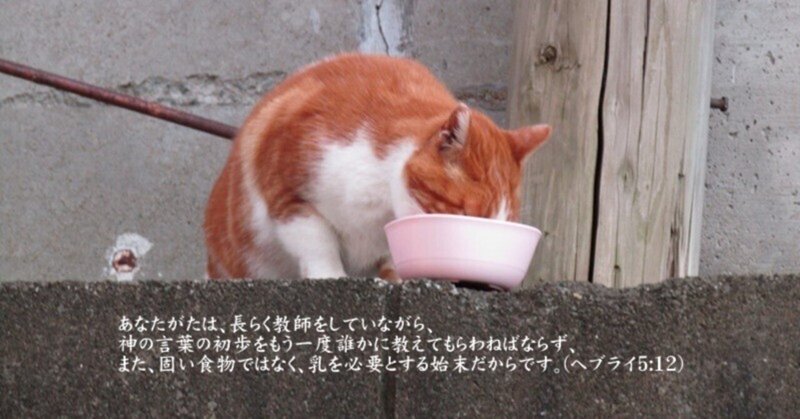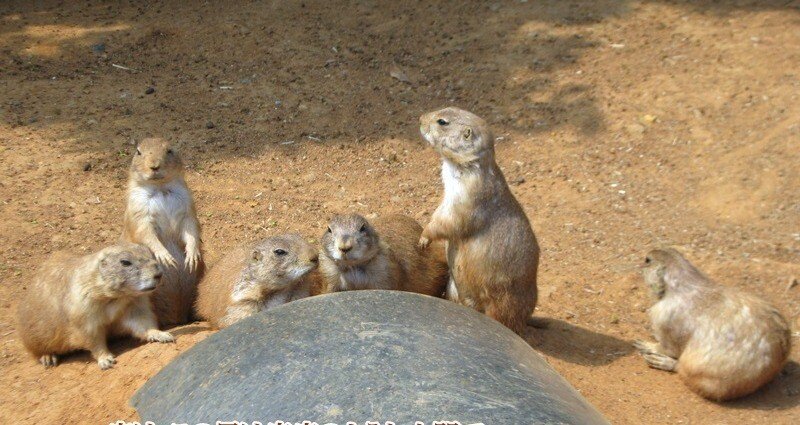
キリスト教会はとても居心地のよいところです。でも、満点を期待してはいけないでしょう。たくさんの問題を抱えています。とくに内側にいると見えないものを、なんとか見ようとするひねた者が…
- 運営しているクリエイター
#説教
ヨシタケシンスケ展かもしれない
意表を突いたタイトルの展覧会が、いま福岡で開催されている。昨年から日本各地で開かれているものだそうで、やっと福岡もその波に追いついたというところであろう。
もしヨシタケシンスケさんの本をご存じないとしたら、人生の何%か、損をしていることになるだろう、とまで言いたいと思う。その絵や言葉に触れたら、きっと自分では絶対に見えてこないものが見えてくる体験をするだろう。けれどもそれは、かつて子どもの頃に