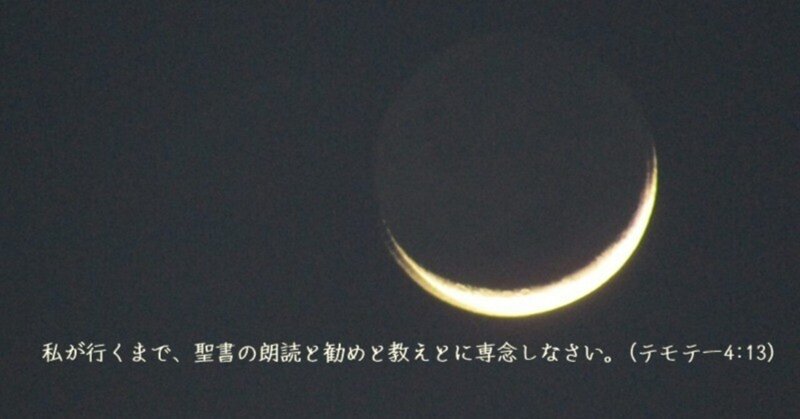
他人の説教を読む礼拝
アウグスティヌスの言葉らしい。説教者が、他人の説教を語る、ということについて述べているという。「有能ならざる説教者は、安んじて他人の説教を用いるように、と忠告している。」
ボーレンの『説教学Ⅰ』からの孫引きである。純粋に理論的に、というよりも、かなり情熱的な勢いも感じるこの本であるが、ここは冷静な態度を示しているように見える。他人の説教を語る、とはどういうことか。
牧師は、礼拝説教を、礼拝の中で語ることになっている。神からの言葉を取り次ぐような仕事であり、聖書の説き明かしをする、あるいは信仰生活の勧めをする、そうした重点は人により教会によりいろいろ違うだろうが、説教者自身が神から聞いたことを、人々に語る、というのが当然視されている。
つまり、その都度説教者のオリジナルであるのが、説教としては極めて当たり前のことなのである。それを、ボーレンの『説教学』は、他人の名説教を読むようなことがあってもよい、と言っているのである。これは、ボーレン自身が、そういう考え方である、という意味である。
そこへ、アウグスティヌスの考えが援軍として見出されたために、引用した、ということであるだろう。ただ、そこにはきつい一言が冠せられている。「有能ならざる説教者」という言葉だ。
「有能ならざる説教者」から、自分のオリジナルの原稿を説教として毎週聞かされるとする。正直これはたまったものではない。それならばいっそ、有名な説教を朗読してくれたほうが、聞くほうはまだうれしいだろう。そういうことを言っているのである。
これは、牧師としては、プライドが潰されることを意味する。あんたの話などは聞いていられないよ、他人の良い説教を聴かせておくれ。そう求められているのである。しかし、アウグスティヌスもボーレンも、これを認める。なにより、聞く信徒の立場とすれば、これは確実に良いことである。神を礼拝する心になって、神を礼拝するに相応しいひとときをもつことができるだろう。良い話を聞くからである。
しかしそうなると、この説教者、牧師だとすると、なんのために給与をもらっているのか、ということにも目が向くだろう。教会の留守番でもするだけなら、アルバイトでも十分である。朗読の上手な人がいればよいのである。
もちろん、説教はその語る人の魂の中から零れてくるものによって、できるはず。その声や、抑揚や、話す速さなどによっても、信仰は伝わってくる。神が襲ってくるかのように、「語り」が成立するだろう。素人の朗読に、それを期待することはできない。
だが、そういう負の面を想定してもなお、「有能ならざる説教者は、安んじて他人の説教を用いるように、と忠告している」を認めるというのである。
せいぜい、それを読み上げることで、説教者の腕も上がることを願う。だが、説教は練習によって上達するというものではない。最初はおどおどしていたけれど、だんだん慣れてくると流暢に話せるようになった、ということはあるが、それによって説教に命が加わるものでもない。当人と神との関係次第なのである。
そして、それは表にちゃんと現われてくるのである。腕前が問題なのではない。語る者が、キリストと出会ったことがなければ、何をどうやっても、命の言葉は語れない。どうぞ、早速来週から、優れた説教を、読み上げるがいい。いくらでも書店で、特にキリスト教書店があれば、手に入る。ネット注文ならば、何十年分の説教を、手にすることができるはずである。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
