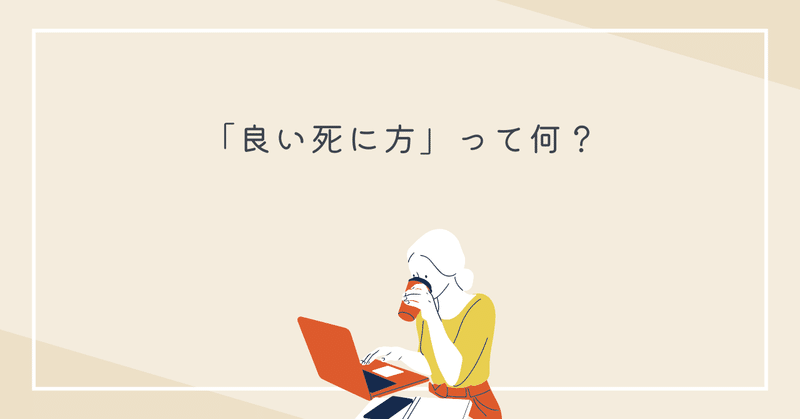
(読書)人はどう死ぬのか?の本が目からうろこだった話
おはようございます!
こちらの本、最初から最後まで「目からうろこがボロボロ×10乗」だった、という話をしたいと思います。
まず、死と、医者に対する考え方が変わりました。
死は恐れなくて良いのだ、と腹落ちしました。
最後にある「人気の死に方」の話については、がんに対する考え方も180度変わりました。
臨床医者の「言ってはいけない」本音を、遠慮なく書いた本、とでも言えばよいのでしょうか。
人生観ががらっと変わるような本だと思いますので、ぜひご紹介させてください。
人はどう死ぬのか

臨床医の経験をもとに書かれたこちらの本、死ぬ間際の人の話がたくさん出てきます。
おおよそのケースで「延命治療」、心臓マッサージなどは基本的には「無駄」なものであり、親族が医者のパフォーマンス(儀式)として行っているものもあるということ。
医者が当直を交代する際、
「この患者は”儀式”(延命パフォーマンス)はいらない(親族が無駄なのをわかっているから)」
「この患者は、"儀式"ありで」
などとやり取りをするそうです。
遺族から文句が出ないように、本気ではないけれども医師や看護師が「延命治療らしい」ことをしてから死亡告知する、というのが「儀式」。
超・高齢者で意識がない場合に、救急車を呼ぶものではない、というのも知りませんでした。
医療従事者は、運ばれた方がかなり高齢の場合
「どうして救急車なんか呼んだんだ、そのまま自宅で逝かせてあげればいいのに」
と思いながら、かといって、放置はできないので、無駄だと分かりながら延命治療を思うことがあるそうです。
意識がない・危篤=救急車、というのは、一般人の浅はかな考えだったようで、医者からすると「実は不要で有害な延命措置」というものも多く存在するようです。
医者も、顧客(遺族)向けのサービス業という局面もあるのだな・・・
訴訟リスクも高いし、大変だな・・・
と思うところばかりでした。
私は医療や死に関しては完全な素人であり、本で批判されているような人と同じような反応をしてしまうだろう、と思う箇所がたくさんありました。
こちらの本を読んで、医者に対してどう接したらよいのかをとても考えさせられましたし、今後お世話になる際の勉強になりました。
延命治療の必要性
某元政治家の方が、心肺停止の状態であったにもかかわらず、親族が到着するまで5時間以上の間、輸血され続け、心臓マッサージが行われたというニュースを聞いたことがあります。
実際に蘇生する可能性は低いものの、親族が駆けつけて死に目に合うための措置だったのかもしれません。また、著名な方が患者の場合、世間が注目するため、病院側の落ち度を指摘されるリスクも限りなく大きいので、病院として、そのような判断されたのだと思いますが、真相は分かりません。
著者は、寿命を迎える人、そのような状況の人に対して、ほぼ延命治療はいらない、という立場をとっています。
家族が駆けつけるまでの間、人工呼吸のための気管内挿管、カウンターショックのために皮膚にやけどを作り、心臓マッサージで肋骨をバキバキと折り、家族が死に目に会えるようにする、というようなことは非道な蘇生処置である。と断言しています。
これは穏やかに臨終を迎えようとしていた末期がん患者のケースですが、某元政治家の方同様に、家族が駆けつけるまでの間の処置でした。
著者も若いころ、とある患者に熱心に延命治療をフルセットで行ったところ、逆に死期をはやめたり、患者を苦しめたことがあり、多くの医者が自然と行っている、死に向かう人を治療することへの「諦め」のようなものの意味を知ったそうです。
延命治療は無駄で残酷なことであり、行うとしたら、冒頭の「儀式」同様、遺族から「あの病院は何もしてくれなかった」というような噂をたてられるのを避けるためであるといいます。
死に対しては医療は無力なのに、世間の人はそう思っていないので、ベストを尽くすフリをしなければならないのだそうです。
これは知りませんでした。
在宅医療においても、死に目に医者がいるかどうかは問題はないにもかかわらず、「到着が遅かった」などと遺族から言われるケースもある。
看護師が行う、死後のご遺体の「エンゼルケア」の実態も詳細に書かれています。これも実際に本で読んでいただきたいのですが、わたをつめたり、化粧をしたり、遺体の便を処理したりと、私の知らないことばかりでした。
ドラマの影響か、闘病のすえ、死にかけている人に遠方から駆け付けた親族が「頑張れ!」「死なないで!」などと声をかけて励ます人もいるそうですが、ずっとそばにいて闘病していた家族や医者、看護師は、「もう頑張らなくていい」という気持ちで静かに、臨終を迎えるそうです。
いい死に方とは、死を受け入れて在宅で死ぬこと。
悪い死に方とは、意識のない状態で延命治療でチューブやら機械につながれ、病院で死ぬような「死を受け入れない」こと。
まとめると、こんな著者の考えのようです。
事故など冷静にはいられないこともある一方、
病気など一般的な死因の場合、「静かに受け入れる」ことが大事なのだそうです。
一方、若い年代の遺族の場合には、しっかりと親族の死に目に合わせることも大事であり、本当の延命処理をすることもあるそうです。もちろん、本当に蘇生の可能性があれば、医者として対応するのでしょう。
「死に目に合う」という価値観
著者は「死に目より大事なのは、それまでの時間どう人と過ごしたか」であるといいます。
よく考えてみれば、当たり前の話ですね。
相手が最期に昏睡状態や下顎呼吸(かがくこきゅう)をしているときだけ「愛してる」や「ありがとう」などというのは死にゆく本人には(おそらく)伝わっていませんので、「気休め」にしかならない。
昏睡状態でほぼ聞こえてない時に、わざわざ大事なことを言うのではなく、ふつうに意思疎通できるときにそれを、言っておいたらどうか。
死に際で一言言いたいのはエゴであり、死について考えれば、一日一日を大事に生きるしかない、という結論になります。
生きている間に、十分感謝の気持ちを伝えれば改めてわざわざ死を迎える場で念を押す必要はないし、それを別れ際に「言わせる」必要もない。
臨終の場に同席して「異様なほど感情を乱す家族」がいるので、医者としてそういった感慨を抱くことがあるそうです。(おそらく一般的に、患者側の親族が、ドラマの見過ぎなのかもしれませんね、、、)
個人的には、親の死に目に会いたいという希望はもともとなかったので、これらの考え方が日本では根強いというのは、とても目新しいものでした。
私自身、海外に住んでいたことから祖父母の死に目にも立ち会っていません。「死に目にあう」「同席する」ことへのこだわりや執着は、後悔など様々な弊害があるため、こだわりすぎない方がいいのでは、というのがこの本では推奨されています。
死に目ではなく、生きているうちに親孝行・親族孝行をするべし、ということですね。
死を受け入れること
また、著者がみとった多くの患者さんを見ていて、上手な最後を迎えるコツは「死を受け入れる」ということだと言います。
いつものように、眠って起きなかったらそれが死というもの。だったら痛くもない。
もしくは、死ぬときは多少の苦しみがある、と心づもりしておくこと。(今は緩和ケアなど充実しているようですが)
それでも死ぬのが怖いのであれば、それは死について慣れること。
考え続けて、自分が死の恐怖という幻影に振り回されていたことを実感し、だんだんと受け入れられるようになり、死ぬべき時が来れば受容して受け入れられる。受け入れられずになんとかしようとする人ほど、下手な最期を迎えるようです。
人間の致死率は100%なので、現在20代や30代でも、その意味ではいつこの心境になるのか、事前に準備できるのか、という、いずれは誰にでも当てはまる問題なのだと思います。
アダルトサイト閲覧歴や、日記など見られて恥ずかしいものはそもそも残しておかない、遺産整理なども準備の一環ですね。
話はそれますが、延命治療の下りでも思いましたが、子どもが風邪をひくと病院に連れていく・・・というのも、医者からすると、ある意味過剰医療なのかもしれない、と思いました。
”結局ノロなのかロタなのかコロナなのか、ウイルスはわからないのでとりあえず、風邪薬(解熱剤など)をもらう。”
過去に何度も小児科医と繰り返した、ある意味不毛なやり取りは、遺族とのやりとりのように、「母親として何かアクションを起こした」という納得感の問題だったのかもしれません。もちろん、万が一でも重大な病気では、という思いがあるので、連れていくのですが。
市販薬で様子を見ているとだいたい2-3日で回復しますので、本当の重篤な患者を押しのけてまで病院に行く必要は、本当はないのかもしれません。
アメリカでは本当に行かざるを得ないときだけ行く、というインセンティブが料金体系で(1回医者と話して3万円以上、の社会)すでについていましたが、場所によっては無料で医療を提供する日本においては、多すぎる医者通いも、消費者へのサービスとして行われるものなのだ、と医者目線で考えるきっかけになりました。
「100歳まで死ねない」日本社会
著者は、日本社会においては、臭いものには蓋をして、死や犯罪の加害者の話をメディアは取り上げないといいます。
さらに、高齢化が進み、「100歳まで生きられる」社会になってきた、と言われていますが、著者は「それがが真に意味するところは、100歳まで死ねない、ということである」といいます。
高齢者医療の現場では、100歳近くまで生きて悲惨な状況の患者さんを多く見てきたそうです。メディアでは、食欲旺盛だの、腕立て伏せができるだの、今でも仕事しているだの、明るい部分しか伝えません。
実際はあちこち痛く、関節が曲がらず、不眠と便秘と頭痛に苦しみ、心不全などの予兆に怯え、様々な老いの現実に苦しんでいる人も多くいるのに、それを伝えようとはしません(まあ、確かにその現実をテレビで見ても、そこまで面白くはないですよね)
実は、「ピンピンコロリ」と死ぬには、若いうちから不摂生をし、ヘビースモーカー、大酒のみ、カロリーオーバーで睡眠・運動不足、血液検査は異常値ばかりの人が心筋梗塞や脳卒中でコロリと死ねるのであって、健康的な人は「よろよろ、かつ、へとへと」になって人生の最後を過ごし、結果的に親族にも迷惑をかけるかもしれません。
死ぬよりマシと、死んだ方がマシの差はそんなにないと思う、というのは小説家である著者の名言だと思いました。
私の親族のひとりは、待ちに待った65歳の退職生活3か月目で、配偶者が倒れて、本人は精神病院に入院し、体中が痛んで全く外出できなくなりました。ほかの親族も、今透析で介護中です。退職後にやりたかった旅行、趣味など、何もできないまま何年も過ごしています。
気の毒なケースではありますが、この身近な例だけ見ても、長生きって、それだけが善で本当にいいことなのか?と思っていましたが、本を読んで改めてそれを考えてしまいました。
医者に人気の死に方というのがあるらしい
以前雑誌の特集で、医者たちが選んだ「人気の死に方」のランキングのようなものがあり、1位は「がん」だそうです。
びっくりしました。多くの医者は、「老衰」ではなく、がんで死にたいらしいです。
病院にかかっても死ぬときは死ぬので、がんは治療さえしなければ、ある程度の死期がわかるので、それに向けて行きたいところに行ったり、会いたい人に会い、迷惑をかけた人にあやまるなどして、準備ができる、ということが理由のようです。
老衰のケースだと、イメージ通り「安らかに死ぬ」というよりは、時間をかけ、親族がケアを長年してから亡くなることが多く、それはそれで周りにとっては負担になってしまうもの。
一方で、がん治療においては治らないけれど死なない、という現状の「がんとの共存」治療により、充実しながら生きられる時間が増えている。
逆にがんを根絶することに執着すると、残された時間を辛い副作用で無駄にしてしまうことがあるようです。例えば、医者自身は治療を中止した方が患者さんのためになるのにと思いながら治療を継続し、やはり最後の最後で「治療をやらなければよかった」と嘆くパターンがとても多いとのこと。
もちろん、メディアはこういった「がんという死に方のメリット」や「本当はやらなければよかった治療」について伝えようとはしません。(一定の批判があるからだと思います)当然、私も知りませんでした。
がんに悩む人に対して、「メリットがある」というのは酷ですが、まだガンではない人に向けて、そのメリットあらかじめ伝えて心の準備をしておくことは有意義だというのが著者の考えです。
そういう意味では、自分の死に対しては(がんなどを除いては予想不可なので)意見を持たず、不安になりすぎず、冷静にいるということが大事なのかもしれません。
ちなみに、医者は、余命告知の際に、あとから批判されることを防ぐために余命は短めに伝えるそうです(少しでも長ければ感謝されるため)
知りませんでした。
医者は、いろいろ考えてから発言が求められる、辛い立場なのですね。
高度な医療で救われる人が増える一方で、病院で高度な治療をするから、徒に苦痛が引き延ばされる事象も発生してしまっている。
その中で生まれているのが、医者の苦悩。
結局のところ、医者や看護師、警察、消防など救急系対応の方、特殊清掃など以外はすべて「死」の素人。
医者も死は救えません、というところ、過剰な期待をかけられているというのが実情なのだと思います。もちろん、安楽死も日本では許されていませんので、延命治療は患者のためにならなくても、家族のためにならなくても、やらねばならないときがあると思います。
医者も、人を助けようとすればするほど悩んでしまうのが現状。安楽死をすると、刑事罰にもなる社会。
「無駄な延命治療が嫌なら、病院に行かないのが良いんです」
と著者。
うーむ、なるほど。
常に死を思う「メメント・モリ」
著者は、自分だけではなく、妻や子供や孫、母親の死を常に意識するようにしているそうです。
悲しいことですが、起こらないとも限らないため、そのように日々考えていると、身内が生きてくれているだけでうれしいと感じるそうです。
いつか別れが来るかもしれないなら、あとで悔やまないように常に死を意識しておく。慣れてしまえば当たり前になる、と。
親族の死を考えると不安な気持ちになりますが、いつかは起こるものとして受け入れる、慣れるという考えですね。
今私も、本を読んで死ぬときのことを考えていますが、FIREしたい、不動産投資はじめよう、などと言っているものの、死ぬ間際になって「資産形成しました!」と言ったところで何なんだ?という気持ちになってきました。
結局、自分の死をあるがままに受け入れる、いろいろと「求めない力」が強い人が、上手な最期を迎えているようです。
ネガティブ・ケイパビリティですね。
誰も死んだ経験がないので、だれも教えてくれない。
中絶や、流産、染色体検査など、女性の誰にも言えない経験と似たところがあります。
まとめると
・医者からすると、病院に行くこと、病院で死ぬことが全てではない
・延命治療は必要ではないこともある(むしろ本当は不要でもやっているケースが多い)
・がんは悪いことばかりではない(むしろほかの死に方よりよいと医者は思っている)
・死を常に思いながら、毎日楽しく、死ぬ間際に後悔のないように過ごしたほうが良い
安易な結論になってしまいますが、わたしからすると医療に過剰な期待をしている(私含む)一般人の存在について、考えさせられました。
今時点においては、少なくともチューブや機械につながれて、尊厳もなく死にたくはないな、とうっすら思いました。
まずは、いい人生だった!と思って、うまく死を迎える準備をしたいと思います。
少しでも皆さんの参考になれば幸いです。
いただいたサポートはクリエイターとしての活動費、これからもっとよい作品を送り出すための投資にさせていただきます!
