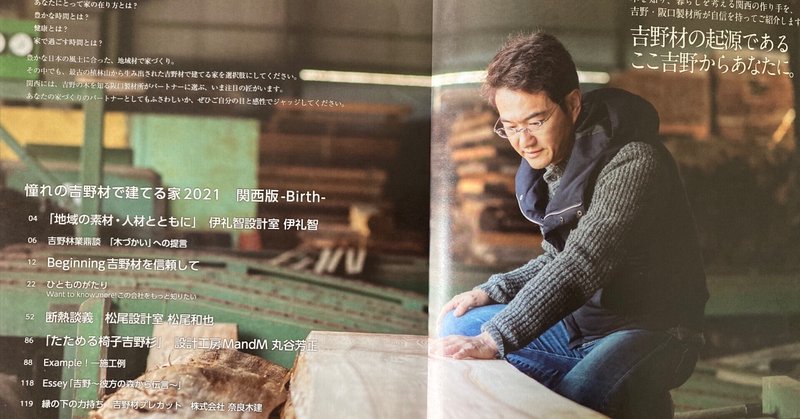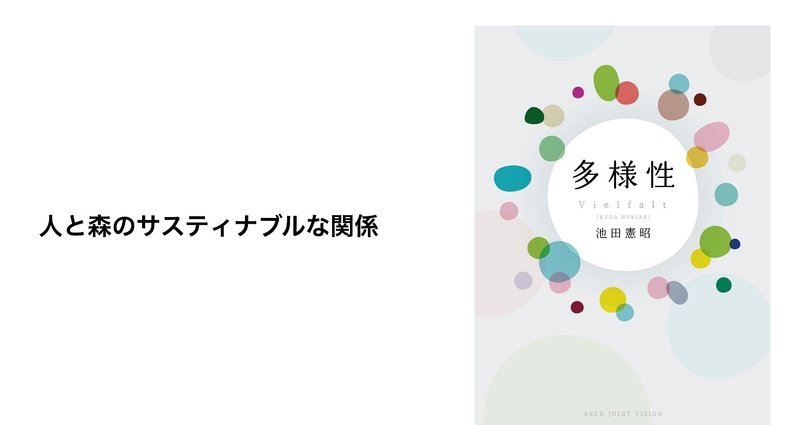
- 運営しているクリエイター
#森林
書評 「多様性」 by 藤森隆郎さん
藤森隆郎さんは、1938年生まれ、日本を代表する森林生態学者で、国際的にも活躍をされた方です。「気候変動枠組み条約政府間パネル(IPCC)」が2007年にノーベル平和賞を受賞したことに貢献したとして、IPCC議長から表彰を受けられています。
2010年の日本森林再生プラン実践事業の際に、私は藤森さんと数回に渡って交流させていただきました。
藤森さんは、現役引退後も熱心な活動をされており、2015年
『多様性〜人と森のサスティナブルな関係』がPOD出版コンテストで賞をもらいました
『多様性〜人と森のサスティナブルな関係』
https://www.amazon.co.jp/gp/product/B091F75KD3
POD(プリントオンデマンド)出版のコンテストで優秀賞をいただきました。
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000004456.000005875.html
PODとは、普通の出版社を通さない自己出版の方法で、注文が来てから印
自然と音楽は嘘をつかない!
好評いただいている7月のオンラインセミナーの締めは、7月27日18時30分から、高山の長瀬土建の長瀬雅彦さんにゲストスピーカーとして登場してもらいます。
「経年美化」する土木業者になるために 〜SDGsに取り組む長瀬土建の挑戦
https://nagasedoken.peatix.com
長瀬さんとは10年以上の付き合いで、年に1、2回はドイツか日本で会って仕事、プライベートで交流している私の大