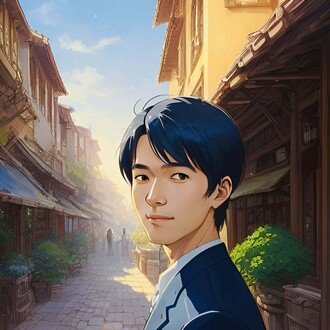#執筆
エッセイ「詩と小説」1. #執筆観
詩という絵画をいくら重ね合わせても物語にはならない。詩の持つ、時間と空間の・主体と客体の伸縮性が、小説の時間的順序の中では、双方に悪影響を及ぼしてしまうからだと思う。
詩的な物語を書きたいと思った時、登場人物に詩的な散文を吟じさせて満足するか、筋に重きを置かず客観的事実が少なく抽象性の高い文章に挑戦するか、しかないのか?
と、ここまで書いて結局自分は詩的な物語ではなく、実は美的な物語を書きたいとい
青い風花
第一詩集『青い風花』 矢口蓮人 著
ビルの隙間風に舞うのは、枯葉でも花びらでもなく、いつかの日に溢れて拾い損ねた想いだった。
16の詩に乗せて謳う、青年の強がりと少女の孤独。
大人になってしまったあなたが、なくした鍵がここにある。
http://www.gentosha-book.com/products/9784344972452/
https://www.amazon.co.jp/dp