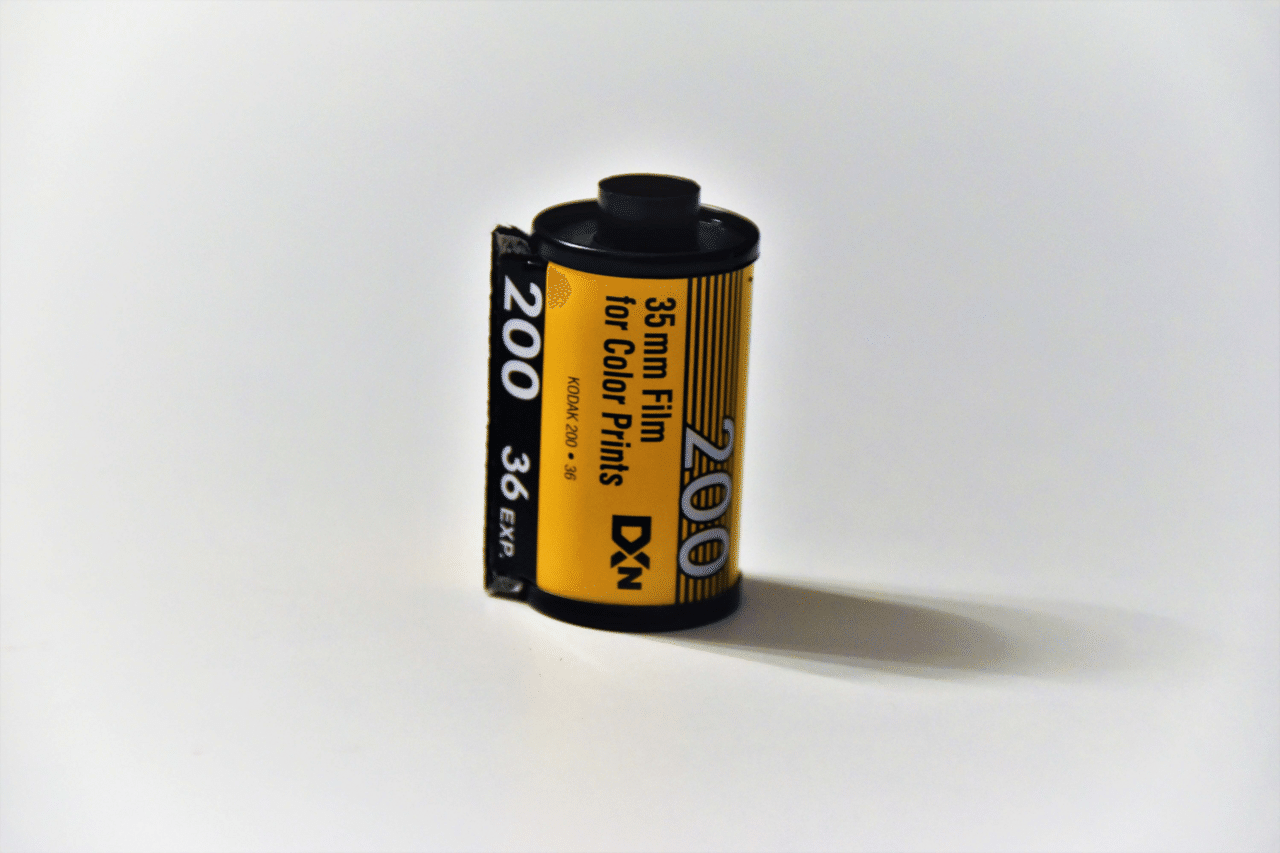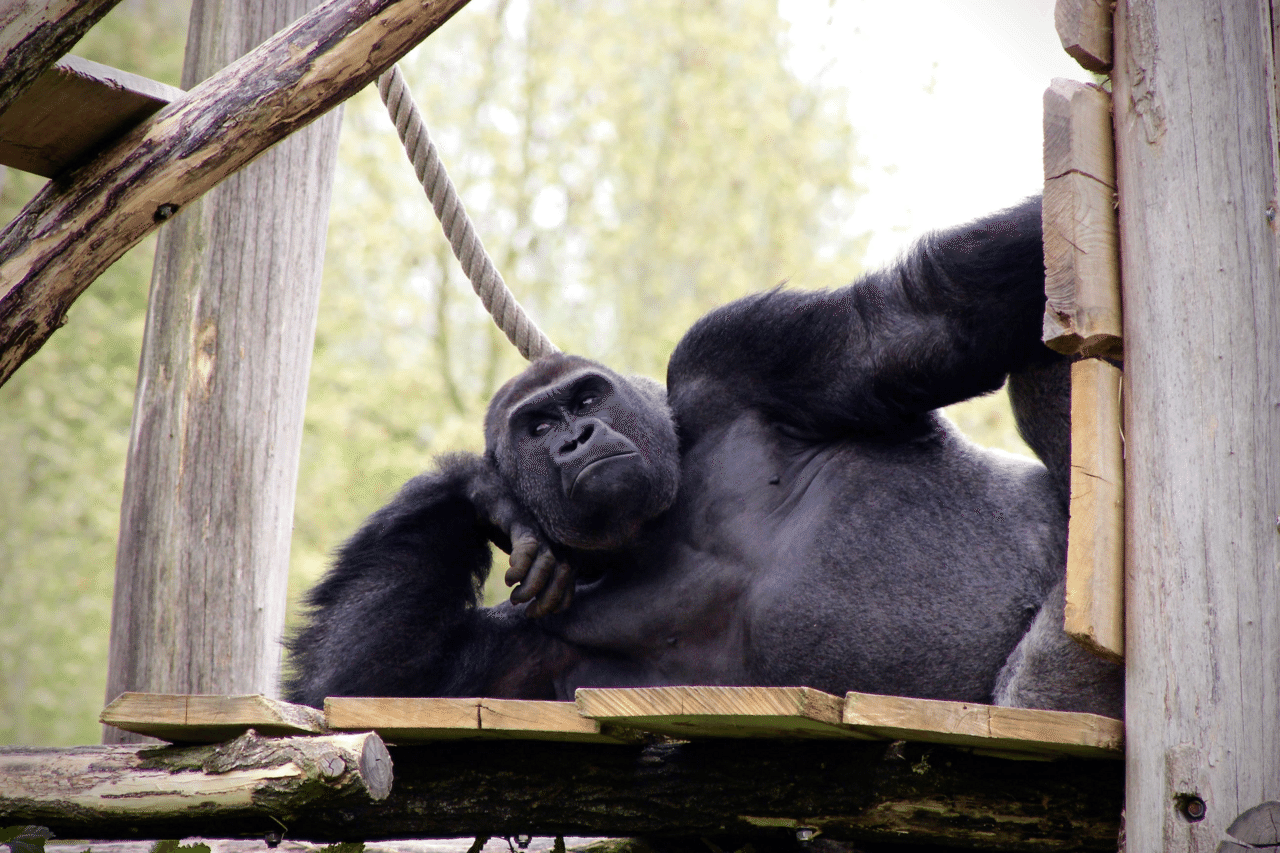2023年12月の記事一覧
【焼き肉】
昔、オトナの方がメンバー全員に
"焼き肉"をご馳走してくれる事になった。
着いた先は
赤提灯の『焼き鳥屋さん』。
(たしかに"焼き…肉"だな)とうなずき、食べた。
とにかく食べて、とにかく呑んだ。
「君たちはザルだね」
お会計表をみてオトナの方が震えていた。

【「お」のつく言葉】
お醤油、お味噌汁、おそば、おうどん
「お」をつけると美しくなる。
「娘さん、お幾つですか?」
そう聞かれたら、
「おはっさいです。」と答えている。
「じゃあ来年は"おくさい"ですか?」
ツッコミ待ちだが、未だこず。
落語「雛鍔」の引用で遊ぶ父。