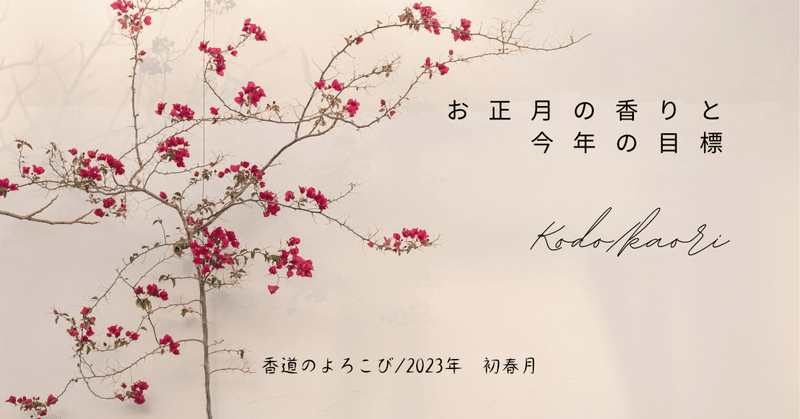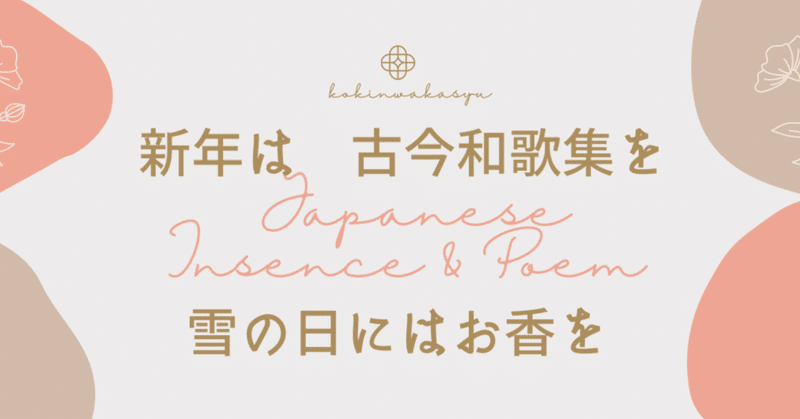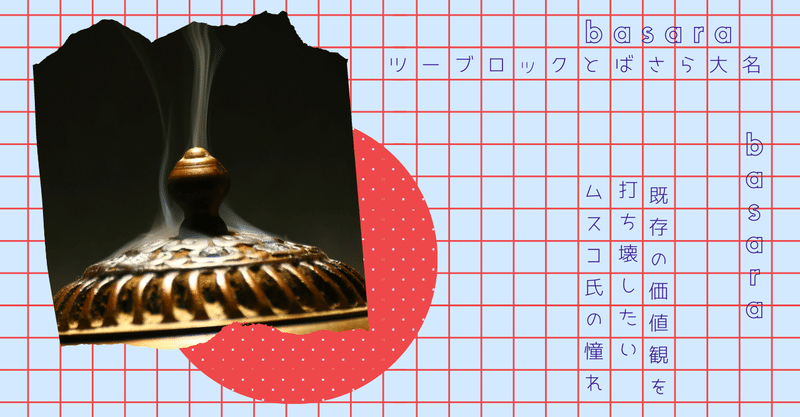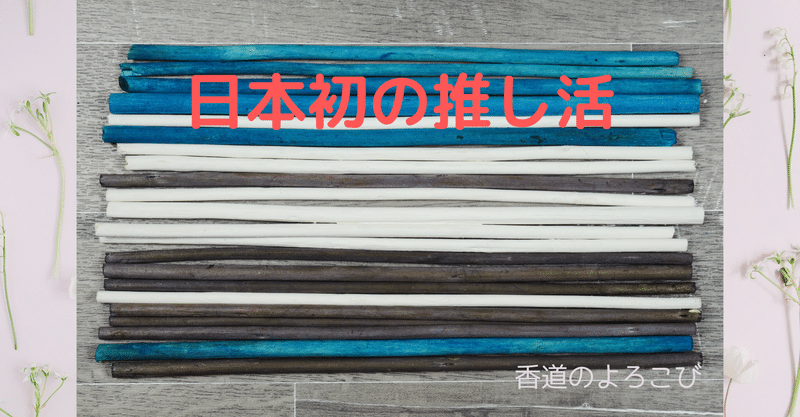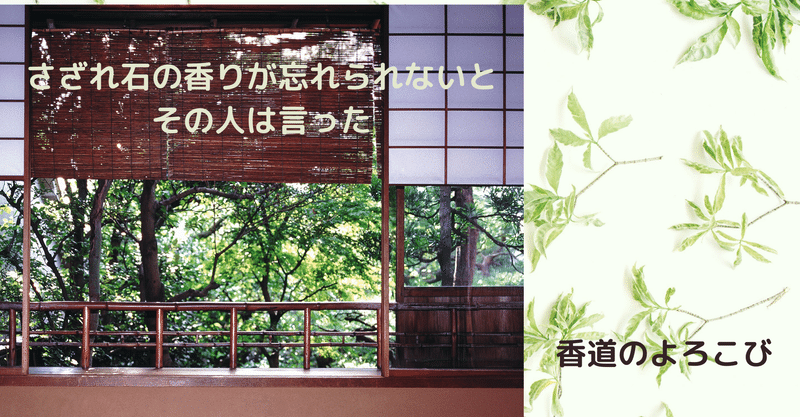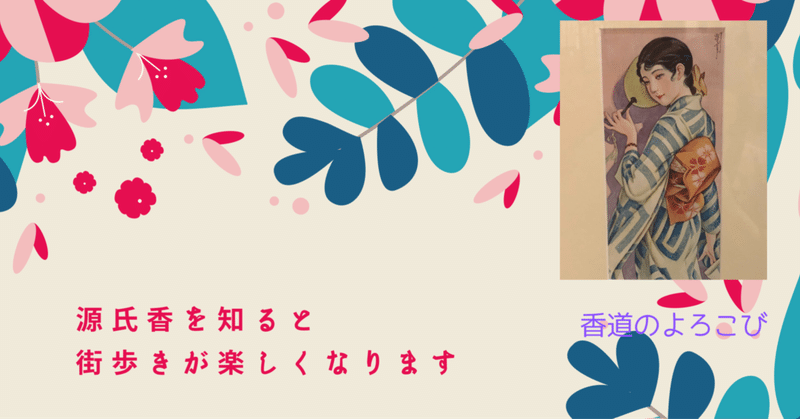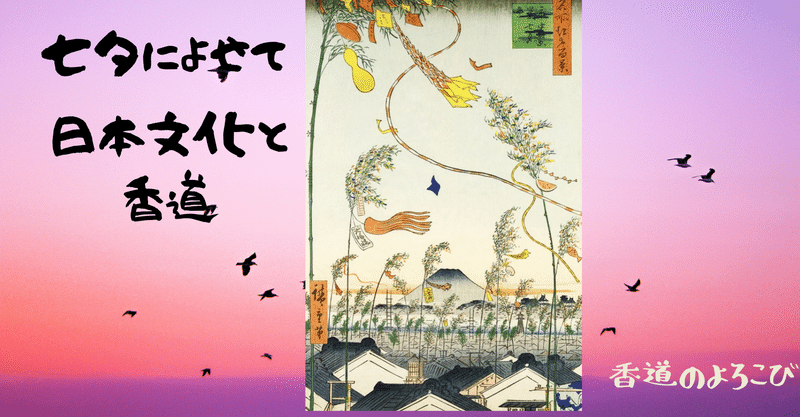#香道
ツーブロックとばさら大名
「これって、ツーブロックだよね」
帰宅したムスコ氏が言いました。ツーブロックとは男子のヘアスタイルで、一般に頭部の耳より上を残して下を刈り上げるスタイルのことです。一般紙などでもブラック校則のひとつとして話題になっていたことがある、あのツーブロックです。整容検査では男子の頭髪は耳にかかるといけないという校則があるそうで、ずぼらで面倒くさがり屋のムスコ氏は、まったくだらけた感じのもっさり頭だったわけ
憧れのあのひとは何色の香りですか
「こんなおとなになりたい」という憧れをもって成長することができるのは幸せです。
2020年、小学生が選ぶ憧れの人物ランキングでは1位が『鬼滅の刃』の竈門炭次郎でした。ちなみに3位が胡蝶しのぶで10位までのなかに7人が入るという『鬼滅の刃』の独占具合でした。
『鬼滅の刃』は主人公が鬼になってしまった妹を助けるために鬼と戦う姿を描いた作品です。主人公の竈門炭次郎は緑と黒の市松模様着物を着て戦い、妹の
さざれ石の香りが忘れられないとそのひとは言った
「さざれ石の香りが忘れられない」と初めて香を聞いた男性は言いました。
パリのとある美術館にしつらえられた香席でのことです。私たちはここで香道をするために招かれて来ていました。ちなみにさざれ石というのは当日行われた渚香、という組香で使用した香木の銘(名前)のことです。
源氏香の仕組みを知ると街歩きが楽しくなります
根津にある、弥生美術館をご存じでしょうか。
弥生美術館の源氏香柄弥生美術館は、東京都文京区にある私立美術館で、高畠華宵と竹久夢二の作品を収蔵、展示しています。併設に竹久夢二美術館があります。この美術館を設立したのは鹿野琢見さんという弁護士さんです。鹿野さんは、9歳の時に高畠華宵が描く「さらば故郷」というイラストを見て大変影響を受けて出征するまで部屋に大切に保管していました。その絵は失われてしまっ