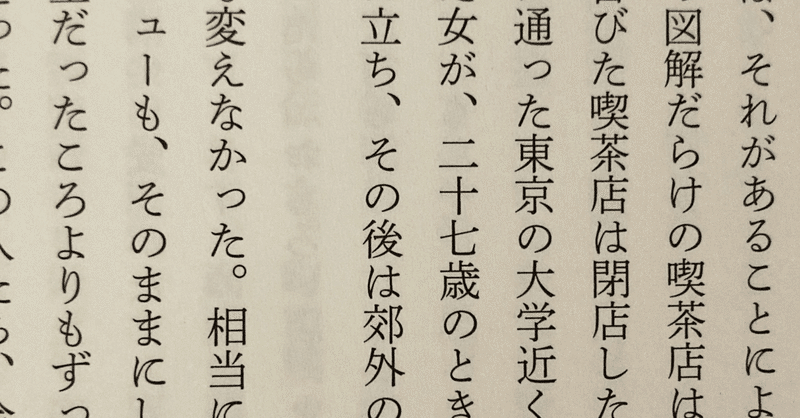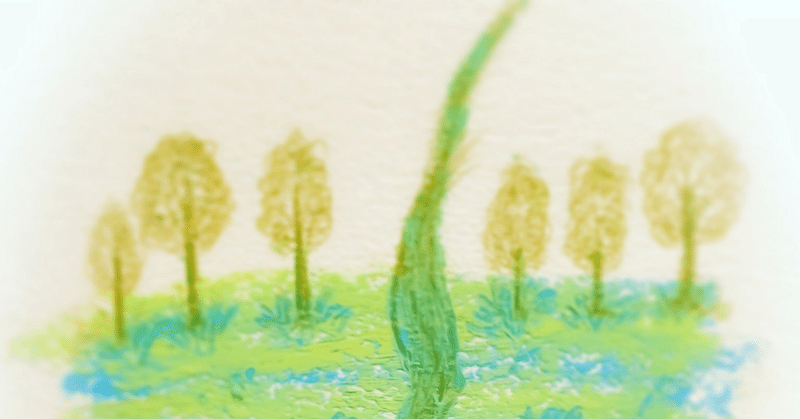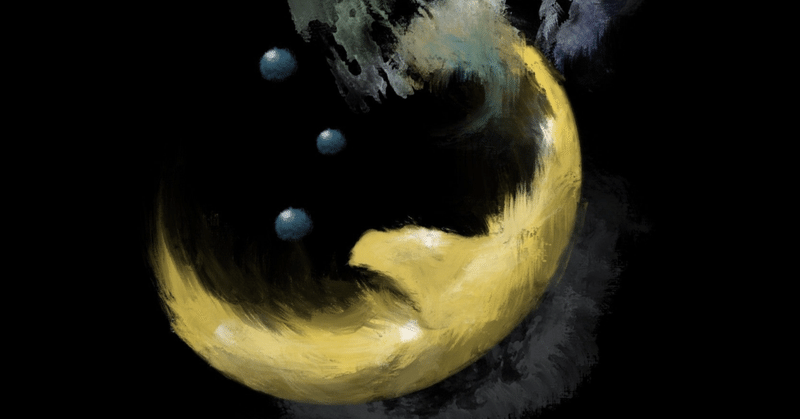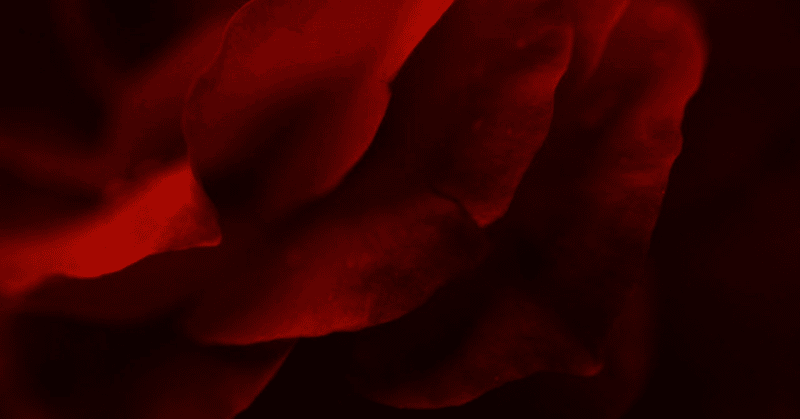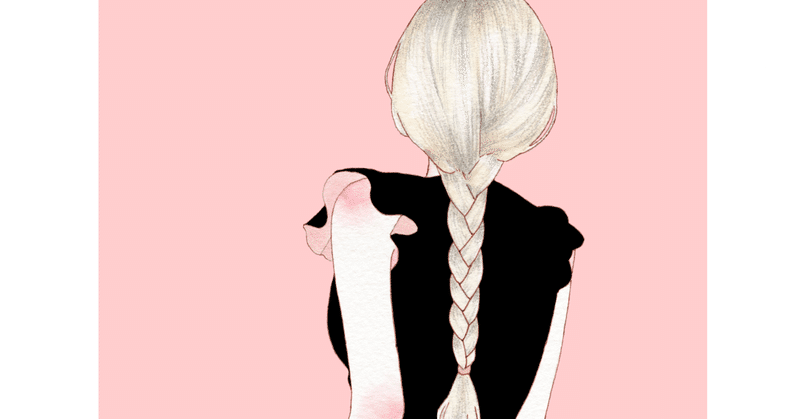#読書
『渚にて 人類最後の日』 ネヴィル・シュート
悲しく救いのない終末小説。しかし、ここまで救いがないにも関わらずこんなにも美しく、穏やかに凪いだ読後感を与える小説が、他にあるだろうか。
物語の舞台設定は1963年。この小説の初版は1957年なので、近未来というよりも同時代を描いたフィクションだ。
60年代初頭に起きた第三次世界大戦で核戦争が勃発し、核爆弾によって地球の北半球は壊滅状態になった。
今は南半球に位置する国だけで、かろうじて人間が生
“The Swimmer” John Cheever
カーヴァー、ブローティガン、アップダイク•・・。少し昔のアメリカの小説家が、全般的に好きである。
今回はそんな私のお気に入りのアメリカ人作家達の一人、ジョン・チーヴァーの、素晴らしい短編小説を一つ紹介したい。
『泳ぐ人』という題名で翻訳もあり、映画化もされている作品だ。
*****
真夏のある日曜日。昼過ぎの高級住宅街。
ネッドは友人宅のプールサイドでくつろいでいる。
もう若くはないもののまだ
『夏草の記憶』 トマス・H・クック
痛ましく残酷な、青春の愛の物語である。
南部の田舎町で、地元の医師として敬愛されているベン。しかし、穏やかな中年医師の顔からはうかがい知れない深い闇を、その心は抱えている。
妻にも親友ルークにも告げることのできない、ベンの胸に秘めた大きな重荷は、青春時代に起きたある出来事に関するものだ。
ベンがハイスクールの2年生の時、北部の大都会ボルティモアから、一人の転校生がやって来た。
浅黒い肌と黒い巻
『階段を下りる女』 ベルンハルト・シュリンク
美しい女性の登場するラブストーリーと思いきや、消化不良になりそうな難易度の高い内容だった。ストーリー自体はシンプルなのだが。
語り手の「ぼく」は、フランクフルトで駆け出しの弁護士だった頃、忘れられない恋をした。
発端は奇妙な依頼だった。
依頼主はシュヴィントという画家。彼はグントラッハという金持ちの注文で、グントラッハの妻イレーネをモデルにした絵を描いたのだが、その後イレーネと恋仲になり駆け落ち