
【短歌表現】終章:新種千人一首

王朝和歌の絢爛たる世界が蘇る!
藤原定家の「小倉百人一首」。
「原色小倉百人一首」 (シグマベスト)鈴木日出男/山口慎一/依田泰(著)

「小倉百人一首―みやびとあそび―」平田澄子/新川雅朋(著)

足利義尚の「新百人一首」に続き、
丸谷才一が新たに編んだ「新々百人一首」。
「新々百人一首〈上〉」(新潮文庫)丸谷才一(著)

「新々百人一首〈下〉」(新潮文庫)丸谷才一(著)

新百人一首は、藤原定家撰の小倉百人一首に漏れた著名な歌人の歌を、勅撰和歌集から百首選定したものであり、新々百人一首は、25年の歳月をかけて、定家と義尚が選んだ二百人を敬遠せず、かつ両人の取った二百首との重複は避けて厳選した不朽の秀歌百首と、スリリングな解釈(それに付された滋味溢れる長短繁簡とりどりの注釈)を施した現代版「百人一首」であり、通読すると歌で読む「日本文学史」にもなっている優れものです(^^)
上巻は、「春」「夏」「秋」「冬」の部を、下巻は、「賀」「哀傷」「旅」「離別」「恋」「雑」「釈教」「神祇」の部を収録しています。
さて、その他の異種百人一首としては、
日本人ならこれだけは知っておいて欲しい、近代100首を、当代随一の歌人が選び、心熱くなるエッセイとともに、未来へ贈る名歌集「近代秀歌」。
「近代秀歌」(岩波新書)永田和宏(著)

大好評を得た「近代秀歌」の続篇として、「今後100年読まれ続けて欲しい」、主として戦後の秀歌100首を編み、著者ならではの視座から、歌の現在を、そして未来を語る一冊「現代秀歌」。
「現代秀歌」(岩波新書)永田和宏(著)

明治から現代迄の100首以上の名歌を取り上げながら、人生という長い旅路の途中には、必ず節目となる瞬間が存在し、その時、たった31文字の言葉に勇気づけられたり、救われたりした自らの体験を、ふんだんに織り交ぜて綴った、心熱くなるエッセイ&短歌鑑賞入門「人生の節目で読んでほしい短歌」。
「人生の節目で読んでほしい短歌」(NHK出版新書)永田和宏(著)

「文藝春秋」創刊90周年企画として、藤原定家が選んだ「小倉百人一首」の向こうを張って、近現代短歌の「新・百人一首」を編み、本書は、読者からの好評を受けてのその新書化「新・百人一首 近現代短歌ベスト100」。
「新・百人一首 近現代短歌ベスト100」(文春新書)岡井隆/馬場あき子/永田和宏/穂村弘(著)

百人百様の“生きた”幕末史を堪能することで、維新の別の一面が浮き彫りになる一冊「幕末百人一首」。
「幕末百人一首」(学研新書)菊地明(著)

歴史の本からは分からない、詠み人の人となりや、日本文化に深く根ざした、お茶の文化を垣間見ることができる一冊「茶の湯百人一首」。
「茶の湯百人一首」(淡交新書)筒井紘一(著)

本書は、中国人60人、日本人40人の古代から現代に及ぶ代表的な漢詩を精選し、和歌に影響を与えた漢詩文を、詩人独自の読みを附すと共に、詩句の由来や作者の経歴、時代背景などを紹介した「漢詩百首 日本語を豊かに」。
「漢詩百首 日本語を豊かに」(中公新書)高橋睦郎(著)

岡本かの子といえば、桜だけを題材にしたものすごい勢いの連作「桜百首」。
「桜」岡本かの子
これらの真・異種百人一首の向こうを張って、短歌表現を「詠んだ人」の視点と「読む」側の感覚を織り交ぜて、新or追体験させてくれる穂村弘さんが選ぶ何でもありの短歌ガチャ100の本書を真似て、
「短歌のガチャポン」穂村弘(著)

もう、なんでもありのマジカルな短歌ワールドを、とことん楽しみなが、考えさせられながら、近・現代短歌を中心に、百人一首選び(≒遊び)をしてみたので、お時間有れば、お立ち寄り下さい(^^♪
【新種千人一首】
■序章:異種百人一首(100首)
「クラビクラと呼ばるるときを知らぬままふたつの窪みはみづを拒みぬ」
(佐藤せのか『西瓜』第六号より)
「ガラス器の無数の傷を輝かすわが亡きのちの二月のひかり」
(松野志保『われらの狩りの掟』より)
「音立てずスープのむときわがうちのみづうみふかくしづみゆくこゑ」
(菅原百合絵『たましひの薄衣』より)
「何度でもめぐる真夏のいちにちよまたカルピスの比率教えて」
(岡本真帆『水上バス浅草行き』より)
「鏡面に揺るる水銀 カデンツァのゆび砕くごと冬はゆくべし」
(金川宏『アステリズム』より)
「罪を知り海を知らないあの場所でかすかに揺れている水たまり」
(島楓果『すべてのものは優しさをもつ』より)
「重力に逆らって翔ぶ鳥の目よ 逆らふ者の美しい目よ」
(片岡絢『カノープス燃ゆ』より)
「水と塩こぼして暮らす毎日に水を買いたり祈りのごとく」
(辻聡之『あしたの孵化』より)
「庭から呼ぶ生きものの声あるような苔盛りあがる美しい冬」
(源陽子『百花蜜のかげりに』より)
「壺とわれ並びて佇てる回廊に西陽入りきてふたつ影伸ぶ」
(睦月都『Dance with the invisibles』より)
「〈青とはなにか〉この問のため失ひし半身と思ふ空の深みに」
(山中智恵子『喝食天』より)
「「とりかえしのつかない ことがしたいね」と 毛糸を玉に 巻きつつ笑う」
(穂村弘『ラインマーカーズ』より)
「「用意」から「ドン!」のあひだの永遠を生まれなかつたいのちがはしる」
(千葉優作『あるはなく』より)
「あはと消ゆる南のゆきのかろきをば降らせたやなうそなたがうへに」
(紀野恵『フムフムランドの四季』より)
「あやまちて野豚(のぶた)らのむれに入りてよりいつぴきの豚にまだ追はれゐる」
(石川信夫『シネマ』より)
「ある時は小さき花瓶の側面(かたづら)にしみじみと日の飛び去るを見つ」
(北原白秋『雲母集』より)
「うす青き朝の鏡にわが眉の包むにあまるかなしみのかげ」
(蒔田さくら子『秋の椅子』より)
「うつしみの手首にのこる春昼はるひるの輪ゴムのあとをふといとほしむ」
(小池光『サーベルと燕』より)
「うるほへる花群のごと人をりて揺れなまぬなり夏の朝を」
(高木佳子『玄牝』より)
「おだやかな眼差しかへすキリンたちいつも遠くが見えてゐるから」
「looking back at me
so calm, these giraffes
because
they can always see
such a distance」
(田中教子(翻訳:アメリア・フィールデン/小城小枝子)『乳房雲』より)
「おほかたの友ら帰りし構内に木の椅子としてわれを置きたし」
(澤村斉美『夏鴉』より)
「オルガンに灯る偽終止、頑張れば楽になるとふ属音ドミナントあはれ」
(濱松哲朗『翅ある人の音楽』より)
「きたる世も吹かれておらんコリオリの力にひずむ地球の風に」
(井辻朱美『コリオリの風』より)
「きみの指を離れた鳥がみずうみを開いていけば一枚の紙」
(平岡直子『みじかい髪も長い髪も炎』より)
「くちびるに迫る夕日のつめたさを海に告げたり海はわらふも」
(水原紫苑『さくらさねさし』より)
「クリスマス・ツリーを 飾る灯の 窓を旅びとのごとく 見てとほるなり」
(大野誠夫『薔薇祭』より)
「くれなゐを久遠に閉ざすかのごとく光をおびてゆくりんごあめ」
(門脇篤史『微風域』より)
「ゲットーの四角い窓から降る雪をみているもうすぐ永遠に留守」
(野樹かずみ『もうひとりのわたしがどこかとおくにいていまこの月をみているとおもう』より)
「こころとは見えぬ虚空の水仙の夏の没日に逃げ惑う蝶」
(正岡豊『白い箱』より)
「こんなにも ふざけたきょうが ある以上 どんなあすでも ありうるだろう」
(桝野浩一『てのりくじら』より)
「ささぶねの杭に堰かれてゆつくりと艫を捩らせ流れゆきたり」
(久保茂樹『ゆきがかり』より)
「セケン帝なる皇帝がいるらしいあの日の丸の赤の奥には」
(松木秀『Rera』より)
「そこにはだれもいないのにそこには詩人もいないのにそこにも白い」
(蝦名泰洋『ニューヨークの唇』より)
「それでいてシルクのような縦パスが前線にでる 夜明けはちかい」
(永井祐『広い世界と2や8や7』より)
「ダージリンティーにそえたる砂時計ひそかに吾のときを奪いぬ」
(野上卓『チェーホフの台詞』より)
「だいどこ、と呼ぶ祖母が立つときにだけシンクにとどく夕焼けがある」
(岡野大嗣『音楽』より)
「たくさんの空の遠さにかこまれし人さし指の秋の灯台」
(杉﨑恒夫『食卓の音楽』より)
「たましいを引きあげる手の静けさで記憶以前の場所に燃える火」
(古川順子『四月の窓』より)
「ともすればかろきねたみのきざし来る日かなかなしくものなど縫はむ」
(岡本かの子『かろきねたみ』より)
「どれほどの量の酸素に 包まれて眠るふたりか 無垢な日本で」
(小佐野彈『メタリック』より)
「なにとでも呼べる気持ちの寄せ植えにきみの名前の札をさしこむ」
(遠野サンフェイス『ビューティフルカーム』より)
「ね え見て よ この 赤 今後 見せ られる ことな いっすよ この量の 赤」
(木下龍也『玄関の覗き穴から差してくる光のように生まれたはずだ』より)
「ノウミソガズガイノナカデサドウシテセカイハイミトコトバニミチテ」
(森本平『モラル』より)
「ベツレヘム。生まれてきてから知ることの遅さで届くこの遠花火」
(toron*『イマジナシオン』より)
「マッチ擦る つかのま海に 霧ふかし 身捨つるほどの 祖国はありや」
(寺山修司『空には本』より)
「まひるまのひかり食べかけのポテトチップスに贅肉のごとき影なせり」
(西村美佐子『猫の舌』より)
「みづうみにあはくさしだすただむきのこの世にあれば桟橋と呼ぶ」
(黒田瞳『水のゆくへ』より)
「やはり<明日>も新鮮に来てわれわれはながい生活(たつき)の水底にゆく」
(三枝昻之『暦学』より)
「ゆうまぐれまだ生きている者だけが靴先を秋のひかりに濡らす」
(竹中優子『輪をつくる』より)
「わたくしの絶対とするかなしみも素甕に満たす水のごときか」
(築地正子『花綵列島』より)
「われを呼ぶ うら若きこゑよ 喉ぼとけ 桃の核ほど ひかりてゐたる」
(河野裕子『森のやうに獣のやうに』より)
「椅子に深く、この世に浅く腰かける 何かこぼれる感じがあって」
(笹川諒『水の聖歌隊』より)
「一枚の玻璃を挟みてそれを拭く男とわれと生計(たつき)ちがへり」
(今井聡『茶色い瞳』より)
「稲妻が海を巨いなる皮として打ち鳴らしたる楽の一撃」
(奥山心(NHK BS2「ニッポン全国短歌日和」 2010年10月24日放送分)より)
「雨にも眼ありて深海にジャングルに降りし記憶のその眼ずぶ濡れ」
(小島なお『サリンジャーは死んでしまった』より)
「下京区天使突抜(てんしつきぬけ) 雪晴れのさんぽはクノップフの豹をおともに」
(橘夏生『セルロイドの夜』より)
「海を見るような眼をわれに向け語れる言葉なべて詩となる」
(今井恵子『分散和音』より)
「街が海にうすくかたむく夜明けへと朝顔は千の巻き傘ひらく」
(鈴木加成太『うすがみの銀河』より)
「街をゆき 子供の傍を通るとき 蜜柑の香せり 冬がまた来る」
(木下利玄『紅玉』より)
「巻き上がる蔓に支柱の尽きたれば深さ果てなし天上の青」
(木下のりみ『真鍮色のロミオ』より)
「完璧のかたちさびしく照り映えてアル=ケ=スナンの製塩工場」
(安田茜『結晶質』より)
「簡単に生きてみるのは もう止めにするんだ 風が唸る屋上」
(山田航『水に沈む羊』より)
「逆立ちて視る風景よわたくしは芯まで熱き地球儀の脚」
(鈴木英子『鈴木英子集(淘汰の川)』より)
「襟元をすこしくづせり風入れておもふは汝(おまへ)かならず奪ふ」
(春日井建『友の書』より)
「月させば梅樹は黒きひびわれとなりてくひこむものか空間に」
(森岡貞香『白蛾』より)
「月わたる夜を思えば袋田の瀧双つ瀧赤くなりたし」
(佐佐木幸綱『アニマ』より)
「玄界灘の波濤めがけて走り出すともだちのいま生きている背中」
(鯨井可菜子『アップライト』より)
「言葉淡き地上にあれば手は常に強く握れと教えられたり」
(中沢直人『極圏の光』より)
「菜の花を摘めばこの世にあるほうの腕があなたを抱きたいという」
(山崎聡子『青い舌』より)
「坂道で鴇色となり燃え落ちる。午後、妹の髪を噛むとき」
(大橋弘『既視感製造機械』より)
「四万十に 光の粒をまきながら 川面をなでる 風の手のひら」
(俵万智『かぜのてのひら』より)
「子ども抱へし ボート難民の リアルなる渚を 思ふ冬の入口」
(馬場あき子『馬場あき子全歌集』より)
「自転車の後ろに乗ってこの街の右側だけを知っていた夏」
(鈴木晴香『夜にあやまってくれ』より)
「手套(てぶくろ)にさしいれてをりDebussyの半音に触れて生(なま)のままのゆび」
(河野美砂子『無言歌』より)
「初夏の空がどの写真にも写り込みどこかが必ず靑、海のよう」
(立花開『ひかりを渡る舟』より)
「人のかたち解かれるときにあおあおとわが魂は深呼吸せん」
(松村由利子『大女伝説』より)
「人生を やってることには なってるが あまりそういう 感じではない」
(工藤吉生『世界で一番すばらしい俺』より)
「生きるとは 死へ向かうこと 薄明は 部屋を青へと 染め上げていく」
(伊波真人『ナイトフライト』より)
「生きるとはなにか死ぬとは ハンドソープがわが手に吐きし白きたましい」
(北辻一展『無限遠点』より)
「前に出す脚が地面につくまへの、ふるはせながら人ら歩めり」
(山下翔『温泉』より)
「太陽は山上にあそぶ子供らを食べ鳥どもを食べてかくれぬ」
(松平修文『水村』より)
「地に降りて水へと戻る束の間の白きひかりを「雪」と呼び合う」
(本川克幸『羅針盤』より)
「朝おきて泡たてながら歯をみがくまだ人間のつもりで俺は」
(嵯峨直樹『神の翼』より)
「爪のない ゆびを庇って 耐える夜 「私に眠りを、絵本の夢を」」
(鳥居『キリンの子』より)
「冬木立高くそびゆる傍らに人はゆっくり時計のネジを巻く」
(清水あかね『白線のカモメ』より)
「透明な月球のごとき丸氷にバーボン注げば夏がきている」
(笹公人『終楽章』より)
「曇天のくもり聳ゆる大空に柘榴を割るは何んの力ぞ」
(浜田到『架橋』より)
「覗(のぞ)いてゐると掌(て)はだんだんに大きくなり魔もののやうに顔襲(おそ)ひくる」
(前川佐美雄『植物祭』より)
「白抜きの文字のごとあれしんしんと新緑をゆく我のこれから」
(安藤美保『水の粒子』より)
「薄明のままに明けない日のやうに卵の殻のやはらかな白」
「like the dim light
before day dawns
is
the soft whiteness
of this egg’s shell」
(紺野万里『星状六花』より)
「微生物ひきつれ弥陀はたたなづく青垣を越ゆしたしたと越ゆ」
(永井陽子『樟の木のうた』より)
「風。そしてあなたがねむる数万の夜へわたしはシーツをかける」
(笹井宏之『てんとろり』より)
「並び立つ書架にどよめく死者のこゑ樟のひかりにしずむ図書館」
(上村典子『草上のカヌー』より)
「防犯カメラは知らないだろう、僕が往きも帰りも虹を見たこと」
(千種創一『砂丘律』より)
「癒えること なきその傷が 癒えるまで 癒えるその日を 信じて生きよ」
(萩原慎一郎『滑走路』より)
「夕映えの原子炉一基にやわらかきイエローケーキが降るあさき夢」
(加藤英彦『プレシピス』より)
「葉桜の葉言葉は「待つ」三つ折りのメニューをお祈りみたいに閉じて」
(工藤玲音『水中で口笛』より)
「流灯に重なる彼の日の人間筏わが魂も乗りて行くなり」
(山口彊、Chad Diehl(訳)『And the River Flowed as a Raft of Corpses』より)
「恋ふは乞ふましろの梨の花のもと雨乞ふ巫女か白く佇ちたる」
(大沢優子『漂ふ椅子』より)
「眩むほど水かがやきぬ街を縫ふ細き流れを朝越ゆるとき」
(高野岬『海に鳴る骨』より)
■第一章:新種二百人一首(+100首)
「あの夏の数かぎりなきそしてまたたつたひとつの表情をせよ」
(小野茂樹『羊雲離散』より)
「黄昏にふるるがごとく鱗翅目ただよひゆけり死は近からむ」
(小中英之『わがからんどりえ』より)
「わがために塔を、天を突く塔を、白き光の降る廃園を」
(黒瀬珂瀾『黒耀宮』より)
「クリムトの金の絵の具のひと刷毛の一睡の夢をわれら生きたり」
(加藤孝男『十九世紀亭』より)
「晩夏光おとろへし夕 酢は立てり一本の瓶の中にて」
(葛原妙子『葡萄木立』より)
「蜜満ちてゆくガーデニア・ガーデンを等圧線は取り囲み 雨」
(錦見映理子『ガーデニア・ガーデン』より)
「おれの中の射殺魔Nは逃げてゆく街に羞(やさ)しい歌が溢れても」
(谷岡亜紀『臨界』より)
「カーテンのレースは冷えて弟がはぷすぶるぐ、とくしやみする秋」
(石川美南『砂の降る教室』より)
「十円じゃなんにも買えないよといえばひかって走り去る夏休み」
(盛田志保子『木曜日』より)
「フィルムに風をとどめて三脚はしずかに倒れる春の渚に」
(ひぐらしひなつ『きりんのうた。』より)
「透視図法の焦点となるかみしみのかなたにくらく森がにおえり」
(三枝浩樹『銀の驟雨』より)
「天使(エンジェル)の羽ならざれば温み持つ金具を外したる夕つ方」
(中澤系『uta 0001.txt』より)
「一切は烏有に帰する悦びへ火は立ち上がる逝く秋の野に」
(小笠原和幸『テネシーワルツ』より)
「抱き癖の大王イカを寝かしつけ僕を殺しに戻る細い腕」
(高柳蕗子『潮汐性母斑通信』より)
「下宿までいだく袋の底にして發火點いま過ぎたり檸檬」
(江畑實『檸檬列島』より)
「垂直線もて天頂と結ばるる夜にポロシャツをまとへるが我」
(浜田蝶二郎『からだまだ在る』より)
「文字ひとつ手紙から落ちとめどなく文字剥落し雪となり降る」
(西橋美保『漂砂鉱床』より)
「もろこしのおほき國原バーボンに古(ふ)るあめりかの霜の味はも」
(松原未知子『戀人(ラバー)のあばら』より)
「まぎれなく〈季〉うつろうと虎杖(いたどり)の群生ぬけて海にむかえり」
(西勝洋一『コクトーの声』より)
「光芒の水に折れゆく見てあれば調絃の音ほのかにきざす」
(今野寿美『花絆』より)
「集会のお知らせの壁に黄ばむ駅けむりのやうに汽車を降りれば」
(川野里子『太陽の壺』より)
「風の上に軌道はあらむひと方を指してすぎゆくひと群(むら)の星」
(資延英樹『抒情装置』より)
「目薬のつめたき雫したたれば心に開く菖蒲あやめむらさき」
(岡部桂一郎『一点鐘』より)
「星のなき空めざすごと玻璃濡れて無人エレベーター夜を昇りゆく」
(影山一男『空には鳥語』より)
「落下する骨と螢と石ころと見ているわれとモナドと神と」
(市原克敏『無限』より)
「乳母車押しゆく五月かたわらの花叢をはや過去となしつつ」
(花山多佳子『楕円の実』より)
「ざわめきは遠く聞きつつ街を出る内耳にふかき海を湛えて」
(山田消児『アンドロイドK』より)
「いま我は生(よ)のどのあたり とある日の日暮里に見し脚のなき虹」
(桑原正紀『月下の譜』より)
「純喫茶〈ミキちゃん〉出でたる路地裏に風太郎しんと尿(ゆまり)しており」
(島田修三『晴朗悲歌集』より)
「水瓶の形に水はひつそりと置かれてゐたり秋の門辺に」
(古谷智子『ガリバーの庭』より)
「いっせいに鳩が飛び立つシグナルの青あの部屋にブラウスを取りに」
(岡崎裕美子『発芽』より)
「うす霜の降りたる冷凍庫の奥の豚肉(ポーク)やさしくたたまれてある」
(阪森郁代『ナイルブルー』より)
「たすけて枝毛姉さんたすけて西川毛布のタグたすけて夜中になで回す顔」
(飯田有子『林檎貫通式』より)
「針先は蟻酸したたり濡れながらくまん蜂ひとつ空よりくだる」
(恩田英明『白銀乞食』より)
「あはあはとあはいあはひをあはせつつうたひあひゐるしやぼん玉はも
(由季調『互に』より)
「ガーゼ切り刻みたるごと散るさくらわがてのひらのまほろばに来よ」
(杉森多佳子『忍冬(ハネーサックル)』より)
「ブイ揺れて取り残さるる夏蝶を喩となす前に君に差し上ぐ」
(棚木恒寿『天の腕』より)
「あふぎつつ泥濘ゆけば空のまほ水のきはかと思(も)ふひかりあり」
(池田はるみ『奇譚集』より)
「オカリナに口づけせしごと冷ややかに朝(あした)は白き光放てり」
(花山周子『屋上の人屋上の鳥』より)
「人生を乗せいる電車ひとすじの光の詩形そこに射しこむ」
(大滝和子『竹とヴィーナス』より)
「せんせいのおくさんなんてあこがれない/紺ソックスで包むふくらはぎ」
(野口あや子『くびすじの欠片』より)
「カフェの壁あまりに白しエンダイヴこの苦さこそわれを在らしむ」
(尾崎朗子『蝉観音』より)
「食べてゐてふと明るさに気がつきぬわが負ふ影のなかより見つむ」
(天草季紅『青墓』より)
「晴れ上がる銀河宇宙のさびしさはたましいを掛けておく釘がない」
(杉崎恒夫『パン屋のパンセ』より)
「澄むものと響きあいたるあきあかね君の頭上を群れて光れり」
(遠藤由季『アシンメトリー』より)
「粥を食みつゆさきほどの時間さへとりもどせねば粥どこへおつ」
(渡辺松男『蝶』より)
「真青なる空とびてゆくしろたへのはくてうの羽の暗き内がは」
(本田一弘『眉月集』より)
「思ひきり苦いやさうは刻み込むどれつしんぐのはるさらだなる」
(川崎あんな『エーテル』より)
「こもりぬのそこの心に虹たちてあふれゆきたり夢の青馬」
(江田浩司『まくらことばうた』より)
「よみがえるこころ、車窓を信号機のうつくしく過りゆく転瞬を」
(内山晶太『窓、その他』より)
「あくびする口ひとまはり大きくなり猫はおのれをいま脱がむとす」
(花鳥佰『しづかに逆立をする』より)
「生者死者いづれとも遠くへだたりてひとりの酒に動悸してをり」
(真中朋久『エフライムの岸』 より)
「自閉する日々にも秋の降るように惑星(ほし)は優しく地軸を傾ぐ」
(法橋ひらく『それはとても速くて永い』より)
「岸にきてきしよりほかのなにもなくとがびとのごと足をとめたり」
(吉田隼人『忘却のための試論』より)
「通らない時にもレールがあることの表面に降り濡れてゆく雨」
(相原かろ『浜竹』より)
「夏すべて壊れものなり指先に切子の波は鋭く立ちて」
(宮川聖子『水のために咲く花』より)
「ああここにも叫び続けるものがゐるほどけつつある靴紐たち」
(惟任将彦『灰色の図書館』より)
「湖の底に沈みし銀の匙魚知らざるや背に秋の光(かげ)」
(井上孝太郎『サバンナを恋う』より)
「今日もまた前回までのあらすじを生きているみたい 雨がやまない」
(鈴木美紀子『風のアンダースタディ』より)
「太陽へあなたの傘を広げれば昨日の午後の雨がにほへり」
(熊谷純『真夏のシアン』より)
「手羽先にやはり両手があることを骨にしながら濡れていく指」
(山階基『風にあたる』より)
「とある朝クリーム色の電話機に変化(へんげ)なしたり受付嬢は」
(本多真弓『猫は踏まずに』より)
「水に書く言葉に似たるこの生をマルクス=アウレリウスも生きしと想へば」
(鷺沢朱理『ラプソディーとセレナーデ』より)
「三百頭のけもののにおいが溶けだして雨は静かに南瓜を洗う」
(白井健康『オワーズから始まった。』より)
「笑つてはいけない、いけない 眉検査に前髪を切り貼りつけて来ぬ」
(桜川冴子『キットカットの声援』より)
「この街にもつと横断歩道あれ此岸に満つるかなしみのため」
(田村元『北二十二条西七丁目』より)
「キャベツ色のスカートの人立ち止まり風の匂いの飲み物選ぶ」
(竹内亮『タルト・タタンと炭酸水』より)
「ああみんな来てゐる 夜の浜辺にて火を跳べば影ひるがへりたり」
(梶原さい子『リアス / 椿』より)
「ぬばたまの黒醋醋豚を切り分けて闇さらに濃く一家團欒」
(堀田季何『惑亂』より)
「イチモンジセセリ一頭の重さあり指に止まりて羽ばたく須臾に」
(春野りりん『ここからが空』より)
「ぼろぼろと光を零してはつ夏のきゅうりを交互に囓りあう朝」
(柴田葵『母の愛、僕のラブ』より)
「変わりたいような気がする廃屋をあふれて咲いているハルジオン」
(北山あさひ『崖にて』より)
「シンクへと注ぐ流れのみなもとの傾きながら重なるうつわ」
(嶋稟太郎『羽と風鈴』より)
「ていねいな暮らしに飽きてしまったらプッチンプリンをプッチンせずに」
(水野葵以『ショート・ショート・ヘアー』より)
「少女期のしめりを帯びし手のひらに十薬の白ほのかににほふ」
(小野りす「庭」『西瓜』第八号より)
「患いて街を離れたわたくしをやさしく照らすヤコブの梯子」
(澤本佳步『カインの祈り』より)
「山鳥の骸をうづめ降る雪のきらら散らして白き扇は」
(渡邊新月「楚樹」より)
「カーブする数秒間を照らされて蕾のようにひらく左眼」
(早月くら「ハーフ・プリズム」より)
「電車から駅へとわたる一瞬にうすきひかりとして雨は降る」
(薮内亮輔「花と雨」より)
「お互ひに聞かぬ言はぬの距離ながら白露の萩に解けてゐたり」
(中西敏子『呼子』より)
「「smileの綴りはスミレとおぼえてた」どうりでそんなふうに微笑む」
(西村曜『コンビニに生まれかわってしまっても』より)
「人はみな馴れぬ齢を生きているユリカモメ飛ぶまるき曇天」
(永田紅『日輪』より)
「つひにゆく道とはかねて聞きしかど昨日今日とは思はざりしを」
(在原業平『古今和歌集』巻16哀傷歌861より)
「五分ほど遅れてをれば駅ごとに日本の車掌は深く深く詫ぶ」
(齋藤寛『アルゴン』より)
「頭とは何ぞと問ふにジャコメッティ端的に応ふ胸の付け根」
(玉城徹『われら地上に』より)
「ふるさとはハッピーアイランドよどみなくイエルダろうか アカイナ マリデ」
(鈴木博太「ハッピーアイランド」『短歌研究』2012.09より)
「ふと思ふ我を見守るあたたかき心に気附かず過ぎしことあらむ」
(安立スハル『この梅生ずべし』より)
「人間はひとつの不潔なる川と靠(もた)るる窓に夕茜燃ゆ」
(阿木津英『天の鴉片』より)
「歌数首読みて心の静まれば銀のくさりを引きて灯を消す」
(田附昭二『造化』より)
「元気よくおりこうさんの返事するニュースの子ども 子どもは窮屈」
(細溝洋子『コントラバス』より)
「黙ることは騙すことではないのだと短い自分の影踏みながら」
(山本夏子「スモックの袖」/「現代短歌」2018年7月号より)
「白磁器にたまるうすら陽かなしがり方のしずかなひとに寄りゆく」
(中田明子「Ammonite」『砦』,2021.11より)
「モロヘイヤいくつあってもモロヘイヤこの夏幸せなモロヘイヤ」
(吉田奈津「短歌研究」2015年9月号より)
「水鳥のからだのなかに水平を保てる水のあり冬の空」
(永田和宏『日和』より)
「新しき黒もて黒を塗りつぶす分厚くわれの壁となるまで」
(大西民子『雲の地図』より)
「われはわれにてなお何ならむ焦がるれば夜の稲妻膝照らすなり」
(李正子『ナグネタリョン』より)
「海を過去、空をその他とおもひつつ海上飛べる鷗見てをり」
(原賀瓔子『星飼びと』より)
「地下のバー酔ひやすくして己が手に残る時間を人ら埋(う)もるる」
(篠弘『凱旋門』より)
「トンネルをいくつも抜けて会いにゆく何度も生まれ直して私は」
(藤田千鶴『貿易風(トレードウインド)』より)
「見せあうものは悲しみのたぐい黒衣きて雪野を遠く来る人に逢う」
(百々登美子『盲目木馬』より)
■第二章:新種三百人一首(+100首)
「ああ夕陽 明日のジョーの明日さえすでにはるけき昨日とならば」
(藤原龍一郎『夢見る頃を過ぎても』より)
「白き霧ながるる夜の草の園に自転車はほそきつばさ濡れたり」
(高野公彦『汽水の光』より)
「廃村を告げる活字に桃の皮ふれればにじみゆくばかり 来て」
(東直子『春原さんのリコーダー』より)
「照りかげる砂浜いそぐジャコメッティ針金の背すこしかがめて」
(加藤克巳『球体』より)
「道の端にヒールの修理待つあいだ宙ぶらりんのつまさきを持つ」
(沖ななも『衣裳哲学』より)
「蒼穹に重力あるを登攀のまつ逆さまに落ちゆくこころ」
(本多稜『蒼の重力』より)
「リバノールにじんだガーゼのようだから糸瓜の花をあなたの頬に」
(入谷いずみ『海の人形』より)
「落胆はうすかげの射す目に顕ちて煮くづれをして沈む大根」
(桝屋善成『声の伽藍』より)
「ゆふぞらにみづおとありしそののちの永きしづけさよゆうがほ咲(ひら)く」
(小島ゆかり『月光公園』より)
「水の面にはなびらはのりはなびらの運ばるるゆゑみづぞ流るる」
(喜多昭夫『夜店』より)
「風鈴を鳴らしつづける風鈴屋世界が海におおわれるまで」
(佐藤弓生『世界が海におおわれるまで』より)
「ビル抱く暗き淵よりせりあがり観覧車いま光都(くわうと)を領(し)れり」
(沢田英史『異客』より)
「たましいの年はいまだおさなくてふたり手をふる異国の船に」
(里見佳保『リカ先生の夏』より)
「胸もとに水の反照うけて立つきみの四囲より啓(ひら)かるる夏」
(横山未来子『樹下のひとりの眠りのために』より)
「雑然たる日々のすきまに見えきたる光の如く年を迎うる」
(高安国世『光の春』より)
「サンチョ・パンサ思ひつつ来て何かかなしサンチョ・パンサは降る花見上ぐ」
(成瀬有『遊べ、櫻の園へ』より)
「手でぴゃっぴゃっ/たましいに水かけてやって/「すずしい」とこえ出させてやりたい」
(今橋愛『O脚の膝』より)
「口が口を食ふかなしさよ丸干しのいわし食ひたりまづあたまから」
(大松達知『フリカティブ』より)
「髪の毛のかかる視界でこの町を見ていたのびていくあいだじゅう」
(本田瑞穂『すばらしい日々』より)
「剃刀をつつみながらにみづ流れちかくの苑にねむるくちなは」
(多田零『茉莉花のために』より)
「どんぶりに桜花(あうくわ)をもりて塩ふりぬ朝焼け激しき食卓なれば」
(仙波龍英『墓地裏の花屋』より)
「象さんの鼻となりたるわが弓手(ゆんで)背には殺意の馬(め)手遊ばする」
(内藤明『壺中の空』より)
「薄き血の色のマニュキュア愉しまん誰にも気付かれないそのことも」
(十谷あとり『ありふれた空』より)
「娘の肩の蝶結びほどけばぱたぱたと蝶は逃げゆき子と秋老いぬ」
(塩野朱夏『そして彼女は眼をひらいた』より)
「モルヒネに触れたる手紙読むときに窓の湛える水仙光よ」
(山下泉『光の引用』より)
「茹で加減よろしきパスタ半分こ模様のちがふ皿に移しぬ」
(高木孝『地下水脈』より)
「天地のちとおもしろきいそうろうとこの身思えば手足鮮し」
(鹿野氷『クロス』より)
「つり革にのぞく少女の切れかけた生命線が吸ふ晩夏光」
(日置俊次『ノートルダムの椅子』より)
「手の甲に試し塗りする口紅を白い二月の封緘として」
(兵庫ユカ『七月の心臓』より)
「留守番の妻の声聞くつまらなさ辻褄合わせのメッセージ入れる」
(小塩卓哉『樹皮』より)
「われのみが内臓をもつやましさは森の日暮れの生臭きまで」
(なみの亜子『鳴』より)
「日を葬(はふ)りざぶんと蒼きゆうぐれにこの世の橋が浮かびあがりぬ」
(白瀧まゆみ『自然体流行』より)
「休日の鉄棒に来て少年が尻上がりに世界に入って行けり」
(佐藤通雅『水の涯』より)
「駆けて逃げよわが血統は短距離馬かわされざまに詠むな過去形」
(小嵐九八郎『叙事がりらや小唄』より)
「空の樹の水の祈りを聴きとむるかなしみの瞳(め)のしづかなる耳」
(櫟原聰『光響』より)
「身のうちにみづかねといふ蝕あるを思ふゆふべの『テレーズ・ディケイルー』」
(有沢螢『朱を奪ふ』より)
「石段の段の高さに刻まれて降りてゆきたり手に抱え持ち」
(高橋みずほ『フルヘッヘンド』より)
「ぐじやぐじやの世界の上に日は照りて植物相(フロラ)は次なる時にそなふ」
(酒井佑子『矩形の空』より)
「右の手を夜にさし入れてひきいだすしたたる牡蠣のごとき時計を」
(鳴海宥『BARCAROLLE [舟唄]』より)
「真白の光を作るため青きセロファンを挿す この視界にも」
(中島裕介『Starving Stargazer』より)
「アボカドの種子に立てる刃 待つといふ時間はひとを透き通らせる」
(森井マスミ『ちろりに過ぐる』より)
「ししむらを借りてたましひ傷めるをさくらまばゆき闇に還さむ」
(関口ひろみ『あしたひらかむ』より)
「ゆふぐれの背にまたがりて駆けてゆくきのふの街に手をふりながら」
(鎌倉千和『ゆふぐれの背にまたがりて』より)
「おたがいの母語に訳して聴いてみるおのまとぺいあミュンヘンは雨」
(光森裕樹『鈴を産むひばり』より)
「影重く垂らしてきみに逢いにゆく花に牙ある夕暮れ時を」
(柳澤美晴『一匙の海』より)
「咲きみちて一枝の花も散らざれば手触れむほどに過ぎてゆく時」
(桜木由香『連祷』 より)
「羽ばたけるせつなひかりを零しけり天に属する若きかもめら」
(藤沢蛍『時間(クロノス)の矢に始まりはあるか』より)
「ゆふぐれの庭に佇つ犬尾を振れりわれに見えざるものに向ひて」
(徳高博子『ローリエの樹下に』より)
「少年はあをきサロンをたくしあげかち渡り行く日向(ひなた)の河を」
(前田透『漂流の季節』より)
「夕暮れが日暮れに変わる一瞬のあなたの薔薇色のあばら骨」
(堂園昌彦『やがて秋茄子へと到る』より)
「海沿いのちいさな町のミシン屋のシンガーミシンに砂ふりつもる」
(久野はすみ『シネマ・ルナティック』より)
「みぬちなる音盤(ディスク)は風にほどけゆき雪ふる空のあなたへ還る」
(紀水章生『風のむすびめ』より)
「あるときは斜めに生きておもしろし御笠の川みず浅く流れる」
(山中もとひ『〈理想語辞典〉』より)
「夏さびて知らぬふりする月の頃ピアスをもとな揺らす間夜(あひだよ)」
(廣庭由利子『ぬるく匂へる』より)
「秋はひとりまぶたをとじて耳を澄ます 雨のなかに隠した音楽」
(安井高志『サトゥルヌス菓子店』より)
「盆踊り同じ高さにそよぐ手の上(へ)をわたりゆく魂のあるべし」
(芹澤弘子『ハチドリの羽音』より)
「さるすべり炎天にひらく形にて暗くよぢれる臓物(わた)もつわれら」
(楠誓英『禽眼圖』より)
「はすかひに簷(のき)の花合歓(ねむ)うつしつつ化粧鏡は昏(く)れのこりたり」
(明石海人『明石海人歌集』より)
「星ひとつ滅びゆく音、プルタブをやさしく開けてくれる深爪」
(田丸まひる『ピース降る』より)
「約束はひとつもなくて日傘をささず帽子をかぶらずに行く炎天下」
(黒﨑聡美『つららと雉』より)
「みづの上(へ)に青鷺ひとつ歩めるを眼といふ水にうつすたまゆら」
(藪内亮輔『海蛇と珊瑚』より)
「ひと雨に花となりゆく六月の杳き眼をしたぼくのそれから」
(窪田政男『汀の時』より)
「失った時間をチャージするためにサービスエリアがあるたび止まる」
(九螺ささら『ゆめのほとり鳥』より)
「測量士冬に来たりかぎりなき雪上に紙上の文字を重ぬる」
(高石万千子『外側の声』より)
「花の名を封じ込めたるアドレスの@のみずたまり越ゆ」
(杉谷麻衣『青を泳ぐ。』より)
「人を待ち季節を待ちてわが住むは昼なお寂し駅舎ある町」
(阿部久美『ゆき、泥の舟にふる』より)
「大いなる今をゆっくり両肺に引き戻しつつのぼる坂道」
(五島諭『緑の祠』より)
「傘を盗まれても性善説信ず父親のような雨に打たれて」
(石井僚一「父親のような雨に打たれて」より)
「ピンホールカメラを覗くごと新国立美術館建つ夕暮れにうかびて」
(西五辻芳子『金魚歌へば』より)
「まぶしいものに近づいてみる近づいて舗道の上に柿はひしゃげる」
(阿波野巧也『ビギナーズラック』より)
「西の方角(かた)へ一滴ひかるあれは海掌(て)にひとかけらトパズのせゐて」
(浦上和子『根府川』より)
「目を閉じた人から順に夏になる光の中で君に出会った」
(木下侑介『君が走っていったんだろう』より)
「心とはそれより細きひかりなり柳がくれに流れにし蛍」
(増田まさ子、合同歌集『恋衣』より)
「さらさらとさみしき冬日 花の茎ゆはへて水にふかくふかく挿す」
(木下こう『体温と雨』より)
「出窓からこぼれるようにゆるやかに揺らめく冬の床の陽光」
(永井駿「迷信」『西瓜』第七号より)
「二塁手になるはずだったマスターがシェーカーを振る腕の残像」
(中井スピカ『ネクタリン』より)
「費やした年月だけがぼくならば ぶあついパンケーキを縦に裂く」
(からすまぁ「春風に備えて」より)
「白壁にあかく日の差す丁字路の突きあたりまであゆみつつをり」
(川本浩美『起伏と遠景』より)
「ドアを出づ、―― 秋風の街へ、 ぱつと開けたる巨人の口に飛び入るごとく。」
(土岐哀果『黄昏に』より)
「ぼくはぼくを生きるほかなく沸点を越えてゆらめく水を見つめる」
(西巻真『ダスビダーニャ』より)
「どこにでもある不安なりペンに書く文字をゆがめてブルーブラック」
(久我田鶴子『雀の帷子』より)
「今日の水は流れいるかと問う我に年々異なる者が答える」
(長谷川富市『水の容体』より)
「とりあへず「括弧」でくくりかなしみの方程式は解かずに置かう」
(豊島ゆきこ『りんご療法』より)
「身をひとつ左へゆるい坂道にめぐらせゆけばそこが海です」
(大久保春乃『まばたきのあわい』より)
「白き雲流れゆくなり 雲梯を這って渡ったこと一度ある」
(野田光介『半人半馬』より)
「ではなく雪は燃えるもの・ハッピー・バースデイ・あなたも傘も似たようなもの」
(瀬戸夏子『そのなかに心臓をつくって住みなさい』より)
「見ゆるもの見ゆるまま描け目から手はぢれったく月のごとく遠かり」
(笹谷潤子『夢宮』より)
「アラームの鳴る一分前に目覚めればその六十秒を抱きて眠る」
(和嶋勝利『天文航法』より)
「めだま焼き片目ながれて涙目の朝には軽い出社拒否症」
(大井学『サンクチュアリ』より)
「人を傷(いた)めぬよき子になれと中の子の広き額を撫でてをりたり」
(宮柊二『日本挽歌』より)
「真剣に聞くとき自分をぼくという君の背筋のあたたかい月」
(山内頌子『うさぎの鼻のようで抱きたい』よち)
「一斉にはばたく音に振り向けばいま満ちてゆく木蓮の花」
(樋口智子『幾つかは星』より)
「十代の自分を恋えりローリング・ストーンズ聞いて幸せだった」
(川本千栄『樹雨降る』より)
「新しく求めし傘がこの町に大きすぎたと思って歩く」
(吉村明美『HAFU』より)
「コロッケを肉屋に買ひて歩みつつ少年の日のよろこびを食ふ」
(柳宣宏『施無畏』より)
「うぬぼれていいよ わたしが踵までやわらかいのはあなたのためと」
(佐藤真由美『恋する歌音』より)
「一匹の孤狼であれば聴こえぬか風よ悲傷のマンドリンはや」
(福島泰樹『柘榴盃の歌』より)
「湯の中に塩振りながら ブロッコリーお前程いさぎよき緑になれたら」
(文屋亮『月ははるかな都』より)
「あせたる を ひと は よし とふ びんばくわ の ほとけ の くち は もゆ べき もの を」
(会津八一『鹿鳴集』より)
「燠のごときひかりと思うガラス戸に身をつけて見る闇の海の灯」
(武川忠一『秋照』より)
■第三章:新種四百人一首(+100首)
「いる筈のなきものたちを栗の木に呼びだして妹の意地っ張り」
(平井弘『顔をあげる』より)
「木曜の夕べわたしは倦怠を気根のように垂らしてやまず」
(早川志織『種の起源』より)
「形容詞過去形教へむとルーシーに「さびしかった」と二度言わせたり」
(大口玲子『海量(ハイリャン)』より)
「ポール・ニザンなんていうから笑われる娘のペディキュアはしろがねの星」
(小高賢『本所両国』より)
「酢のなかでゆっくりと死ぬ貝類の声聞く七月某日真昼」
(村上きわみ『fish』より)
「歳月は餐をつくして病むもののかたへに季節(とき)の花を置きたり」
(中山明『愛の挨拶』より)
「わたしたちはなんて遠くへきたのだろう四季の水辺に素足を浸し」
(佐藤りえ『フラジャイル』より)
「さまよえる夢のおわりを棄てるとき飛沫があがる砂嘴 (さし) の向こうに」
(小林久美子『恋愛譜』より)
「死者はうたふあかときの窓むらさきのそのむらさきの葡萄のしづく」
(寺井淳『聖なるものへ』より)
「罎の内側から見ると恋人は救世主(メシア)のやうに甘く爛れて」
(魚村晋太郎『銀耳』より)
「白壁の一本の罅たどりつついのちのやぶれ目を見てゐたる」
(林和清『木に縁りて魚を求めよ』より)
「昼つ方先祖の墓の苔むして瓶のなか万緑のみづ燃ゆ」
(田中富夫『曠野の柘榴』より)
「睾丸に似たる蘭の実脆ければスプーンで神を掬い難きか」
(菊池裕『アンダーグラウンド』より)
「ワン・タッチの傘をひろげてゆかむかな男の花道には遠けれど」
(吉岡生夫『勇怯篇 草食獣・そのIII』より)
「仄暗き骨のあいだを子は駆ける窓に桜の揺らす日を踏み」
(吉野亜矢『滴る木』より)
「きみの脚の骨をそろりと抜き取つてうすあおいろに染めたきゆふべ」
(大津仁昭『海を見にゆく』より)
「〈時〉翳る半球のかなた血のごとく鯉沈みゐる小さき国よ」
(米川千嘉子『一夏』より)
「暁(あけ) 死してねむるわが裡(うち)こうこつと霜ふれり霜ふりの牛肉(ビーフ)に」
(下村光男『少年伝』より)
「水鳥のつばさを奪ふ シャッターを切りて時空の網を放てり」
(目黒哲朗『CANNABIS』より)
「髣髴(ケシキ)顕(タ)つ。速吸(ハヤスヒ)の門(ト)の波の色。年の夜をすわる畳のうへに」
(釈迢空『海やまのあひだ』より)
「ずぶ濡れの俺の背中に夕星が輝くという嘘を悲しむ」
(吉田純『形状記憶ヤマトシダ類』より)
「とぶ鳥を視をれば不意に交じりあひわれらひとつの空のたそがれ」
(柏原千恵子『七曜』126号より)
「独房の闇なき夜の壁際に光源のごとカサブランカ咲く」
(重信房子『ジャスミンを銃口に』より)
「多武峰もみぢしづかに燃ゆるいろたまゆらあそべ父のいのち火」
(一ノ関忠人『群鳥』より)
「メスにより切り啓(ひら)かれた空間にきょうも漂う船は一艘」
(光栄堯夫『空景』より)
「廃されし管制塔まで書きに行き詩を放つとき世界は眠り」
(八木博信『フラミンゴ』より)
「ヤマト糊のたましひ失せて初恋の秘蔵写真が剥がれ落ちたり」
(小泉史昭『ミラクル・ボイス』より)
「ピカソ展見終えて濠に光あり静かに充ちてわが日々を撃て」
(大島史洋『時の雫』より)
「十指とふこの十全なかたちのゆゑにかなしみのくる秋の食卓」
(笹原玉子『われらみな神話の住人』より)
「文鳥の胸の真白をかきやれば暗紫(くらむらさき)の肉の色もつ」
(伊津野重美『紙ピアノ』より)
「くあとろとやわらかくなるキーボードぼくらの待っているのは津波」
(加藤治郎『ハレアカラ』より)
「腐りたるトマトを捨てし昨日のことふと思い出す地下鉄に乗り」
(吉野裕之『空間和音』より)
「今日よりは蝶の受胎の日に入りぬ寒青葱の水染む緑」
(佐竹彌生『天の螢』より)
「沈むとき上下にくらくゆれたりし飯の茶碗を思うときあり」
(上野久雄『夕鮎』より)
「腰のリボン蝶々結びにしてやれば夏の道へと攫われやすし」
(前田康子『色水』より)
「苦しみて花咲かすべし夕闇のなか垂直に木蓮光る」
(大谷雅彦『白き路』より)
「花々に/眼のある夜を晩年の/父あらはれて/川渉りゆく」
(辺見じゅん『闇の祝祭』より)
「わたくしの夕暮れてゆく街にある影といふ名の数多のimages(いまあじゆ)」
(中川宏子『いまあじゆ』より)
「あめつちはいちにんのため季(とき)を繋(と)めくろき扇に撒かれし雲母」
(須永朝彦『定本須永朝彦歌集』より)
「八月の雨てのひらに受けてゐる誰にも属してをらぬ冷たさ」
(黒田和美『六月挽歌』より)
「ブーストを立ち上がらせつつ走りゆく前にも後にも時間はなくて」
(永田淳『1/125秒』より)
「ああマトリョーシカ開ければ無上なる怖さ 人より出でてまた人となる」
(浦河奈々『マトリョーシカ』より)
「おごそかなダンスに雪は生まれおり輝きはあれ午後の世界に」
(田中濯『地球光』より)
「しろき円をたもちて皿は暮れなづみ卓は卓として四方へとがる」
(菊池孝彦『声霜』より)
「目をあけてみていたゆめに鳥の声流れこみ旅先のような朝」
(雪舟えま『たんぽるぽる』より)
「一滴の青を落としてわが画布にはばたく鳥の羽を弑(しい)する」
(寺島博子『王のテラス』より)
「あれは明日発つ鳥だろう 背をむけて異境の夕陽をついばんでいる」
(岩尾淳子『眠らない島』より)
「南北の極ありて東西の極なき星で煙草吸える少女の腋臭甘く」
(フラワーしげる「ビットとデシベル」より)
「驟雨ななめにまちを疾りて匂ひたつ魂ぞしとど〈歓喜(ジョイ)〉てふ」
(大和志保『アンスクリプシオン』より)
「姉であることを忘れるウエハースひとひら唇に運んでもらう間」
(天道なお『NR』より)
「箸茶碗こともなく持ち両の手の互に知らぬ左右の世界よ」
(照屋眞理子『恋』より)
「禽肉(とりにく)はすでに死屍たる冷(ひえ)持てばまばたきもせず銀の塩振る」
(山口雪香『白鳥姫』より)
「碧釉漣紋器(へきいうれんもんき) 青をたどればしづかなる縁の乱るるひとところあり」
(経塚朋子『カミツレを摘め』より)
「縦向きの見本見ながら横向きに落ちてくるのを待つ缶コーヒー」
(蒼井杏『瀬戸際レモン』より)
「歩道橋越えても踏切渡つてもだれかの家の前に行きつく」
(橋場悦子『静電気』より)
「もうここへやってきている夕映えの手首まで塗るハンドクリーム」
(笠木拓『はるかカーテンコールまで』より)
「透明になる過程が見たい紙一重というところが見たい」
(宮崎信義『地に長き』より)
「なだらかに底を見せたる泥の上を鷺は歩めり影揺らしつつ」
(西川啓子『ガラス越しの海』より)
「バス停がバスを迎えているような春の水辺に次、止まります」
(𠮷田恭大『光と私語』より)
「月までを数秒で行く君の名のひかりと呼べばはつ夏の空」
(五十子尚夏『The Moon Also Rises』より)
「本当に愛されてゐるかもしれず浅ければ夏の川輝けり」
(佐々木実之『日想』より)
「月草のうつろふ時間たぐり寄せたぐり寄せつつゆく京の町」
(黒田京子『揺籃歌』より)
「刻々と報道される事実より吾は信じる線路の勾配」
(勺禰子『月に射されたままのからだで』より)
「親指はかすかにしずみ月面を拓くここちで梨を剥く夜」
(國森晴野『いちまいの羊歯』より)
「日の落ちてわづかに残すあかねいろの千切れ雲見ゆ旅の車窓に」
(服部崇『ドードー鳥の骨』より)
「火の粉ふり払う消防夫の如く螢の夜から出でし少年」
(中山俊一『水銀飛行』より)
「生と死を量る二つの手のひらに同じ白さで雪は降りくる」
(中畑智江『同じ白さで雪は降りくる』より)
「目覚むればこの世の果てより曳ききたる光はよわく落花にのこる」
(三島麻亜子『水庭』より)
「天降(あも)りくる光の無量か載りてゐむ天秤かたむくガラス戸の内」
(永守恭子『夏の沼』より)
「開けっ放しのペットボトルを投げ渡し飛び散れたてがみのように水たち」
(近江瞬『飛び散れ、水たち』より)
「ここはしづかな夏の外側てのひらに小鳥をのせるやうな頬杖」
(荻原裕幸『リリカル・アンドロイド』より)
「水たまりに光はたまり信号の点滅の青それからの赤」
(宇都宮敦『ピクニック』より)
「琥珀色の宝石みたいな水ぶくれ 七回撫でたらちょっとだけ秋」
(上坂あゆ美『老人ホームで死ぬほどモテたい』より)
「ありうべき光をさがす放課後のあなたはたぶん詩の書架にいる」
(塩見佯「図書館の午後」『西瓜』第八号より)
「細やかに組み立てられたランドリーラックを壊す夏のゆふぐれ」
(岡本恵「結束」『西瓜』第六号より)
「透き至るものの綺麗さはなちつゝ立つ空き瓶のゆふぐれは あき」
(川﨑あんな『triste』より)
「ひそやかに語る女生徒ふたりいて渡り廊下は校舎の咽喉(のみど)」
(山田恵理『秋の助動詞』より)
「リヤドロの陶器人形たおやかに諫死しており書架のくらみに」
(吉村実紀恵『バベル』より)
「立つわたし、いきなり語り出すわたし ウラル=アルタイ語圏のわたし」
(田中槐『ギャザー』より)
「ふららこという語を知りてふららこを親しく漕げば春の夕暮」
(大下一真『月食』より)
「最後まで話さなくていいカーテンに染みこませておく君の悩みは」
(野村まさこ『夜のおはよう』より)
「あと何を買ったら僕の人生は面白くなり始めるのかな」
(辻井竜一『遊泳前夜の歌』より)
「救ひなき裸木と雪の景果てし地点よりわれは歩みゆくべし」
(中城ふみ子『乳房喪失』より)
「人として生れたる偶然を思ひをり青竹そよぎゐる碧き空」
(志垣澄幸『日月集』より)
「ひとり酌む新年の酒みづからに御慶(ぎよけい)を申す(すこしは休め)」
(岡井隆『神の仕事場』より)
「やさやと生存圏を拡げつつ浮かぶや宙に愛のピカチュウ」
(上條素山「外大短歌第7号」より)
「空の海にさらはれたりや飛行船 五月の空は底なしの青」
(竹内由枝『桃の坂』より)
「ああ、博士 まるでひとりの島みたいどこまでも心が浜になる」
(瀬口真司「天使給電篇」『いちばん有名な夜の想像にそなえて』)
「『「いい人」をやめると楽になる』…本を戻して書店を出づる」
(平林静代『雨水の橋』より)
「地湧の菩薩として僧俗和合で〔魔の所為〕を砕滅する」
(森山光章『句集〔法華折伏破権門理〕、喜悦のみがある』より)
「霞立つながき春日に子供らと手毬つきつつこの日暮らしつ」
(良寛『良寛歌集』より)
「ねむりつく方法みつけられなくてあるだけ莢の豆はじきだす」
(青柳守音『風ノカミ』より)
「花束を買ふよろこびに引きかえて渡す紙幣はわづかに二枚」
(北沢郁子『夢違』より)
「一年に十分の時を先に行く居間の時計にわれの従ふ」
(吉田直久『縄文の歌人』より)
「後ろより誰か来て背にやはらかき掌を置くやうな春となりゐつ」
(稲葉京子『宴』より)
「キッチンは逆立ちしてもいいところ君もケチャップ我もケチャップ」
(大谷ゆかり『ホライズン』より)
「パブロ・ピカソさんらんとして地に死ぬをありあけの馬は見て忘れけむ」
(坂井修一『群青層』より)
「桑の實數千(すせん)熟れつつ腐るすでにして踰(こ)ゆべき海も主(しゆ)もわれになし」
(塘健『出藍』より)
「口紅と座薬とジャムと練りからし冷ゆる冷蔵庫夏過ぎてより」
(浜名理香『風の小走り』より)
「石(いは)ばしる垂水(たるみ)の上のさわらびの萌(も)え出づる春になりにけるかも」
(志貴皇子『万葉集』巻8・1418より)
■第四章:新種五百人一首(+100首)
「あなたとは遠くの場所を指す言葉ゆうぐれ赤い鳥居を渡る」
(松村正直『駅へ』より)
「昏れゆく市街(まち)に鷹を放たば紅玉の夜の果てまで水脈(みを)たちのぼれ」
(山尾悠子『角砂糖の日』より)
「夕雲は蛇行しており原子炉技師ワレリー・ホムデチェック遺体無し」
(吉川宏志『夜光』より)
「瘡蓋(かさぶた)のごとく凍土に生きながらわれはたつとぶモハメッド・アリ」
(時田則雄『北方論』より)
「夕ぞらへざくろの花は朱を献ず梅雨神(つゆがみ)のためわが生(いき)のため」
(雨宮雅子『悲神』より)
「烏羽玉の音盤(ディスク)めぐれりひと無きのちわれも大鴉を飼へるひとりか」
(大塚寅彦『刺青天使』より)
「撃ち堕とすべきもろもろを見据ゑつつ今朝くれなゐの橋をわたらな」
(高島裕『旧制度(アンシャン・レジーム)』より)
「ペリカンの死を見届ける予感して水禽園にひとり来ていつ」
(生沼義朗『水は襤褸に』より)
「花びらを掬ふてのひら染み透る面影はまだ指のあひだに」
(尾崎まゆみ『酸つぱい月』より)
「たましいを預けるように梨を置く冷蔵庫あさく闇をふふみて」
(島田幸典 『no news』より)
「我にまだ父ありたりし昨夜(きぞ)の皿デリシャスの果(み)は透きとおりたり」
(佐伯裕子『未完の手紙』より)
「なんどでもひかりはうまれもういちど春の横断歩道で出会う」
(伴風花『イチゴフェア』より)
「人はかく大人にならむ はにかみて「Bonjour」と言ふ時期のみじかさ」
(小川真理子『母音梯形(トゥラペーズ)』より)
「海風は君がからだに吹き入りぬこの夜抱かばいかに涼しき」
(吉井勇『酒ほがひ』より)
「したたれる蒼さするどさ受けながら身はつくねんと秋空に向く」
(入野早代子『散華』より)
「七月は漂う 僕から逃げようとする僕の影をまたつかまえて」
(千葉聡『そこにある光と傷と忘れもの』より
「古き井戸に一匹の鯉棲むと言へど見しことはなしその酷(むご)き緋を」
(真鍋美恵子『蜜糖』より)
「象のかたちに象押し上ぐるしらほねの軋みおりたり雲あつき下」
(中津昌子『遊園』より)
「この道のゆるやかな勾配気づく夜は花屋で一人 COSMOS を買う」
(大野道夫『秋階段』より)
「「現象」に創りだされた「考え」が「現象」のことを考えている」
(小笠原魔土『真夜中の鏡像』より)
「魚を呑みのみていのちの深まれる黒鵜の胸が闇を動かしむ」
(松平盟子『青夜』より)
「尖塔の建てられてよりこの街の空は果てなき広さとなりぬ」
(香川ヒサ『PAN』より)
「薄明に水分多きかたまりとなるわがからだ転がしておく」
(江戸雪『百合オイル』より)
「みつばちが君の肉体を飛ぶような半音階を上がるくちづけ」
(梅内美華子『若月祭』より)
「真より偽へブール変数ひるがへすただ一行をつかまへかねつ」
(吉浦玲子『精霊とんぼ』より)
「母という永遠の謎ふくふくと空豆を煮てわれを待ちおり」
(後藤由紀恵『冷えゆく耳』より)
「さんさんと夜の海に降る雪見れば雪はわたつみの暗さを知らず」
(山田富士郎『アビー・ロードを夢みて』より)
「たこ焼きのたこを楊枝にいらいつつ薄い利益にわれはも泣かゆ」
(勝野かおり『Br』より)
「ひと息にキリマンジャロを飲みいるは先ほどはつか怒りし咽喉(のみど)」
(中川佐和子『海に向く椅子』より)
「どうしても現象(フェノメノン)に目がゆきさうだ枇杷がゆさゆさ陽を孕むだから」
(酒向明美『ヘスティアの辺で』より)
「さりげなくさしだされているレストランのグラスが変に美しい朝」
(早坂類『風の吹く日にベランダにいる』より)
「タルト生地まだ熱すぎる黒すぐり載せる前にまたイラクの死者達」
(三井修『軌跡』より)
「この世には善はないって言い切ったきみの口からこぼれるアイス」
(本多忠義『禁忌色』より)
「蒼蒼と瞠(みひら)くまなこ森のうへに降る点ありてこゑを放たず」
(都築直子『青層圏』より)
「「ひかりは森をなしつつ滅ぶ」窓際に置かれしものは冬の鉄球」
(岩田眞光『百合懐胎』より)
「一掬(イツキク)の記憶を愛す。忘却は祝(ほ)ぐべき人間(ひと)の習慣(ならひ)なれども」
(石井辰彦『全人類が老いた夜』より)
「ジャム瓶の口に凭るるスプーンの細長き柄の先端五月」
(奥田亡羊『亡羊』より)
「珈琲にミルク注ぎて「毎日がモカとキリマンジャロのほどの差ね」」
(西田政史『ストロベリー・カレンダー』より)
「われをめがけ降る雪のあれ たれのたれの脚注でもなき道をゆくとき」
(松本典子『いびつな果実』より)
「黒揚羽頭(づ)を越えゆきぬ 心音とふ羽音ひびかせ地にわれは生く」
(柚木圭也『心音[ノイズ]』より)
「エル・グレコの〈ピエタ〉のイエスは晩年のプレスリーに似ると我に教えき
(王紅花『夏の終りの』より)
「金柑は小鳥のために捥がずにおく ひよどり、君は遠慮せよ」
(藤島秀憲『二丁目通信』より)
「聖典を我は持たねば菊花茶をまるき茶碗にひらきゆくのみ」
(齋藤芳生『桃花水を待つ』より)
「人々の嘆きみちみつるみちのくを心してゆけ桜前線」
(長谷川櫂『震災歌集』より)
「近代を希望のごとく抱きとめて舵手は深みに沈む何度も」
(佐久間章孔『声だけがのこる』 より)
「行きちがふ電車の窓を幻のごとく透かして照る街衢(がいく)見ゆ」
(尾崎左永子『鎌倉もだぁん』より)
「ひとはなお天花を待てり果てのある塔を昇降機に運ばれて」
(屋良健一郎『本郷短歌』創刊号より)
「忘れずにいることだけを過去と呼ぶコットンに瓶の口を押しあて」
(大森静佳『てのひらを燃やす』より)
「模型飛行機のやはやはとした羽根ごしにたわむ世界はみどりを帯びて」
(秋月祐一『迷子のカピバラ』 より)
「デニーズをひとつ過ぎれば夕暮れのすべての海は死者たちのもの」
(斎藤真伸『クラウン伍長』より)
「光にも質量があり一輪車ゆっくりあなたの方へ倒れる」
(服部真里子『行け広野へと』より)
「いつかまた還す日が来るからだへと黒糖入りのソイ・ミルクティー」
(天野慶『つぎの物語がはじまるまで』より)
「ひかりながらこれが、さいごの水門のはずだと さようならまっ白な水門」
(井上法子『永遠でないほうの火』より)
「紅鶴(フラミンゴ)の桃色の脚 生くなればやすらはざれば地にそよぎたり」
(今川美幸『雁渡りゆき』より)
「死に急ぐ者にはあらぬわが影をふたたび蝶のよぎる突堤」
(富田豊子『漂鳥』より)
「坂道の続くゆふぐれ死んでゐる魚を提げて女歩めり」
(松本実穂『黒い光 2015年パリ同時多発テロ事件・その後』より)
「綿飴かい うんにや、ひとだま 石垣をふはり越ゆるはほんに美味さう」
(小黒世茂『雨たたす村落』より)
「「神の救ひ」見えぬ誰かに説く横で少年の送球宙繋ぎたり」
(木ノ下葉子『陸離たる空』より)
「をはりゆく恋などありて春寒の銀のボウルに水をゆらせり」
(田口綾子『かざぐるま』より)
「故郷を離れし人と失くしたる人のにほひの混ざり合ふ街」
(江國梓『桜の庭に猫をあつめて』より)
「もう戻りこぬ時惜しむこともなく子は水色のランドセル選ぶ」
(鶴田伊津『夜のボート』より)
「午後ずっと猫がふざけて引きずった魚のまなこが見上げる世界」
(ユキノ進『冒険者たち』より)
「地図に散る島のかたちのそれぞれに夜明け飲み干す水の直立」
(大室ゆらぎ『夏野』より)
「眉の無い男の背の磔刑図を背景として羽斑蚊(ハマダラカ)飛ぶ」
(松岡秀明『病室のマトリョーシカ』より)
「夕暮れの商店街にまぎれたし赤きひれ持つ金魚となりて」
(佐藤モニカ『夏の領域』より)
「きらめいて墜ちゆく血のとりたちの残したうたで開く 夏」
(筒井富栄『未明の町』より)
「夏木立新緑の樹のたまきはるいのち濡れをり村雨の後」
(藤田喜久子『青い仮象』より)
「これの世に咲き残れるもあはれにて祈りのやうに秋薔薇剪りぬ」
(安田百合絵「風景のエスキース」『本郷短歌』vol. 3より)
「にりん草いずれか先に散りゆきて残れる花に夕日ただよう」
(宇佐美ゆくえ『夷隅川』より)
「眼とふ裸火ふたつかかげゆき炎昼はわが灼くべき羅馬」
(川野芽生『Lilith』より)
「肉裂きて熟るる石榴よ優しくもわれを許すなにじり寄る父」
(新城貞夫『新城貞夫全歌集』より)
「ある覚悟静かに示すヘルメット血液型を大きく書いて」
(奥村知世『工場』より)
「風呂場の髪の毛さえも愛しいよ編んで月光を捕まえに行く」
(手塚美楽『ロマンチック・ラブ・イデオロギー』より)
「罫線を無視したくなるときもあり少し外れてゆく通学路」
(小金森まき「ライン」『西瓜』第八号より)
「天と地のあわいに揺れて揺れながら扉を開く短夜がある」
(優木ごまヲ「寄港地」『西瓜』第九号より)
「鼻煙壺(びえんこ)に悲しき魚は泳ぎゐて鳥より先に離りゆくらしも」
(山科真白『鏡像』より)
「ホームページ・ミクシィ・ツイッター・ズームなど渡り来し我は歌人うたびとである」
(奥村晃作『蜘蛛の歌』より)
「観覧車回れよ回れ想ひ出は君には一日(ひとひ)我には一生(ひとよ)」
(栗木京子『水惑星』より)
「人恋ふにあらねきさらぎ雪積めばさ夜更けてひかりいづるわが髪」
(黒木三千代『貴妃の脂』より)
「カナリヤの囀り高し鳥彼れも人わが如く晴を喜ぶ」
(正岡子規『竹の里歌』より)
「ミュージカルについてあまり悪く言わなかったことが結果的にプラスに働いた」
(佐クマサトシ「ゲームみたいで楽しい」(Website「TOM」より))
「いのちあるすべてのものを同胞としたり若冲、ダ・ヴィンチもまた」
(田村よしてる『いとしきもの』より)
「牛乳が切れたら次の牛乳をあぶない橋をわたるみたいに」
(山中千瀬『さよならうどん博士』より)
「朝くらき花屋の土間に包まれて仮死せるごとき白百合の束」
(さいとうなおこ『キンポウゲ通信』より)
「幸せだ!バスが涼しい!幸せだ!バスが涼しい!バスが涼しい!」
(逢坂みずき『虹を見つける達人』より)
「自転車の高さからしかわからないそんな景色が確かにあって」
(加藤千恵『ハッピー☆アイスクリーム』より)
「どのレジに並ぼうかいいえ眠りに落ちるのは順番にではない」
(斉藤斎藤『人の道、死ぬと町』より)
「潮のおと耳より心に入れながら脱にんげんの一瞬もある」
(伊藤一彦『言霊の風』より)
「憧れは哀しからずや病窓に 果実に飽きしみどりごのあり」
(中島らも『今夜すべてのバーで』より)
「全身にゆきのにほひをまとひたるこどもがをりぬ。ほら、わたくしが。」
(小島熱子『りんご1/2個』より)
「すくすくと生ひたつ麦に腹すりて燕飛びくる春の山はた」
(橘曙覧『橘曙覧全歌集』より)
「ゆつくりと二人でのぼる長谷寺の石段一つひとつ大切」
(大寺龍雄『草の火』より)
「眠りより身を引き抜いてけさ過ぎし雨に濡れたる芝を踏みたり」
(大辻隆弘『汀暮抄』より)
「見ていたら夜が終わるのではなくて朝が始まるのだとわかった」
(谷じゃこ『ヒット・エンド・パレード』より)
「さかみちを全速力でかけおりてうちについたら幕府をひらく」
(望月裕二郎『ひらく』より)
「伊香保ろの八尺(やさか)の堰塞(ゐで)に立つ虹(ぬじ)の顕ろまでもさ寝をさ寝てば」
(作者不詳『万葉集』東歌・巻14・3414より)
「濁流だ濁流だと叫び流れゆく末は泥土か夜明けか知らぬ」
(斎藤史『魚歌』より)
「暁(あけ)までをひとり起きゐてかく道に佇む幾度 生は闌(た)けつつ」
(森山晴美『グレコの唄』より)
「田に降りてまだ静まらぬ鶴(たづ)むらの白きゆらぎの中に踏み入る」
(岡野弘彦『天の鶴群』より)
「春の雨降りやむまでを電話のない電話ボックスの中で待ってる」
(郡司和斗『遠い感』より)
■第五章:新種六百人一首(+100首)
「絆創膏二つ貼りいる左手の指より初夏の朝が始まる」
(田中拓也『雲鳥』より)
「真直なる生は誰にもあらぬもの雪原を行きし人の足跡」
(柏崎驍二『北窓集』より)
「割れ落ちたフロントガラスの隙間から流れ出てゆくほそながき猫」
(佐佐木定綱『月を食う』より)
「雪底に押しつぶされし根の怒りある朝噴きて水仙となる」
(日高堯子『野の扉』より)
「あまだむ軽きジャンプの終るまで地球の自転やや遅くなる」
(山吹明日香『風返し峠』より)
「歯車の無数なる歯が噛み合ひしまま静止せる闇夜とおもふ」
(真鍋美恵子『玻璃』より)
「エントランス前で雪かきする人がはげしき息の挨拶をせり」
(紺野裕子『硝子のむかう』より)
「昼のバス閑散として黒人の運転手軽やかに聖歌を歌ひ出づ」
(秋山佐和子『空に響る樹々』より)
「十四インチ望遠鏡のレンズいつぱいに這入つて来た巨大な月!」
(前田夕暮『水源地帯』より)
「切除されし妻の乳房は黒々と小さくなりて盤(さら)に置かれつ」
(清水房雄『一去集』より)
「地の上に立ちてほのぼの空仰ぐ人間というかたちに生きて」
(川端弘『白と緑』より)
「折る膝のなければ敗れし軍鶏はからだごと地へ倒れてゆけり」
(田村広志『旅の方位図』より)
「歩みきて去年の団栗拾ひたりわづか濡れたる土の上より」
(大河原惇行『昼の花火』より)
「塀の上を過ぎゆく猫に見られつつストッキングに片足とほす」
(高田流子『猫町』より)
「舟屋ってけっこう広いTシャツとカマスの干物が二月に吹かれ」
(高田ほのか『短歌往来』4月号 第31号第4巻より)
「四月七日午後の日広くまぶしかりゆれゆく如しゆれ来る如し」
(窪田空穂『清明の節』より)
「すずやかな空の青さで顔を洗う心地のあした七月となる」
(五十嵐きよみ『港のヨーコを探していない』より)
「靴下は穿くためにある――十二月二十四日の母の口癖」
(大村陽子『砂がこぼれて』より)
「電話中につめを切ってる 届くかな 届け わたしのつめを切る音」
(初谷むい『花は泡、そこにいたって会いたいよ』より)
「あるときは泣きたきほどに百合蕊の粉に塗れて戻る道なり」
(河野泰子『春の扉』より)
「房に入り我れの虜のこおろぎよ澄みたる音色さむざむとして」
(郷隼人『LONESOME隼人』より)
「ダライ・ラマ帰るなき夏の宮殿に咲き盛る僧衣に似たる緋の花」
(五十嵐順子『Rain tree』より)
「母たちは乳母車より手を放すセガンティーニの絵に見入るとき」
(小林幹也『探花』より)
「野の上の風に吹かるる青菜あり青菜は常にあたらしく見ゆ」
(土屋文明『青南集』より)
「指しゃぶりやめない吾子のつむじからふっくら土と雨と春の香」
(塚田千束『アスパラと潮騒』より)
「なんの花か知らずにあなたが買ってきた火花をときどき散らすその花」
(堀静香『みじかい曲』より)
「さかんなる火事に見ほるるわが顔を夢にみてをり何燃えてゐむ」
(小谷陽子より)
「いつのとき遂げんひそかなる冬の旅花しげき三椏を幻として」
(竹内邦雄『幻としてわが冬の旅』より)
「ささやかな歌創るより忙しき一記者のわれに没頭せむとす」
(小名木綱夫『太鼓』より)
「父なくば育たぬ種など滅ぶべし月下を豹の母と子はゆく」
(小関祐子『Sein(ザイン)』より)
「くちなはの水を切りゆくすばやさをちらと見しより心やぶれぬ」
(金子薫園『覚めたる歌』より)
「鳩の咽喉腫れしゆうべは西空の奥ふかくあかあかとにじむ夕映え」
(赤座憲久『罪の轍』より)
「梨の実は固きままにて熟しゆく花びら落ちし日の清しさに」
(野上晴子・合同歌集『雲』より)
「おほかたの秋くるからにわが身こそかなしき物と思ひ知りぬれ」
(よみ人しらず『古今集』より)
「君がため 惜しからざりし 命さへ 長くもがなと 思ひけるかな」
(藤原義孝「小倉百人一首」50番より)
「数ふれば二万五千日を越えてをり君にわかれしそのかの日より」
(山川京子「桃の会だより」15号より)
「白玉の美蕃登(みほと)をもちて少女子(をとめご)は夜咲く花の嘆きするらむ」
(三浦義一『悲天』より)
「瓢箪の鉢植ゑを売る店先に軽風立てば瓢箪揺れる」
(公田耕一「朝日新聞」2009年9月7日より)
「みじかびのきゃぷりきとればすぎちょびれかきすらすらのはっぱふみふみ」
(大橋巨泉/CM短歌より)
「群雀ねぐらあらそふ竹村のおくまであかく夕日さすなり」
(大正天皇『おほみやびうた』より)
「夕かげる桜木のもとわが想ふひとりのために花よやすらへ」
(鈴木正博『海山の羇旅』より)
「おぼろなる月もほのかに雲かすみ晴れてゆくへの西の山のは」
(武田勝頼/辞世の句より)
「バスのドア開かるるたびにわが足に冬の日が差す心渇きて」
(黒田淑子『丘の外燈』より)
「薄れゆく記憶のひとつ 雨の日は算盤の玉が重かつたこと」
(大崎瀬都『メロンパン』より)
「銀のビーズつなぎてゐたる雪の夜の初潮のごとく死はふいにくる」
(岡部由紀子『父の独楽』より)
「頭ぶつけ胃はおどるとも砂漠ゆくバスはうしろがいちばん落ちつく」
(和田沙都子『月と水差し』より)
「たよりなく白いお前が本当に褐色のあの蝉になるのか」
(荒木る美『茎を抱く』より)
「ひとりゐて魚焼きをれば魚の眼の爆ぜてこぼれぬしづかなる日よ」
(三國玲子『空を指す枝』より)
「大口を開けて己の重たさにうなかぶすダツラの煙雨にそぼつ」
(楠田立身『白雁』より)
「一人(ひとり)の子を呼ぶとてけさも五人(いつたり)のみなの名を呼び子にはやされぬ」
(中河幹子『女流十人集』中河與一編より)
「艦砲射撃坪九百発の読谷村(よみたんそん)ハイビスカスは芯立てて咲く」
(奥原宗一『幾山河』より)
「たなぞこの上にのせたる見もあかぬ金剛石よ国の気は寄る」
(高田浪吉『高草』より)
「声なきは静かな脅威蟻の群れにじつとりと昼を囲まれてゐる」
(川瀬千枝『山上の海』より)
「かへりみてあやまちなしと誰が言はむ人と物との歪みしげき世に」
(山本雄一『うたびとⅠ 森山晴美集2』より)
「貴人(あでびと)は誰よりうけし勢力(いきほひ)ぞわれに詩あり神の授けし」
(服部躬治『迦具土』より)
「この国に愛されたいと書店にて詩集一冊もとめていたり」
(鑓水青子「真冬ロシア」「短歌人」2018年7月号より)
「満月がぐぐつと空より迫りきて猫の目らんらん輝きはじむ」
(鈴木良明『光陰』より)
「円周に(指は潰れてしまったが)穴あけ回転木馬を降りる」
(吉岡太朗「町」創刊号より)
「泣きに来た少年のためひめじをん群咲くなかのベンチを譲る」
(黒沢忍『遠』より)
「昨日の敵は今日も敵にて慇懃に「ごきげんよう」と言いて別れ来」
(久々湊盈子『風羅集』より)
「契りきな かたみに袖を しぼりつつ 末の松山 波越さじとは」
(清原元輔「小倉百人一首」42番より)
「交番の裏窓に見ゆる食器洗剤の黄色の液は残り少なし」
(髙栁サダヱ『狐日和』より)
「深山木(みやまぎ)のその梢とも見えざりし桜は花にあらはれにけり」
(源頼政『詞花和歌集』より)
「ソヴェートの韻律はかくも新しくわれらのクラスに没日(いりひ)反射す」
(山田あき『紺』より)
「西日カッと部屋にさしこみあらあらと一枚の壁起ちあがる」
(山崎孝『やどかり』より)
「ねこバスが迎えに来ぬかと大きめの傘さして待つ雨のバス停」
(蔵本瑞恵『風を剖く』より)
「まだ人のかたちをせるよ夜の駅の大き鏡の前よぎりゆく」
(安田純生『でで虫の歌』より)
「初心者の衒(てらい)にあらむこそこそとメガネのレンズふく昼さがり」
(晋樹隆彦『秘鑰(ひやく)』より)
「ついさっき裸の馬が駆け抜けたそんな二月の午前五時半」
(坪内稔典『雲の寄る日』より)
「母逝きしのちの五月もアマゾンの母の日ギフトの案内は来ぬ」
(畑中秀一『靴紐の蝶』より)
「青年死して七月かがやけり軍靴の中の汝が運動靴」
(安藤正「國學院大學内立て看板」より)
「舞い上がるぺらぺらな紙このままで十三月の空に死にたし」
(吉田千枝子『十三月の空』より)
「風鈴の音の通りたるみずいろの穴見ゆ闇のところどころに」
(広坂早苗『夏暁』より)
「生ひ出てそこを動かぬ木草らのもの思ふ日暮れ白き十薬」
(米田律子『滴壷』より)
「たけだけしき酢葉に種子の実りたりアメリカ種らしきがただにうとましく」
(小見山輝『寄物六百歌』より)
「言い訳はしないましてやきみのせいにしないわたしが行く場所のこと」
(谷村はるか『ドームの骨の隙間の空に』より)
「アイスクリーム君が食べしと死の四日前に記せり読むたびに泣く」
(草田照子『聖なる時間』より)
「学生帽目深くつけて歩(あり)くとき樹木のごとき思ひぞ我ら」
(杉山隆『人間は秋に生まれた』より)
「キリストに臍あることのかなしみにつながっている夜の水道」
(山下一路『スーパーアメフラシ』より)
「われはいま静かなる沼きさらぎの星のひかりを吉野へひきて」
(前登志夫『野生の聲』より)
「冬山の遠き木靈にのどそらせ臟腑枯らして吠ゆる犬あり」
(多田智滿子『遊星の人』より)
「コピー機の足りない色に紫陽花はかすんでここに海があったの?」
(吉田竜宇「pure bomb」京大短歌17号より)
「心強く生きがたきかな晩夏光輝く茄子の畑にゐたり」
(板宮清治『麦の花』より)
「終夜業とどろく露天の工場に立ちつつ思ふ突撃のさまを」
(相澤正『相澤正歌集』より)
「灰色の空に黙(もだ)せるNIKORAIの黒き円屋根(まろやね)われも黙せる」
(与謝野鉄幹『相聞』より)
「驟雨に濡れし鉄骨の乾く時われは感情の処理にとまどふ」
(眞鍋美恵子『朱夏』より)
「熱を病むわが子の脈をさぐりつゝ窓ごしに見る日まはりの花」
(相馬御風『御風歌集』より)
「悲し小禽つぐみがとはに閉ぢし眼に天のさ霧は触れむとすらむ」
(新井洸『微明』より)
「かくとだに えやは息吹の さしも草 さしもしらじら 燃る想いを」
(藤原実方「小倉百人一首」51番より)
「ちと一本拝借するぜ蕗の葉を傘に旦那は雨の花街」
(八木幹夫『青き返信』より)
「たれこめて春の行方も知らぬ間に待ちし桜もうつろひにけり」
(藤原因香『古今和歌集』巻第二春歌下80より)
「おたまじやくし小さき手足生えそめて天地に梅雨のけはひただよふ」
(出口王仁三郎『王仁三郎歌集』より)
「み吉野の 象山(きさやま)の際(ま)の木末(こぬれ)には、ここだもさわく 鳥の声かも」
(山部赤人『万葉集』巻6・924より)
「もの言へば 泣けくるものを。通夜ふけて、親しき友の また一人着(ツ)く」
(穂積忠『叢』より)
「秋たけし獄舎はかなし夜ごと夜ごと/鈴虫の音の/細ぼそり行く」
(金子文子『金子文子歌集』より)
「曇るとも何かうらみん月こよひ はれを待つべき身にしあらねば」
(山縣大弐/江宮隆之『明治維新を創った男』より)
「南(みんなみ)の阿波岐(あはき)の浜に我在りて想ふ事なし年暮れにけり」
(檀一雄『檀一雄歌集』より)
「病院のゆかに眠れずをりをりに覗く夫も眼あけゐし」
(佐藤志満『立秋』より)
「地球ごと電源が落ち液晶といふ液晶が鏡に変はる」
(結樹双葉「早稲田短歌43号」より)
「みちのべに埃(ほこり)をあびてしげる草秋は穂に出(で)て名はあるものを」
(岡麓『庭苔』より)
■第六章:新種七百人一首(+100首)
「抑留に働きし炭鉱のブカチャチャ炭弟が輸入せるとふ奇跡」
(大建雄志郎『風の回廊』より)
「せとものゝひゞわれのごとくほそえだは淋しく白きそらをわかちぬ」
(宮澤賢治「歌稿A」より)
「人間が行方絶ちしを蒸発と湯気のごとくに言ひし日のあり」
(江田浩之『夕照』より)
「一つ二つ小石にまじる青蜆萌えいづる春の色にもあるかな」
(若山喜志子『女流十人集』中河與一編より)
「一秒後には冷えにけりさわらびのぼくと天使とぼくのスラング」
(加部洋祐『亞天使』より)
「仕事場の/小さい窓から覗かれる/灰色の空が自分の心だ」
(渡辺順三『貧乏の歌』より)
「放物線を描いて谷に落ちゆくは鳥?否、礫?否、ひとつやくそく」
(桂保子『天空の地図』より)
「妬心を鎮めゐたれば家並より炬火(きよくわ)のやうなる月のぼりくる」
(米口實『ソシュールの春』より)
「夕暮れの書店に集ひ一冊の本選ることに安らぐ者ら」
(柴田典昭『樹下逍遙』より)
「わたしにもやさしい背中があったよね ランプのような猫の背をみる」
(大森千里『光るグリッド』より)
「電車でも眠ってともだちの部屋でも眠ってなんのために行ったのか」
(平岡あみ『ともだちは実はひとりだけなんです』より)
「身の中にマブチモーターを仕込んでるとしか思えぬ奴の素振りだ」
(しんくわ「卓球短歌カットマン」より)
「派や系でくくって話す 単純化した部分だけ伝えるために」
(牧野芝草『整流』より)
「神経のいちにち分のゼンマイが一気に解き放たれてめまひす」
(齋藤佐知子『帰雲』より)
「すべり落つるその瞬間に白き皿は思ひ出だせり鳥なりしこと」
(福井和子『花虻』より)
「ニュートリノ奔る気ままさもて晩夏全身を貫いて去れる喩」
(楠見朋彦『神庭の瀧』より)
「マシーンの赤きが光引きてゆく地上を愛すこの一瞬を」
(藤井常世『鳥打帽子』より)
「にがき夏まためぐり来て風が揉む無花果に不安な青き実の数」
(角宮悦子『ある緩徐調』より)
「ボルト屋が来てボルトのことながながと喋りてゆけりボルトかなしも」
(千々和久幸『祭という場所』より)
「わたくしも此処で死ねるか姑(はは)の死にしベッドを借りてお昼寝をする」
(石川不二子『ゆきあひの空』より)
「百千体じぐざぐに並ぶ石仏のかたぶきしまま夜は眠らむか」
(森比左志『月の谷』より)
「でもそれでいいんだとてもみぞれ降る二月のことを聞かせてほしい」
(岐阜亮司「デート」『北大短歌』第五号より)
「裂けて地にある花びらに人間の童話を聞かす。五月某日」
(杉原一司遺稿「未定稿」より)
「ゆるやかな心変わりで幽霊に会えなくなった八月のこれから」
(N/W「幽霊たち」Website「TOM」より)
「もみぢいよいよ燃えて一切まにあはぬ我のひと日を笑ふうつくし」
(馬場あき子『渾沌の鬱』より)
「夕ぎりに見えわかねども松風の音するかたや湊なるらむ」
(落合直文『萩之家歌集』より)
「もうどんな約束もなし身ひとつを運びきたりて菖蒲にかがむ」
(三井ゆき『天蓋天涯』より)
「敗れたる國といへども涙ふきゐるをとめあり映畫館にて」
(二宮冬鳥『黄眠集』より)
「野イバラが素足に痛くて今きみをみたら泣いてしまうなきっと」
(北川草子『シチュー鍋の天使』より)
「友の家の厠へゆくと下駄穿きぬみやこべ遠くわれは来てあり」
(三ヶ島葭子『吾木香』より)
「停車場(ていしゃば)に札(ふだ)を買ふとき白銀(しろがね)の貨(かね)のひゞきの涼しき夜なり」
(若山牧水『独り歌へる』より)
「見れるだけ爪を見ている少年の母の怒号を受けてる睫毛」
(川島結佳子『感傷ストーブ』より)
「冬虹の弧はふかきかな夫在らぬ空間ふいにあらはとなれり」
(春日真木子『野菜涅槃図』より)
「雪の夜はをみななるわれ温石(をんじやく)の言葉となりて夫を寝(い)ねしむ」
(田宮朋子『星の供花』より)
「仕事終へ白布かければ計器類にはかに支配者のかたちをくづす」
(鈴木諄三『ぜふぃいるす』より)
「てのひらにつつむ胡桃の薄緑この惑星に子よ生れてくるしめ」
(西王燦『バードランドの子守歌』より)
「twilight in L.A./golden shining reflections/on asphalt pavement/the city becomes holy/everything forgiven」
(Ron L. Zheng(鄭龍超)『Leaving My Found Eden』より)
「山城のみづのみ草につながれて駒ものうげに見ゆる旅かな」
(西行『山家集』より)
「おどろきて歩み逃げ去る丹頂は頸さし伸べて描かれにけり」
(半田良平『幸木』より)
「「行つて来ます」言はずに登校したる子の茶碗のねばねばいつまでも洗ふ」
(山口明子『さくらあやふく』より)
「うちつけにものぞかなしき木の葉ちる秋のはじめになりぬとおもへば」
(藤原公任『和漢朗詠集』より)
「忘れ路の 行く末までは 難ければ 今日限りの 命かもねむ」
(儀同三司母「小倉百人一首」54番より)
「うちなびき春は来にけり青柳のかげふむ道に人のやすらふ」
(藤原高遠『新古今和歌集』より)
「水漬く屍と死ぬべかりしを生きつぎて穢汚の裡に在るが宜しも」
(村上一郎『撃攘』より)
「梅雨雲(つゆぐも)にかすかなる明(あか)りたもちたり雷(らい)ひくくなりて夏に近づく」
(中村憲吉『しがらみ』より)
「家にてもたゆたふ命。波の上に浮きてし居れば、奥処(おくか)知らずも」
(大伴旅人傔従『万葉集』巻17・3896番より)
「秋を待たで枯れゆく島の青草は、皇国の春によみがへらなむ」
(牛島満/辞世の句より)
「雲を踏み嵐を攀て御熊野の果無し山の果も見しかな」
(伴林光平『南山踏雲録』より)
「身はたとひ武蔵の野辺に朽ちぬとも留めおかまし大和魂」
(吉田松陰『留魂録』より)
「吹く風に潔く散れ山さくら残れる花はとふ人もなし」
(井上甃介/野津猛男『臨床漢法医典』緒言より)
「虫籠のやうな肋骨わたしにもありて夜々こほろぎが鳴く」
(朝井一恵『手描きの地図』より)
「「このシーン雨降らせよう」と監督(ディレクター)そんな感じだ結句の雨は」
(川田一路『NEXT 0NE』より)
「花々に埋もれてわれも風のなき柩のなかにひと世終へんか」
(山中律雄『変遷』より)
「安物のパズルのような隙間あり この家にあるいはわたしの中に」
(宮地しもん『f字孔』より)
「遠山の時雨にしづむ昼つ方われと暮らしてさびしいか君」
(加藤和子『天球の春』より)
「いやべつにああさうだつけ聞いてないそれでいいじやんもう眠いから」
(藤野早苗『王の夢』より)
「遂ぐる日をしらねはろけき祈りもて久遠におのれを繋ぐといはむ」
(岸野愛子『女流十人集』中河與一編より)
「麦うれて細い流れが光っている わたしでない農夫が鎌研いでいる」
(光本恵子著『人生の伴侶』より)
「ローソンの袋の皺に眼はありてじいつと俺の方を見てゐる」
(斎藤寛『アルゴン』より)
「夕刊を読みをはりしが妙高に雪降りつみし記事も親しも」
(堀内通孝『丘陵』より)
「もやの中ひかりて落ちるいくすじの分れて再また会う光いくすじ」
(中村幸一『あふれるひかり』より)
「拾い読みして戻すその本の背文字が光りその本を購う」
(浜田康敬『梁』98号より)
「カラメルをとろり煮る午後猫が鳴く昨日はどこにもありませんよう」
(吉田優子『ヨコハマ・横浜』より)
「駆けつこの迅きは英雄となりて墜ち鈍足の群れに射せる黄昏」
(松川洋子『ハロ族の星』より)
「読んだことさえ忘れた本の真下にも速やかに白く地下用水路(カレーズ)走る」
(大田美和『飛ぶ練習』より)
「牡丹雪樹林(じゆりん)にふかくふりこめばかくも豊かにてものみなゆらぐ」
(坪野哲久『桜』より)
「華やぎのいまだ残れる西空に一揆のごとくわがゆかむとす」
(高嶋健一『草の快楽』より)
「棒のごと羽をすくめて飛びながら鳥はときどきただ落ちてゐる」
(朝井さとる『羽音』より)
「動く歩道の端の端まで歩みきてひとつ飛びにつく龍馬空港」
(宮本永子『青つばき』より)
「満月はかさぶたみたいな色をして(あれが地球の影なんだね)」
(浅川洋『空洞ノ洞DOU』より)
「熟柿(うれがき)はわれを抱きし伯母のやうぽたぽたとして皮破れさう」
(中野昭子『夏桜』より)
「あ、蝉と思ふたちまち揃ひ鳴く 台風すでに外(そ)れたるならむ」
(神谷佳子『原景』より)
「病むわれは暗闇の中に立たされて壁泥(かべどろ)のごときものを飲まさる」
(村野次郎『樗風集』より)
「印章を売る店すぎてわれと子は思い思いの夕焼けに遭う」
(小守有里『こいびと』より)
「約束をつんと破ってみたくなる二月の空にもりあがる月」
(干場しおり『天使がきらり』より)
「高雲は夕映えしつつ鉄筋のアパートが曳く影の鋭角」
(古舘佐智子・合同歌集『雲』より)
「八月の耳はとがれりバケツ打つ雨音しきりにポツダムポツダム」
(春日いづみ『八月の耳』より)
「朝刊が濡れないように包まれて届く世界の明日までが雨」
(吉田恭大歌集『光と私語』より)
「啄める林檎の肉のたっぷりとありてひそけくながれゆく時」
(角倉羊子『ヴェネチアの海』より)
「右足から蔓を伸ばして右耳に凌霄花の花咲かせたし」
(駒田晶子『銀河の水』より)
「みづからの恋のきゆるをあやしまぬ君は御空(みそら)の夕雲男」
(与謝野晶子『佐保姫』より)
「我のみが知る記念日は数ありてそのたびひとりのさびしさに気付く」
(田中雅子『令月』より)
「活けるまま糠揉み込みてぬめりとるあな耐へられず蛸の目を抓(つ)む」
(松崎英司『青の食単(レシピ)』より)
「ああさうだこの声だつたと思ふためそのためだけに君と会話す」
(水上芙季『静かの海』より)
「雨期の地に呪詛の掌のごと揺れてゐる羊歯ありくらく永き平和よ」
(杜沢光一郎『黙唱』より)
「となりにてざらりざらりと節分の鬼やらひ豆を炙る鍋の音」
(太田水穂『鷺・鵜』より)
「昨夜(きぞ)の雪消えぬ尾根より風来たり言葉いくたび人に滅びし」
(寺尾登志子『黄道光』より)
「冷めてなほ唇(くち)に張りつく乳の膜おのがことばにおのれ欺き」
(さいかち真『裸の日曜日』より)
「ホイッスルに咎められつつ駆けぬけぬゼブラゾーンの水はねかへし」
(桜木裕子『片意地娘(ララビアータ)』より)
「風を従へ板東太郎に真向へば塩のごとくに降りくる雪か」
(石川一成『麦門冬』より)
「河二つぶつかり合えば冬近き朝々を靄街深く来る」
(清原日出夫『流氷の季』より)
「かつと燃えるウヰスキイの夏ぞら 弱々とたかくのぼらぬ煙突のけむり」
(西村陽吉より)
「この夕べ片附け終へし文机にあはあはと置く埃を拭かん」
(大塚大/歌誌「コスモス」1973年九月号より)
「胸うちに棲みつく獣起きるなと願ひつつ今日の会に出でゆく」
(小西久二郎『湖との訣れ』より)
「玉の緒よ 絶えねば絶えね ながらへば 忍ぶることの 弱りもぞする」
(式子内親王「小倉百人一首」89番より)
「ま昼どき畳のうへにほうほうと猫の抜毛の白く飛びつつ」
(古泉千樫『青牛集』より)
「雨暗く/部屋の明かりが輝けり/甦りといふことを思へる」
(坂口弘『常しへの道』より)
「地獄酒極楽酒のけじめなく二升たちまち火の粉となりぬ」
(菱川善夫『菱川善夫歌集』より)
「八雲立つ 出雲八重垣 妻ごみに 八重垣作る その八重垣を」
(スサノオノミコト『古事記』より)
「兵営に消燈喇叭の鳴るときし南十字はかたむきにけり」
(田中克己『歌集戦後吟』より)
■第七章:新種八百人一首(+100首)
「梓弓はるは来にけり武士の引きかへさじと出づるたびかな」
(久坂玄瑞/辞世の句より)
「今日にかけてかねて誓ひし我が胸の思ひを知るは野分のみかは」
(森田必勝/辞世の句より)
「烏口(からすぐち)の穂尖(ほさき)に思ひひそめては磨(と)ぐ日しづかに雪は降りけり」
(堀口捨己『堀口捨己歌集』より)
「除染とて地の面までも剥がれつつ見る見る町が無くなりそうな」
(波汐國芳『渚のピアノ』より)
「でで蟲の身は痩せこけて肩書の殻のみなるを負へる我はも」
(西田幾多郎『西田幾多郎歌集』より)
「プリントを授業で配るそれだけでありがとうを言う子供らがいる」
(桃林聖一『ネバーランドの夕暮』より)
「いつだつて蛍光灯に照らさるるわれは浅蜊の殻より暗し」
(高村典子『雲の輪郭』より)
「月面に咲くかも知れずと思ふほど月光に蕎麦の花が照りゐる」
(山下太吉『冬の日溜まり』より)
「球を中に一つに動くルーズ・スクラムこの時の間を心張り来る」
(松村英一『初霜』より)
「男系の孔子三世の墓ありて墓なき女は空にかがやく」
(川口美根子『光る川』より)
「アルタイルならぬ老い人ベガの待ちゐるとは思はねど橋渡る」
(大塚健『経脈』より)
「喉元(のどもと)に銃(つつ)のはさまりし夢さめてかなかなは暁(あけ)を鳴きそめにける」
(加藤將之『対象』より)
「海岸山観音寺の朝ぼらけ空々くろろんと啼くは誰が子ぞ」
(陀仙(辻潤) 観音寺歌碑より)
「羆の身ゆるりと返りこなた向く花の散り込む檻の片隅」
(小林サダ子『廻廊』より)
「ダイヤモンドゲームの駒を青と決めいちばん遠い場所にゆく旅」
(やすたけまり『ミドリツキノワ』より)
「革命歌作詞家に凭りかかられてすこしづつ液化してゆくピアノ」
(塚本邦雄『水葬物語』より)
「ふとからだ軽くなりたるゆふぐれをさくら樹が産み落とす花びら」
(辰巳泰子『紅い花』より)
「人間に最も近き植物は茸なりしとあるを書きとむ」
(高瀬一誌『レセプション』より)
「声挙げた者は省かれ しずけさの粒子となって雪はふりつむ」
(佐藤晶『冬の秒針』より)
「<死などなにほどのこともなし>かく詠ふ人も苦しみて死へ渡るなり」
(竹山広/初出2001年「短歌往来」1月号より)
「外苑の縁(へり)の彎曲あゆみをればみどり濃き人ちかづいてくる」
(前川佐重郎『孟宗庵の記』より)
「やわ肌の火照りの止まぬ発疹に似て筐体にランプが点る」
(堀合昇平『提案前夜』より)
「まつぼくりきのうひろってきょうひらきいえあだだかいゆぎもまんがい」
(マルタ・モライス「日本歌人東京歌会詠草」より)
「高々と資材吊り上げ夕焼けの中にクレーンなほ動きゐる」
(神作光一『冴え返る日』より)
「伏せ置ける棚の茶碗のなかの闇茶碗の外の闇と異なる」
(五所美子『和布刈』より)
「じりじりとセメントの袋担(にな)ふさま重心の移るさま見えてをり」
(田谷鋭『乳鏡』より)
「前よりはきたらず後より追いついて追い越されゆく齢とおもう」
(関根榮子『旅枕』より)
「百年後も決して終はらぬ三月がまた来る冬のコート着たまま」
(小林真代『Turf』より)
「屋上で白く干されたシーツたち五月はきっと揮発する夏」
(鈴木智子「イラン、夏」より)
「二十九歳父の軍服は夏のまま七十回目の八月迎ふ」
(四竃宇羅子『翼はあつた』より)
「蠟燭が花を大きな影にする きのふを明日とよびかへてみむ」
(大地たかこ『薔薇の芽いくつ』より)
「香りたつ栄螺の腸を巻きとりてふつと誰かを許したくなる」
(森岡千賀子『坂のない町』より)
「なくでない泣いてはならぬと鳴く蝉の津浪のごとき号泣にあう」
(安森敏隆『百卒長』より)
「灯消し稚き妻が息づきぬ窓の外に満ちし冬の月光」
(島田修二『花火の星』より)
「わが額にかそか触るるはわが髪にあらねはるけき岬(さき)に潮(しお)鳴る」
(中野照子『しかれども藍』より)
「いひたいことに突き当つて未だ知らない言葉子はせつなげに母の目を見る」
(五島美代子『新輯母の歌集』より)
「夜半すぎてこころのしまりくるときのこの真顔(まがほ)ひとりわれのみぞ知る」
(木俣修『呼べば谺』より)
「ガザ地区と足立区響き似ていると吾子(あこ)が言いけり空爆怖い」
(田中有芽子『私は日本狼アレルギーかもしれないがもう分からない』より)
「しんしんと雪ふるなかにたたずめる馬の眼(まなこ)はまたたきにけり」
(斎藤茂吉『あらたま』より)
「いきなり父は十露盤(そろばん)を投げつけつ歌などいぢりのぼせてをれば」
(片山貞美『魚雨(うをあめふる)』より)
「竹・藁・葦こまかく堅く編みつぎてここにもモンスーン圏に生くる者たち」
(太田青丘『アジアの顔』より)
「しよんぼりと霧に飢ゑをるえんとつのまるみなり日暮れはこころも猫なり」
(早野臺氣『海への會話』より)
「さりながら死ぬのはいつも他人なり夢野久作荻野久作」
(佐々木六戈『佐々木六戈歌集成』より)
「はるばるとよさの湊の霧はれて月に吹き越す稲のうら風」
(細川幽斎『衆妙集』より)
「シルクロード展を出できて見る青葉嬰児のミイラ永遠(とわ)に乾ける」
(東洋『春の古書店』より)
「カレンダーを家族の予定で埋めし日々終りていまは詳しく知らず」
(近藤かすみ『雲ヶ畑まで』より)
「思い出が痛くて眠れぬ夜半の雨オキシドールのように沁むるよ」
(久保みどり『熊野のアリア』より)
「下手糞の上級者への道のりは己が下手さを知りて一歩目」
(安西光義/「スラムダンク」より)
「死の穢れなどといふものを落とすためわが身に人は塩の粒まく」
(今泉重子『龍在峠』より)
「まだまだとおもいてすごしおるうちに はや死のみちへむかうものなり」
(村岡花子/村岡恵理『アンのゆりかご』より)
「まむかへば天そそり立つ足助山寄りくるごとくいよよきびしく」
(一ノ関明「くまかし短歌会」より)
「水はやき小川の浮藻いまのわが心にも似てゆれやまぬかも」
(岩本素白/来嶋靖生『岩本素白 人と作品』より)
「離りゐて 思ふはすべなし。常世子は 雛祭(ひゝなまつり)に 仕へつらむか」
(藤井貞文『藤井貞文全歌集』より)
「かへらじとかねて思へば梓弓なき数にいる名をぞとどめむ」
(楠木正行『太平記』より)
「益荒男がたばさむ太刀の鞘鳴りに幾とせ耐へて今日の初霜」
(三島由紀夫/辞世の句より)
「君ならぬ車つれなう門(かど)すぎてこの日も暮れぬ南河内(みなみかはち)に」
(石上露子『石上露子集』より)
「百キロで走ってごらん掌を出せば触るる空気は乳房の如し」
(岩切久美子『湖西線』より)
「夕がたの日影(ひかげ)うつくしき若草(わかくさ)野(の)体(からだ)ひかりて飛び立つ蛙等(かはづら)」
(結城哀草果『山麓』より)
「老眼鏡掛くれば延びる生命線このさびしさに慣れねばならぬ」
(宮原望子『哀蚊』より)
「ひとりぼっちに働かされている洗濯機 思案してより反転をする」
(星野秀子『秋の使者』より)
「「凍てる」とはただ一点が痛むこと 「冬」は鼻腔の奥で決めます」
(中森舞『Eclectic』より)
「遠見ゆる白鳥三百ふつふつと流れ地上に白き波立つ」
(安部洋子『西方の海』より)
「とどろきて風吹きゆする硝子戸に紅はきよし沈丁花のつぼみ」
(五味保義『此岸集』より)
「干し網は白く芝生にうたれつつ輝く時のいまは過ぎゆく」
(松坂弘『輝く時は』より)
「三河地震に宿舎はつぶれ二ヶ月余余震におびゆる日の続きたり」
(保田ヒロ『薄墨桜』より)
「わが戦友らいのち死ゆきし草丘のいくつを越ゆる時雨降りつつ」
(鈴木英夫『先陣秘帖』より)
「円満の秘訣は一割言はぬこと 南瓜の種を匙で抉りぬ」
(井川まさみ『桜の家』より)
「僕はいくつになっても夏を待っている 北蠅座というほろびた星座」
(土岐友浩『Blueberry Field』より)
「ぴあのぴあのいつもうれしい音がするようにわたしを鳴らしてほしい」
(嶋田さくらこ『やさしいぴあの』より)
「夕ぐれは焼けたる階に人ありて硝子の屑を捨て落すかな」
(近藤芳美『埃吹く街』より)
「炎天下掃除のさなか後悔と仏教関係の本が湧きたり」
(片岡総一『海岸暗号化』より)
「心臓穿刺して鮮烈に血は噴き出ず Sursum cordaと鳴く海猽の」
(原田禹雄『錐体外路』より)
「日の下に妻が立つとき咽喉(のど)長く家のくだかけは鳴きゐたりけり」
(島木赤彦『切火』より)
「雨の降はげしくなりし沙の上は明かるむまでに白き花殻」
(岡部文夫『雪天』より)
「磯城島(しきしま)の日本(やまと)の国は言霊の幸(さき)ふ国ぞま幸くありこそ」
(柿本人麻呂『万葉集』巻13より)
「うなだれてゐたるうばらが水上げて勢ひづいたりしやきつとしたり」
(春日井政子『細波』より)
「遠い朝のように母来て縁側の夏のほとりに吸うている桃」
(秋山律子『或る晴れた日に』より)
「今われは都市の貌(かほ)して足早に群れの流れの中に融け行く」
(玉井慶子『黙契の譜』より)
「歳月に意味を問うなら問うことの問いの形がとり残さるる」
(糸川雅子『タワナアンナ』より)
「子ども神輿のワッショイワッショイやけくそな掛け声さえも受け継がれてる」
(三原由起子『ふるさとは赤』より)
「田も畑も見渡す限り沼となり遺体浮く見ゆ三月十二日」
(金野友治『震災のうた―1800日の心もよう』より)
「五月雨に物思ひをれば郭公夜ぶかくなきていづちゆくらむ」
(紀友則『古今集』夏歌よりより)
「風鈴がふるえる九月生きてゆくための思想に上書きはなく」
(宮本史一『cahiers』vol.7,2017.11より)
「アエイオウ 口つぼめたりひろげたり 窓の向こうの雪の唇」
(長澤ちづ『海の角笛』より)
「ブラスバンドが同じところで間違ふを二人聞きをり春の三角州(デルタ)で」
(高橋ひろ子『ラディゲの齢』より)
「熱湯に月桃花茶のティーバッグふかく沈めてこの世にひとり」
(渡英子『レキオ 琉球』より)
「かなしくも恋と知る日はかたみにも悔いて別るる二人なるべき」
(原阿佐緒『白木槿』より)
「ここにただ仰ぎてゐたり青空を剥がれつづける場所の記憶を」
(小林幸子『場所の記憶』より)
「咲く花は五分こそよけれ身のうちに残れる五分の力ににほふ」
(山埜井喜美枝『歩神』より)
「銃弾が打ち貫きし手帳がそのままに行李の中に収められゐぬ」
(渡辺直己『渡辺直己歌集』より)
「ゆっくりとわかるのだろうほっとかれそのままでいるプラスティックを」
(柳谷あゆみ『ダマスカスへ行く 前・後・途中』より)
「もの思ひにしづみゐるのかかはたれを重たげに咲く千年桜は」
(萩岡良博『漆伝説』より)
「夜半の湯に肉塊のわれしづむとも地球はうかぶくらき宇宙に」
(坂野信彦『銀河系』より)
「敗け方の下手なわたしは点になるまでのひばりを又聞いている」
(田井安曇(我妻泰)『我妻泰歌集』より)
「溶けあうものすべて溶けあいからみあう声が木馬のごと揺れるなり」
(大庭れいじ『ノーホエア・マン』より)
「血は出口探して巡れるものならず夜の運河と遥か釣り合ふ」
(桑原亮子「塔」2010年8月号より)
「黄楊の葉にさがる蜘蛛の子うつつには見えざる糸をのぼりはじめつ」
(落合けい子『じゃがいもの歌』より)
「小禽(ことり)の人にさからふくちばしををりふし汝に見ればさびしき」
(内藤鋠策『旅愁』より)
「池水はすり鉢状に渇水し搏動(いき)のごときを岸辺に刻む」
(宮西史子『秋時間』より)
「充電器に鎮座している携帯の何かに似ている そうだ位牌だ」
( キム・英子・ヨンジャ『百年の祭祀(チェサ)』より)
■第八章:新種九百人一首(+100首)
「かひごぞよ帰りはてなば飛びかけり育みたてよ大鳥の神」
(平清盛『古活字本 平治物語』より)
「蜜入りの南高梅の一粒をねぶりて足れるわが夕がれひ」
(佐藤祐禎「未来」2012年10月号より)
「おもしろきこともなき世におもしろくすみなすものは心なりけり」
(高杉晋作/辞世の句より)
「いづくにかわれは宿らむ高島の勝野の原にこの日暮れなば」
(高市黒人『万葉集』巻3・275番歌より)
「ピカッドンと 一瞬の間の あの静寂(しじま) 修羅と化すときの あの静寂」
(正田篠枝『唉!原子爆弾』より)
「燕飛ぶ空を仰ぎて立ち尽くすわれ兵たりき人を殺しき」
(川口常孝『川口常孝全歌集』より)
「召さるる日あるひは近しひと夜おそく焚くべきは焚けり思ふべきは思へり」
(大西巨人『日本人論争 大西巨人回想』より)
「おりたちて今朝の寒さを驚きぬ露しとしとと柿の落葉深く」
(伊藤左千夫『左千夫歌集』より)
「厨べにすてし茶がらは凍りつき雀は降りて餌を探すかも」
(松倉米吉『松倉米吉歌集』より)
「無人野菜売場に小さき筍が男雛女雛のごとくに置かる」
(今井千草『パルメザンチーズ』より)
「十六歳の君の写真が見下ろすは柩に眠る十八歳の君」
(植田美紀子『ミセスわたくし』より)
「ひと穴に一匹づつ待つ蟻地獄ベージュの砂をへこませてゐて」
(松原あけみ『ペロポネソス駅』より)
「再開発のビル建設は進められ古びつつある仮設住居(かせつ)を囲む」
(武山千鶴「1099日目」より)
「わが手より三歩駆け出し待っている自動改札茶色い切符」
(武富純一『鯨の祖先』より)
「思ふことね覚めの空に尽きぬらむあしたむなしきわがこころかな」
(香川景樹『桂園一枝』より)
「海ふかく沈める艦がかぎりなき潮のながれに音ひびくとぞ」
(川島喜代詩『波動』より)
「暴力でオキナワくらいはなんとかなると軍用道路で話しているよ」
(淺川肇「無人島」第12号より)
「一山をゆるがしすぐる風のこゑしましはやがてひそまりにけり」
(三好達治『詩集 覊旅十歳』より)
「「ゴメンネ」と羞しく言いて寝につきし夫の夜毎の言葉忘れず」
(菊地原芙二子『言葉の小石』より)
「本当のことを伝へて憎まれてあげるくらゐの愛はなくつて」
(枡野浩一「短歌ヴァーサス」創刊号より)
「ちゃんと歩いてここまで来たってわかるから靴は汚れているほうがいい」
(上澄眠『苺の心臓』より)
「星あかりのわずかに届く闇を来てものやわらかな音楽ひとつ」
(甲村秀雄 『短歌往来』4月号 第32巻4号より)
「抑え難く感情の動く二日三日椅子に突き当り階に躓く」
(石田比呂志『無用の歌』より)
「分別のない人増えて分別のある犬増えて日本恐ろし」
(松尾祥子『シュプール』より)
「行きずりにタアバン白き少女見て塑像かと思ふくれぐれの橋」
(前川緑『みどり抄』より)
「目隠しをされたらきっと折り鶴の額のかたちを忘れてしまう」
(狩野悠佳子「早稲田短歌42号」より)
「待ちわびしコウホネひとつ水の面(も)のひかり集めて今日咲きにけり」
(鳥海昭子『ラジオ深夜便 誕生日の花と短歌365日』より)
「夕ぐれは肉のもなかに盛んなる肉屋の指をかいまみるかな」
(河野愛子『魚文光』より)
「採光窓歩道に開(あ)けば地階よりの光漏れ来ぬわが足もとに」
(吉野昌夫『遠き人近き人』より)
「日常のわが段落に埋めおきし球根がけさ洎夫藍に咲く」
(高橋幸子『花月』より)
「弟のかんばせ蔽ふ白布(しろぬの)を落葉の匂ふ風が通れり」
(橋本喜典『無冠』より)
「夏草のくさむらふかく住む母のポストにま白な封書きている」
(山形裕子『かばれっと』より)
「今日は水出でぬ噴水の渇きいてあからさまなる空間が見ゆ」
(金井秋彦『金井秋彦遺歌集』より)
「無抵抗主義者のやうなる草の根のおどろくばかり長し三月」
(荒垣章子『虚空の振子』より)
「われは一人の死の意味にながく苦しまむ六月十五日の警官として」
(筑波杏明『海と手錠』より)
「右からも左からも愛されていて肩をすぼめる九月の寝床」
(御糸さち『ねこのね、』より)
「こころはあおい監獄なのに来てくれた かすかな足音を積もらせて」
(小林朗人「しかし薄氷の上で」『率』8号,2015.05より)
「右半盲の母の視界の外に立ちミモザの花はあふれて咲けり」
(曽我玲子『薬室の窓』より)
「手の触れる範囲に誰かきつとゐるガマの闇からひそひそと声」
(佐藤理江『避雷針の先端の銀』より)
「ぬるま湯に蛸踊りつつ死を迎ふ快楽のむらさきのこむらがへり」
(和田大象『くらはんか』より)
「もうずっとそこにあるような雰囲気で子の顔の真中に置かれしめがね」
(森尻理恵『S坂』より)
「薔薇(ばら)もゆるなかにしら玉ひびきしてゆらぐと覚ゆわが歌の胸」
(山川登美子『恋衣』より)
「俳優の演技終はりて曲げゐたる細枝しづかに戻す助手の手」
(岩井謙一『光弾』より)
「ひるがえる踵ばかりを見てしまう知らない人についてゆくとき」
(増田静『ぴりんぱらん』より)
「何にすといふならねども輪ゴム一つ寂しき夜の畳に拾ふ」
(田中順二『書斎内外』より)
「生きがたき世と思ふ夜半開きたる丘(きう)の言葉もやせがまんなる」
(上條雅通『駅頭の男』より)
「てのひらに稚きトマトはにほひつつ一切のものわれに距離もつ」
(滝沢亘『断腸歌集』より)
「塩振りてひとりの轢死払ひ去る夜半の詰所(つめしょ)に食に戻りぬ」
(御供平佶『車站』より)
「冬椿、手ふれて見れば凍れるよ、我が全身ををののかしめて」
(平野万里『わかき日』より)
「朝床にきく風音のゆたかなり鯉幟ながき尾をふりあぐる」
(造酒廣秋『秋花冬月』より)
「証明写真と同じわが顔嵌まりたり帰り来て入る部屋の鏡に」
(小潟水脈『扉と鏡』より)
「日の沈めばうす暗き世の隅にゐていぢらしうわれ涙ぐむなり」
(米田雄郎『入没』より)
「馬追虫(うまおい)の髭(ひげ)のそよろに来る秋はまなこを閉ぢて想(おも)ひみるべし」
(長塚節『長塚節歌集』より)
「入りがたの峰の夕日にみがかれてこほれる山の雪ぞひかれる」
(伏見院『伏見院御集』より)
「いつしらに庭の白梅咲きさかり夕かぎろひのなかに散りゆく」
(羽場喜彌『心象風景以後』より)
「君がためつくす心は水の泡消えにし後ぞすみ渡るべき」
(岡田以蔵/辞世の句より)
「やがて来む終の日思ひ限りなき生命を思ひほゝ笑みて居ぬ」
(菅野すが『死出の道艸』より)
「宿ちかく花たちばなはほり植ゑじ昔をしのぶつまとなりけり」
(花山院『詞花和歌集』より)
「明日という日もなき命いだきつつ文よむ心つくることなし」
(木村久夫『きけわだつみのこえ』より)
「聞きわびぬはつきながつき長き夜の月のよさむにころもうつこゑ」
(後醍醐天皇『新葉和歌集』より)
「鳴けや鳴け蓬(よもぎ)が杣(そま)のきりぎりす過ぎゆく秋はげにぞ悲しき」
(曾根好忠『後拾遺和歌集』秋上・273より)
「いつにても顔の高さに海音のありて明るし寂し療園」
(太田正一『風光る』より)
「わが胎より出でたる者を何(なに)のそのと妻はためらはず子供の日記読む」
(柴生田稔『入野』より)
「常通る汽車の火の粉に焼けたりし露草の花曼珠沙華(まんじゅしゃげ)の花」
(田中子之吉『現身』より)
「くらあい誰もゐない博物館大きなほとけさまがぼくをみつめてゐる」
(島津忠夫『心鋭かりき』より)
「四ツ橋筋に欄間屋ありてうつくしき欄間の彫りにひびく街音」
(水沢遙子『空の渚』より)
「子の学費払い終えたるビルの狭間篠懸の刈られいるを仰ぎつ」
(太宰瑠維『夕星』より)
「をのもしれなきてしおもてひとしらしとひてもをしてきなれしものを」
(西園寺実兼「詠百首応制和謌」より)
「十楽(どくだみ)の賢(さか)しく白き花咲きて江戸町裏の女(をみな)ありしか」
(石川恭子『雲も旅人』より)
「世の中は夢かうつつかうつつとも夢ともしらずありてなければ」
(小野小町『芸術家まんだら』より)
「深々と裾野を埋めし雲の海のいまだ見えゐて山は暮れゆく」
(大悟法利雄『翼』より)
「花崗岩の花ひらく巓(いただき)をとりかこみ五峰・天女・勢至・無涯峰とうちよせる天上の奏楽」
(逗子八郎『山岳歌集 雲烟』より)
「飢ゑきれぬ腑のごときもの青竹の空洞といふさびしき宇宙」
(喜多弘樹『銀河聚楽』より)
「本当は声に言葉にしたかつた空を歌つてにごしたあの日」
(中野迪瑠『青色ピアス』より)
「下り坂下から見れば上り坂インテグラルのかたちをえがく」
(笹本碧『ここはたしかに』より)
「屈折率ほどせいひくくみえながら水に沿(そ)うさまざまのはるの樹」
(村木道彦『天唇』より)
「いくたびも廻転扉(ドア)に吸はれ入り芝郵便局に新しきコスモス運ぶ」
(宮英子『婦負野』より)
「カミガミノムレアソブ カノ/ムラサキノウミノ アカツキ/ アブラアビ トリハシニウキ/パケム ウィルムクエ カノ」
(中村真一郎「鳩よ!」1991年5月号特集「湾岸の海の神へ」より)
「疾風を押しくるあゆみスカートを濡れたる布のごとくにまとふ」
(上田三四二『遊行』より)
「鉱脈の輝き放つ星の下革ジャケットの匂い吸い込む」
(中西由起子『迦楼羅の嘴』より)
「生(なま)蒸気がパイプを戻りくる音をとらへて午後のわが耳は鳴る」
(外塚喬『喬木』より)
「すすみゆく時にあふともいそのかみふるきてぶりをわすれざらなむ」
(明治天皇「明治神宮南門の看板」より)
「早春の風を踏みつつ来しなだり紅梅その他君の背も見ゆ」
(青井史『青星の列』より)
「会ふ人の皆犬つれし小公園吾が曳く白狐他人(ひと)には見えず」
(富小路禎子『芥子と孔雀』より)
「冬日てる街あゆみ来て思ひがけず吾が視野のなかに黒き貨車(くわしや)あり」
(佐藤佐太郎「黄炎抄」合著『新風十人』より)
「緩き時間まとう木橋を渡り終え人は陽射しの中へ還らむ」
(桜井健司『融風区域』より)
「三月の暦が壁にぶら下がる君の部屋より見ゆる葉桜」
(武藤雅治『暗室に咲く白い花』より)
「泣ききれず泣きやみきれず六月の空こきざみに肩をふるはす」
(福士りか『サント・ネージュ』より)
「なめらかなわたしの腕を撫でる手がわたし以外にあるべき、九月」
(小原みさき「殴って撫でた」/「東北短歌」第3号より)
「わたくしを生きているのは誰だろう日々わずかずつ遅れる時計」
(岸原さや『声、あるいは音のような』より)
「湧きあがる清水匂えるわさび田のみどりを透きて一輪車のレイナ」
(岩崎嘉寿子『春の交叉点』より)
「もっともっとさみしくなるとガラス窓にあじさいは頭を押しつけてくる」
(松野広美『二月の兎』より)
「手をつなぐかと問ふわれに君はただ笑みて水筒の紐を直しぬ」
(小林信也『千里丘陵』より)
「秋空は高かりき青かりき広かりき昔昔のさらなる昔」
(青木昭子『申し申し』より)
「ちちははのゐぬふるさとに帰り来て先づはひと泣きさせてもらひぬ」
(狩野一男『栗原』より)
「プラカード持ちしほてりを残す手に汝に伝えん受話器をつかむ」
(岸上大作『意志表示』より)
「戦時中灯籠を拾ってきたという祖父の遺影は加工されてる」
(戸田響子『煮汁』より)
「日昏れ来る 黒き帽子をかむりたる紳士の群れの降り立つやうに」
(笠井朱実『草色気流』より)
「人のをらぬ改札口を通り過ぎやうやく僕の無言劇果つ」
(栗原寛『月と自転車』より)
「死者の魂(こん)翼に乗ると空みつつまなこ澄みけむ古へびとら」
(高橋睦郎『虚音集(そらみみしゆう)』より)
■終章:新種千人一首(+100首)
「何ものかを守るかたちに擦る燐寸バーナーに湯を沸かさむとして」
(林田恒浩『晩夏をわれに』より)
「看板に〈傍観者〉とありときをりは店主が出でて小窓を磨く」
(長谷川と茂古『幻月』より)
「油さしの長い触覚/油をさせば/歯車に踊る朝の心だ。」
(清水信『煙突』より)
「沈黙は苦手といふより恐怖なり 顔まつしろな牛がひしめく」
(石井幸子『挨拶(レヴェランス)』より)
「鬼神もあはれと思はむ桜花愛づとは人の目には見えねど」
(本居宣長『枕の山』より)
「夕さればそぞろあきりす銃器屋のまへに立ちてはピストルを見る」
(萩原朔太郎『短歌』より)
「春畠に菜の葉荒びしほど過ぎて、おもかげに 師をさびしまむとす」
(折口春洋『鵠が音』より)
「かの子等はあをぐもの涯にゆきにけり涯なるくにを日ねもす思ふ」
(西田税『妻たちの二・二六事件』より)
「いまよりはなるにまかせて行末の春をかぞへよ人の心に」
(里村昌琢/司馬遼太郎『播磨灘物語』より)
「昏れゆけば信濃は早き夕餉どき母のなき娘が膳運びくる」
(山村湖四郎『山村湖四郎のうた』より)
「川そこの光消えたれ河郎は水こもり草に眼をひらくらし」
(芥川龍之介『芥川龍之介全集8』より)
「とほ世古りし丘にならびて子らの見るゆふ焼け空の中に還りぬ」
(保田與重郎『木丹木梅集』より)
「さ夜ふくる窓の燈(ともしび)つくづくとかげもしづけし我もしづけし」
(光厳院『光厳院御集』より)
「薪(たきぎ)伐(こ)る鎌倉山の木垂(こだ)る木を松と汝(な)が言はば恋ひつつやあらむ」
(作者不詳『万葉集』東歌・巻第14・3488より)
「まるまるとまるめまるめよわが心まん丸丸く丸くまん丸」
(木喰上人『歌集』より)
「ブロッコリーの花を咲かせて生けている米寿の母のふしぎひろがる」
(上條節子『森喰うわたし』より)
「大川にあと白浪の春立ちて名探偵もねぶたかりけり」
(福永武彦『夢百首 雑百首』より)
「ロベリアの青きが風と揉みあえり 巴御前は素手でたたかう」
(谷口純子『金色の橋』より)
「一口のパンが喉(のみど)を通った日私は真紅の薔薇になった」
(柳澤桂子『冬樹々のいのち』より)
「携はる放送の仕事の一つにて毒蛾育てゐる室に入りゆく」
(松田さえこ『さるびあ街』より)
「身体(からだ)もう返上したいといふ母よ椿のはなを食べにゆかんか」
(日高尭子『振りむく人』より)
「筑波根の新桑まゆの糸なれや心引くよりみだれそむらん」
(頓阿/新日本古典文学大系『中世和歌集 室町篇』より)
「逢わねども存在としてわが沼のごとき五十年充たして呉れぬ」
(今西久穂『冬の光』より)
「過ぎてゆく一日一日をまた秋の光となりて茶の花咲けり」
(新免君子『冬のダリア』より)
「公園のふん水に立つ尺のにじわがよろこびもそれほどの事」
(正宗敦夫『正宗白鳥 文学と生涯』より)
「青空にジューンベリーの花の白 今までのすべて号泣したい」
(小川佳世子『ジューンベリー』より)
「このビルの完成予定のきょうまでになんか変わっているはずだった」
(脇川飛鳥『テノヒラタンカ―ぎゅっと大切な言葉を、あなたの手のひらへ』より)
「降る雪も過ぐる時雨も沁まざれば我が深淵のかたち崩れず」
(安永蕗子『魚愁』より)
「病窓に下界を見れば辛うじて犬だとわかるかたちのゆらぎ」
(廣西昌也『神倉』より)
「おなじ地におなじ木ならび今日もまたおなじ葉と葉とあひ触れて鳴る」
(尾上紫舟『永日』より)
「別に嫌な人ではないが演出の方針なればギラギラと撮る」
(矢部雅之『友達ニ出会フノハ良イ事』より)
「残照のなかにおよげり鉄塔のさきの四角の台にひとゐて」
(香川進『氷原』より)
「踏み板が二つに割れて、君は聴いたか永山則夫の地に落つる音」
(飯沼鮎子『サンセットレッスン』より)
「道路脇の怒りの爆発、路上の会話の拒否、松林の無言、」
(リディア・デイヴィス作・岸本佐知子訳『ほとんど記憶のない女』より)
「子供より親が大事、と思ひたい。子供よりも、その親のはうが弱いのだ。」
(太宰治『桜桃』より)
「救急車のサイレンに二つの表情あり近づく不安離(さか)る哀感」
(岩田正『泡も一途』より)
「こんなにも太つてしまひし青柿よ六月まひる出会ひがしらに」
(足立晶子『雪耳(シュエアル)』より)
「蜂蜜にカリンの輪切り五つ六つ浮かせて風邪を待つごとくゐる」
(中地俊夫『覚えてゐるか』より)
「寒波襲来の予報流るる一月の晦日の夜更け母は逝きけり」
(小見山泉『みづのを』より)
「生け垣が羊の群れになる四月「大学通り」に咲くユキヤナギ」
(本条恵「春の羊はどこまでも」より)
「六月の雨吸ひつくしたる量感に山あり山の木木は立ちたり」
(三崎澪『日の扉』より)
「天からのサインが風に溶けてゐて諦めよといふ九月の朝に」
(新井蜜『鹿に逢ふ』より)
「大空のホールにみえざる群衆の椅子をひく音夏の雷鳴」
(渋谷祐子『青金骨法』より)
「こりもせず光のほうへ手を伸ばす私のような蔓 クレマチス」
(槌谷淳子『ホワイトライズ』より)
「下山する日は近づけり立ったまま齝(にれが)む牛の目はふかみどり」
(池本一郎『草立』より)
「月も日も吾等が爲の光ぞといひてし日より天地を知る」
(柳原白蓮『踏繪』より)
「立つと……あなたの背中どこまでも伸びてゆくように他人ね。」
(玲はる名『たった今覚えたものを』より)
「母死にて四日泣きゐしをさならが今朝(けさ)登校す一人また一人」
(吉野秀雄『寒蝉集』より)
「挽歌ふたつときの間に成り成りしことのふいに膝頭さむきわれかも」
(川井怜子『メチレンブルーの羊』より)
「割り算にあまりってのがあったでしょ給食よりもあれが好きなの」
(小野田光『蝶は地下鉄をぬけて』より)
「育ちては何の記憶もなからめど時にはわれも押すベビーカー」
(来嶋靖生『梟』より)
「残党を狩るごとく口腔内のフォワグラ舌で拭ひたりけり」
(三宅勇介『棟梁』より)
「我の所掌となりし機密の書庫の鍵に赤く小さきリボン付け持つ」
(鎌田弘子『海』より)
「のどを疾み苦しき朝は― 鳥の影 われより低く飛べるを見たり」
(藤井貞和『うた ゆくりなく夏姿するきみは去り』より)
「真木(まき)ふかき谿よりいづる山水(やまみづ)の常あたらしき生命(いのち)あらしめ」
(今井邦子『紫草』より)
「子を抱く妻残しきて時計塔に雀こぼるるさまに向かえり」
(石本隆一『木馬騎士』より)
「冬の医師とわれは思へり椅子ひとつ持ちきて夕べ白くゐるひと」
(犬飼志げの『鎮花祭』より)
「救急車が通り過ぎたら右肩がカパッと開いてカプッと閉じた」
(鳥本純平『言訳と鼻歌と時々くしゃみ』より)
「筑波嶺の 峯より落つる 男女の川 恋ぞ積もりて 淵となりぬる」
(陽成院「小倉百人一首」13番より)
「三十年経て生々しこの家に充員召集令状を夜に携へき」
(小島宗二『余響』より)
「沈み果つる入日の際(きは)にあらはれぬ霞める山のなほ奥の峰」
(京極為兼『風雅和歌集』春上27より)
「あかげらの叩く音するあさまだき音たえてさびしうつりしならむ」
(昭和天皇『おほうなばら』より)
「わが洞(うろ)のくらき虚空をかそかなるひかりとなりて舞ふ雪の花」
(石牟礼道子『海と空のあいだに』より)
「昨日まで莫妄想(まくもうざう)を入れおきしへなむし袋今破りてむ」
(太田道灌『名将言行録』より)
「白露の色は一つをいかにして秋の木の葉を千ぢに染むらむ」
(藤原敏行『古今和歌集』巻5秋歌下257より)
「時によりすぐれば民の嘆きなり八大龍王雨やめたまへ」
(源実朝『金槐和歌集』より)
「生きて来てふっと笑いぬ今正午百合ケ丘は坂ばかりある町」
(松実啓子『わがオブローモフ』より)
「散髪を終へたる頭持ち歩き何かひらめく寸前にあり」
(本阿弥秀雄『傘と鳥と』より)
「空高く手を 人体はみづからの腋下に口をつけえぬかたち」
(七戸雅人「本郷短歌」第三号より)
「十年(とせ)前に断(き)りたる脚(あし)ふと見ま欲しく、訊(たづ)ぬれば、あでやかに笑ふ看護婦」
(尾山篤二郎『さすらひ』より)
「ゆつくりと朝の机を拭き終へて場所が居場所に変はれる不思議」
(鈴木千登世『向きあふ椅子』より)
「今日は少し疲れてゐるのハロウィンの南瓜のやうに笑つて見せる」
(三澤吏佐子『シャドーグレー』より)
「アイスクリーム食べながらなんで君なのか考えて食べるアイスクリーム」
(長谷川麟『延長戦』より)
「危き足に走りゆく者なり追ふ勿れ笑ふ勿れ影を見送れ」
(小暮政次『暫紅新集』より)
「潮曇るむかうの島をねむらせてまひるまの空に游ぶアヂサシ」
(角田純『鴨背ノ沖ノ石』より)
「吾が妻の笑まひは清し傍にみどり児はまだうぶ毛ぬれたり」
(中島栄一『指紋』より)
「鳥は飛ばねばならぬ 人は生きねばならぬ怒濤の海を 飛びゆく鳥のように」
(坂村真民「はな」第176号 本多豊明筆「宝積寺と坂村真民の詩碑」より)
「「ぜんぶ好き」以外出口のない問いに「おっぱいです」で勝負して散れ」
(佐々木あらら『モテる体位』より)
「捨て猫の瞳の底に銀の砂 四月の雨はふいに降りやむ」
(山崎郁子『麒麟の休日』より)
「肛門が/一つしかない人間に/もう用はない/出ていきたまえ」
(青木麦生『阿佐ヶ谷ドクメンタ』より)
「デスマスクとられしおそれ水無月の油なす闇に顔をひたせば」
(玉井清弘『久露』より)
「それはもう判このようなさびしさを紙きれの上に押してもろうた」
(山崎方代『右左口』より)
「かぎりなくかぎりなき雨かぎりある生を厭ひてかぎりもあらね(いつまでもあめがふるのはいつまでもいきてゐるのがいやだからなの)」
(小池純代「短歌ヴァーサス」第二号より)
「するキスとしてくれるキスどちらかは選んでほしい しないのは無し」
(天国ななお「短歌男子」より)
「もう死にたい まだ死なない 山須臾(さんしゅゆ)の緑の青葉 朝の日に揺れているなり」
(鶴見和子『遺言』より)
「新しき瞬間がありネオンサイン必ず消えてまた灯るとき」
(初井しづ枝『藍の紋』より)
「<世界より私が大事> 簡潔にただ率直に本音を言えば」
(道浦母都子『夕駅』より)
「寝る前のしどろの闇の弾力は押し返しくるいきほひ持てり」
(斎藤すみ子『梅園坂』より)
「役にたつやうさまたげにならぬやう名札小さく〈ボランティア〉なり」
(木畑紀子『歌あかり』より)
「梢(うれ)たかく辛夷の花芽ひかり放ちまだ見ぬ乳房われは恋ふるも」
(小野興二郎『天の辛夷』より)
「波止場には大き魚の頭(ず)残されてその目見ており二月の空を」
(田中栄『海峡の光』より)
「はる四月白くさびしき花水木もうすぐ夫のなずき削らる」
(佐波洋子『時のむこうへ』より)
「六月の折鶴かなし八人の子供に長き死後とふ時間」
(木村輝子『海の話』より)
「「もう秋ね」「もう十月ね」もうという枕詞があるかのごとし」
(山田曜子『道化師の午後』より)
「鳥のこゑ松の嵐の音もせず山しづかなる雪の夕暮」
(永福門院『風雅和歌集』より)
「ハルウララ敗れることが義務であるごとく走りき泥濘の馬場」
(村田馨『疾風の囁き』より)
「月光の素足に触れてきみは地に繭は樹上に浮かべりわづか」
(森島章人『月光の揚力』より)
「夏ゼミの鳴き声達者七つ時うちで育ちし蟬と思えば」
(隈元榮子『なんでもない日』より)
「「さびしい時うさぎは死ぬ」と母言ひき呪文めきたるさびしき言葉」
(米田靖子『水ぢから』より)
「絶間なく漕がれ続けてきしみ鳴る日常といふ脆きぶらんこ」
(富野小路禎子『吹雪の舞』より)
・
・
・
<今後の予定>
【短歌表現】新第一章:新種千百人一首(行けるところまで!)
・
・
・
【予習:短歌表現】
1.短歌の歴史
短歌の歴史は古い。
その短歌を集めた、歌集の一つとされる万葉集は、7世紀後半から8世紀後半にかけて編まれた日本に現存する最古の和歌集である。
和歌は、万葉集の時代以来、1300年余りにわたって脈々と詠み継がれて来た日本独自の文学形式といえる。
古い歌にも、その良さがある。
和歌とは、中国の詩である漢詩に対して、日本における大和歌の意味で使われた。
和歌には、奈良時代までは、五音と七音を組み合わせた様々な形式のものがあったが、平安時代以降、「五音・七音・五音・七音・七音」五句三十一音の短歌以外はあまり作られなくなった。
現在では、江戸時代までの作品は和歌、明治時代から後の作品は短歌と呼んでいる。
現在使われている仮名使いは、1946年11月に告示されたもので、それを新仮名遣いと言うが、それ以前(平安期以来)使われてきた仮名遣いは、「歴史的仮名遣い」「旧仮名遣い」と呼ばれる。
どちらを使っても良い事になっているが、一首の中では、「歴史的仮名遣い」と「旧仮名遣い」を混合させない事となっている。
さらに、一首の短歌は、口語体で詠んでも文語体で詠んでも、口語体の中に文語体が混ざっても、良い事になっている。
ただ、文語体で詠むなら、品詞の分解や動詞・助動詞などの活用形、接続の法則などの文語文法についての理解が欠かせない。
短歌においては、口語と混用される文語はそう多くないので、その部分については誤りがないか確認する必要がある。
内容によって文語体の方が良い場合と、口語体の方が良い場合があるが、現代短歌は、外来語なども多用されるので、口語で詠むのが、主流になって来ている。
歌人にとって、自分で納得のいく一首が出来た時の喜びは、他の何にも、換え難いものである。
2.短歌の世界
近代以降の短歌は、自然に触れ、生活の場で、また、社会の流れの中にあって、人間の心の在り様を表現したものである。
それは、すべてが、抒情であるとも言える。
しかし、短歌の世界では、対象の捉え方を、叙景歌(自然の風景等を詠んだ歌)、叙事歌(事実をありのままに述べた歌)、抒情歌(感情、感動を述べ表した歌)という分け方をしてきた。
便宜上、直接的に短歌の対象となった事柄を捉えて、何々詠という呼び方をしている。
このように短歌は、人の感情や感動を伝える抒情詩なので、事実や情報を伝える記事や報告ではなく、意見や研究を述べる評論や論文でもない。
つまり、詩(韻文)であって、散文ではないのである。
議論や説明ではなく、詩情があるかどうか、心の波立ちが出ているかどうかということである。
短歌では、一首に、ひとつの心情だけを読み込むようにする。
例えば、一番鮮やかに心に残ったこと、胸の高鳴りを覚えたこと等を思い出してみる。
また、自分の身の回りを振り返ってみるのもよい。
そして、日常を観察する場合、情景ばかりではなく、自分の内部の観察も必要である。
さらに、観察したことを、自分の言葉で書き著してみる。
そこで、始めて自分のものになる。
また、一つの素材で、さまざまな角度から歌うとき、連作という方法がある。
なんといっても31音なので、一首に盛り込むことのできる心情には、限度がある。
何首かに分けることで、一首を、すっきりさせることができる。
普段の生活の中で、断片でもいいので、歌を思いついたらメモをしておくと、落ち着いた後で、ゆっくり短歌を詠むことができる。
人間が生きていること自体が大切であるように、短歌とは、人生そのもの、人間そのものということが言える。
3.歌の世界
歌は、詩形のうえからも、簡潔な圧縮された表現を求める。
短歌の形式がわかれば、字数を数えながらでも、短歌を作ることはできる。
しかし、ただ、漫然と短歌を作ろうとしてもできるものではない。
自分の見たこと、感じたことが、短歌の内容なので、一首の短歌に表現してみたいというものが、まず、なければならない。
そして、人の作品は、これを読むとき、理屈で読まず、胸で受け止めること。
どんなに初心者の作品でも、決して、自分が優位に立って見ない。
自分にないよさを見逃さない。
整って淡い作品より、欠点があっても、内容の濃い作品のほうが、おもしろみがある。
必死に作った作には、上手下手を超えて、心打つものがある。
歌のよさは、声調、調子にある場合が少なくない。
語気の生きている作品を見落としてはならない。
仮名遣いの誤り、語法の違い、日本語の成長から外れていることなどは、極めて積極的に改める。
丁寧に、しっかり歌を作ることが大事である。
五七五七七に、言葉をあてはめれば、形のうえでは確かに短歌である。
しかし、
「よい歌」
かどうか。
そもそも、どんな歌が
「よい歌」
か、常に、問い続けていることが大事である。
日本語は、工夫しだいで、うまく五音七音にはまっている。
五音も、七音も、奇数であることも、重要視されている。
奇数なので、一句の中の音数が、半々にならない。
それが、味わいを生むというわけである。
短歌のことをよく、
「みそひともじ」(三十一文字)
と呼ぶが、実際には、
「文字」
ではなくて、
「音」
のことである。
あるいは、
「みそひともじ」
とは、和歌を、すべて、ひらがなで書いていた頃の名残の呼び方ともいえる。
全部、ひらがなで書けば、三十一文字ちょうどか、それに近いものになる。
現在の短歌は、漢字と仮名の交じった表記をするのが普通である。
短歌には、とても広い幅がある。
まず、一つには、句切れがある。
句切れとは、短歌をいくつかの部分に分ける場所を設け、それぞれの部分で、いろいろなことを述べながら、全体で、別次元のことを詠いあげる、というものである。
一首の中に句切れを入れることによって、短歌で表現されるものの幅はぐんと広がる。
4.短歌を詠む意義
短歌を作ってみたいと思ったこと、それが、何より大切である。
それは、短歌をつくることに価値があるか、ということを問うことからはじめるものではない。
短歌を詠むこと自体が大切なのであり、意義のあることなのである。
人間が生きていること自体が大切であるように、短歌とは、人生そのもの人間そのものなのである。
生活の実感を大切にし、自分の思うがままを述べていくことは、自分にとっての安らぎであるばかりでなく、人や物等と繋がっていく。
短歌を作る意味とは、人間らしさを求めていくことにつながる。
自分の外側は写真で写すことができる。
しかし、その写真は、内面までをも描くことはできない。
それだけに、短歌は、一人ひとりにとって大切なものである。
二つとないその人らしさや、その瞬間を残しておきたいと思うことは、人として、当然の要求であると考える。
人間らしさを求めるがゆえに短歌なのである。
したがって、手間暇かけて短歌を作ることに意味がある。
短歌を作っていくということは、 単に、趣味的なことなのではなく、その人の生き方を支えていくものである。
人間と言うのは、人と繋がりつつ、孤独なものを支えて生きている。
ただ、それを歌うことで、寂しい時も生きる意欲や張りを与えてくれる。
我々が、折に触れて短歌を作ろうという思いになる根底には、日本語、そのものの特色が生きている。
単に、鑑賞するということだけではなく、実作していくことが重要である。
5.短歌を詠む目的
短歌を作る目的とは、人間らしさを求めていくことになるのではないかと考えられる。
自分の外側は、写真で写すことができるが、内面については、そのようにはいかない。
言い換えれば、心の内が、短歌と言うことになる。
誰しも、再びはない、一人ひとりの、この瞬間を、その人なりに、残しておきたいと思うのは、当然の欲求である。
人間らしさを求めるがゆえに、短歌なのである。
要するに、短歌を詠むにあたっては、手間暇をかけることに、意味がある。
短歌には、深い味がある。
その人の、折に触れての感情表現でありつつ、その人の、生き方の象徴になっている。
短歌は、文献や報告と異なり、自分の感情の高まりを表現するものであって、抒情詩の一つであるといわれている。
しかし、それは、感情を、そのまま表現することではない。
例えば、感情的に悲しいというよりも、その感情のもとになったところを描写するほうが、感情がよく伝わる。
短歌を詠むにあたっては、心の思いを述べるにしても、事柄を通して、正確に伝えられることが求められる。
描写力とは、冷静に感情を押さえて、表現することである。
しかし、散文と違って、感動そのものが、根拠になければならない。
そして、リズムがある。
言葉の選び方、並べ方、リズムの取り方等を吟味して、歌の姿を整えること、それを、「推敲」と言う。
言葉を選び、姿を整えるといっても、別に、難しい規則があるわけではない。
その人、その時、その場所にあった姿であればよいのである。
わからない表現を、わかりやすく、あいまいな言い方を、くっきりと鮮明に、自分の心に、一番ぴったりした表現に、整えていくのである。
6.短歌の意義と魅力
短歌とは、和歌の形式の一種である。
それは、五・七・五・七・七から構成される。
その短歌は、五句体の歌で、遥か昔から詠まれ長い歴史を生きてきた形である。
その短歌は、五・七・五・七・七の31文字から構成される。
そして、この短歌は、三十一文字(みそひともじ)といわれることもある。
このように短歌とは、一定の形式によって心を表現する、長い伝統をもった文芸である。
そして、短歌を詠むときには、自らの作品を受け止めてくれる読者の存在を想定することが求められる。
そこに、言葉と他者に対する不信感の広がっている現代社会における、短歌の意義と魅力がある。
初めて短歌を読む場合には、難しいことは考えず、
「まずは31文字で詠んでみる」
ことを心がける。
そこで、和歌のもつテンポやリズム等をつかみ、徐々に字余り、字足らずの短歌を詠んでいくことが好ましい。
また、現代短歌において、季語の有無は、それほどこだわらない。
俳句では、季語が必須といわれる。
俳句の源流といえるほど古くからある短歌において、季語については、特に、縛りはない。
しかし、短歌では、31文字という不自由さをもうけ、文章としての自然さよりも、リズムやテンポを優先させることで、詠み手独自の新しい表現が生まれる。
その新しい表現には、詩歌性ともいうべき文学的なものが生まれてくる。
生活の実感を大切にし、自分にとって、思うがままに述べていくことが、大切である。
それは、自分にとっての安らぎであるばかりでなく、人や者等と、繋がっていくことを意味する。
つまり、短歌を詠むことは、人間らしさを求めていくことにつながる。
それは、極論すれば、あらゆる人に、短歌を作ることが求められていることを意味する。
短歌には、万葉集以来、千数百年の命脈を保っているのも、それぞれの時代に生きてきた人の人間らしさを求める思いがあってのことである。
短歌は、自分の感情の高まりを表現するものである。
そのため、短歌は、感動や感情を伝える抒情詩の一つなのだといわれている。
7.短歌の作り方
短歌とは、韻文である和歌の一形式で、五・七・五・七・七の五句体の歌体のことである。
三十一文字ではない、あくまで、三十一音なのである。
普通の五十音、濁点、半濁点がついたものは一音。
きゃ、きゅ、きょ、しゃ、しゅ、しょ、など小さいヤ行音(拗音)を伴うものは、それで一音。
小さい「っ」(促音)は、一音。
長音「-」は、一音となる。
定型を守るとは、できるだけ、五・七・五・七・七に揃えることである。
この形は、短歌が、長い歴史を生きてきた証の一つである。
短歌が、長い歴史を生きてきたのは、この定型五・七・五・七・七の魅力にあるといってよい。
短歌は、三十一文字という不自由さを設け、文章としての自然さよりも、リズムやテンポを優先すると、詠み手、独自の新しい表現が生まれ、そこに、詩歌性というか、文学的な何かが生まれてくる。
三十一文字きっちり守るようにして詠むと、日本語について、研ぎ澄まされる。
詠み手は、
「どの単語と互換しようか」
と悩むし、それに合わせて、
「てにをは’の助詞はどれにしようか」
「漢字、ひらがな、カタカナのどれを使おうか」
等、三十一文字の制限のなかで、精一杯遊ぼう、伝えようと、思考をめぐらすようになる。
短歌は、一首、二首と数える。
短歌の何首かのかたまりを、連作と呼ぶ。
例えば、五首連作や十首連作は、それぞれ、短歌五首、十首のかたまりである。
連作には、タイトルがついていることが多い。
よくある情景を書きとめただけでは、短歌にはならない。
この短歌では、それに作者の発見を加えることで、おもしろさが生まれる。
さらに、三十一音という短い音数の中で、くり返しや反対の意味のことばを用いることで、リズム感や変化が生まれて歌になる。
短歌をつくるときは、情景と発見、あるいは、発見を含んだ情景を考えればよい。
どのようなとき、誰に向かって歌うのかということも知らなければ、つくる気分に持っていくことが難しい。
短歌は、独り言の歌と、相手に呼び掛ける歌との二つに、大きく分けられる。
ふと心に浮かんだ感情や、強い印象を受けたできごとを呟く場合もあれば、誰かに思いを伝える歌にする場合もある。
短歌は、人の感情・感動を伝える抒情詩である。
それは、事実や情報を伝える記事や報告ではなく、意見を述べる評論でもないことを意味する。
つまり、短歌は、詩(韻文)であって、散文ではないのである。
短歌は、詩情があるかどうか、心の波立ちが出ているかどうか、ということである。
一首で、全てを言おうなどと思うのではなく、少しずつ、何首もの歌に、詠めばよいのである。
大切なのは、プロセスを詠むことで、結論を言うことではないということである。
短歌を詠む中で、難しいのは、結句にあたる第5句である。
「初句は軽く、結句は重く」と言われるが、これは、歌の中心になるところは、結句に据えるほうが、落ち着いた歌になる確立が高いという意味である。
どのように結んでもよいが、比較的多いのは、助動詞・動詞・形容詞など用言の終止符で終わるものや、名詞・用言の連体形で終わるもの、助詞で終わるものなどがある。
また、日本語では、古くから、主語を省略しても分かるように、敬語が発達しており、遠回しに、相手のことを、述べることもある。
8.短歌表現の面白さ
日常生活をテーマにした短歌は、生活の中でも、例えば、仕事・学校・家事・育児・介護に焦点を絞って詠むと、より、自分らしさが出てくる。
生活の中でも、ちょっと余裕のある事柄を詠むのも、よいかもしれない。
短歌を詠むときに気をつけなければならないことは、独りよがりにならないことである。
趣味、娯楽には思い入れがあり、文言が、不明瞭になってしまう可能性がある。
短歌というと、自分に籠もりがちになることがある。
生活の一瞬でも、空を見たり、山を見たり、海を見たりすると、思い込みから解放され、新しい自分に、気がつくものである。
本当に、現地、現物に関わりながら詠むのとは、現実味が違ってくる。
そうでないと、当事者意識が希薄になり、無責任な歌になってしまうからである。
短歌の中には、日常でも、あまり使わない表現が、見受けられることがある。
その例として、短歌の実作の中に見られる「わが夫(妻)」や「わが子(娘)」等があげられる。
短歌の言葉の中に、あえて人の名前を言わずとも、それを示すところに、短歌表現の面白さがある。
短歌では、他人の目からは、どう見えるであろうかと考えるところに、真情の深味が、出てくるはずである。
短歌を作ろうと思うときには、何かしらのテーマに、心が働くときなので、一首だけで収まるはずがないということが本意である。
全体の流れの中で、一首が生きてくるように表現すれば、良いのである。
言い過ぎにならないようにするためにも、連作が何よりである。
また、あまり、飾り立てるよりも、日常生活の中の当たり前の言葉が、短歌として生きてくる。
短歌を作ることで、人は、その感性が豊かになる。
ものをよく観察する目が養われ、語彙も豊富になってくる。
また、自作の短歌を発表しあうことで、私たちの気持ちも通じ合い、生活圏内の雰囲気にも、良い効果が生まれる。
古の学びとともに、日常生活の中での周りの風景や四季の移り変わり、そして、かけがえのない人生について、観察してみて、歌にする。
このような取り組みを通して、一人の人間として、生きていく一瞬一瞬が、今までにはなく、新鮮に見えてくるものである。
9.短歌の作品を読むことの有意性
時代の移り変わりとともに、私たちの生活は変化している。
自然から離れ、都市で生活する人が増えた現代では、「自然詠」が減り、「都市詠」が増える傾向にある。
また、超高齢社会を反映し、「介護詠」という分類名も耳にするようになった。
テーマとして、例えば、家族のことを歌うのは、毎日顔を合わせたりはしているだけに、かえって難しいところがある。
それだけに、当たり前のところに光をあてる工夫が必要であり、おもしろさと難しさがある。
自分の詠んだ歌を、人に読んでもらうということは、例えて言えば、他人と会うのと同じことである。
TPOと言うように、人に会うには、やはり、それらしい服装がある。
ということで、言葉の選び方、並べ方、リズムの取り方などを吟味して、歌の姿を整えることを「推敲」という。
わからない表現をわかりやすく、あいまいな言い方をくっきりと鮮明に、自分の心に、一番ぴったりした表現に整えていく。
さらに、優れた短歌の作品を読むことによって、ものの見方を悟ることができる。
つまり、作歌と並行して優れたものを読み、読んで得たものを作歌に実行するという努力を積み重ねて、物の状態を、確実に言い当てた歌、輝きと響きとに満ちた歌ができるようになる。
10.短歌の本質
短歌は、理論や技巧を覚えただけで詠めるものではない。
自分の心と素直に向き合って、その心の核を言葉にすることが、必要不可欠である。
心の核を掴めるようになるためには、名歌を多く詠み、推敲し、それを、長く続けることである。
また、ひとつの歌をめぐって、作者と読者の思いや楽しみは、別であってもかまわない。
短歌は、内容の難しいところを詠む必要はなく、単純な中に、何か情のようなもの、心のようなものが出ていれば、それでいいのである。
それが案外難しいという人もいるが、とにかく、はじめから難しいところを考えないで、素直に短歌を作ってみてほしい。
人が短歌を作ることで、周りの読み手が、その人の生き方をも支えてゆくものである。
[テキスト]
(出典「短歌表現―コミュニケーション技術における学習効果の検討―」土永典明(著)
【授業:短歌のことを考えました】
カテゴリー「短歌のことを考えました」の47件の記事
【復習:意外と知らない百人一首の世界を探求】
【参考記事】
【参照文献】
コレクション日本歌人選 源実朝 三木麻子 著(笠間書院)
コレクション日本歌人選 菅原道真 佐藤信一 著(笠間書院)
コレクション日本歌人選-紫式部 植田恭代 著(笠間書院)
伊勢物語・大鏡・古事談・徒然草 新編日本古典文学全集(小学館)
一条摂政御集注釈 平安文学輪読会(塙書房)
院政期政治史研究 元木泰雄 著(思文閣出版)
栄花物語・大鏡 新編日本古典文学全集(小学館)
王朝の映像 角田文衛 著(東京堂出版)
王朝の映像-平安時代史の研究 角田文衛 著(東京堂出版)
王朝の歌人9 乱世に華あり 藤原定家 久保田淳 著(集英社)
王朝の変容と武者:古代の人物6〈三条天皇 藤原道長との対立〉 中込律子 著(清文堂出版)
王朝歌壇の研究 桓武仁明光孝朝篇 山口博 著(桜楓社)
歌合集 日本古典文学大系(岩波書店)
季刊墨スペシャル 百人一首(芸術新聞社)
貴族社会と古典文化 目崎徳衛 著(吉川弘文館)
金槐和歌集 新潮日本古典集成(新潮社)
愚管抄 日本古典文学大系(岩波書店)
訓読 明月記 今川文雄著(河出書房)
古事談・保元物語 新編日本古典文学全集(小学館)
後撰和歌集・拾遺和歌集・後拾遺和歌集 新日本古典文学大系(岩波書店)
後鳥羽院御口伝・井蛙抄 歌論歌学集成(三弥井書店)
後鳥羽院御口伝・近代秀歌 日本古典文学大系 歌論集 能楽論集(岩波書店)
最勝四天王院障子和歌全釈 渡邉裕美子 著(風間書房)
三条天皇 倉本一宏 著(ミネルヴァ書房)
紫式部集全釈 笹川博司 著(風間書房)
人物叢書 菅原道真 坂本太郎 著(吉川弘文館)
崇徳院怨霊の研究 山田雄司 著 (思文閣出版)
袋草紙考証 雑談篇 藤岡忠美 他 著(和泉書院)
大鏡 新編日本古典文学全集(小学館)
大和物語 新編日本古典文学全集(小学館)
大和物語・栄花物語・大鏡 新編日本古典文学全集(小学館)
淡光ムック 百人一首入門 有吉保・神作光一 監修(淡光社)
藤原定家『明月記』の世界 村井康彦 著(岩波新書)
読み下し 日本三代実録 武田祐吉・佐藤謙三 訳(戎光祥出版)
悲境に生きる 源実朝 志村士郎 著(新典社)
百人一首 定家とカルタの文学史 松村雄二 著(平凡社)
百人一首 鈴木日出男(ちくま文庫)
百人一首(全) 谷 知子(角川ソフィア文庫)
百人一首に絵はあったか 定家が目指した秀歌撰 寺島恒世 著(平凡社)
百人一首の作者たち 目崎徳衛 著(角川書店)
百人一首の新考察 吉海直人 著(世界思想社)
百人一首研究必携 吉海直人 編(桜楓社)
扶桑略記 新訂増補国史大系(吉川弘文館)
平安朝 皇位継承の闇 倉本一宏 著(角川書店)
平安朝歌合大成 萩谷 朴 著(同朋社)
別冊太陽 百人一首への招待 吉海直人 監修(平凡社)
保元・平治の乱 元木泰雄 著 (角川ソフィア文庫)
枕草子・俊頼髄脳・袋草紙 新編日本古典文学全集(小学館)
訳注 藤原定家全歌集 上下 久保田淳 著(河出書房新社)
歴代宸記 増補史料大成(臨川書店)
蜻蛉日記ー新編日本古典文学全集(小学館)
近代秀歌 (岩波新書) 永田和宏(著)
現代秀歌 (岩波新書) 永田和宏(著)
人生の節目で読んでほしい短歌 (NHK出版新書) 永田和宏(著)
【参考図書】
「日本うたことば表現辞典 全15冊揃」

万葉から現代の和歌・短歌・俳句をテーマ別・表現手法の修辞別に分類した我が国文学史上最大規模の作品辞典。
「わたくしが『日本うたことば表現辞典』の第一期の最初の巻に監修のことばをよせたのは1997年のことであった。
そして第二期の最終巻に筆をとったのが2010年である。
この間、書肆の遊子館の辞典編集部は、とどまることなく編集作業を着実に積み上げてきたのである。
おそらく、日本の詩歌文学において、このような一つのテーマで、持続的に、しかも古代から現代の領域に及んで体系的に纏めた出版企画は少ないと思う。
第一期は「うたことば」の表現分野の構成であり、第二期は表現手法(修辞)の構成となっており、この二つの必然の組み合せにより、読者は日本の「うたことば」の全容を知ることができるであろう。」〔監修者序より〕
通巻1・2 日本うたことば表現辞典—植物編(上・下)
通巻3 日本うたことば表現辞典—動物編
通巻4 日本うたことば表現辞典—叙景編
通巻5 日本うたことば表現辞典—恋愛編
通巻6・7 日本うたことば表現辞典—生活編(上・下)
通巻8・9 日本うたことば表現辞典—狂歌・川柳編(上・下)
通巻10・11 日本うたことば表現辞典—枕詞編(上・下)
通巻12・13 日本うたことば表現辞典—歌枕編(上・下)
通巻14 日本うたことば表現辞典—掛詞編
通巻15 日本うたことば表現辞典—本歌・本説取編
「王朝百首」(講談社文芸文庫)塚本邦雄(著)

百人一首に秀歌はない――かるた遊びを通して日本人に最も親しまれる「小倉百人一首」(藤原定家・撰)にあえて挑戦、前衛歌人にして“現代の定家”とも称されたアンソロジスト塚本邦雄が選び抜き、自由奔放な散文詞と鋭い評釈を対置した秀歌百。
『定家百首』『百句燦燦』と並び塚本美学の中核であると同時に、日本の言葉の「さはやかさ」「あてやかさ」を現代に蘇らせんとする至情があふれる魂魄の詞華集である。
「英語で読む百人一首」(文春文庫)ピーター・J・マクミラン(著)

日本の美と心を写しだす「百人一首」。
日本人なら誰もが親しんできた和歌が美しい英語で生まれ変わりました。
オリジナルの和歌と英訳バージョンを見開きで一覧できるレイアウト。
英語の美しさを味わうことができるのはもちろん、英語であらためて読み直すことで、なじみ深かったあの歌この歌の「意味」を、もっと深く理解することもできます。
英語を知りたい読者にも、日本の美をもっと知りたい読者にもうってつけの一冊です。
アイルランド生まれの学者の視点から見た『百人一首』についての解題も収録。
新たな眼で日本古典文学を読み解く面白さも。
「百首でよむ「源氏物語」 和歌でたどる五十四帖」(平凡社新書)木村朗子(著)

今から約1000年前に執筆された『源氏物語』。
その作者である紫式部は歌人でもあった。
『源氏物語』には795首の和歌が含まれており、それらは登場人物のパーソナリティーをうまくとらえている。
本書はそのなかから100首の和歌を厳選し、現代語訳、意図などをわかりやすく解説。
『源氏物語』の原文や現代語訳を読むときに手元に置いておきたい1冊。
「日本とは和歌 国史のなかの百首」松浦光修(著)
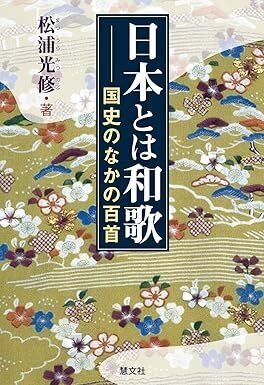
長年にわたり日本思想史を研究してきた著者が厳選した、神代から現代に至る100人の名歌、100首を解説!
「おやすみ短歌 三人がえらんで書いた安眠へさそってくれる百人一首」枡野浩一/pha/佐藤文香(編著)

人気歌人・作家・俳人がコラボし、安眠がテーマの短歌を百首集め、見開きで紹介する現代版「百人一首」。
短い文章付きなので、短歌の読み方がわからなくても楽しめます。
「安野光雅きりえ百首 俵万智と読む恋の歌より」安野光雅(著)

俵万智が現代短歌から選び出した恋の歌に、安野光雅が美しい切り絵を添える。
朝日新聞日曜版連載をまとめたもの。
既刊「あなたと読む恋の歌百首」が文章中心だったのに対し、今回は切り絵の作品集として編集されている。
「あなたと読む恋の歌百首」(文春文庫)俵万智(著)

出会い、初デート、新生活から失恋、別離まで。
満ち足りた幸せいっぱいの恋があれば、心が張り裂けそうな辛い恋もある。
伊藤左千夫、若山牧水、石川啄木、北原白秋、佐々木信綱、与謝野晶子、岡本かの子、中城ふみ子、寺山修司、穂村弘――。
新旧百人の歌人たちがうたった百首の恋の歌を俵万智が選んで、自己流の解釈が添えられた、ユニークな短歌鑑賞かつ恋愛手引きの書。
何度も読み返したくなる、宝石箱のような一冊である。
【読書メモ】
「英詩訳・百人一首香り立つやまとごころ」(集英社新書)マックミラン・ピーター(著)佐々田雅子(訳)

[ 内容 ]
『小倉百人一首』はこれまでも英語で翻訳出版されたことがあるが、従来の翻訳では和歌の世界を充分に表現しえなかった。
この言葉の結晶の新訳に、アイルランド生まれの著者が挑戦。
かくして、まったく新しいアプローチによって和歌に重層的に折り込まれた“やまとごころ”を英語で表現してみせた。
その翻訳は、英語の詩としても通用する。
ドナルド・キーン博士の高評を得て、原著は二〇〇八年コロンビア大学出版より刊行。
同年度日本翻訳文化特別賞等を受賞し、学問的にも評価された。
本書は平易な英語による『小倉百人一首』翻訳の決定版である。
[ 目次 ]
マックミラン訳の魅力(ドナルド・キーン)
日本語版のための序論
英詩訳百人一首
原書版序論
マックミラン訳が解き放したもの(アイリーン加藤)
[ 問題提起 ]
「これやこの ゆくもかえるもやくしては しるもしらぬも ひゃくにんいっしゅ」
失礼。
英詩訳も凄いが、その至らぬところを通して、短歌という形式の凄さ、そして、それを可能にした日本語の凄さを、改めて感じることの出来る良著。
「ひさかたのひかりのどけき春の日に」ひもとくのに。最上の一冊だ。
本書は、日本一、すなわち、世界一読まれてきた日本語詩集の、最新にして、最良の英訳。
ドナルド・キーンが、こう太鼓判をおしているぐらいだ。
「五七五(七七)というのはどうやら人類的普遍性のあるリズムであるようで、注意すると欧米のポップスにもこれが登場しているのがよくわかるぐらいだ。
こういう「隠れた」五七五だけではなく、今や haiku の方は世界語になっている。
その証拠というわけではないが、OS X Leopard 内蔵のスペルチェカーは haiku を通す。
tanka を通さないのがいささか残念だ。」
それだけに、百人一首の訳者たちは、「五七五七七」の強い呪縛に、支配されてきた。
勢い、それを優先するがあまり、元の歌の意が失われてしまいがちであったのである。
[ 結論 ]
本書は、それを、敢えて捨てたところに、凄さがある。
たとえば、冒頭のパロディの元の句、
「これやこの ゆくもかへるも わかれては しるもしらぬも あふさかのせき」
が、訳者の手にかかるとこうなる。
So this is the place!
The crowds,
coming
going
meeting
parting
friends
strangers,
known
unknown---
The Osaka Barrier.
これほど「これやこの」感、「ゆくもかへるも」感、「しるもしらぬも」感に溢れた訳が、かつてあっただろうか。
そのために、あえて「逢坂の関」を「外だし」しているところは、たしかに、原作忠実派の格好の攻撃対象になりそうだが、もし、蝉丸が、英語を話せたら、蝉丸も、また、本首に、一票投じると、私は想像する。
しかし、である。
それでも、やはり、著者の訳は、文脈を補いすぎていると、感じてしまうのである。
例えば、これ。
おそらく百人一首の中でも最も「わかりやすい」一首。
「君がため 惜しからざりし 命さへ 長くもがなと 思ひけるかな」
I always thought
I would give my life
to meet you only once,
but now, having spent a night
with you, I wish that I may
go on living forever.
間違い、ではない。
確かに百人一首は、
「よくもまあこんな猥褻な詩を小学生に教えますね」
というほど色恋の歌(色恋の文脈でないと成立しない歌)が多いが、しかし、この一首は、そうでない文脈でも、成立するところに、その妙味があるのではないか。
"having spent a night with you"とは。
世阿弥がこれを見たら、
「ああ、花が散ってしまう」
と、憐れんだかも知れない。
私なら、こうするだろうか。
詩には、なってないかもしれないが。
I would die just to see you.
Now that I have seen you,
I wish to live forever with you.
なんと、これでも、"I have seen you"という文脈を補っている。
本当のところ、こういう文脈だったかどうかは、わからないのに。
短歌や俳句の魅力は、人それぞれ、いや、一首一句、それぞれにあるのだろうけど。
私にとってのそれは、
「異なった文脈で異なるように成立すること」
である。
その妙を楽しむには、本書の訳は、彩りが強すぎると感じた。
しかし、よくよく考えてみれば、対象読者にとって、ピンとこない文脈を、訳注などで補うのは、翻訳の常套手段であり、王道でもある。
異なる文脈で使いたいのであれば、自分で読み直せばいいのだし。
それにしても、百人一首というのは、
「門前の小僧習わぬ経を読む」
の格好の例ではないか。
百人一首は、高校時代に覚えたが、もちろん、その時には、ほとんどの首は、意味不明だった。
「世をうぢ山と人はひふなり」なんて、「蛆山」と解釈してたぐらいだ(^^;
年を追うごとに、その意味がつかめる(わかるとは、とてもいえない)なって、なんとすごいものを知らぬうちに、もらったのだと、感動することしきりである。
[ コメント ]
今日日の小学生は、百人一首を覚えたりするのだろうか。
「蛆山」でいいから、覚えておいてほしい。
後で、宝の山に化けるのは、私が、惜しからざりし命をかけて、お約束します。
【関連記事①】
生きるって短歌のようなものね。
朝顔、蝉、蛍、時代の情操と音律。
【改訂版】今日はミュージック♪の日(短歌と詩と音楽)
声なき声を聞けるか!?
【関連記事②】
【詩論雑考】私(あなた)があなた(私)のことをどう考えられるのか?
【小品文】晴耕雨読(縦書きの国)
【エッセイ】詩と暮らす-うたう(歌う×詠う×訴う)-
【漫筆】語幹と語感と五感
【迷文】短歌の文字数も端数処理してみたら・・・
【備忘録】2023年度版trafalgar・選短歌集
【宿題帳(自習用)】ふと目を向けた風景、しゃがんだ時に見えるもの。
【雑考】幻想文学から幻想的な短歌への誘い(その1)
【雑考】幻想文学から幻想的な短歌への誘い(その2)
【一筆】絵と短歌と詩と
【雑考】絵画的風景写真と絵画と短歌と
【一筆】詩はうたに恋している ことばは音楽に恋している
【新鋭短歌シリーズ】生きたことばを掬う短歌たち。生活に「うた」の彩りを。 「うた」のある暮らしのすすめ
【現代短歌クラシックス】星の林と遊び種
【現代歌人シリーズ(その1)】青空の青ってどんな色?
【現代歌人シリーズ(その2)】言葉に選ばれる
【現代歌人シリーズ(その3)】心で感じなければ
【本日の思いつきバックナンバー】「百人一首(近代・現代短歌)ある世界」版バックナンバー
【自主勉ノート】三字熟語(一字+一字+一字):雪月花
【1週間短歌ごはん生活】4月に旬を迎える食材と短歌
【1週間短歌ごはん生活】5月に旬を迎える食材と短歌
【1週間短歌ごはん生活】6月に旬を迎える食材と短歌
【1週間短歌ごはん生活】7月に旬を迎える食材と短歌
【事実】勉強のいちばんの成果
【普段歩いている道をよく見渡せば】ほんの少し優しい風景に出会えるかもしれない
【音楽とお酒とうた】時代が鳴らす音やうたに耳を傾ける
【愛する世界】音楽と文学
【観察するとは自分自身を体験すること】色んな音を表現した随筆や短歌
【身近な坂にまつわる物語】坂と言えば何が思い浮かびますか?
【探偵モーニングスクープ?】調査結果は、毎回、大雑把。けれども、いつも明るく愉快痛快がモットーの探偵事務所発。
【コンビニ誕生から半世紀】短歌が詠んだコンビニ半世紀
【猫を踏めば】そこから事件が始まる
【短歌系男子】究極の選択的短歌
【短歌表現】紫陽花
【秘密の鍵】うまく期待をコントロールできるようになるには?
【心の故郷】「森山直太朗のにっぽん百歌」と「迢空百歌輪講」
【今日は何の日】一年の折り返しの日・真ん中の日
【関連記事③】
[テキスト]
「百人一首の秘密 驚異の歌織物」林直道(著)

[参考記事]
百人一首の成立、いつ誰がどのように選んだのか。
三流歌人なぜ選ばれた 百人一首めぐる5つのナゾ
[異種百人一首事例紹介]
[参考図書]
「地球儀のスライス A SLICE OF TERRESTRIAL GLOBE」(講談社文庫)森博嗣(著)

「定説というのか、これが真実だ、といった唯一確実な回答は存在しません。
ただ・・・
僕は、西之園先生の仮説を伺って、非常に納得しました。
つまり、それで安心し、自分で考えることを放棄することができたのです。」(森博嗣著「石塔の屋根飾り」より)
藤原定家は、百人一首の和歌を、自分なりのルールに従って歌を選んだと言われており、その選定基準を明かしておらず、いろいろな人が研究をしていますが、本書に依ると、
「百人一首の現在」 中川博夫/田渕句美子/渡邉裕美子(編)

定家が撰者である「百人秀歌」を基にして、
「御所本百人秀歌 宮内庁書陵部蔵」(笠間影印叢刊)久曽神昇(編)

鎌倉中期以降に、別の人物によって編さんされたのが百人一首であると結論付けています。
[参考記事]
そうであれば、益々、どういった選定基準で編纂されたのか不明・・・、と言うことで、前述の「新種千人一首」の選考基準も、ナイショってことで良いよね(って程の選定基準ではないんだけどね)(^^)
さて、近代・現代短歌を中心に選考して行く中で、選定から外れた短歌の中から、良い歌だったよなあ~って感じた短歌達を、一挙に紹介しておきますので、お時間有れば、現実世界と、何処かでリンクしている色んな短歌表現での世界観を、
見て・・・
読んで・・・
感じて・・・
考えて・・・
先の見通せない闇の中に進むすべを・・・
想いの力で、超えみて下さい(^^♪
[異種百人一首選考外短歌(その1)](229首)
「〈あげた愛〉〈ほしい愛〉とのバランスを計りかねてるセーの法則」
(田中槐『ギャザー』より)
「「ありがとう」よりも「ごめんなさい」が増え 僕の日記が遺書に近づく」
(島井うみ『うたらば』より)
「「とりかえしのつかないことがしたいね」と毛糸を玉に巻きつつ笑」
(穂村弘 『シンジケート』より)
「「ほんとうは誰も愛していないのよ」ペコちゃんの目で舐めとるフォーク」
(ゆず/穂村弘編『短歌ください』より)
「「好きだつた」と聞きし小説を夜半に読むひとつまなざしをわが内に置き」
(横山未来子『水をひらく手』より)
「「酔ってるの?あたしが誰かわかってる?」「ブーフーウーのウーじゃないかな」」
(穂村弘『シンジケート』より)
「『鶴の恩返し』で鶴に共感するぼくは身体にいいやつTSUTAYAで探す」
(永井祐『広い世界と2や8や7』より)
「Amazonのどんなサイズの箱であれ中身はいずれ猫になります」
(木村比呂『うたらば』より)
「SOMETIME AGO 海辺 あなたの菫色の日傘が揺れていしが 戻らず」
(谷岡亜紀『風のファド』より)
「twilight in L.A./golden shining reflections/on asphalt pavement/the city becomes holy/everything forgiven」(Ron L. Zheng(鄭龍超)『Leaving My Found Eden』より)
「ああいたい。ほんまにいたい。めちゃいたい。冬にぶつけた私の小指(←足の。)」
(千葉すず(水泳選手)『FAX短歌会「猫又」』より)
「ああ人は諭吉の下に一葉をつくり英世をその下とした」(工藤吉生『うたらば』より)
「あいうえおかきくけこさしすきでしたちつてとなにぬねえきいてるの」
(まひろ(葛山葛粉)『食器と食パンとペン わたしの好きな短歌』より)
「あかときの雪の中にて 石 割 れ た」
(加藤克己『球体』より)
「あたまでは完璧にきみが描けるからときどきわたしは目を閉じている」
(樋口智子『つきさっぷ』より)
「あたらしい明日があなたにくるようにかうして窓をあけてゐる」
(中山明『食器と食パンとペン わたしの好きな短歌』より)
「アドレスが一件増えて着信のすべてに期待が生まれてしまう」
(とき『うたらば』より)
「あの夏と僕と貴方は並んでた一直線に永遠みたいに」
(木下侑介/穂村弘編『短歌ください』より)
「あの夏の数かぎりなきそしてまたたつた一つの表情をせよ」
(小野茂樹『羊雲離散』より)
「ありがとう なんてことない人生をちゃんと物語にしてくれて」
(檀可南子『食器と食パンとペン わたしの好きな短歌』より)
「アリよ来い迷彩アロハシャツを着た俺が落とした沖縄の糖へ」
(小林晶/穂村弘編『短歌ください 2』より)
「あんかけのあん煮立つような音させてぼこりと夫が寝入る木曜」
(てこな/穂村弘編『短歌ください』より)
「イカ墨のパスタを皿に盛るように洗面器へと入れる黒髪」
(麻倉遥/穂村弘編『短歌ください』より)
「いちまいの皮膚にほかならない皮膚を引き裂くほどに愛してもみた」
(菊池裕『アンダーグラウンド』より)
「エスカルゴ用の食器があるのだし私のための法で裁いて」
(麻倉遥/穂村弘編『短歌ください 2』より)
「エックス線技師は優しい声をして女の子らの肺うつしとる」
(猿見あつき/穂村弘編『短歌ください 2』より)
「おうどんに舌を焼かれて復讐のうどん博士は海原をゆく」
(山中千瀬『さよならうどん博士』より)
「おねがいねって渡されているこの鍵をわたしは失くしてしまう気がする」
(東直子第一歌集『春原さんのリコーダー』より)
「カッキーンって野球部の音 カッキーンは真っ直ぐ伸びる真夏の背骨」
(木下ルミナ侑介/穂村弘編『短歌ください 2』より)
「かまわないでかまわないわよかまってよ(フリルのついた鎌振り下ろす)」
(峰子/穂村弘編『短歌ください』より)
「かみくだくこと解釈はゆっくりと唾液まみれにされていくんだ」
(中澤系『uta0001.txt』より)
「きみの名とわたくしの声吸いこめるケルト渦巻模様円盤」
(大滝和子『竹とヴィーナス』より)
「きんにやもんにやきんにやもんにやと踊りゆくしだいにきんにやもんにやにわれもなるなり」
(馬場あき子『太鼓の空間』より)
「この顔にピンときたなら110番キュンときたならそれはもう恋」
(山本左足『うたらば』より)
「この星の重力美しく青々と梅の葉かげに球体実る」(清水あかね『白線のカモメ』より)
「この道はいつか来た道 ああそうだよ 進研ゼミでやったところだ」(あみー『うたらば』より)
「こんなにもふざけたきょうがある以上どんなあすでもありうるだろう」
(枡野浩一『ハッピーロンリーウォーリーソング』より)
「こんにちは私の名前は噛ませ犬 愛読書の名は『空気』です」
(冬野きりん/穂村弘編『短歌ください』より)
「コンビニに生まれかわってしまってもクセ毛で俺と気づいてほしい」
(西村曜『コンビニに生まれかわってしまっても』より)
「サバンナの象のうんこよ聞いてくれだるいせつないこわいさみしい」
(穂村弘 『シンジケート』より)
「さみしいとうつくしいって似ているね 青海と青梅を間違えず乗る」
(ショージサキ(あるきだす言葉たち)「遠くの国」朝日新聞夕刊2022年07月13日より)
「さみしいは何とかなるがむなしいは躑躅の低いひくい木漏れ日」
(千種創一『千夜曳獏』より)
「さらさらさらさらさらさらさらさらさらさら牛が粉ミルクになってゆく」
(穂村弘『水中翼船炎上中』より)
「しあわせにしてますように でも少しわたしが足りていませんように」
(月夜野みかん『食器と食パンとペン わたしの好きな短歌』より)
「ジャンヌ・モローのややよぢれたる唇のやうな小説読みをり深夜」
(花鳥佰『しづかに逆立ちをする』より)
「しらさぎが春の泥から脚を抜くしずかな力に別れゆきたり」
(吉川宏志『夜光』より)
「スカートにすむたくさんの鳥たちが飛び立つのいっせいに おいてかないで」
(ちゃいろ/穂村弘編『短歌ください』より)
「すれ違うときの鼻歌をぼくはもらうさらに音楽は鳴り続ける」
(阿波野巧也『さらに音楽は鳴り続ける』より)
「セーターの編み目のとこから指を出し「ハロー」とか言ってしあわせだった」
(ユキノ進『うたらば』より)
「だしぬけに葡萄の種を吐き出せば葡萄の種の影が遅れる」
(木下龍也/穂村弘編『短歌ください 2』より)
「たまり水が天へかえりてかわきたるでこぼこの野のようにさみしい」
(中野昭子『草の海』より)
「ドアの隙間に裏の世界が見えました線対称な隣の間取り」
(弱冷房/穂村弘編『短歌ください 2』より)
「トウキョウノユキハナキムシぐちゃぐちゃに轢かれた青い雑誌を濡らす」
(加藤治郎『ニュー・エクリプス』より)
「どうしても思い出せない色がありその空白を黒と名付けた」
(実山咲千花『食器と食パンとペン わたしの好きな短歌』より)
「どこでもないところへゆきたい あなたでなければならないひとと」
(山崎郁子『麒麟の休日』より)
「どこにでも行ける気がした真夜中のサービスエリアの空気を吸えば」
(木下ルミナ侑介/穂村弘編『短歌ください 2』より)
「ともにゐてかなしいときにかなしいと言はせて呉れるひとはゐますか」
(資延英樹『抒情装置』より)
「なだれこむ青空、あなた、舌の根をせつなくおさえこまれるままに」
(佐藤弓生『眼鏡屋は夕ぐれのため』より)
「なにもかも派手な祭りの夜のゆめ火でも見てなよ さよなら、あんた」
(林あまり『MARS・ANGEL―林あまり歌集』より)
「なんでも麻雀で喩えたがるならこのドッグランも ETERNAL」
(郡司和斗「犬の話」『くくるす』創刊号より)
「ににんがし、にさんがろくと春の日の一段飛ばしでのぼる階段」
(むしたけ『うたらば』より)
「ハムレタスサンドは床に落ちパンとレタスとハムとパンに分かれた」
(岡野大嗣『食器と食パンとペン わたしの好きな短歌』より)
「パンセパンセパン屋のパンセ にんげんはアンパンをかじる葦である」(
(杉崎恒夫『短歌タイムカプセル』より)
「ビール狂体に悪いと改心しワインに変えるもアンドレは死す」
(ターザン山本(プロレスラー)『FAX短歌会「猫又」』より)
「ピクニックって想像上の生き物だそれにはあなたがいたりしていて」
(西村曜『コンビニに生まれかわってしまっても』より)
「ひそやかな祭の晩に君は待つ コンビニ袋に透けるレモンティー」
(ちゃいろ/穂村弘編『短歌ください』より)
「ひた泣きて訴へたりし幼の日よりわが身に添へる不安といふもの」
(さとうひろこ『呑気な猫』より)
「ひとすじの光はここへ本、扉、すべての閉じていたものたちへ」
(星乃咲月『うたらば』より)
「ひとりでも生きていけると知ったからきちんと君と手を繋ぎたい」
(とき『うたらば』より)
「ブラウスを着ればブラウスの形にて私は座る職場の椅子に」
(川本千栄『青い猫』より)
「ペガサスは私にはきっと優しくてあなたのことは殺してくれる」
(冬野きりん/穂村弘編『短歌ください』より)
「ホームと車体とを他者にした闇によだれを垂らす聖者は8歳」
(冬野きりん/穂村弘編『短歌ください 2』より)
「ぼくの聴く音楽こそが素晴らしいと思いながら歩く夜が好きだよ」
(岡野大嗣『たやすみなさい』より)
「マヨネーズ時計ではかるゆうぐれの時間は赤いところへ降りる」
(やすたけまり/穂村弘編『短歌ください』より)
「みそ汁に口を開かぬしじみ貝はじめて母に死を教わりぬ」
(麻倉遥/穂村弘編『短歌ください 2』より)
「めきゃべつは口がかたいふりをして超音波で交信するのだ」
(鶯まなみ(女優・本上まなみ)『FAX短歌会「猫又」』より)
「もう一軒寄りたい本屋さんがあってちょっと歩くんやけどいいかな」
(岡野大嗣『たやすみなさい』より)
「もう一度言うがおれは海の男ではない」
(フラワーしげる『ビットとデシベル』より)
「もう何も傷つけぬよう切る爪が思いもよらぬ方向へ飛ぶ」
(ちょこま『うたらば』より)
「もう無理!無理無理無理無理テンパってぱってぱってと飛び跳ねており」
(花山周子『屋上の人屋上の鳥』より)
「ゆきたりと知りて極まるさびしさのなか揃へある赤きはきもの」
(百々登美子『大扇』より)
「ゆふがほのひかり一滴露けくて永遠(とは)にわれより若き恋人」
(河野裕子『森のやうに獣のやうに』より)
「ゆるやかに櫂を木陰によせてゆく明日は逢えない日々のはじまり」
(加藤治郎『昏睡のパラダイス』より)
「よくみれば体育座りは複雑に折り畳まれたこころのようだ」
(柳本々々『食器と食パンとペン わたしの好きな短歌』より)
「ラーメンを食べてうとうとしているとゴールしていた男子マラソン」
(綿壁七春/穂村弘編『短歌ください 2』より)
「ルーベンスの薔薇色の雲わが手には君の重たき上着が眠る」
(梅内美華子『若月祭』より)
「レディレディ、位置に着いたら一番になりたい理由を考えなさい」
(リオ『うたらば』より)
「わがシャツを干さん高さの向日葵は明日ひらくべし明日を信ぜん」
(寺山修司『空には本』より)
「わたくしも誰かのカラーバリエーションかもしれなくてユニクロを出る」
(辻聡之『あしたの孵化』より)
「わたくしを温めるため沸かす湯はかつて雪なる記憶を持てり」
(中畑智江『食器と食パンとペン わたしの好きな短歌』より)
「わたしたち/わたしたち/わたしたち/わたしたち/わたしたち/わたしたち/わたし」
(今橋愛『短歌WAVE』創刊号より)
「わたしたち全速力で遊ばなきや微かに鳴つてゐる砂時計」
(石川美南『砂の降る教室』より)
「われを抱く荒々しき腕かいなありジャーマンスープレックスホールドということばのなかに」
(肉球『FAX短歌会「猫又」』より)
「愛してる、幸せ、だけどこの先は別料金が発生します」
(赤井悠利『うたらば』より)
「愛を告げすぎて不安になるこころあまたなるゆすらうめの実のゆれ」
(渡辺松男『けやき少年』より)
「愛恋のはざまむなしも雪崩つつけぶるがままに幾夜ありけむ」
(小中英之『翼鏡』より)
「逢えばくるうこころ逢わなければくるうこころ愛に友だちはいない」
(雪舟えま『たんぽるぽる』より)
「逢ひたいと思ふ、思へば昼も夜も緋の澱を手に掬ふきさらぎ」
(高島裕『雨を聴く』より)
「胃からりんご。/りんごの形のままでそう。/肩はずれそう/この目。とれそう」
(今橋愛『O脚の膝』より)
「育つとは大きくなることではなくてもう戻れなくなることである」
(泳二『うたらば』より)
「一秒でもいいから早く帰ってきて ふえるわかめがすごいことなの」
(伊藤真也/穂村弘編『短歌ください』より)
「雨だから迎えに来てって言ったのに傘も差さず裸足で来やがって」
(盛田志保子『木曜日』より)
「雨の日の空間がぴたぴたとしててほんとはぼくじゃないかもしれない」
(阿波野巧也『食器と食パンとペン わたしの好きな短歌』より)
「雨後の筍のように私が生える 狩ってそれから食えるように炊いて」
(柴田葵『母の愛、僕のラブ』より)
「影として水面うつろふ水鳥にこころ寄りゆくふたり黙せば」
(柚木圭也『心音(ノイズ)』より)
「永遠と思いこんでた「青春」の二文字の中に「月日」があった」
(逢『うたらば』より)
「屋外は現在、屋内は未来、中庭は過去、につながりて夜の秋」
(松平修文『トゥオネラ』より)
「音は消ゆ人も逝きたりめぐりやまぬ季節のなかに残る音楽」
(河野美砂子『ゼクエンツ』より)
「下駄箱の前にちいさなやぎがいてまた食べられるあたしの勇気」
(山田水玉『うたらば』より)
「夏の朝体育館のキュッキュッが小さな鳥になるまで君と」
(木下ルミナ侑介/穂村弘編『短歌ください 2』より)
「家に着くまでが遠足帰りたい家を見つけるまでが旅です」
(空木アヅ『うたらば』より)
「家族の誰かが「自首 減刑」で検索をしていたパソコンまだ温かい」
(小坂井大輔『平和園に帰ろうよ』より)
「花の散る速度と競ひ音階をのぼりたりわが少女期のカノン」
(米川千嘉子『夏空の櫂』より)
「花水木いつまでも見上げる君の 君の向こうを一人見ており」
(前田康子『ねむそうな木』より)
「花水木の道があれより長くても短くても愛を告げられなかった」
(吉川宏志『青蟬』より)
「花瓶だけうんとあげたい絶え間なくあなたが花をうけとれるように」
(笠木拓『食器と食パンとペン わたしの好きな短歌』より)
「会えない人はみんなきらいだ眠ったらぜんぶ忘れる話は好きだ」
(嶋田さくらこ『食器と食パンとペン わたしの好きな短歌』より)
「会えるとは思わなかった 夏が麻痺してゆく船の倉庫のかげで」
(千葉聡『そこにある光と傷と忘れもの』より)
「会心の一撃として向日葵が天に撃ち込む黄の鮮やかさ」
(中西大輔『うたらば』より)
「街のここかしこにカノン湧き上がり落ち葉は落ち葉を掃く人に降る」
(稲葉京子『花あるやうに』より)
「乾いてる春をかわして行く君はさよならのときも振り返らない」
(中島裕介『Starving Stargazer』より)
「顔文字の収録数は150どれもわたしのしない表情」
(一戸詩帆/穂村弘編『短歌ください 2』より)
「幾人もわたしを腹に詰めこみてときおり淡く声が重なる」
(辻聡之『あしたの孵化』より)
「気持ちだけいただこうかと思ったら気持ちの方が空っぽやんか」
(じゃこ『うたらば』より)
「君が火を打てばいちめん火の海となるのであらう枯野だ俺は」
(真中朋久『雨裂』より)
「君の事忘れるための旅なのに 話したいことばかりが増える」
(きつね『うたらば』より)
「君の手のひらをほっぺに押しあてる 昔の日曜みたいな匂い」
(木下ルミナ侑介/穂村弘編『短歌ください 2』より)
「君を待つ3分間、化学調味料と旅をする。2分、待ち切れずと目を覆い、蓋はついに暴かれた。」
(せつこ/穂村弘編『短歌ください 2』より)
「君一人置きしベンチに近づきて横顔はかくも侵し難かり」
(吉野亜矢『滴る木』より)
「結界のように真白い冷蔵庫ミルクの獣臭も冷やして」
(高橋徹平/穂村弘編『短歌ください 2』より)
「献血の出前バスから黒布の覗くしずかな極東の午後」
(虫武一俊/穂村弘編『短歌ください』より)
「枯れたからもう捨てたけど魔王つて名前をつけてゐた花だつた」
(藪内亮輔『食器と食パンとペン わたしの好きな短歌』より)
「後ろから抱きしめるとき数一〇〇〇(かずいっせん)の君のまわりの鳥が飛び立つ」
(白瀧まゆみ『自然体流行』より)
「誤植あり。中野駅徒歩十二年。それでいいかもしれないけれど」
(大松達知『アスタリスク』より)
「好きだって言うより先に抱きしめた言葉はいつも少し遅れる」
(木下龍也『うたらば』より)
「好きでしょ、蛇口。だって飛びでているとこが三つもあるし、光っているわ」
(陣崎草子/穂村弘編『短歌ください』より)
「好き嫌い嫉妬妄想妻妥協「女」のつく字がみなおそろしい」
(瀬波麻人『うたらば』より)
「幸せがのびのびしてる小説で少し曇った眼鏡を掛ける」
(今野浮儚『食器と食パンとペン わたしの好きな短歌』より)
「降りては来ないあふれるのよ遠いはかないまなざしからきっとここへ」
(井上法子『永遠でないほうの火』より)
「降りみだれみぎはに氷る雪よりも中空にてぞわれは消ぬべき」
(浮舟の歌 『源氏物語』「浮舟」の巻より)
「告げざりし心愛(お)しめば一枚の画布(トワール)白きままにて残す」
(安永蕗子『魚愁』より)
「今どこにいますか何をしてますかしあわせですかもう春ですか」
(たきおと『うたらば』より)
「今二匹蚊を殺したわ息の根を止めましたこの手あなたをさわる手」
(森響子/穂村弘編『短歌ください』より)
「砂たちに行動の自由与えたら湘南海岸どうなるだろう」
(奥村晃作『スキーは板に乗ってるだけで』より)
「再びを調べつつ書く楽しさを吾に給えな越えるべき日々」
(大島史洋『どんぐり』より)
「細々と暮らしたいからばあさんや大きな桃は捨ててきなさい」
(木下龍也『うたらば』より)
「昨年の夏に野球を共に観た女子はファウルをよけられなくて」
(ハレヤワタル/穂村弘編『短歌ください』より)
「雑踏にまぎれ消えゆく君の背をわが早春の遠景として」
(大辻隆弘『水廊』より)
「散髪の帰りの道で会う風が風の中でいちばん好きだ」
(岡野大嗣『食器と食パンとペン わたしの好きな短歌』より)
「四十肩 三段腹に 二重あご 一重まぶたで ツルツルあたま」
(水野川順平/穂村弘編『短歌ください』より)
「指切りのゆび切れぬまま花ぐもる空に燃えつづける飛行船」
(穂村弘『シンジケート』より)
「死というは日用品の中にありコンビニで買う香典袋」
(俵万智『チョコレート革命』より)
「私って幸せだったのかなーと四つ葉のクローバーが死ぬ夜」
(こしあん『うたらば』より)
「詩はすべて「さみしい」という4文字のバリエーションに過ぎない、けれど」
(木下龍也『オールアラウンドユー』より)
「試着室くつを脱ぐのかわからない わからないまま一歩踏み出す」
(竹林ヾ来/穂村弘編『短歌ください 2』より)
「自動巻き腕時計ってどういう仕組み? 勝ってうれしいサッコ&ヴァンゼッティ」
(由良伊織「よくできた蓋」『早稲田短歌』より)
「七階からみおろす午後の がらくたの あのごみどもの 虫けら達の ああめちゃめちゃの東京の街」
(加藤克己『宇宙塵』より)
「煮えたぎる鍋を見すえてだいじょうぶこれは永遠でないほうの火」
(井上法子『食器と食パンとペン わたしの好きな短歌』より)
「煮え切らぬきみに別れを告げている細胞たちの多数決として」
(九螺ささら/穂村弘編『短歌ください 2』より)
「手套(てぶくろ)に さしいれてをり Debussyの 半音に触れて 生(なま)のままのゆび」
(河野美砂子『無言歌』より)
「終わらせる為の「レモン」に君がすぐ「ソーダ」を足して続くしりとり」
(こころ『うたらば』より)
「十二月二十四日と十二月二十五日は異様に長い」
(木下龍也『うたらば』より)
「縦書きの国に生まれて雨降りは物語だと存じています」
(飯田和馬『うたらば』より)
「重ねればやわらかい指ぼくたちは時代錯誤の愛を着ている」
(東直子『青卵』より)
「助走から疾走までにあったこと君に話そうひと夏のこと」
(紗都子『うたらば』より)
「女には人生一度か二度くらい逃さねばならぬ終電がある」
(倉野いち『うたらば』より)
「少しだけネイルが剥げる原因はいつもシャワーだよシャワー土下座しろ!」
(古賀たかえ/穂村弘編『短歌ください』より)
「寝た者から順に明日を配るから各自わくわくしておくように」
(佐伯紺『食器と食パンとペン わたしの好きな短歌』より)
「振り上げた握りこぶしはグーのまま振り上げておけ相手はパーだ」
(枡野浩一『てのりくじら』より)
「森を歩す、新秋を歩す 美しき言葉のありていま月を歩す」
(高野公彦「「カノン」の迷子」『短歌』より)
「深海に生きる魚族のように、自らが燃えなければ何処にも光はない」
(明石海人『白描』より)
「神妙な面持ちですねあと少し待てば赦すと思ってますね」
(こはぎ『うたらば』より)
「図鑑には載ってないけど木漏れ日が一番きれいなのは栗の木」
(山本左足『うたらば』より)
「水の輪が水の輪に触れゐるやはらかなリズムのうへにまた雨が降る」
(河野裕子『紅』より)
「水際に夕日を引き込む重力が遠いわたしに服を脱がせる」
(平岡直子『同人誌「町」4号』より)
「水筒を覗きこんでる 黒くってきらきら光る真夏の命」
(木下ルミナ侑介/穂村弘編『短歌ください 2』より)
「睡りゐる麒麟の夢はその首の高みにあらむあけぼのの月」
(大塚寅彦『声』より)
「世界一やさしい単語のひとつだと思うあなたのなまえ呼ぶとき」
(月夜野みかん『うたらば』より)
「晴れの日は風と暮らして雨の日は涼しいなって気持ちと暮らす」
(岡本真帆『水上バス浅草行き』より)
「生きるとは硬貨を抱いていつまでも着かないバスを待つ人のごと」
(田中ましろ『燈心草を香らせて』より)
「生と死のうづうづまきてをりにけむ丸縁眼鏡の志功のなかに」
(花鳥佰『逃げる!』より)
「生態系食物連鎖をくつがえしあたしがあなたをたべる日が来た」
(小玉裕理子/穂村弘編『短歌ください』より)
「青き空 わたしの上にひるがえる旗には「壊せ神殿を」とありぬ」
(大島史洋『どんぐり』より)
「静やかにスノードームが飾られた空を研究する人の部屋」
(廣野翔一『食器と食パンとペン わたしの好きな短歌』より)
「雪国に行くトンネルを反対に抜ければそれが春ではないか」
(あみー『うたらば』より)
「蝉が死んでもあなたを待っています バニラアイスの木べらを噛んで」
(ゆず/穂村弘編『短歌ください』より)
「痩せようとふるいたたせるわけでもなく微妙だから言うなポッチャリって」
(脇川飛鳥『かんたん短歌の作り方』より)
「脱ぎ捨てた服のかたちに疲れても俺が求めるお前にはなるな」
(奥田亡羊『亡羊』より)
「誰のこともさして恋はずに作りたる恋歌に似て真夏のうがい」
(石川美南『砂の降る教室』より)
「単純でいて単純でいてそばにいて単純でいてそばにいて」
(嵯峨直樹『神の翼』より)
「男ゆゑ男への恋が実らずと高校生が保健室で泣く」
(大松達知『アスタリスク』より)
「男女とは一対にしてはるかなる時間差で置く白き歯ブラシ」
(大野道夫『秋階段』より)
「地球上すべてのひとが信号を渡ったあとで青は渡った」
(実山咲千花『うたらば』より)
「長雨の明けてとんぼの高く飛ぶいのち余さず秋空をゆけ」
(久我田鶴子『転生前夜』より)
「鉄分が不足しているその期間車舐めたい特に銀色」
(九螺ささら/穂村弘編『短歌ください 2』より)
「電子レンジは腹に銀河を棲まわせて静かな夜に息をころせり」
(陣崎草子/穂村弘編『短歌ください』より)
「冬の朝つめたき陶となる髪に従容と来てひとは唇触る」
(佐竹彌生『雁の書』より)
「冬の朝窓開け放ちてあおむけば五体にひろがりやまぬ風紋」
(寺井龍哉/穂村弘編『短歌ください 2』より)
「入賞じゃ以下同文の賞状をもらってお辞儀して下がるだけ」
(じゃこ『うたらば』より)
「脳みそがあってよかった電源がなくても好きな曲を鳴らせる」
(岡野大嗣『うたらば』より)
「薄っぺらいビルの中にも人がいる いるんだわ しっかりしなければ」
(雪舟えま『たんぽるぽる』より)
「髪あげてやや美しと思ふときひとと別れむ心定まる」
(石川不二子『牧歌』より)
「抜けてきたすべての道は露に消え連続わたし殺人事件」
(吉岡太朗『ひだりききの機械』より)
「非常口マークの奴も時々は逃げたくないと思うんだろう」
(葛山葛粉『うたらば』より)
「風が苦しみ始めたやうだわたくしの深い疲労に気づいたらしい」
(岡井隆『阿婆世あばな』より)
「歩きつつ本を読む癖電柱にやさしく避けられながら街ゆく」
(柳澤美晴『一匙の海』より)
「母からの「可愛い」という一言をお守りにしてゆく夏祭り」
(小川千世『うたらば』より)
「母語圏外言語状態(エクソフォニー) この美しき響きには強風に立つ銀河が見える」
(黒瀬珂瀾『空庭』より)
「忘れてく思い出たちは優しいと午後四時半の物理実験室」
(マイ/穂村弘編『短歌ください』より)
「僕らはママの健全なスヌーピーできるだけ死なないから撫でて」
(柴田葵『母の愛、僕のラブ』より)
「味の素かければ命生き返る気がしてかけた死にたての鳥に」
(九螺ささら/穂村弘編『短歌ください 2』より)
「無理をしてほしいと言えば会いにくる深夜かなしく薔薇を抱えて」
(俵万智『チョコレート革命』より)
「毛を刈ったプードル怖いと言う彼にあれは唐揚げと思えと伝えた」
(モ花/穂村弘編『短歌ください』より)
「黙らせるために渡した飴なのに「おいしいね」って君は笑った」
(赤井悠利『うたらば』より)
「夜は来る(地球四十六億年ぶんの)不安を引き連れてきて」
(二玉号『食器と食パンとペン わたしの好きな短歌』より)
「夜光虫のニュースのなかにくりかえし生れては死ぬるひかり わたしの」
(辻聡之『あしたの孵化』より)
「優秀なペンギンなので空を飛ぶことを望んでなんていません」
(谷じゃこ『食器と食パンとペン わたしの好きな短歌』より)
「友だちが百人できてもさみしいと先生ちゃんと教えてください」
(chari『うたらば』より)
「夕やけよあらゆる色を駆逐せよ 頬が冷めてくモザイクの街」
(めぐみ・女・21歳『短歌ください』より)
「夕空を旅客機一機離り行き工学はいま文学を呼ぶ」
(曽川文昭『スイッチバック』より)
「卵らが身を寄せあってひからびる二十時の回転寿司銀河」
(古屋賢一/穂村弘編『短歌ください』より)
「履歴書は白紙のままで鶴になる 折るという字は祈るに似てる」
(山本左足『うたらば』より)
「旅先で僕らは眠るすべてから知らない街の匂いをさせて」
(ソウシ/穂村弘編『短歌ください』より)
「林檎からうさぎを創り出すような小さな魔法に生かされている」
(松尾唯花『食器と食パンとペン わたしの好きな短歌』より)
「淋しい人影が夢の芯になり銀河を擁いて傾いてくる」
(糸田ともよ『しろいゆりいす』より)
「冷蔵庫にほのかに明かき鶏卵の、だまされて来し一生のごとし」
(岡井隆『神の仕事場』より)
「恋ですよ芋の芋まで掘り起こしありったけポテトフライにしたい」
(阿波野巧也『さらに音楽は鳴り続ける』より)
「釉薬を身体(からだ)に巻きて佇つごとし近づくわれをかすか怖れて」
(島田幸典『no news』より)
「銜(くは)へ来し小枝はくちばしより落ちぬ改札を抜け君に笑むとき」
(栗木京子『けむり水晶』より)
[異種百人一首選考外短歌(その2)](353首)
「マッチ擦るつかのまの海に霧ふかし身捨つるほどの祖国はありや」
(寺山修司『空には本』より)
「文に代へ碧瑠璃(へきるり)連らね贈り来し人によ夏の氷(ひ)の言葉遣る」
(紀野恵『架空荘園』より)
「人は去りゆくともめぐる夏ごとに怒りを込めて咲くダリアなれ」
(松野志保『モイラの裔』より)
「内に飼い慣らす怪物 哄笑とともに若葉を吹くこの街で」
「夜のプール塩素の臭いに囊(つつ)まれてまず魂が腐りはじめる」
「いつか色褪せることなど信じないガーゼに染みてゆくふたりの血」
(松野志保『Too Young to Die』より)
「黄金のひかりのなかにクリムトの口吻ふ男ぬばたまの髪」
(山中智恵子『夢之記』より)
「さくらばな陽に泡だつを目守まもりゐるこの冥き遊星に人と生まれて」
(山中智恵子『みずかありなむ』より)
「絶望に生きしアントン・チェホフの晩年をおもふ胡桃割りつつ」
「兵たりしものさまよへる風の市(いち)白きマフラーをまきゐたり哀し」
(大野誠夫『薔薇祭』より)
「美しき脚折るときに哲学は流れいでたり 劫初馬より」
(水原紫苑『びあんか』より)
「美しきナイフ買ひたしページ切り天球のごときまなこ切るべし」
(水原紫苑『快楽』より)
「薄氷(うすらひ)の上を生きつつみひらけばきみ立ちて舞ふ月のおもてに」
「終はりなき狂言ありや終はりなきいのちのごとく水のごとくに」
(水原紫苑『武悪のひとへ』より)
「君の目に見られいるとき私はこまかき水の粒子に還る」
(安藤美保『水の粒子』より)
「くりかえし繰り返す朝わたくしの死後も誰かが電車に駆け込む」
(松村由利子『鳥女』より)
「時に応じて断ち落とされるパンの耳沖縄という耳の焦げ色」
(松村由利子『耳ふたひら』より)
「平日のマチネー混めば東京はまだ大丈夫(なのか)日本も」
(松村由利子『光のアラベスク』より)
「神学の果てぐらぐらと煮えたぎる鍋ありはつか血の匂いする」
(加藤英彦『スサノオの泣き虫』より)
「うすきグラスに泛びて凜(さむ)したまゆらの夏をさやさやゆれる茗荷は」
(加藤英彦『プレシピス』より)
「波がしらにとまらむとして晩夏の蛾黄金の鱗粉をこぼせり」
(松平修文『水村』より)
「夜空の果ての果ての天体(ほし)から来しといふ少女の陰(ほと)は草の香ぞする」
(松平修文『トゥオネラ』より)
「「幽霊とは、夏の夜に散る病葉(わくらば)のことです」とその街路樹の病葉が言ふ」
(松平修文『蓬(ノヤ)』より)
「日本史のかたまりとして桜花湧きつつ消える時間の重み」
(松木秀『5メートルほどの果てしなさ』より)
「ハルシオン 今亡き君はわれを待つ その百錠の果ての花園」
(大津仁昭『霊人』より)
「陽の下に島国の文字わわらかし遅れて届く春の絵葉書」
(今井恵子『分散和音』より)
「切株の裂け目に蟻の入りゆきて言葉以前の闇ふかきかな」
(今井恵子『やわらかに曇る冬の日』より)
「ルサンチマンのかわりに夜空へ放ちやるぼくらのように美しい蛾を」
(森本平『モラル』より)
「胸おもくまろくかかえて鳥たちははつなつ空の果実となりぬ」
(佐藤弓生『眼鏡屋はゆうぐれのため』より)
「暮れながらたたまれやまぬ都あり〈とびだすしかけえほん〉の中に」
(佐藤弓生『薄い街』より)
「十月の孟宗竹よそうですか空はそんなに冷えていますか」
(佐藤弓生『世界が海におおわれるまで』より)
「花びらはしずかにながれすぎにけり水のおもてのわれを砕いて」
(野樹かずみ『路程記』より)
「卓上の静物画ナチュールモルト 断つまでは果実のなかに流れゐる時間」
(林和清『匿名の森』より)
「まばたきの終え方を忘れてしまった 鳥に静かに満ちてゆく潮」
「しっとりとつめたいまくらにんげんにうまれたことがあったのだろう」
(笹井宏之『ひとさらい』より)
「デンジマスク作り終えたる青年のハンダゴテ永遠(とわ)に余熱を持てり」
(笹公人『抒情の奇妙な冒険』より)
「校廊のどこかで冷える10円玉むらさき色に暮れる学園」
(笹公人『念力家族』より)
「戦争で死にたる犬や猫の数も知りたし夏のちぎれ雲の下」
(笹公人『終楽章』より)
「何時までが放課後だろう 春の夜の水田(みずた)に揺れるジャスコの灯り」
(笹公人『念力ろまん』より)
「生ける蛾をこめて捨てたる紙つぶて花の形に朝ひらきをり」
(森岡貞香『白蛾』より)
「逢ふといふはこの世の時間 水の上を二つの星の光(かげ)うごくなり」
(森岡貞香『帯紅』より)
「おほ空に色かよひつつ桐さけり消ぬべく咲けり消ぬべく美しも」
(柏原千惠子『彼方』より)
「うちがはにこもるいのちの水の色の青条揚羽みづにひららく」
「野獣派のマチスの「ダンス」手を繋ぐときあらはれる人間の檻」
(尾崎まゆみ『明媚な闇』より)
「万緑に隧道(トンネル)ふかく穿たれてあばら骨愛しぬきたる闇」
(尾崎まゆみ『時の孔雀』より)
「わが居間の鏡にむかひひとり踊る狂へるにあらず狂はざるため」
(一ノ関忠人『帰路』より)
「ひとつ水脈ひきて渡れる鳥の陰ちさくうかべてあしたの川は」
(黒田瞳『水のゆくへ』より)
「君の着るはずのコートにホチキスを打てば室内/ひどくゆうぐれ」
(嵯峨直樹『神の翼』より)
「安っぽき照明の下打ち解けてスープきらめくうどん啜れり」
(嵯峨直樹『半地下』より)
「なつのからだあきのからだへと移りつつ雨やみしのちのアスファルト踏む」
(小島なお『サリンジャーは死んでしまった』より)
「白色のスーザフォーンを先立てて行進すれば風の不意打ち」
(杉崎恒夫『食卓の音楽』より)
「夏の夜のわれらうつくし目の下に隈をたたへてほほ笑みあへば」
(石川美南『裏島』より)
「銀紙で折ればいよいよ寂しくて何犬だらう目を持たぬ犬」
(石川美南『体内飛行』より)
「人間のふり難儀なり帰りきて睫毛一本一本はづす」
(石川美南『離れ島』より)
「友だちを口説きあぐねてゐる昼の卓上に傾(なだ)るるひなあられ」
「放つとくと記憶は徐々に膨らみて四コマ漫画に五コマ目がある」
(石川美南『架空線』より)
「蓮の花ひかりほどかむ朝まだき亡き父母近し老い初めし身に」
(大塚寅彦『ハビタブルゾーン』より)
「蜜といふ黄昏いろのしづもれる壜購(か)ひてふと秋冷ふかむ」
(大塚寅彦『夢何有郷』より)
「モニターにきみは映れり 微笑(ほほゑみ)をみえない走査線に割(さ)かれて」
(大塚寅彦『空とぶ女友達』より)
「夏まひるメトロ冷えをりトンネルに長鳴鳥はこゑ呼びあひて」
「〈弧(ゆみ)をひくヘラクレス〉はも耐えてをり縫ひ目をもたぬひかりのおもさ」
(都築直子『淡緑湖』より)
「白みゆく空と消えゆく夏の声 記憶にありきこの傾きは」
(田中槐『サンボリ酢ム』より)
「沈黙はマイノリティーの物語 サ変動詞がし、する、すれ、せよ」
「横にいてこうして座っているだけで輪唱をするあまた素粒子」
「気づかないふりしてただけ回転を終えた景色は遅れて止まる」
(田中槐『退屈な器』より)
「リリシズムの行方思(も)いつつ烏賊墨に汚れし口を拭う数秒」
(生沼義朗『関係について』より)
「劣情が音立つるほど冷えている。きさらぎ、デスクワークのさなか」
「ぼそぼそとももいろの塊(かい)食べながらハムも豚だと思い出したり」
(生沼義朗『水は襤褸に』より)
「老いのさきに死のあることのまぎれなさ藍重くして梅雨の花垂る」
(佐藤通雅『強霜』より)
「雨が降り出す前の暗さに蛍光灯は二、三度力を込めて点きたり」
(菊池孝彦『まなざさる』より)
「滑るやうに車線変更してしまふコンサバティブな春の夕暮れ」
(喜多昭夫『早熟みかん』より)
「頭(づ)のうへを蜻蛉つーい、つーい飛ぶ明日といふ日はあさつてのきのふ」
「ムンクの絵〈叫び〉を〈あくび〉と改名す女子高生はただものでない」
(喜多昭夫『青霊』より)
「まひるまの有平棒は回りけり静かにみちてゆける血液」
(加藤治郎『しんきろう』より)
「思い出を持たないうさぎにかけてやるトマトジュースをしぶきを立てて」
「パーマでもかけないとやってらんないよみたいのもありますよ 1円」
(永井祐『日本の中でたのしく暮らす』より)
「横浜はエレベーターでのぼっていくあいだも秋でたばこ吸いたい」
(永井祐『広い世界と2や8や7』より)
「フローリングに寝転べばいつもごりごりと私は骨を焦がして生きる」
(野口あや子『夏にふれる』より)
「押し黙ればひとはしずかだ洗面器ふるき卵の色で乾けり」
(野口あや子『眠れる海』より)
「くしゃっ、って笑うあなたがまぶしくてアップルパイのケースさみどり」
(野口あや子『くびすじの欠片』より)
「雑踏の中でゆっくりしゃがみこみほどけた蝶を生き返らせる」
(木下龍也『つむじ風、ここにあります』より)
「また水に戻るときまで他者としてグラスのなかでふれあう氷」
(木下龍也『オールアラウンドユー』より)
「ゆふかげの糸こがねいろひともとの花をめぐりて我を遠くす」
(目黒哲朗『VSOP』より)
「君よたとへば千年先の約束のやうに積乱雲が美しい」
(目黒哲朗『CANNABIS』より)
「曼珠沙華一むら燃えて秋陽つよしそこ過ぎてゐるしづかなる道」
(木下利玄『みかんの木』より)
「一本の避雷針が立ちじりじりと夕焼の街は意志もちはじむ」
「白昼の星のひかりにのみ開く扉(ドア)、天使住居街に夏こもるかな」
「戸口戸口あぢさゐ満てりふさふさと貧の序列を陽に消さむため」
(浜田到『架橋』より)
「この愛に根づけと絡め取られさうで跳ねる 金の鈴跳ねる 空へと」
(松本典子『ひといろに染まれ』より)
「セーターを脱げばいっせいに私たちたましいひとつ浮かべたお皿」
(山崎聡子『手のひらの花火』より)
「背泳ぎで水の終わりに触れるとき音のない死後といわれる時よ」
(山崎聡子『青い舌』より)
「ホネガイの影ひらきゆく夕べまで傾けつくす夜の水差し」
(山下泉『海の額と夜の頬』より)
「刈られたる草の全きたふれふし辺りの空気あをみ帯びたり」
(高木佳子『青雨記』より)
「生けるもの皆みずからを負ひながら歩まむとするこの砂のうへ」
(高木佳子『玄牝』より)
「隊列のほどける時にきわやかに鳥のかたちを取り戻したり」
(後藤由紀恵『ねむい春』より)
「遠いドアひらけば真夏沈みゆく思ひのためにする黙秘あり」
(澤村斉美「黙秘の庭」より)
「かはきゆくみづのかたちを見てゐれば敷石の上ひかりうしなふ」
(澤村斉美『夏鴉』より)
「冬鳥の過ぎりし窓のひとところ皿一枚ほど暮れのこりたり」
(澤村斉美『ガレー galley』より)
「シメコロシノキに覆はれて死んでゆく木の僅かなる樹皮に触れたり」
(本多稜『惑』より)
「天穹にふかく浸かりて聴きゐるは宙(そら)を支ふる山々の黙(もだ)」
(本多稜『蒼の重力』より)
「無差別は格闘技ではなく殺傷の島国に藤の花房垂るる」
「念校は人生のためあるのだろう想い出広がる冬の草はら」
(中川佐和子『春の野に鏡を置けば』より)
「ヒルティを枕に置きて話し出(い)ず人のひと生(よ)のよろこびの淵」
(中川佐和子『卓上の時間』より)
「手を振られ手を振りかえす中庭の光になりきれない光たち」
(千葉聡『今日の放課後、短歌部へ!』より)
「はゞたける空あるやうにひらきをる貝殻骨の ゆふかたまけて」
(川崎あんな『あんなろいど』より)
「風のなき夜の十字架のもとにしてわがみどりごは生まれたりけり」
(大松達知『ゆりかごのうた』より)
「小余綾(こゆるぎ)の急ぎ足にてにはたづみ軽くまたぎぬビルの片蔭」
(阪森郁代『ボーラといふ北風』より)
「右クリック、左ワトソン並び立つ影ぞ巻きつる二重螺旋に」
(資延英樹『リチェルカーレ』 より)
「サブマリン山田久志のあふぎみる球のゆくへも大阪の空」
(吉岡生夫『勇怯篇 草食獣・そのIII』より)
「海苔フィルム外して巻いてゆくときのさみしきさみしき音を聞かしむ」
(吉岡生夫『草食獣 第七篇』より)
「ああ檸檬やさしくナイフあてるたび飛沫けり酸ゆき線香花火」
(山田航「夏の曲馬団」より)
「りすんみい 齧りついたきりそのままの青林檎まだきらきらの歯型」
(山田航『さよならバグ・チルドレン』より)
「ガソリンはタンク内部にさざなみをつくり僕らは海を知らない」
(山田航『水に沈む羊』より)
「光年を超える単位を我ら持たず秋のナナカマド濡れていて」
(田中濯『氷』 より)
「リモコンにつまづくインコ秋深みわれより親しく死を内包す」
(尾崎朗子『タイガーリリー』 より)
「ドナーから移植患者(レシピエント)へうつり棲む臓器を直(ぢか)に触れるゆびさき」
(菊池裕『ユリイカ』より)
「ゆっくりとやって来るものおそらくはその名を発語せぬままに待つ」
(吉野裕之「胡桃のこと II」『吉野裕之集』より)
「南からやって来た船大きくて横切ってゆく ゆっくり私」
(吉野裕之『砂丘の魚』より)
「昼すぎの村雨の後ふいに射すひかりよそこにうつしみ立たす」
(江戸雪『昼の夢の終わり』より)
「この世には釦の数だけ穴がありなのにあしたの指がこわばる」
「死ぬものと死なないものに分けていく思考に鳥が座礁している」
(江戸雪『空白』より)
「陸(くが)しづみ国土ちひさくなる夏のをはりても咲きみだるる朝顔」
(森井マスミ『まるで世界の終りみたいな』より)
「たましひのほの暗きこと思はせて金魚を容れし袋に影あり」
「クロアゲハ横切る木の下闇の道 許せなくてもよいのだ、きつと」
(西橋美保『うはの空』より)
「このストールを巻くたびに遭うかなしみの砂漠へ放つ、一羽の鷹を」
(千種創一『砂丘律』より)
「樹皮削られ水かけられて除染といふ苦しみののちのりんご〈国光〉」
(大口玲子『桜の木にのぼる人』より)
「夕映えに逆らふごとく耐へゐるか君の眼に棲む水鶏(くひな)を放て」
(大口玲子『海量』より)
「ああすべてなかったことのようであり凌霄花は塀をあふれる」
「つよい国でなくてもいいと思うのだ 冬のひかりが八つ手を照らす」
(中津昌子『むかれなかった林檎のために』より)
「湿り気を空が含んでくる時に言葉は少し曲げやすくなる」
(中津昌子『記憶の椅子』より)
「噴水は空に圧されて崩れゆく帰れる家も風もない午後」
(鳥居『キリンの子』より)
「竈(くど)の火に呑まれし反故のひとつかみ白もくれんは路傍に散れり」
(島田幸典『駅程』 より)
「口内炎舐めつつエレヴェーター待てり次の会議に身を移すべく」
(島田幸典「竹の葉」「八雁」2018年5月号より)
「感情の水脈(みお)たしかめて読点を加えるだけの推敲なせり」
(島田幸典『no news』より)
「一本のワインはテーブルに立ちながら垂直にして燃える歳月」
(加藤孝男『曼茶羅華の雨』より)
「アヌビスはわがたましいを狩りに来よトマトを囓る夜のふかさに」
(吉川宏志『青蝉』より)
「砂肝にかすかな砂を溜めながら鳥渡りゆくゆうぐれの空」
(吉川宏志『鳥の見しもの』より)
「小夜しぐれやむまでを待つ楽器屋に楽器を鎧ふ闇ならびをり」
(光森裕樹『山椒魚が飛んだ日』より)
「世界よりいつも遅れてあるわれを死は花束を抱へて待てり」
(西田政史『スウィート・ホーム』より)
「火のつかぬ松明のよう人は立ち亡き父と入りし立ち飲みは夜明け」
(大野道夫『秋意』より)
「靴ずれを見むと路上にかがむとき雨の路上の音量あがる」
(睦月都『Dance with the invisibles』より)
「生きている者らに汗は流れつつ静かな石の前に集うも」
(松村正直『午前3時を過ぎて』より)
「この先は小さな舟に乗りかえてわたしひとりでゆく秋の川」
(松村正直『風のおとうと』より)
「傘の柄のかたちの街灯つらねては雨の気配に満ちる国道」
(伊波真人『ナイトフライト』より)
「春泥を飛び越えるときのスカートの軽さであなたを飛び越える朝」
(岡崎裕美子『わたくしが樹木であれば』より)
「冬の陽ざしにおもたさ生まれ寺町通(てらまち)の度量衡店に天秤ありつ」
(河野美砂子『無言歌』より)
「プルトップ引きたるのちにさはりみる点字の金色(きん)の粒冷えてをり」
(河野美砂子『ゼクエンツ』より)
「電話ボックス工場のまへに立ちてをり歩哨のごとく廃兵のごとく」
(山田富士郎『商品とゆめ』より)
「アルヘイ棒縞のぐるぐるをやみなく天へ汲み上げらるるたましひ」
(十谷あとり『風禽』より)
「弓張のひかりのなかを黒髪はたゆたひながら結はれゆきたり」
「スジャータのミルクしたたる午(ひる)を生き僕らはやがて樹下のねむりへ」
(小佐野彈『メタリック』より)
「マーブルの光まばゆき煉獄にたつたひとりのをみな、わが母」
(小佐野彈『銀河一族』より)
「天涯花ひとつ胸へと流れ来るあなたが言葉につまる真昼を」
(大森静佳『カミーユ』より)
「ふとぶとと水を束ねて曳き落とす秋の滝、その青い握力」
(大森静佳『ヘクタール』より)
「白木蓮(はくれん)に紙飛行機のたましいがゆっくり帰ってくる夕まぐれ」
(服部真里子『遠くの敵や硝子を』より)
「サリン吸い堕胎を決めたるひとのことそのはらごのことうたえ風花」
(鈴木英子『油月』より)
「東京の水渡りゆくゆりかもめこの日も一生(ひとよ)と墨いろに啼く」
(鈴木英子『月光葬』 より)
「二分咲きの梅に降りくるにわか雪梅花は真白でなきを知りたり」
(なみの亜子『「ロフ」と言うとき』より)
「天使断頭台の如しも夜に浮かぶひとコマだけのガードレールは」
(穂村弘『水中翼船炎上中』より)
「呼吸する色の不思議を見ていたら「火よ」と貴方は教えてくれる」
(穂村弘『シンジケート』より)
「わが顔を剃る人の胸かぐわしく死にたき日には来る理髪店」
(八木博信『ザビエル忌』より)
「満月にすこしかけたる白月が朝顔蔓の輪に入りつ」
(高橋みずほ『白い田』より)
「神々は隠れませども歌うがごとく祈りは残る 花は菜の花」
(佐久間章孔『州崎パラダイス・他』より)
「震えながらも春のダンスを繰り返し繰り返し君と煮豆を食べる」
「ひかりまばらな壁の震えを知るためにコンクリートの窪みに触る」
(堂園昌彦『やがて秋茄子へと到る』より)
「置時計よりも静かに父がいる春のみぞれのふるゆうまぐれ」
(藤島秀憲『すずめ』より)
「三月のわが死者は母左折する車がわれの過ぎるのを待つ」
(藤島秀憲『ミステリー』より)
「朝食の卓に日は射し詩人の血わが静脈にこそ流るるを」
(藤原龍一郎『ジャダ』より)
「夜は千の目をもち千の目に監視されて生き継ぐ昨日から今日」
(藤原龍一郎『202X』より)
「ゆめみられる象(かたち)になり/時をゆく/夢みる者が/彫(きざ)んだ柱」
(小林久美子『アンヌのいた部屋』より)
「切れ長の目をしてゐるね半島の朝、瞼の縁でゆれるバラソル」
(笹原玉子『偶然、この官能的な』より)
「聴いている。茗荷ふたつに切り分けた静けさに耳ふたつひろげて」
(遠藤由季『鳥語の文法』より)
「心いま針のようなりひとすじの糸通さねば慰められぬ」
(遠藤由季「うさぎ座の耳」(「短歌研究」2018年3月号より))
「大鳥よその美しき帆翔を見上げずに人は汚泥を運ぶ」
(齋藤芳生『湖水の南』より)
「その枝のあおくやさしきしたたりよひとは水系に傘差して生く」
(齋藤芳生『花の渦』より)
「お互いの生まれた海をたたえつつ温めてあたたかい夕食」
(𠮷田恭大『光と私語』より)
「諦めたものから燃えて空色の地図を汚してゐるバツ印」
(濱松哲朗『翅ある人の音楽』より)
「桜花コンクリートに溶けてゆくひとひらにひとひらのまぼろし」
(鈴木晴香『心がめあて』より)
「野の花を挿せばグラスの底よりも深く沈んでしまう一輪」
(鈴木美紀子『金魚を逃がす』より)
「夕焼けの浸水のなか立ち尽くすピアノにほそき三本の脚」
(鈴木加成太「革靴とスニーカー」より)
「銀盆にひまはりの首級盛りて来る少女あれ夏空の画廊に」
「この町に雪は降りだす少年の描きさしの魔方陣に呼ばれて」
(鈴木加成太『うすがみの銀河』より)
「傘のまるみにクジラの歌は反響す海へとつづく受け骨の先」
「三月の君の手を引き歩きたし右手にガーベラ握らせながら」
(立花開『ひかりを渡る舟』より)
「交番の手配写真に過激派の若き微笑はながくそのまま」
(野上卓『チェーホフの台詞』より)
「なにもなき日々をつなぎて生きてをり皿の上には皿を重ねて」
(門脇篤史『微風域』より)
「軽やかに蝶白くいく灼熱の土にその影ひきずるように」
(木下のりみ『真鍮色のロミオ』より)
「鉢の上にブーゲンビリアの苞落ちぬ思慕燃え残るごときむらさき」
(本川克幸『羅針盤』より)
「われの血の通いてちいさな臓器となるその一瞬の蚊を打ち殺(や)りぬ」
(北辻一展『無限遠点』より)
「はるかなる処より矢が放たれて地に突き刺さりをり曼珠沙華」
(片岡絢『カノープス燃ゆ』より)
「きみにしずむきれいな臓器を思うとき街をつややかな鞄ゆきかう」
「三〇歳を抜けたる先の麦の穂のなんて壮大なボーナストラック」
「父を憎む少年ひとりをみつめゐる理科室の隅の貂の義眼は」
(楠誓英『薄明穹』より)
「三角定規で平行の線を引くときの力加減で本音を話す」
(竹中優子『輪をつくる』より)
「くれないのくずれし薔薇(そうび)すてるとき花瓶の水ににげるひとひら」
(池田裕美子『時間グラス』より)
「どの線路が薔薇へ向かうか知っている今日も火口に雨の降る朝」
(大橋弘『既視感製造機械』より)
「火をつけるときのかすかなためらひを共犯のやうに知るチャッカマン」
(千葉優作『あるはなく』より)
「くちびるに触れるあたりをつと触れて盃ふたつ買う陶器市」
(toron*『イマジナシオン』より)
「かなしいね人体模型とおそろいの場所に臓器をかかえて秋は」
(安田茜『結晶質』より)
「由比の海に対える如月朔日に身は乾きゆく午後をしずかに」
(永田淳『竜骨(キール)もて』より)
「天心に半月清かに駆けており君を想わんための一時」
(永田淳『1/125秒』より)
「バス停に本読む老人(ひと)よ桜散るこの世の何を知らむとや急く」
(王紅花『窓を打つ蝶』より)
「死にたいとそっと吐き出すため息の軽さで少し進む笹舟」
(岡本真帆『水上バス浅草行き』より)
「しっぽだけぶれてるphotoのそうやってあなたに犬がそばにいた夏」
(岡野大嗣『音楽』より)
「ショッピングモールはきっと箱船、とささやきあって屋上へ出る」
「日の照れば返すひかりのはかなさのさくらばなとは光の喉首(のみど)」
(笠木拓『はるかカーテンコールまで』より)
「秋深し桔梗の色の海を渡る移動サーカスの象の姉妹に」
(蝦名泰洋『ニューヨークの唇』より)
「雑沓を怖るる象よゆらゆらと影のみ顕(た)てる夏のサーカス」
(橘夏生『セルロイドの夜』より)
「「お母さん」と亡きがらにこそ呼べ時計屋の針いつせいにかがやく五月」
(橘夏生『大阪ジュリエット』より)
「子は腕に時計を画いていつまでもいつまでもそは三時を指せり」
(久保茂樹『ゆきがかり』より)
「見るだろう驟雨のあとのさよならをしずかにひかる夏のいのちを」
(窪田政男『Sad Song』より)
「鋤跡のわずかに残る冬の田をパンタグラフの影わたりゆく」
(鯨井可菜子『アップライト』より)
「うつつならうつつのものとして触れる花あわあわとけぶる栴檀」
(古川順子『四月の窓』より)
「燃えている色の紅葉を踏むときの燃え尽きた音 駅まで歩く」
(工藤玲音『水中で口笛』より)
「もの割るる音してのちに上がるべき悲鳴を聞かず春のゆふぐれ」
(高野岬『海に鳴る骨』より)
「冬には冬の時間があってひとときの余白を病める土鳩のように」
(笹川諒『水の聖歌隊』より)
「檀弓(まゆみ)咲くさつきのそらゆふりいづる母のこゑわれにふるへてゐたり」
(山下翔『温泉』より)
「生は揺らぎ死はゆるぎなし夕暮れて紫深きりんだうの花」
(小笠原和幸『黄昏ビール』より)
「ヒト以外ノモノノ生(シヤウ)ニハ使命有リ晩鴉(バンア)ノ夫(ソレ)ハ感傷ノ駆除」
(小笠原和幸『穀潰シ』より)
「車窓よりつかのま見えてさむざむと乗馬クラブの砂にふるあめ」
(小池光『サーベルと燕』より)
「トライアングルぎんいろの海をみたしつつ少年が打つ二拍子ほそし」
「いまだ掬はぬプリンのやうにやはらかくかたまりてゐるよ夏の休暇日」
(上村典子『草上のカヌー』より)
「あの夏の拾い損ねたおはじきがためてるはずの葉擦れのひかり」
(正岡豊『白い箱』より)
「きみがこの世でなしとげられぬことのためやさしくもえさかる舟がある」
(正岡豊『四月の魚』より)
「廃線を知らぬ線路のうすあおい傷をのこして去りゆく季節」
「死ぬまでが暇だな 歌をうたひたい花の名前をもつと知りたい」
「東京ゆき夜行バスにていま君がともす小さな灯りを思ふ」
(逢坂みずき『虹を見つける達人』より)
「昼すぎの木立のなかで着ぶくれの君と僕とはなんども出会う」
(宇都宮敦『ピクニック』より)
「ともかくも家の明かりを全部消す今日のつじつま合はなくてよし」
(永井陽子『小さなヴァイオリンが欲しくて』より)
「鹿たちも若草の上(へ)にねむるゆゑおやすみ阿修羅おやすみ迦楼羅」
(永井陽子『てまり唄』より)
「会うことも会わざることも偶然の飛沫のひとつ蜘蛛の巣ひかる」
「肝臓の細胞とどく秋の日のほのかな廊下に受け取りサインす」
「時間にも色や気泡のあるならむ容器に溜めて振ってみるなら」
(永田紅『春の顕微鏡』より)
「春雨のしずかに濡らす屋根がありその屋根の下ふたつ舌あり」
「まぶたにも縞を持ちたる縞馬に桜の花の降りやまずけり」
「もの思うごとくしずかに沈みゆき花びらひとつふたつ吐きたり」
(奥田亡羊『亡羊』より)
「一日のなかば柘榴の黄葉のあかるさの辺に水飲み場みゆ」
「夏草をからだの下に敷きながらねむり足(た)りたれば服濡れてをり」
(横山未来子『花の線画』より)
「夕風のいでたる庭を丈たかき百合揺れてをり花の重みに」
(横山未来子『とく来たりませ』より)
「燃えたぎる鍋を見すえて だいじょうぶ これは永遠でないほうの火」
(井上法子『永遠でないほうの火』より)
「それは世界の端でもあつてきみの手を青葉を握るやうに握つた」
「人の内部はただの暗がりでもなくてあなたの底の万緑をゆく」
「常に世界にひかりを望むといふやうな姿勢ゆるめて緑蔭をゆく」
(荻原裕幸『リリカル・アンドロイド』より)
「わが生にいかなる註をはさめども註を超えつつさやく青葉は」
(荻原裕幸『デジタル・ビスケット―荻原裕幸歌集』より)
「壁のそばに葉が揺れてゐる葉のうらに風が光つてゐる五月であるも」
(加藤克巳『螺旋階段』より)
「歪形(わいけい)歯車の かんまんなきざみの意志たちの冷静なかみあいの、──この地球のこのおもいおもい午後」
(加藤克巳『球体』より)
「君を択び続けし歳月、水の中に水の芯見えて秋の水走る」
(河野裕子『紅』より)
「時の流れにさからうための筋力よ鉄棒の鉄の匂いをつけて」
(花山周子「現代短歌」2022 No.88より)
「小説を書くとは蛇になることぞ 川端康成の眼をおもふ」
「夕皃(ゆふがほ)の花しらじらと咲めぐる賤(しづ)が伏屋に馬洗ひをり」
(橘曙覧『橘曙覧全歌集』より)
「飲食(おんじき)の最後にぬぐう白き布汚されてなお白鮮(あたら)しき」
(錦見映理子『ガーデニア・ガーデン』より)
「いまを吹く風 恐竜のほんとうの鳴き声を誰もずっと知らない」
(近江瞬『飛び散れ、水たち』より)
「夢のなかで誰とはぐれしわれならむはぐれたること少しうれしく」
(栗木京子『ランプの精』より)
「ゴンドラが緑の谷の上をゆく うれしさと不安の起源はおなじ」
(五島諭『緑の祠』より)
「木の柵に進入禁止と記さるる言葉の後ろに回つてみたり」
(香川ヒサ『The Blue』より)
「何故ああであつたか 神の沈黙は押し入つてくる扉閉めても」
(香川ヒサ「それぞれの夏」(角川「短歌」2018年10月号)より)
「けし、あやめ、かうほね、あふひ、ゆり、はちす、こがねひぐるま夏の七草」
(高野公彦『河骨川』より)
「わたしたち/わたしたち/わたしたち/わたしたち/わたしたち/わたしたち/わたし」
(今橋愛「短歌WAVE」創刊号より)
「あぢさゐも樹だと気づけて良かつたよ並木道へと変はるこの路地」
「あまりにも帰りたすぎるどこへ、いつへ、帰りたいのか分からないけど」
「おまへは何になる気なんだと父が言ふ何かにならねばならぬのか、われは」
「ケイコウペンのケイは蛍であることを捕まへて見せてくれし大き手」
「ストーブの効いた部屋から雪を見る 出会ふまへ他人だつたのか僕らは」
「だれにでもやさしくしなくていいんだよ過去への手紙は届けられない」
「ななななと故郷の時は流れけり おどでな きんな ゆべな さつきな」
「なめらかなプリンを先割れスプーンで掬ふやうなる一日なりけり」
「ハッピーに長生きしたい人生というバイキングで元を取りたい」
「胸元にDESTINYと書かれたる服着て夜の車窓に映る」
「寝過ごせば動物園に着くといふ電車を今日も途中で降りる」
「東京の夜景の中で泣いてゐたあれはがんばれる人の光だ」
「ヒーローはみんなを助ける人なりと京王線にをさなご元気」
(今野寿美『さくらのゆゑ』より)
「一片の雲ちぎれたる風景にまじわることも無きわれの傷」
「はかなさを美へとすりかえるいっしゅんの虚偽を射よ 杳(くら)き眼光もて」
「優しさを撃て 隊列のくずされてゆく一瞬の真蒼な視野」
「ああされど 火中(ほなか)に立ちて問うこともせず問われるままに過ぎゆきつ」
「日常の視界のかなた何ゆらぎつつあらん ひと群の樅そよげるを」
「ああソーニャ、霜おく髪の孤独より失意よりわれを発たしむなかれ」
(三枝浩樹『朝の歌』より)
「神よいかなる諸力のもとにつかのまの光芒としてあゆむわれらぞ」
「ゆく人も来る人もなしひもすがらこまかなる葉をこぼすからまつ」
「あやめざるこころのなかへひきかえす夏のゆうべの火のほとりより」
「南天の実のかたわらを過ぐるとき杳(とお)き悲傷の火のにおいくる」
「告げなむとして翳る舌 灯のなかにわれらしずかな死をかさねあう」
「雨の午後しずかに昏れてうつうつとむらさきの葡萄ジャムを煮つむる」
(三枝浩樹『銀の驟雨』より)
「ルリカケス、ルリカケスつてつぶやいた すこし気持ちがあかるくなつた」
(秋月祐一『この巻尺ぜんぶ伸ばしてみようよと深夜の路上に連れてかれてく』より)
「大輪の花火はじける五億年後にぼくたちの化石をさがせ」
(秋月祐一『迷子のカピバラ』より)
「ゆふぞらを身ひとつで行く鳥たちは陽の黄金(わうごん)につつまれて飛ぶ」
(小島ゆかり『馬上』より)
「針葉樹は燃えやすい樹といつ誰に教はつたのか、空よ、夕焼け」
(杉森多佳子『つばさ』第17号より)
「ギャラリーへ続く階段くだるときしんと寡黙になる貌を見き」
「スカートの裾ゆつたりと捌きつつ春のねむたき坂くだりゆく」
「午前から午後へとわたす幻の橋ありて日に一度踏み越す」
(菅原百合絵『たましひの薄衣』より)
「春は花の磔(はりつけ)にして木蓮は天へましろき杯を捧げつ」
「さからはぬもののみ佳しと聞きゐたり季節は樹々を塗り籠めに来し」
「晴らす(harass) この世のあをぞらは汝が領にてわたしは払ひのけらるる雲」
(川野芽生『Lilith』より)
「責めるとか許すとかいふのもちがふ 馬肥ゆる秋 だから忘れず」
(染野太朗「反転術式」『外出』八号より)
「そのままのきみを愛するなんてのは品のないこと 秋 大正区」
(染野太朗『うた新聞』より)
「ブロイラーをレグホンの卵でとじたもの同僚一○人一斉に食む」
(大井学『サンクチュアリ』より)
「つるつるに頭を剃っておりますが僧の中身は誰も知らない」
(大下一真『即今』より)
「母生きてヴァージンオリーヴオイル持ち我へ手渡すそのたまゆらよ」
(大滝和子『竹とヴィーナス』より)
「猫たちが思い思いに伸びをする世界は今日も平和ちゃうかな」
(谷じゃこ『ヒット・エンド・パレード』より)
「A god has a “life file”, which is about the collapse of my cool core. (罪色の合わせ鏡のその奥の君と名付けた僕を抱き取る)」
(中島裕介『Starving Stargazer』より)
「みな白き家電並びぬ わたくしは汚れるために生活をする」
(辻聡之『あしたの孵化』より)
「みぎの手をそらにかざしてうたふこゑ君はやつぱり晴れをとこゆゑ」
(田口綾子『かざぐるま』より)
「藤棚のやうに世界は暮れてゆき過去よりも今がわれには遠い」
(田村元『北二十二条西七丁目』より)
「不義にして富むニッポンの俺である阿阿志夜胡志夜(ああしやこしや)こは嘲笑ふぞ」
(島田修三『晴朗悲歌集』より)
「歩道橋を降りてまっすぐ歩いてる日陰まであと三歩の遠さ」
「途中からツツジの色が白くなるセブンイレブン前の歩道は」
「くるぶしの近くに白い花が咲く靴紐を結い直す時間に」
(嶋稟太郎『羽と風鈴』より)
「揺り椅子にゆれているのは〈時〉を漕ぎ疲れて眠るリリアン・ギッシュ」
(藤沢蛍『時間(クロノス)の矢に始まりはあるか』より)
「通過電車の窓のはやさに人格のながれ溶けあうながき窓みゆ」
(内山晶太『窓、その他』より)
「存分に愉しみしゆゑ割れるのを待たずに捨てる緑のグラス」
(内藤明『薄明の窓』より)
「〈みんなのもの〉のむごさの中にすりきれた公園のパンダ夕べに沈む」
(梅内美華子『真珠層』より)
「ウオッカといふ牝馬快走その夜のわたしの肌のやすらかな冷え」
(梅内美華子『エクウス』より)
「ティーバッグのもめんの糸を引き上げてこそばゆくなるゆうぐれの耳」
(梅内美華子『若月祭』より)
「はくれんにレンギョウそして桃の花おまえの空に色をそよがす」
「日めくりを猛スピードでめくりゆく風のただなか突っ張っている」
(樋口智子『幾つかは星』より)
「言葉から言葉つむがずテーブルにアボカドの種芽吹くのを待つ」
(俵万智『アボカドの種』より)
「お軽、小春、お初、お半と呼んでみる ちひさいちひさい顔の白梅」
(米川千嘉子『滝と流星』より)
「蔑(なみ)されて美(は)しき東洋黒馬の踏みたつごときSUSHI・BARの椅子」
(米川千嘉子『一夏』より)
「傘といふすこし隙ある不思議形にんげんはあと何年つかふ」
(米川千嘉子『あやはべる』より)
「靴先で流れ裂きつつ遡上せむ梅雨の坂道水脈引きながら」
「いつせいに風上を向く傘の先雨が歌だと知つてゐるのだ」
(木ノ下葉子『陸離たる空』より)
「すべてを選択します別名で保存します膝で立ってKの頭を抱えました」
(飯田有子『林檎貫通式』より)
「人の声渦巻く中に眼つぶれば笑うというより咲いている君」
(入谷いずみ『海の人形』より)
「草むらをひとり去るとき人型に凹(くぼ)める草の起ち返る音」
(宮柊二『日本挽歌』より)
「ヒヤシンスの根の伸びゆくをみつめいる直線だけで書ける「正直」」
(鶴田伊津『百年の眠り』より)
「らくがきの「かじ山のバカ×一〇〇〇〇〇〇〇〇〇」のかじ山を思ひ出せず」
(真中朋久『重力』より)
「二千年 前、に生(うま)れた嬰児(みどりご)の(さう!)血の色のリボン、を、結ぶ」
(石井辰彦『蛇の舌』より)
「燐寸使ふことの少なくなりしより闇照らすなし濃密の闇を」
(伊藤一彦『新月の蜜』より)
「冀(こひねが)ふ鳥のこゑ降る林なりひもじさこそ詩ひもじさこそ歌「
(伊藤一彦『土と人と星』より)
「「はえぬき」の炊きたてを食む単純な喜びはいつも私を救う」
(三枝昻之『上弦下弦』より)
「忘恩というえにしあり花咲けばゆるむこころのあわれなりけり」
(三枝昻之『遅速あり』より)
「ゆふがほの解(ほぐ)れるときのうつつなるいたみはひとの指をともなふ」
(平井弘『振りまはした花のやうに』より)
「知る人ぞ知る体温として残れかし辞書への赤字を日々に重ねて」
(大島史洋『封印』より)
「ヘヴンリー・ブルー 花であり世界でありわたくしであり まざりあう青」
(早坂類『ヘヴンリー・ブルー』より)
「寄り弁をやさしく直す箸 きみは何でもできるのにここにいる」
(雪舟えま『たんぽるぽる』より)
「「青ですね」「青ですね。でもわたしたち歩行者ではありま「赤ですね」」
(斉藤斎藤『渡辺のわたし』より)
「坂を登ると見ゆる水面や登りきて打ちつけに光の嵩にまむかふ」
(春日井建『朝の水』より)
「ふり仰ぐ一生(ひとよ)半ばの夏空をよろこびとせむ 私(わたくし)祭」
(高島裕『嬬問ひ』より)
「ガラス一枚へだてて逢えばひとはたれもゆきずりの人となりてなつかし」
(光栄堯夫『ゴドーそれから』より)
「右へでも左へでもなだれ打つときの「群」といふもののその怖さつたら」
(岡井隆『ネフスキイ』より)
「背中から十字に裂ける蝉の殻 生きゆくは苦しむと同義」
(伊津野重美『紙ピアノ』より)
「繁りたる木したを潜りゆく膚に椎の花の香触れつつながれ」
(阿木津英『黄鳥』より)
「死者に逢ふ、ことだつてある……… 写真帖(アルバム)を繰るやうに街角を曲れば」
(石井辰彦『詩を弃て去つて』より)
「三年ガラス拭かぬわれが日に五たび床を拭き床に映る鳥影」
(酒井佑子『矩形の空』より)
「『夜と霧』つめたきこころのままに読みときどきおほき黄の付箋貼る」
(藪内亮輔「海蛇と珊瑚」より)
「山に来て二十日経ぬれどあたたかく我をば抱く一樹だになし」
(岡本かの子『かろきねたみ』より)
「きつとある後半生のいつの日かサヨナラゲームのやうなひと日が」
(影山一男『桜雲』より)
「秋光のいまなにごとか蜘蛛の巣に勃(お)こるまでわが視野の澄むべし」
(小中英之『わがからんどりえ』より)
「一束の野の青草を朝露と共に負ひゆく農婦に遇へり」
(築地正子『花綵列島』より)
「覚めてまたわが目とならむ双眼をしづかに濡らし今朝秋の水」
(照屋眞理子『抽象の薔薇』より)
「予言者の闇には時の星座あれ蒼き髪より蝶を発たしむ」
(江田浩司『メランコリック・エンブリオ』(北冬舎)より)
「蔽はれしピアノのかたち運ばれてゆけり銀杏のみどり擦りつつ」
(小野茂樹『羊雲離散』より)
「人間を休みてこもりゐる一日見て見ぬふりの庭の山茶花」
(志垣澄幸『東籬』より)
[異種百人一首選考外短歌(その3)](557首)
「世間よのなかは霰よなう 笹の葉の上への さらさらさつと降るよなう」
(『閑吟集』より)
「三月はいつ目覚めても風が吹き原罪という言葉浮かび来」
(さいとうなおこ『逆光』より)
「年下の若きからだをおもうときわが指先は草汁に触る」
(なみの亜子『バード・バード』より)
「膝を折るきりんの檻に背をつけて雨より深いくちづけをして」
(ひぐらしひなつ『きりんのうた。』より)
「きみが十一月だったのか、そういうと、十一月は少しわらった」
(フラワーしげる『ビットとデシベル』より)
「なつかしい野原はみんなとおくから来たものたちでできていました」
(やすたけまり『ミドリツキノワ』より)
「ボンネットに貼りつく無数の虫の死が星座のように広がっている」
(ユキノ進『冒険者たち』より)
「すれ違うときの鼻歌をぼくはもらう さらに音楽は鳴り続ける」
(阿波野巧也「さらに音楽は鳴り続ける」(「短歌研究」2016年11月号)より)
「眼も魔羅も老いさらばえよわがものにはやもはやなりてしまえよ」
(阿木津英『紫木蓮まで・風舌』より)
「とどろける環状七号線上の橋をしょんがらしょんがら渡る」
(阿木津英『白微光』より)
「何ものの声到るとも思はぬに星に向き北に向き耳冴ゆる」
(安永蕗子『魚愁』より)
「冬天に残る柘榴のひとつのみ瑕瑾だらけといふが愛しも」
(安永蕗子『緋の鳥』より)
「よきものとなりますように 落鳥の地から萌え出る楡の木もあり」
(伊津野重美「生命の回廊」3号より)
「死に鳥の墓標となりて紫陽花のその身を赤く変じてゆけり」
(伊津野重美『紙ピアノ』より)
「かぜはかぜ われはわれなれど 書かざりしわが詩の一部こそ風の芯」
(伊藤一彦『瞑鳥記』より)
「スプーンがカップの底に当たるときカプチーノにも音階がある」
(伊波真人『ナイトフライト』より)
「飛ぶほたる日かげみえ行く夕暮になほ色まさる庭のあぢさゐ」
(衣笠家良『夫木和歌抄』より)
「瑠璃紺の始祖鳥の胸かがやきて宇宙空間に降れるこなゆき」
(井辻朱美『コリオリの風』より)
「ゆたゆたと泡盛りあがるグリーンティー宇宙樹より来るみどりの時間」
「中国の茶器の白さが浮かぶ闇ここ出でていづれの煉獄の門」
「陶製の浴槽(バス)に体をはめこみて森の国(カレドニア)での暮れぬたそがれ」
(井辻朱美『水晶散歩』より)
「眼路のかぎりみはるかす冬黄昏の地平どこまでわれらが地球(テラ)」
(井辻朱美『地球追放』より)
「みどりごは鳥の形態(かたち)に腕ひろげ飛ぶと見えしがねむりゆくなり」
「楠若葉すでに夕映 屋上にわれはキリンの視野を寂しむ」
(一ノ関忠人『群鳥』より)
「イヤフォンではやりの歌を聴きながらあかるく雪ふるここで待ってる」
(宇都宮敦「ハロー・グッバイ・ハロー・ハロー」『短歌ヴァーサス』10号より)
「はなうたをきかせてくれるあおむけの心に降るのは真夏の光」
「左手でリズムをとってる君のなか僕にきけない歌がながれる」
(宇都宮敦『ピクニック』より)
「コカ・コーラじんじん甘し身のほどの泪の薄くにじみくるまで」
(雨宮雅子『水の花』より)
「曖昧に蓴菜(じゅんさい)すする昼の餉(け)や薄暮家族となりゆくわれら」
(雨宮雅子『昼顔の譜』より)
「レジの女(ひと)の指(おゆび)がひどく荒れてゐる指がわれにおつりを呉れぬ」
(浦河奈々『サフランと釣鐘』より)
「一昔前のやうなる水村(すいそん)をバスより見をり旅にあらねど」
(影山一男『空夜(くうや)』より)
「坂に置かれたオレンジのピンポン玉として残りの八月をくだってく」
(永井祐「広い世界と2や8や7」より)
「いるんだろうけど家に入って来ないから五月は終わり蚊を見ていない」
(永井祐『日本の中でたのしく暮らす』より)
「妙にあかるきガラスのむかう砂丘よりラクダなど来てゐるやもしれぬ」
(永井陽子『モーツァルトの電話帳』より)
「カーテンのむかうに見ゆる夕雲を位牌にも見せたくて夏の日」
(永井陽子『小さなヴァイオリンが欲しくて』より)
「アトリ科の鳥とのみしか分からぬが柿の枝より移りてゆけり」
(永田淳『1/125秒』より)
「繰り返し歌うべきものとして我に近しき死者たちはあり」
「流れないのなら僕はもう帰るよカシオペアを空に残して」
(永田淳『竜骨(キール)もて』より)
「あの胸が岬のように遠かった。畜生! いつまでおれの少年」
(永田和宏『メビウスの地平』より)
「月光の柘榴は影を扉におとす重き木の扉(どあ)なればしずかに」
(永田和宏『黄金分割』より)
「「聖家族教会」なんと作業中の工事現場にて教会にあらず」
(奥村晃作『ピシリと決まる』より)
「羽収めて落ちながら飛ぶ鳥の影ゆだねむわれをわれの見ぬ日へ」
「白昼に覚めたる眼(まなこ)ひらきつつ舟の骨格を見わたすごとし」
「五月の樹をゆるがせて風来たるのち芯までわれを濡らす雨あれ」
(横山未来子『花の線画』より)
「変はり得ぬわれを率ゐて十月と九月をつなぐ真夜を渡りつ」
(横山未来子『水をひらく手』より)
「地球は洋梨の形であると書かれをり うふふふふふと読みつつ笑ふ」
(王紅花『夏の終りの』より)
「『わが告白』なる自著の上に降りそそぐ批判の渦の中の春先」
(岡井隆「短歌」2013年1月号より)
「あたたかき日に氷片のごとき日をはさみて冬のはじめ子は癒ゆ」
(岡井隆『αの星』より)
「はい、あたし生まれ変わったら君になりたいくらいに君が好きです。」
(岡崎裕美子『発芽/わたくしが樹木であれば』より)
「バラ咲いて五日を家にこもりけりこの朝土に花くずの嵩」
「冬波のしぶきのあとの乾きたる眼鏡をはずし卓上に置く」
「大いなるくしゃみを二つせし夜のその沈黙に耳は驚く」
(岡部桂一郎『一点鐘』より)
「あおあおと一月の空澄めるとき幻の凧なか空に浮く」
(岡部桂一郎『竹叢』より)
「追突のトラックの音するどくて群集のなかわれは笑えり」
(岡部桂一郎『木星』より)
「妹をさがしゆく夕 どの貌も妹に似てあぢさゐなりき」
(岡部史『海の琥珀』より)
「みづからの雨のしたたりにあぢさゐの花は揺るるにおのおのにして」
(岡部文夫『雪天』より)
「七月の日照(ひでり)の庭にちひさなるとかげ光りて見えかくりする」
(岡本かの子『浴身』より)
「ほんとうの愛のことばをでたらめな花の言葉として贈るから」
(岡本真帆『水上バス浅草行き』より)
「熱き息頬に触るるかと思ふまで近づかしめて射ちはなちたり」
(岡野弘彦『冬の家族』より)
「これも聴いてみる?を聴いていて外の流れる町に春をみている」
(岡野大嗣『音楽』より)
「秋の字の書き順ちがふちがひつつ同じ字となる秋をふたりは」
(荻原裕幸『リリカル・アンドロイド』より)
「まだ会社に慣れないせゐかオフィスでは鏡と犬が区別できない」
(荻原裕幸『世紀末くん!』より)
「われに向ひて光る星あれ冬到る街に天文年鑑を買ふ」
「みづいろの楽譜に音符記されずただみづいろのまま五月過ぐ」
(荻原裕幸『青年霊歌』より)
「首と首互みに鳴らす子きりんの股間きららに風薫る夕」
(加藤孝男『曼茶羅華の雨』より)
「きいんとひきしまつた空へしたたらすしづくは硝酸でなければならぬ」
(加藤克巳『宇宙塵』より)
「春三月リトマス苔に雪ふって小鳥のまいた諷刺のいたみ」
(加藤克巳『球体』より)
「たたきのめされ がーっと家が 無惨無情のこっぱみじんに」
(加藤克巳『天壇光』より)
「パンを焼くベルトが巡るじりじりとざわめく朝のホテル太平洋」
(加藤治郎『しんきろう』より)
「分節はいたく苦しもゆるやかにキリンの舌が枝にからまる」
(加藤治郎『ハレアカラ』より)
「逢ったのはインターネットそこはただ風の生まれる原っぱだった」
(加藤治郎『環状線のモンスター』より)
「宮人の夏のよそひの二藍にかよふもすずしあぢさゐの花」
(加藤千蔭『うけらが花』より)
「夕月夜ほの見えそめしあぢさゐの花もまどかに咲きみちにけり」
(加納諸平『柿園詠草』より)
「ひそかなる盗みに似たりひとりなる姪を抱きて行く街のうら」
(河野愛子『草の翳りに』より)
「ふれがたく黒白の鍵盤(キイ)整列す美しい音の棺のやうに」
「植物に水をあたへてしばらくを耳すましをり濡れてゆく音」
(河野美砂子『ゼクエンツ』より)
「どこからが音であるのか一本の指のおもさが鍵盤(キイ)になるとき」
「すこしづつ息のはやさがずれてゐて合はさつた手のおもさかんじる」
(河野美砂子『無言歌』より)
「六十四まで生きえしこの身をよしとせむ生れ月七月は黄瓜の匂ひす」
(河野裕子『蟬声』より)
「音楽のように生きたい」英語の授業に眠りつつ聞く」
(花山周子『屋上の人屋上の鳥』より)
「紙ヒコーキが日に日に紙にもどりゆく乾ける落葉だまりの上に」
(花山多佳子『春疾風』より)
「教科書の詩を読みながらどうしても唄ってしまう子がやり直す」
「七月十七日かなかな鳴けり幾度か短く鳴けり夜のベランダに」
(花山多佳子『草舟』より)
「紫陽花の葉うらにいたる少さき蜘蛛すばやく降りぬわが眼前を」
(花山多佳子『楕円の実』より)
「フライパンに胡麻をゆすれば胡麻のなき円形現はる つねに一か所」
(花山多佳子『木香薔薇』より)
「からつぽのからだいくつもころがりをり「本番」の声までのつかのま」
(花鳥佰『しづかに逆立ちをする』より)
「音叉庫にギリシア銅貨の墜ちる音わが鎖骨さえ共鳴りのする」
(蝦名泰洋『ニューヨークの唇』より)
「黒峠とふ峠ありにし あるひは日本の地図にはあらぬ」
「みどりのバナナぎつしりと詰め室(むろ)をしめガスを放つはおそろしき仕事」
(葛原妙子『原牛』より)
「拾ひたる落葉は星にかくも似て一つの旅をわれは終へたり」
(喜多昭夫『青霊』より)
「白き花の地にふりそそぐかはたれやほの明るくて努力は嫌ひ」
(紀野恵『フムフムランドの四季』より)
「王女死せし砂漠のうへを吹き来し吾がほそ道の火の躑躅揺る」
「女東宮(にょとうぐう)あれかし庭に雀の子遊ばせてゐる二十五、六の」
(紀野恵『架空荘園』より)
「傾けむ国ある人ぞ妬ましく姫帝によ柑子差し上ぐ」
(紀野恵『短歌パラダイス』より)
「あじさいがまえにのめって集団で土下座をしとるようにも見える」
(吉岡太朗『ひだりききの機械』より)
「本はつねに本を呼びおりその声に引かれて買いぬ雨の表紙の」
「夏空は帽子のつばに区切られて銅貨のように落ちてゆく鳥」
(吉川宏志『燕麦』より)
「おまえにも麒麟にもない喉ぼとけ曝し歩まんマフラーほどいて」
「昔からそこにあるのが夕闇か キリンは四肢を折り畳みつつ」
(吉川宏志『鳥の見しもの』より)
「ふるさとで日ごとに出遭う夕まぐれ林のなかに縄梯子垂る」
「紙コップ熱きを妻に手渡せりキリンの首は秋風を漕ぐ」
(吉川宏志『夜光』より)
「あちこちで瞬くひかり人の役に立ちたいって顔をかき分け進む」
「地中ふかく根を張るものへ憧れを抱き樹形図の先に滴る」
「色薄き頬に手を寄せ我が系(すじ)とのたまう母の遠き紫陽花」
(吉野亜矢『滴る木』より)
「家族には告げないことも濃緑(こみどり)のあじさいの葉の固さのごとし」
(吉野裕之『ざわめく卵』より)
「古びたるジャングル・ジムの胎内を震はすやうに秋風はふく」
(橘夏生『セルロイドの夜』より)
「けふもまた「恋は水色」の音にのつてわらびもち売り来たる不可思議」
(橘夏生『大阪ジュリエット』より)
「吊り橋と吊り橋をゆく人々の影うつしゐる秋の川底」
(久我田鶴子『ものがたりせよ』より)
「梅咲いて梅散ってたちまち終わりにき風ひかる二月われのきさらぎ」
(久々湊盈子『風羅集』より)
「百枚のまぶたつぎつぎ閉じられてもう耳だけの町となりたり」
(久野はすみ『シネマ・ルナティック』より)
「としどしに臘梅紅梅咲きつげばこのまま長く生きむ気のする」
(宮英子『西域更紗(さいゐきさらさ)』より)
「美しく窒息しつつ咲くのだと教える「愛の水中花」ゆら」
(宮川聖子『水のために咲く花』より)
「匂ひの記憶、ではなく記憶そのものの匂ひとおもふ四月の雨は」
(魚村晋太郎『バックヤード』より)
「その位置に窓とめておく金属の穴と突起があつて、夕暮」
(魚村晋太郎『花柄』より)
「聴きつつ睡るラジオの底の夏祭りそこ曲がり紫陽花を傷むるな」
(魚村晋太郎『銀耳』より)
「「生きてるのが不思議なくらゐだ人間は」解剖医の声思ひ出す夏」
(橋場悦子『静電気』より)
「バスの中誰も声せず幼きがあーあとふかきかなしみもらす」
(玉井清弘『六白』より)
「繁みたてる梢をこむる朝もやの白きが中を鳥翔けりゆく」
「六月の朝のくもりを雀とぶそらより土に土より空へ」
「ねむるときとどろきをりし雨の音あかとき聞けばはらつきにけり」
(玉城徹『われら地上に』より)
「冬越えむとして厚き葉がかたはらの祈りのごとき幹に触れをり」
(玉城徹『樛木』より)
「手の甲に浮く老斑の濃く淡くひと恋いしこと長く忘れず」
(錦見映理子『短歌、WWWを走る。』より)
「窓の下を花輪はこびて行きにけり雨となりたる五分ほど前」
(近藤芳美『早春歌』より)
「ミクソリディアン音階かけのぼってゆくひとひらの雪きみのゆびさき」
(金川宏『アステリズム』より)
「はらわたをさらすがごとくドアひらき総武線、中央線の客ら交らふ」
「午後四時の地下鉄に誰もまどろみて都市の腸(はらわた)しづかに傷(いた)む」
(栗木京子『水仙の章』より)
「今しばし日向臭さを持ちゐたし濡れしものみな美しき世に」
(栗木京子『水惑星』より)
「十月の跳び箱すがし走り来て少年少女ぱつと脚ひらく」
(栗木京子『綺羅』より)
「「シュッ、コロリ」などと謳ふを笑ひつつ買ひしがまことシュッ、コロリ死ぬ」
(桑原正紀『一天紺』より)
「はつかなるえにしのありてこの猫と朝の閻浮の水わかち飲む」
(桑原正紀『時のほとり』より)
「ただよひてゐたる未生の言葉らも今はしづけく白水に帰す」
(桑原正紀『白露光』より)
「閉店のやさしい音楽が流れて、旅を勧めてくる雑誌を閉じる」
(郡司和斗『かりん』第43巻第5号より)
「藤の花のにほひしづかに降りてきてわれに王者の夕暮れがくる」
(経塚朋子『カミツレを摘め』より)
「あぢさゐの花のよひらにもる月を影もさながら折る身ともがな」
(源俊頼『散木奇歌集』より)
「ソックスを履かず冷えるにまかせたる指をはつ夏の陽に差し入れぬ」
(源陽子『桜桃の実の朝のために』より)
「まひる日にさいなまれつつ匂ひけりやや赤ばめる紫陽花のはな」
(古泉千樫『屋上の土より』)
「幼子は幼子をふと見返りぬふたつ家族のすれ違ふとき」
(古谷智子『ガリバーの庭』より)
「死を畏れぬ秋の正餐をあはれみし竹山広も死の側のひと」
(古谷智子『立夏』より)
「プレイエルに伏せたる君の背中へと月の光のとけゆく夕べ」
「音楽をするひとはみな美しき種族(ひと) ジャクリーヌ・デュ・プレも君も」
(五十子尚夏『The Moon Also Rises』より)
「新しい人になりたい 空調の音が非常に落ち着いている」
(五島諭『緑の祠』より)
「水に浮くこの全身がわたくしのすべてであれば重たし水は」
(後藤由紀恵『ねむい春』より)
「さしだせるひとさしゆびに蜻蛉(せいれい)はとまりぬ其れは飛ぶための重さ」
(光森裕樹『うづまき管だより』より)
「未来より借り物をするさみしさに書物なかばの栞紐ぬく」
「ムービングウォークの終りに溜まりたるはるのはなびら踏み越えてゆく」
(光森裕樹『鈴を産むひばり』より)
「五種類の薬いつきに飲みたれば絵の具溶くごと胃の腑はあらむ」
(江田浩之『風鶏』より)
「陸橋に棄てられてゐる虹色の買物袋風はらみをり」
(江畑實『瑠璃色世紀』より)
「ビバルディの春はあけぼの花粉へと迂路をゑがいて蜜蜂は飛ぶ」
(甲村秀雄『短歌往来』4月号 第32巻4号より)
「人間の生まれる前は人間の生まれる確率0だつた星」
(香川ヒサ『PAN』より)
「気が付いた時には世界の中にゐて海見むと海に来るのことのあり」
(香川ヒサ『The Blue』より)
「気が付いた時にはすでにしやべつてた日本語だから気付かなかつた」
(香川ヒサ『マテシス』より)
「老いづける歌の友らと白き酒飲みてほのぼのと語ることあり」
(高安国世『夜の靑葉に』より)
「壁の線横に流れるものだけが速度のなかで消されずにある」
(高橋みずほ『凸』より)
「首とわかるまで網棚をころがりてゆくむこうまでゆく」
(高瀬一誌『高瀬一誌全歌集1950-2001』より)
「汗香る髪はいつしか雨となる雨のむかうに灯る紫陽花」
(高島裕『雨を聴く』より)
「哲学を卒(を)へしこころの青々と五月、机上に風ふきわたる」
(高島裕『旧制度アンシャン・レジ-ム』より)
「秋陽さす空の港に集ひゐるつばさ拡げしままの巨鳥(おほとり)」
(高島裕『嬬問ひ(つまどひ)』より)
「われといふ瓶(かめ)をしづかに盈たしたる素水(さみづ)と思ふ、九月の君を」
(高島裕『薄明薄暮集』より)
「琥珀石透かすいつときゆふぐれは右の眼にのみ訪れぬ」
(高木佳子『青雨記』より)
「あきかぜの中にきりんを見て立てばああ我といふ暗きかたまり」
(高野公彦『汽水の光』より)
「人が梯子を持ち去りしのち秋しばし壁に梯子の影のこりをり」
(高野公彦『水苑』より)
「熱き日を走り眩(くら)みてわがいのち鳥けだもののごとく水を恋ふ」
(高野公彦『淡青』より)
「産めやしない、産めはしないがアメジスト耀け五月なる疾風に」
(黒瀬珂瀾『ひかりの針がうたふ』より)
「要するに世界がこはい 夕立に気がついたなら僕に入れてよ」
(黒瀬珂瀾『空庭』より)
「上海は雨けふも雨、午後四時の気象通報おもひだしてる」
(黒沢忍『空洞ノ空KUU』より)
「六月の雨かも知れぬ打たれたる肩に紫陽花色の痣あり」
(黒田和美『六月挽歌』より)
「あなたとふ管(くだ)の湿りをのせてくるこゑに纏はり恋ふ人われは」
(黒木三千代「鱧と水仙」第40号より)
「三月はぬたといふ食じき春泥によごるるごとき葱が甘くて」
(黒木三千代『クウェート』より)
「老いほけなば色情狂になりてやらむもはや素直に生きてやらむ」
(黒木三千代『貴妃の脂』より)
「十二月二十八日午後二時のひかりのなかに二つの林檎」
(今井恵子『渇水期』より)
「たぶの樹を見に行つたらしい 暮れがたの二階の気配失せてしばらく」
(今野寿美『かへり水』より)
「紫陽花あぢさゐはほつかり咲いて青むともひとよたやすくほほゑむなかれ」
(今野寿美『若夏記』より)
「愛すべき冥王星の小ささを誰も言はなくなりけり誰も」
(今野寿美『雪占』より)
「夕光(ゆうかげ)の揺れる縁側 父がいて父のフォークが柿を刺したり」
(佐佐木幸綱『ムーンウォーク』より)
「三十一拍のスローガンを書け なあ俺たちも言霊を信じようよ」
(佐佐木幸綱『群黎』より)
「雨荒く降り来し夜更酔い果てて寝んとす友よ明日あらば明日」
(佐佐木幸綱『直立せよ一行の詩』より)
「眼鏡屋は夕ぐれのため千枚のレンズをみがく(わたしはここだ)」
(佐藤弓生『眼鏡屋は夕ぐれのため』より)
「きざすとききみはいなくて弦楽のうねりに脚をからめていたり」
「風ゆきつもどりつ幌を鳴らすたび四月闌けゆく三月書房」
(佐藤弓生『薄い街』より)
「あぢさゐの藍(あゐ)のつゆけき花ありぬぬばたまの夜あかねさす昼」
(佐藤佐太郎『帰潮』より)
「白藤の花にむらがる蜂の音あゆみさかりてその音はなし」
(佐藤佐太郎『群丘』より)
「追ひ抜かれ後退しゆくランナーをとらへをりしがやがて突き放す」
(佐藤通雅『天心』より)
「地下街をキックボードで滑りゆくみずがね色の猫やなぎたち」
(佐伯裕子『ノスタルジア』より)
「義母のよそうご飯かと思い振り向けば紫陽花白く低く咲きおり」
(佐伯裕子『感傷生活』より)
「地下街の長き歩廊の向こうまで見とおせる席そこがふるさと」
(佐伯裕子『流れ』より)
「霧雨は世界にやさしい膜をはる 君のすがたは僕と似ている」
「三月のビニール傘にわたくしをころさぬほどの雨降りそそぐ」
「人群れて白き階段登りゆく 空にキリンの首折れている」
(嵯峨直樹『神の翼』より)
「なほ生きむわれのいのちの薄き濃き強ひてなげかじあぢさゐのはな」
(斎藤史『魚歌』より)
「「ロバの耳」がたくさん落ちている穴へ私も落とす夕べの耳を」
「カレンダーの反り美しき一月の泉のごとき十日間ほど」
(細溝洋子『コントラバス』より)
「ちはやふる 神代も聞かず 竜田川 唐紅に 水くくるとは」
(在原業平「小倉百人一首」17番より)
「生業(なりはひ)はのどぼとけかも声に打ち人を打ち赤くなるのどぼとけ」
(坂井修一『縄文の森、弥生の花』より)
「蕪よつつひだまりとなりかがやけばぼんぼんと鳴る柱時計が」
(坂井修一『望楼の春』より)
「窮屈な機内に足を組み替へるやうにゆつくり話題を変へむ」
(阪森郁代『パピルス』より)
「いづへよりくるしく空の垂れ来しや麒麟ひつそり立ちあがりたり」
(阪森郁代『ランボオ連れて風の中』より)
「みぞれ みぞれ みずから鳥を吐く夜にひとときの祭りがおとずれる」
(笹井宏之「ななしがはら遊民」「風通し」2008年より)
「滝までの獣の道を走り抜けあの子は歌手になるのでしょうね」
「にぎりしめる手の、ほそい手の、ああひとがすべて子どもであった日の手の」
(笹井宏之『ひとさらい』より)
「爪切りはくちをひらきてわが生の真白き淵を噛みきりにけり」
(笹井宏之『八月のフルート奏者』より)
「このゆびは人さしゆびと名づけられ星座を指した、戦旗を指した」
(笹原玉子『われらみな神話の住人』より)
「みづいろにひたされつづける廊下を歩くこの天体の淵のあたりを」
「形代(かたしろ)は詩歌ばかりの島なれば軽羅のむすめがとほく手招く」
(笹原玉子『偶然、この官能的な』より)
「ソ、レ、ラ、ミと弦を弾(はじ)いてああいずれ死ぬのであればちゃんと生きたい」
「遠目には宇宙のようで紫陽花は死後の僕たちにもわかる花」
(笹川諒『水の聖歌隊』より)
「キリン舎にキリンは帰り夕暮れの泥濘に黒きキリンの足跡」
(三井修『アステカの王』より)
「折り目よりちぎれゆく地図アラビアの海の青さをテープにとめる」
(三井修『砂の詩学』より)
「少年はいつもむきだし 天からの手紙に濡るるその眉と肩」
(三枝浩樹『歩行者』より)
「風景のもろもろと和しひらくとき掌(て)にきざまれし無数の隘路」
(三枝昻之『暦学』より)
「ゆずの花、咲いてゐるよと君呼べばそのたまゆらをにほふ柚の花」
(三島麻亜子『水庭』より)
「ポルトガルの設計ミスのティーポット日曜なればかまわず使う」
(山下泉『海の額と夜の頬』より)
「夢の戸を開ければ美しき夜のなかに孔雀が羽根をひろげゆくなり」
(山科真白『鏡像』より)
「ハムカツにしょうゆを垂らす舌にもうざっくりとした食感がくる」
(山階基『夜を着こなせたなら』より)
「あをぞらの加減を鼻でふれてみてきりんはけふも斑のもやう」
(山崎郁子『麒麟の休日』より)
「確信を込め「永久」と口にする永久凍土のことを言うとき」
「真夜中に義兄の背中で満たされたバスタブのその硬さをおもう」
「忘れてしまうものとして聞く生い立ちに母と別れた夏の日がある」
(山崎聡子『手のひらの花火』より)
「しみじみと三月の空ははれあがりもしもし山崎方代ですが」
(山崎方代『こんなもんじゃ 山崎方代歌集』より)
「わが生みて渡れる鳥と思ふまで昼澄みゆきぬ訪ひがたきかも」
「水甕の空ひびきあふ夏つばめものにつかざるこゑごゑやさし」
(山中智恵子『紡錘』より)
「笑ふより泣くより怒るより前を見つめ続けるといふ感情」
「世界ばかりが輝いてゐてこの傷が痛いかどうかすらわからない」
(山田航『さよならバグ・チルドレン』より)
「しんじつを知りてしまいし人の名のまたひとつ神の指にて消さる」
(山田消児『アンドロイドK』より)
「新宿駅西口コインロッカーの中のひとつは海の音する」
(山田富士郎『アビー・ロードを夢みて』より)
「折り返すマラソン走者のおほきなる呼吸がわれの呼吸こえゆく」
(志垣澄幸『空壜のある風景』より)
「内臓のひとつかすかに疼きゐる春の地球に雨降りそそぐ」
(志垣澄幸『日向』より)
「森駈けてきてほてりたるわが頬をうずめんとするに紫陽花くらし」
(寺山修司『空には本』より)
「王国の猫が抜け出すたそがれや書かざれしかば生まれざるもの」
(寺山修司『月蝕書簡』より)
「馬の屁のやうな匂ひの風が吹きぽつりぽつりと雨が降り来ぬ」
(時田則雄『ポロシリ』より)
「麒麟この異形のものがゆつくりと首めぐらしてわれを見おろす」
(蒔田さくら子『さびしき麒麟』より)
「ばら縷縷と続くばら園 ゆく先に花ある生(よ)などもはや思はぬ」
(蒔田さくら子『紺紙金泥』より)
「くれなゐのつつじをまたぐ歩道橋いま天界の風ながれゐる」
(篠弘『東京人』より)
「ながき夜の ねむりの後も、 なほ夜なる 月おし照れり。 河原菅原」
(釈迢空『海やまのあひだ』より)
「をとめ子は をとめさびせよ。紫陽花の 花のいろひは、さびしけれども」
(釈迢空『近代悲傷集』より)
「紫陽花の花をぞおもふ藍ふくむ濃きむらさきの花のこひさし」
(若山牧水『黒松』より)
「紫陽花のその水いろのかなしみの滴るゆふべ蜩(かなかな)のなく」
(若山牧水『別離』より)
「リタイヤ官吏背広着てカツカレー喰ふ憲政記念館食堂のあどけなき昼」
(酒井佑子『矩形の窓』より)
「アナベルと小さく呼べば紫陽花の薄水色の花鞠ゆらぐ」
(秋山佐和子『豊旗雲』より)
「夏の野はさきすさびたるあぢさゐの花に心を慰めよとや」
(俊恵法師『林葉集』より)
「死などなにほどのこともなし新秋の正装をして夕餐につく」
(春日井建/初出1997年「雁」12月より)
「雪をつむ喫泉の先へ伸びあがり口づくる子の足もとも雪」
(春日井建『水の蔵』より)
「この沼に来し日は知らず発つ時を見ず幾たびか水禽に会ふ」
(春日井建『白雨』より)
「枯れ色にもう抗わぬ冬の街に赤信号は明滅しおり」
(小塩卓哉『風カノン』より)
「玄関にセールスマンが立ちしときたちまち対する外部と内部」
(小笠原和幸『春秋雑記』より)
「いくたびも顎打たれたるボクサーのふたたびを起つ意志を恐るる」
(小高賢『家長』より)
「谷中より風ながれゆく晩夏おそなつのキリンをみあぐ夕暮れにけり」
(小高賢『耳の伝説』より)
「みなそこに沈む平氏へ礼しては爺さま正座に魚釣りあげし」
(小黒世茂『やつとこどつこ』より)
「よろこばしき泉水に来ぬわたくしの喉の奥より蟇(ひき)のこゑ ククッ」
(小黒世茂『雨たたす村落(むら)』より)
「若き日の苦しからむかびしびしと首打ちかはす麒麟を見れば」
(小池光『サーベルと燕』より)
「耳の垢ほりて金魚に食はせ居りいつとはなしに五月となりぬ」
(小池光『草の庭』より)
「日の丸はお子様ランチの旗なれば朱色の飯(いい)のいただきに立つ」
(小池光『日々の思い出』より)
「思想とやはかなきものを音たててああゆるやかにキリンは歩む」
(小池光『廃駅』より)
「月射せばすすきみみづく薄光りほほゑみのみとなりゆく世界」
「きさらぎの雪にかをりて家族らは帰ることなき外出をせよ」
(小中英之『わがからんどりえ』より)
「つはぶきの花は日ざしをかうむりて至福のごとき黄の時間あり」
(小中英之『翼鏡』より)
「一日の終わりに首を傾けて麒麟は夏の動力降ろす」
(小島なお『サリンジャーは死んでしまった』より)
「ねむりゐるからだのうへに猫が来てひとつながりの闇となりたる」
(小島ゆかり『さくら』より)
「もくれんのわらわら白いゆふぐれは耳も目鼻も落としてしまふ」
(小島ゆかり『月光公園』より)
「4Bの鉛筆をもてはじめての円形脱毛塗りつぶすなり」
(小島ゆかり『純白光』より)
「チーズ濃く香る朝なり遠景に書物のごとき森ある九月」
(小島ゆかり『六六魚』より)
「過ぎてゆく時間のなかの昼食に黄身もりあがる玉子かけごはん」
(小島熱子「ポストの影」より)
「あぢさゐもばらも知らない受刑者は妻と三歳のむすめを詠ふ」
(小島熱子『ぽんの不思議の』より)
「ひつじ雲それぞれが照りと陰をもち西よりわれの胸に連なる」
(小野茂樹『羊雲離散』より)
「羆(ひぐま)の身ゆるりと返りこなた向く花の散り込む檻の片隅」
(小林サダ子『廻廊』より)
「雨の日に荷物が多い恋人を待つ紫陽花の咲く公園に」
(小林幹也『裸子植物』より)
「ひとの手に折り畳まれて / 二夜を越え / 君の手のなかに開かれる紙」
「ゆめみられる象かたちになり / 時をゆく / 夢みる者が / 彫きざんだ柱」
(小林久美子『アンヌのいた部屋』より)
「無伴奏ヴィオラは降りて最弱音(ピアニッシモ) つひに二人に浄夜は来たり」
(松岡秀明『病室のマトリョーシカ』より)
「サファリパークは淋しい冬になるだらういつか麒麟が滅びしのちは」
(松原未知子『戀人(ラバー)のあばら』より)
「手を出せば水の出てくる水道に僕らは何を失うだろう」
(松村正直『駅へ』より)
「煮えたぎる鍋をかき混ぜ繰り返す「きれいな兵器きたない兵器」」
(松村由利子『大女伝説』より)
「わたくしの名刺どこかでシュレッダーにかけられて居ん頭が痛い」
(松村由利子『鳥女』より)
「都市の彼方の風吹きすさぶ崖巓に在りて凍てつきし魂の竪琴」
「「トゥオネラの白鳥」を繰りかへし繰りかへし聴く 日輪は過ぎ、月輪は過ぎ」
(松平修文『トゥオネラ』より)
「窪地に湛へゐるくらきものより生まれ飛びたつぎらぎらひかる翅たち」
(松平修文『原始の響き』より)
「「夕顔の苗は残つてゐますか」とFAXを送る 地下街の花舗へ」
(松平修文『蓬(ノヤ)』より)
「冴えわたる四月晴朗どのような顔か母であり母でなきわれは」
(松平盟子『プラチナ・ブルース』より)
「坂の上に桜揺れおりうっすらと眠りが坂よりおりてくるなり」
(松平盟子『愛の方舟』より)
「君の髪に十指差しこみひきよせる時雨(しぐれ)の音の束の如きを」
(松平盟子『帆を張る父のやうに』より)
「ジャグラーが辞儀ふかくして投げあげる白帽昼の月となりたり」
「ひといろに染まれと迫る街をいま振り切って風に飛ばすルイガノ」
(松本典子『ひといろに染まれ』より)
「中央線で死ぬことなんてやめてほら日高本線でのびのびと死ね」
(松木秀『親切な郷愁』より)
「紫陽花を捧げ持ちつつ小さくて冷たい君の頭蓋を思う」
(松野志保『モイラの裔』より)
「手、足、首、骨、血潮、いつたいいくつの言葉で出来てゐるか「わたし」は」
(照屋眞理子『抽象の薔薇』より)
「客去れば椅子を二脚にもどしゆくしろき陶片のごとき陽のなか」
(上村典子『開放弦』より)
「暗やみにマッチをすりて残像のかがやく視野をしばらく歩む」
(上田三四二『雉』より)
「芝の上(え)のわが椅子倒し昨夜またさびしく八ヶ岳颪ゆきしか」
(上野久雄『冬の旅』より)
「消燈のころ世をしのぶごとく来て美しかりき汝がサングラス」
(上野久雄『夕鮎』より)
「朝覚めし母に会へれども耳とほき人として未だこゑをかはさず」
(森岡貞香『九夜八日』より)
「長き竿を前籠と肩に押さへつつ自転車はまづ大通りを渡る」
(真中朋久『エフライムの岸』より)
「午後三時県境に雲影(エコー)あらはれて丹波太郎はいま生まれたる」
(真中朋久『雨裂』より)
「夜となる空気が甘し鉄塔をのぼりゆく人の足裏見えつつ」
「八月のまひる音なき刻(とき)ありて瀑布のごとくかがやく階段」
(真鍋美恵子『羊歯は萌えゐん』より)
「風狂ふ桜の森にさくら無く花の眠りのしづかなる秋」
「野を奔(はし)るけものの肉を食むゆゑにいざべる(、、、、)長き赤き爪もつ」
(水原紫苑『びあんか』より)
「亡き犬のクローンはつか夢見たるわれを罰せむ立枯れ紫陽花」
(水原紫苑『快楽』より)
「かのときの二月岬の潮風になびきてありしえり巻きのQ」
「ペルセウス流星群にのってくるあれは八月の精霊(しょうりょう)たちです」
(杉﨑恒夫『パン屋のパンセ』より)
「一度だけ自分勝手がしてみたいメトロノームの五月の疲れ」
(杉崎恒夫『食卓の音楽』より)
「生まれつきのことなんだから 凍ったりする 離さずにゆめの女の人のにおい」
(瀬戸夏子「町」3号より)
「匂ひ鋭(と)く熟(う)るる果実をわが割(さ)くをまどろみのなか夢に見てゐつ」
(成瀬有『游べ、櫻の園へ』より)
「夕立のはるる跡より月もりて又色かふる紫陽花の花」
(正岡子規『竹の里歌』より)
「十二月八日といふ日つねの如朝の散歩の途次の思ひに」
(清水房雄『已哉微吟』より)
「あるいはそれは骨を握れることならむ手を繋ぎつつまだ歩いてる」
(生沼義朗『関係について』より)
「いつか死ぬ点で気が合う二人なりバームクウヘン持って山へ行く」
(盛田志保子『木曜日』より)
「顔といふからだのいちぶに自意識のすべてが集ふぶだうのやうに」
(西村美佐子『猫の舌』より)
「卓のグラスに映れるわれら人生のこの一齣も劇的ならず」
(西田政史『ストロベリー・カレンダー』より)
「ヨット一艘丸ごと洗ひたし十一月の洗濯日和どこまでも青」
(青井史『月の食卓』より)
「くす玉から平和のハトが弧をえがくドームの骨の上の青空」
(斉藤斎藤「GANYMEDE」58号より)
「すべての菜の花がひらく 人は死ぬ 季節はめぐると考えられる」
(斉藤斎藤『歌壇』2012年4月号より)
「君の落としたハンカチを君に手渡してぼくはもとの背景にもどった」
(斉藤斎藤『渡辺のわたし』より)
「田の水にうつる夏山かなたにはまだかなたには死が続いている」
(斉藤真伸『クラウン伍長』より)
「霊魂(たましひ)の(脆き)甲鎧(よろひ)、か? 若者の(滑(すべ」らかで涼(すゞ)しき)素裸(すはだか)、は」
(石井辰彦『蛇の舌』より)
「春の電車夏の電車と乗り継いで今生きてゐる人と握手を」(運命ではない)
「窓は目を開き続ける 紫に染め上げられて夜といふ夜」(human purple)
「転ぶやうに走るね君は「光源ハ俺ダ」と叫びつつ昼の浜」(沼津フェスタ)
(石川美南『架空線』より)
「わたしたち全速力で遊ばなきや 微かに鳴つてゐる砂時計」
(石川美南『砂の降る教室』より)
「躓きし足よりその日そこにいし石の不運の方が痛しも」
(石田比呂志『邯鄲線』より)
「十月の雨そぼふりぬ公園にをさなごひとりゲートボールす」
(仙波龍英『墓地裏の花屋抄』より)
「やすみなくする波音にうたふやうにかんたあびれにうたふやうにかんたあびれに」
(川崎あんな『エーテル』より)
「〈様式〉のまにまに花を描(か)きいそぐガッシュの赤がすこし足らぬに」
(川本浩美『起伏と遠景』より)
「ひ•な•あ•ら•れ フセインが鳥に撒きやりしちひさな食べもの闇夜に残る」
(川野里子『王者の道』より)
「水飲むとあをあをと深き首垂れてキリンがかたむく夕べの水へ」
(川野里子『青鯨』より)
「夫と子と季節のはざまに変態し擬態し女らやはらかくゐむ」
(川野里子『青鯨の日』より)
「ふり向いて影たしかむる坂道にひと日のわれと俺とが出会ふ」
(前川佐重郎『不連続線』より)
「火のごとくなりてわが行く枯野原二月の雲雀身ぬちに入れぬ」
(前川佐美雄『捜神』より)
「紫陽花の花を見てゐる雨の日は肉親のこゑやさしすぎてきこゆ」
(前川佐美雄『大和』より)
「醜(しこ)の國のメリケンばらと神國(かみぐに)のわが皇軍(みいくさ)を同じに思ふな」
(前川佐美雄『日本し美し』より)
「横顔のきりんの睫毛長くして空の中にて痛くまたたく」
(前田康子『ねむそうな木』より)
「「俺はなあ」つぶやいてみる川風に力が沸いてくる気がして」
(前田康子『黄あやめの頃』より)
「ドアエンヂンなかば閉りて発車せしあはひゆさむき日が脚に射す」
(前田透『漂流の季節』より)
「生まれては死んでゆけ ばか 生まれては死に 死んでゆけ ばか」
(早坂類『ヘヴンリー・ブルー』より)
「栗茸(クリタケ)のごと月光に濡れながら造成地の道帰りてきたり」
(早川志織『クルミの中』より)
「仕方なく雲からこぼれて来たような雨いつかやみ春の夕暮」
「花育て草抜き落葉掃く日々を重ねて青年と呼ばれずなりぬ」
(大下一真『即今』より)
「子を抱きて名取川渡りつつ転びさらに自分がわからなくなる」
(大口玲子『トリサンナイタ』より)
「嬉々として人々は見きX線通したるみづからの手、足、頭」
(大口玲子『ひたかみ』より)
「プールサイドにふたつまなこを洗ひゐるほそき二すぢの水のへだたり」
(大松達知『フリカティブ』より)
「どんぶりで飲む馬乳酒のこくこくと今を誰かが黒き紫陽花」
(大森静佳『カミーユ』より)
「その頬は夜空あおぞらうつす頬 いらないよ、一輪挿しの言葉は」
(大森静佳『ヘクタール』より)
「きららかについばむ鳥の去りしあと長くかかりて水はしづまる」
(大西民子『無数の耳』より)
「おそろしき桜なるかな鉄幹と晶子むすばれざりしごとくに」
(大滝和子『竹とヴィーナス』より)
「川を呑み川を吐きだす橋といふさびしきものの上を歩めり」
(大塚寅彦『ガウディの月』より)
「果汁もて追伸書かば燃やさるるつかのまのみを顕(た)つか言葉は」
(大塚寅彦『夢何有郷』より)
「やがてわが街をぬらさむ夜の雨を受話器の底の声は告げゐる」
(大辻隆弘『水廊』より)
「排泄の音が聞こえる静けさに肩のしこりをほぐさむとする」
(大島史洋『幽明』より)
「堀りすすむ間道いくつも井戸をすぎずぶぬれの身をよこたえるまで」
(大島史洋『藍を走るべし』より)
「仄白く鉄路の死体雨しぶく一九四九年七月五日深夜」
(大野誠夫『行春館雑唱』より)
「半信のダーウィンの本中空へ伸びる麒麟の黒長き舌」
(大野道夫『秋階段』より)
「蛇腹のあたしが巻きとられる頃ブエノスアイレスは午前零時をまわる」
(大和志保『アンスクリプシオン』より)
「春の風いま吹けよそよ、そよとなほこほりてとざすきまじめの顔へ」
(沢田英史『異客』より)
「木漏れ日がまだらに照らす人の顔凹凸はもうさびしさに見ゆ」
(棚木恒寿『天の腕』より)
「カツ丼とおやこ丼とはちがふから慌てずに見よどんぶりの柄」
(池田はるみ『南無 晩ごはん』より)
「箸かろく蕎麦つまみ上げ先をふと撫づるがごとく即すすりたり」
(池田はるみ『妣が国 大阪』より)
「末枯れ咲く紫陽花の毬を剪りてゆく からまわりするせかいのまひる」
(池田裕美子『時間グラス』より)
「今宵ひそと月と野良猫が登場すわが人生の野外舞台に」
(築地正子『みどりなりけり』より)
「黄昏は雲より水へ溶けゆきてそのままうたふ川となりたり」
(築地正子『菜切花』より)
「佐々木ならず佐佐木なることだいじにてその後我は誤たずけり」
(竹山広『一脚の椅子』より)
「コマーシャルのあひだに遠く遅れたるこのランナーの長きこの先」
「六十年むかし八月九日の時計の針はとどまりき いま」
(竹山広『空の空』より)
「蝸牛つの出せ青葉の雨あとに人間のほかなべて美し」
(中城ふみ子『乳房喪失』より)
「流れゆく川のきらめき木の間より見えずも聞ゆその川の音」
(中村幸一『あふれるひかり』より)
「ただの日となりてかろうじて晴れている十月十日ジョギングをせり」
「緑道を黙って歩く父だった四月の霧をほおひげに受け」
(中沢直人『極圏の光』より)
「あみめきりん茫洋とせるまなざしの霜月檻のうちより暮れて」
(中津昌子『遊園』より)
「題名が怖くて長く読まざりし『とびらをあけるメアリーポピンズ』」
(朝井さとる『羽音』より)
「灰色の空見上げればゆらゆらと死んだ眼に似た十二月の雪」
(鳥居『キリンの子』より)
「驛長愕くなかれ睦月の無蓋貨車處女をとめひしめきはこばるるとも」
(塚本邦雄『詩歌變』より)
「馬は人より天にしたがひ十月のはがねのかをりする風の中」
(塚本邦雄『睡唱群島』より)
「イカルス遠き空を墜ちつつ向日葵の蒼蒼として瞠くまなこ」
(塚本邦雄『日本人霊歌』より)
「五月来る硝子のかなた森閑と嬰児みなころされたるみどり」
(塚本邦雄『緑色研究』より)
「陰(ほと)に麦尻に豆なる日本の神話の五月るるんぷいぷい」
(坪内稔典『豆ごはんまで』より)
「かずかずのおもひのはてに透きとほり映画はひかりの河を流るる」
(天草季紅『青墓』より)
「春愁が人のかたちをしてわれに会ひに来てもう六人目なり」
(田村元『北二十二条西七丁目』より)
「よぎる顔の定かならざる日暮れには数式のごとく会えぬ君あり」
(田中雅子『青いコスモス』より)
「食卓にこぼれて光る塩の粒、宇宙の闇をわれは想へり」
(杜沢光一郎『群青の影』より)
「さびしさは父のものなり水底(みなそこ)の泥擦り上げて真鯉浮かび来」
(渡英子『夜の桃』より)
「てふてふのてんぷらあげむとうきたてば蝶蝶はあぶらはじきてまばゆ」
(渡辺松男『蝶』より)
「にんげんとなりたるか傘さしてくる鉄の眼鏡をかけてアトムは」
(渡辺松男『歩く仏像』より)
「爆音のきはまるときに首のべて大気の坂を鉄のぼりゆく」
(都築直子『淡緑湖』より)
「ドアを出(い)ず、――/秋風の街へ、/ぱつと開けたる巨人の口に飛び入るごとく。」
(土岐善麿(哀果)『黄昏に』より)
「ヴェランダは散らかっていて六月の台風がもうじきやってくる」
(土岐友浩『Bootleg』より)
「後頭部をつめたい窓にあずければ電車の音が電車をはこぶ」
「山頭火で三一〇円のラーメンを食べていたのが三月十日」
(土岐友浩『僕は行くよ』より)
「片脚のなき鳩ありて脚のなきことを思わぬごとく歩きぬ」
(島田幸典「短歌」2003年12月号より)
「故郷近くなりて潰せるビール缶の麒麟のまなこ海を見るべし」
(島田幸典『no news』より)
「窓をうつ風雨となれる夜のほどろ目ざめて俺は青年ならず」
(島田修三『帰去来の声』より)
「月かげを背後(そびら)に溜めてなかぞらを量感すごき五月のむら雲」
(島田修三『露台亭夜曲』より)
「痛がりの乳房を持っていたころに初めて嚙んだこのタブレット」
「「そら豆って」いいかけたままそのまんまさよならしたの さよならしたの」
(東直子『春原さんのリコーダー』より)
「ママ なぁに ママ 気泡の如き会話する 君小さくて小さくて 夏」
(筒井富栄『未明の街』より)
「石臼は石となりつつ 庭の上に白く光れり時雨のときは」
(藤井常世『文月』より)
「夏もなほ心はつきぬあぢさゐのよひらの露に月もすみけり」
(藤原俊成『千五百番歌合』より)
「あぢさゐの下葉にすだく蛍をば四ひらの数の添ふかとぞ見る」
(藤原定家『拾遺愚草』より)
「11mm径40mm長マグナム弾愛に殉じて炸裂したり」
(藤原龍一郎「歌壇」2010年11月号より)
「大川を流れる水のゆくすえを都市遊民の夢のあわれを」
(藤原龍一郎『東京哀傷歌』より)
「「お上んなさい」女の声を読むわれの右手は伸びる品川巻に」
(藤島秀憲『すずめ』より)
「飛行士は冷たき空のこと話し外国の塩置いて帰った」
「前籠に午後の淡雪いっぱいに詰め込んだまま朽ちる自転車」
(堂園昌彦『やがて秋茄子へと到る』より)
「淋しさは壊してしまえ生牡蠣(なまがき)に檸檬をしぼるその力もて」
(道浦母都子『花やすらい』より)
「カ行音躓(つまず)くあなたの吃音に交叉している山の水音」
(道浦母都子『風の婚』より)
「口内炎は夜はなひらきはつあきの鏡のなかのくちびるめくる」
「一年を振り返りやがて口腔にひろがる路地を眺めていたり」
「舟ゆきてゆりあがりたる池の面は眠れる人の顔にあらずや」
「さみしさも寒さも指にあつまれば菊をほぐして椿をほぐす」
「観覧車、風に解体されてゆく好きとか嫌いとか春の草」
「鉄道のなかに白夜があるという子どもの声すわれの咽喉より」
「逆光にくろきわが手をことのほか蔑みながら昼の砂浜」
「のびやかな影を曳きつつ老い人は午後の日差しに出逢いつづけぬ」
「にんげんのプーさんとなる日はちかく火の近く手を伸べてぼんやり」
「ひよこ鑑定士という選択肢ひらめきて夜の国道を考えあるく」
「金曜の夜となればほくそ笑むやがて輪郭が溶けてゆくような眠り」
「小龍包は紙よりも破けやすくしてはださむき夜の夢に出でたり」
「あはれなるシールのごとき目をもてるオカメインコにゆうべ餌やる」
「曇天の日の路地にしてままごとのなごりであろう椿置かれつ」
「観音を背に彫らしめて 少女期の悲はやすらかに身の丈を超ゆ」
「木香薔薇の花殻は枝にもりあがり触れたくて他者の柵にちかづく」
「少しひらきてポテトチップを食べている手の甲にやがて塩は乗りたり」
「つくしく、醜く老いてゆくことも光の当たる角度と思う」
「藤の花に和菓子の匂いあることを肺胞ふかく知らしめてゆく」
「とうふ油あげこんにゃくしらたき漂える夏の夜の夢のなかのデパート」
「影絵より影をはずししうつしみはひかり籠れる紙に向きあう」
「降る雨の夜の路面にうつりたる信号の赤を踏みたくて踏む」
(内山晶太『窓、その他』より)
「忘られし帽子のごとく置かれあり畳の上の晩夏のひかり」
(内藤明『夾竹桃と葱坊主』より)
「紫陽花と喋っただけの週末はハリガネムシになりたいや嘘」
(鍋倉悠那「いくじなし」(「九大短歌」第8号)より)
「雨ふくみ頭(づ)を傾ける紫陽花の地中にひかる納骨堂は」
(楠誓英『薄明穹』より)
「たましひが躰のなかで泪する しづかにひととき泣かせてやりぬ」
(日高堯子『玉虫草子』より)
「野良猫が顔を洗ふを見てあればふいと素知らぬかほに立ち去る」
(馬場あき子「歌壇」2021年7月号より)
「水低く鳴き渡る鴨力あり明日ならず今日ならぬ闇のはざまに」
(馬場あき子『ふぶき浜』より)
「断念の思いきっぱりとさびしきに痩せたる川に冬の底見ゆ」
(馬場あき子『桜花伝承』より)
「少年の糸鋸(いとのこ)一つ残りいて夕陽にひろき工作の部屋」
(馬場あき子『地下にともる灯』より)
「夏の風キリンの首を降りてきて誰からも遠くいたき昼なり」
(梅内美華子『若月祭』より)
「能面の内より見る世はせまく細くただ真つ直ぐに歩めよといふ」
(梅内美華子『真珠層』より)
「「青春」は存在しない「老年」も存在しないましてわが「死」は」
「両脚をひらきておのれ身を低め地のものを食むときの麒麟よ」
(柏原千恵子『彼方』より)
「出来たてのスケートリンク傷つけるため美しき少女のエッジ」
(八木博信『フラミンゴ』より)
「たが宿の春のいそぎかすみ売の重荷に添へし梅の一枝」
(伴林光平/伊東静雄『春のいそぎ』より)
「モーツァルト四十番を聞きながらうつむくひとであったよ父は」
(飯沼鮎子『土の色 草の色』より)
「けふもまた明けゆく道に少年の脳(なづき)のやうな紫陽花が咲く」
(飯田彩乃『リヴァーサイド』より)
「スランプの僕の脳みそ唄うのはキリンレモンのリフレイン」
(樋口智子『つきさっぷ』より)
「指先の重たさはみづに沈むやう ゆらめきて髪の中に紛れた」
(尾崎まゆみ『時の孔雀』より)
「七月の雨をからだに容いれるから紫陽花の藍色は濃くなる」
(尾崎まゆみ『綺麗な指』より)
「鳩時計鳴くを止(と)めしが鳩を闇に押しこめし如きこだはり残る」
(尾崎左永子『春雪ふたたび』より)
「燐寸と書きてマッチと読むことを知らざる子らが街を闊歩す」
「七月七日一夜かぎりの逢ひの外白牛はやさしき眠りを得しや」
(尾崎左永子『椿くれなゐ』より)
「とよめきて悶すぎたる胸の野やたのしき鳥と眠は来ぬる」
(尾上柴舟『銀鈴』より)
「白堊(チョーク)をばきゝとひゞかせ一つひく文字のあとより起るかなしみ」
(尾上柴舟『日記の端より』より)
「冷凍庫に冬の氷はやせほそり水に戻せばぱちりとなきぬ」
(尾﨑朗子『蟬観音』より)
「夜は巨大なたまご生むとぞ闇深く匂へるまでに黒きたまごを」
(百々登美子『風鐸』より)
「「この味がいいね」と君が言ったから七月六日はサラダ記念日」
(俵万智『サラダ記念日』より)
「ラジオより天皇陛下の声聞こゆどうやら戦争がおわったらしい」
(浜田康敬『百年後』より)
「かうするつもりだつたが結局かうなつた 長き一生(ひとよ)を要約すれば」
(浜田蝶二郎『わたし居なくなれ』より)
「一九四九年夏世界の黄昏れに一ぴきの白い山羊が揺れている」
「逆光の扉(どあ)にうかび少女立てばひとつの黄昏が満たされゆかむ」
「このごろの日暮れおもえば遠天を あじさいいろのふねながれゆく」
(浜田到『架橋』より)
「道ひとつ渡りて小さくなる兄の振り返り見る父も小さし」
「木の命気負いしころもあるならん下駄の木目に素足を載する」
(浜名理香『流流』より)
「夜学終え歩む一人の長き影われに追われて揺るるわが影」
(武川忠一『青釉』より)
「走れトロイカ おまえの残す静寂に開く幾千もの門がある」
(服部真里子「町」2号より)
「濃く匂ふ百合と匂はぬ紫陽花のあはひにはつか臭(しう)あるわれが」
(福井和子『花虻』より)
「八月の蟻がどんなに強そうに見えるとしてもそれは光だ」
(兵庫ユカ『七月の心臓』より)
「でもなあ散るにも重たげなのがなあハナミヅキどうにかならないか」
(平井弘「みづ糊」「楽座」第70号より)
「やめようときめたのは尖端ではないのだらう蔦があんなところで」
(平井弘『振りまはした花のやうに』より)
「紙ひとえ思いひとえにゆきちがいたり 矢車のめぐる からから」
(平井弘『前線』より)
「詩とはなに 硬く尖れる乳首を舌にもてあそぶときの陶酔」
(米口實『ソシュールの春』より)
「行つてはだめよと言へばいつせいにふりかへるしづかな老人しづかな子供」
「ユーラシアより来しもののしづけさに鯉はをりたり大砲(おほづつ)のごと」
(米川千嘉子『一葉の井戸』より)
「悪徳の壁塗り職人ヘンリー・ミラー氏あるあさ空をあおく蒼く塗る」
(辺見じゅん『雪の座』より)
「えんがはにちちははのゐておとうとゐてネガのなかねぶの花咲く」
(辺見じゅん『秘色(ひそく)』より)
「まさか俺、一生ここで菓子パンを齧ってるんじゃないだろうなと」
(穂村弘「時をかける靴下」朝日新聞2002年3月26日夕刊コラムより)
「酔ってるの?あたしが誰かわかってる?」「ブーフーウーのウーじゃないかな」
「水薬の表面張力ゆれやまず空に電線鳴る十一月」
(穂村弘『シンジケート』より)
「風に舞うレジ袋たちこの先を僕は上手に生きられますか」
(法橋ひらく『それはとても速くて永い』より)
「眼鏡橋の眼鏡の中から眺むれば柳一本風にゆらるる風にゆらるる」
(北原白秋『雲母集』より)
「満月 皺ばめる心を押しひろげ来るもの悲喜のいづれと知らず」
(北沢郁子『春のかぎり』より)
「欅木の黄葉のなかを一葉一葉丹念こめて散りゆく落葉」
(北沢郁子『満月』より)
「紫陽花の青ふかき花に向かひゐしゆゑにか青き死にを夢みぬ」
(北沢郁子『夢違』より)
「だれもみな手首に鍵をゴムで留めほとんど裸で水に入った」
(牧野芝草『整流』より)
「猫をわが全存在でつつみ抱くともだちになつてくれたら魚をあげる」
(睦月都「ゆふやみと強盗」(角川「短歌」2017年12月号)より)
「黄昏のSpotifyより流れくる死者の音楽、死者未満の音楽」
(睦月都『Dance with the invisibles』より)
「読みさしのミステリー枕辺に置いて待てども夢に来ぬ黒揚羽」
(本川克幸『羅針盤』より)
「起こす声聞こえてたけどクワガタの卵になって眠ってたから」
(本多稜『こどもたんか』より)
「夜な夜なを夢に入りくる花苑の花さはにありてことごとく白し」
(明石海人『白描』より)
「ゆるやかにピアノの中にさし入れる千年前の雨の手紙を」
(鳴海宥『BARCALLOLE [舟歌]』より)
「雨垂れの音飲むやうにふたつぶのあぢさゐ色の錠剤を飲む」
(木下こう『体温と雨』より)
「風だけに読める宛名が花びらに書かれてあってあなたへ届く」
(木下龍也『オールアラウンドユー』より)
「波とほく寄する耳鳴り 八月の雲が厚みを増してゆくとき」
(目黒哲朗『CANNABIS』より)
「あなたにはあなたの雲の数へ方ある 新しい眼鏡が似合ふ」
(目黒哲朗『VSOP』より)
「ひいやりと動くキリンの脚つきは君と震わす音叉のように」
(野口あや子「短歌研究 2008.3」より)
「そのあとはわれの鎖骨をこんこんと叩いてきみは眠るのだった」
「くびすじをすきといわれたその日からくびすじはそらしかたをおぼえる」
(野口あや子『くびすじの欠片』より)
「ひょっとしてくっつくかっていう二人の間で水菜をしゃこしゃこと食む」
(野口あや子『夏にふれる』より)
「既視感のある生き方であろうともガソリンの虹またいで駅へ」
(柳澤美晴『一匙の海』より)
「まるまると尻割れズボンよりこぼれたる白桃ふたつ小川に映る」
(有沢螢『ありすの杜へ』より)
「あはあはとあはいあはひをあはせつつうたひあひゐるしやぼん玉はも」
(由季調『互に』より)
「深々と春 額に音叉あてて識るわが内耳にも鈴一つあり」
(里見佳保『リカ先生の夏』より)
「学舎より眩暈(めまひ)をもちて見下ろせる冷泉家の庭つつじの火の手」
(林和清『ゆるがるれ』より)
「銀行に銀の冷房臭みちて他人(ひと)の記憶のなかを生きをり」
(林和清『木に縁りて魚を求めよ』より)
「一両で走る電車を風と呼ぶそう決めたひとりの多数決」
(鈴木晴香『夜にあやまってくれ』より)
「すでにして海の匂いをなつかしむ仕事へ向かう雨の朝(あした)は」
(和嶋勝利『雛罌粟(コクリコ)の気圏』より)
「けいとうげ冠(くわん)はこぶしのほどをして剪ればいつとき虚(そら)の明るさ」
「あぢさゐは過去世の花ときめしよりあの日の深き藍を畏るる」
(廣庭由利子『ぬるく匂へる』より)
「もう愛や夢を茶化して笑うほど弱くはないし子供でもない」
(枡野浩一『てのりくじら』より)
「さよならをあなたの声で聞きたくてあなたと出会う必要がある」
(枡野浩一『歌 ロングロングショートソングロング』より)
「雲を雲と呼びて止まりし友よりも自転車一台分先にゐる」
(澤村斉美『夏鴉』より)
「この病は主の栄光を現すと語ったイエスに縋りつくのみ」
「幾人を煩わせたか省みるほどに切なるカインの祈り」
(澤本佳步『カインの祈り』より)
「耳で聴く風景ならば雪原は最弱音のシンバルだらう」
「単音は波のみなもと わたくしのいづみに足を晒すものたち」
「何度でも鳴りかへすから 色彩を一度うしなふための五線紙」
「フェルマータ 泣いてゐるのはわたしではなくてかつての庭の思ひ出」
「水鉄砲持ちゐし頃に出逢ひたるうすき翅ある人のまぼろし」
(濱松哲朗『翅ある人の音楽』より)
「もう逢えぬ人あまたある三月に小鳥来てふいー、ふいー、と啼くも」
(齋藤芳生『花の渦』より)
「団塊の世代の構成員として父はサボテンの棘を育てる」
(齋藤芳生『桃花水を待つ』より)
「秋風(しゅうふう)に思ひ屈することあれど天(あめ)なるや若き麒麟の面(つら)」
(塚本邦雄『天變の書』より)
[異種百人一首選考外短歌(その4)](567首)
「「はい?」という口癖指摘されてより私はわたしの言葉見張りき」
(細溝洋子)
「「はなびら」と点字をなぞる ああ、これは桜の可能性が大きい」
(笹井宏之)
「「大公」の調べ悲しき寒の夜幾千の眼に見おろされつつ」
(大島史洋)
「「福寿草まだ出ませんね」「そうですね事情は特に聞いてませんが」」
(大下一真)
「「眠れてますか」「はい」これまでもこれからも眠りはながく私を守る」
(小島なお)
「Jeという主語ざわめきて紫の燻るようなアテネ・フランセ」
(小川真理子)
「ああ犬は賢くあらず放射線防護服着る人に尾をふる」
(小島ゆかり)
「ああ皐月仏蘭西の野は火の色す君も雛罌粟われも雛罌粟」
(与謝野晶子)
「あいたいとせつないを足して2で割ればつまりあなたはたいせつだった」
(千原こはぎ)
「あじさいにバイロン卿の目の色の宿りはじめる季節と呼ばむ」
(大滝和子)
「あじさいに降る六月の雨暗くジョジョーよ後はお前が歌え」
(福島泰樹)
「あじさいの色づく速さかなしみて吾のかたえに立ちたまえかし」
(大滝和子)
「あじさいはあわれほのあかく移りゆく変化(へんげ)の花と人のすぎゆき」
(坪野哲久)
「あたたかい十勝小豆の鯛やきのしっぽの辺まで春はきている」
(杉崎恒夫)
「あぢさゐのおもむろにして色移るおほかたの日数雨に過ぎつれ」
(吉野秀雄)
「あぢさゐの花の花間(はなま)にやはらかく雨ふりしづむ 夕雨夜雨」
(高野公彦)
「あぢさゐの花をおほひて降る雨の花のめぐりはほの明かりすも」
(上田三四二)
「あぢさゐの濃きは淡きにたぐへつつ死へ一すぢの過密花あはれ」
(岡井隆)
「あぢさゐの藍のつゆけき花ありぬぬばたまの夜あかねさす昼」
(佐藤佐太郎)
「あぢさゐの毬寄り合ひて色づけり鬼(もの)籠(こ)もらする如きしづけさ」
(高野公彦)
「あふ向けに砂に埋もれて目をひらく少女とわれの睡り重なる」
(小林久美子)
「あやまちて切りしロザリオ転がりし玉のひとつひとつ皆薔薇」
(葛原妙子)
「アラビアに雪降らぬゆえただ一語 ثلج と呼ばれる雪も氷も」
(千種創一)
「ありがとうなんて言うのも今さらのような気がするけどありがとう」
(俵万智)
「アルコール消毒液を手に受ける小さなくしゃみのようなささやき」
(戸田響子)
「アルバムの告知する君 字余りの短歌のように思いあふれて」
(俵万智)
「アンコールし続けている手の平がかゆくてかゆくて出てこい早く」
(相原かろ)
「アンパンの幸福感をふくらます三分の空気と七分のアンコ」
(杉崎恒夫)
「いいんだよライブで歌手がまちがえてそれを愛してしまった耳よ」
(山階基)
「いかにせむ山の青葉になるままに遠ざかりゆく花の姿を」
(俊恵)
「いかにせむ都の春も惜しけれどなれし東の花やちるらん」
(熊野御前)
「いかばかり嬉しからまし秋の夜の月澄む空に雲なかりせば」
(西行)
「いくら書いても消せない記憶の日があるの雨にも陽にもかがやきながら」
(江戸雪)
「いざ子ども山べにゆかむ桜見に明日ともいはば散りもこそせめ」
(良寛禅師)
「いちはやく秋だと気づき手術台のような坂道ひとりでくだる」
(江戸雪)
「いつ摘みし草かと子等に問われたり蓬だんごを作りて待てば」
(野田珠子)
「いにしへの奈良の都の八重桜けふ九重ににほひめるかな」
(伊勢大輔)
「いむといひて影にあたらぬ今宵しもわれて月みる名や立ちぬらむ」
(西行)
「ウェルニッケ野に火を放てそののちの焦土をわれらはるばると征く」
(松野志保)
「うちつけに割つてさばしる血のすぢを鳥占とせむ春たつ卵」
(高橋睦郎)
「うれしいの わたしもうれしいゆふやけが夏の水面をまたたかせると」
(木下こう)
「エミリといふ名にあこがれし少女期あり紫陽花濡るる石段くだる」
(栗木京子)
「エロス・タナトスあやめわかたぬわが夜々にあやしくOのくちひらく刻」
(大和志保)
「オール5の転校生がやってきて弁当がサンドイッチって噂」
(穂村弘)
「おっさんずラブのパラレルワールドのすきまに落ちて泣く恋心」
(枡野浩一)
「おっさんずラブの夫婦やカップルのようにまっすぐ生きずごめんね」
(枡野浩一)
「おにぎりをソフトクリームで飲みこんで可能性とはあなたのことだ」
(雪舟えま)
「おもかげに顕(た)ちくる君ら硝煙の中に死にけり夜のダリア黒し」
(宮柊二)
「おれの名のラベルが貼られ液体のおれが奥へと運ばれてゆく」
(佐佐木定綱)
「おんがくの波の中からあらわれた私をひとり抱きしめてやる」
(笹井宏之)
「お笑いの画面を消しておもむろに笑わぬ前の顔に戻しぬ」
(石田比呂志)
「カーテンが風に押し上げられている まだ消えていないわたしを生きる」
(上本彩加)
「ガードマンは天丼に対うすぐ裏の工事現場の土をこぼして」
(柴善之助)
「ガソリンの投入口から立ちゆらぐ気化した影を見る真夏日」
(黒﨑聡美)
「かたくりのうつむく花を覗くときひとは野原にうすくなるなり」
(小林幸子)
「かたりあひて尽し丶人は先立ちぬ今より後の世をいかにせむ」
(山県有朋)
「ガラス壺の砂糖粒子に埋もれゆくスプーンのごとく椅子にもたれる」
(吉川宏志)
「かりそめの人のなさけの身にしみてまなこうるむも老いのはじめや」
(太宰治)
「きのことは柔らかい釘、森にいる誰かを森に留めおくための」
(千種創一)
「きりわけしマンゴー皿にひしめきてわが体内に現れし手よ」
(江戸雪)
「クラヴィチェンバロ・コル・ピアノ・エ・フォルテといふ長き名を持つ楽器のありき」
(服部崇)
「くれてゆく年の道さへみゆるかとおもふてばかりにてる月夜かな」
(樋口一葉)
「くれなゐの二尺伸びたる薔薇の芽の針やはらかに春雨の降る」
(正岡子規)
「こころなき泉の精となり果ててきよきをのこも影とのみ見む」
(水原紫苑)
「このゆふべ降り来る雨は彦星の早漕ぐ船の櫂の散沫かも」
(詠み人知らず)
「この映はゆい水晶のなかをあるくから大天使ガブリエルさえ風邪の目をして」
(井辻朱美)
「この世をば我(わ)が世とぞ思ふ望月の欠けたることもなしと思へば」
(藤原道長)
「コピー機を腑分けしてゐる一枚の詰まりし紙を探しあぐねて」
(門脇篤史)
「こめかみをひっぱるように青空がまたひろがった逆らえないな」
(本田瑞穂)
「こもごもに郁子(むべ)と通草(あけび)をとり食みて郁子がよしちふこの子があはれ」
(北原白秋)
「こゆびより小さきボタン長く押し、きみはこうして時間をつくる」
(野口あや子)
「コンビニに流れる歌詞に聞き入ってどうかしている今日の私は」
(松原和音)
「コンビニの麵麭と水だけ口にしてとがらせてゆく秋の結末」
(安田茜)
「サキサキとセロリを噛みいてあどけなき汝(なれ)を愛する理由はいらず」
(佐佐木幸綱)
「さくらさくらさくら咲き初そめ咲き終わりなにもなかったような公園」
(俵万智)
「さくら花幾春かけて老いゆかん身に水流の音ひびくなり」
(馬場あき子)
「サルビアに埋もれた如雨露 二番目に好きな人へと君は変われり」
(吉川宏志)
「しかれども飲食清(すが)し魚汁は頭蓋、目の玉、腸(わた)もろともに」
(村上きわみ)
「しきしまの大和心のをゝしさはことある時ぞあらはれにける」
(明治天皇)
「シネコンのトイレでこれから観る人ともう観た人の差がわからない」
(岡野大嗣)
「しのびよる闇に背を向けかき混ぜたメンコの極彩色こそ未来」
(笹公人)
「しばらくは 離れて暮らす コとロとナ つぎ逢ふ時は 君という字に」
(タナカサダユキ)
「しびれるまで冬の真水にさらしおく十指につかむこの先のこと」
(後藤由紀恵)
「しゃべりつつ言葉を選ぶ立ち止まりムーンウォークをする感じにて」
(佐佐木幸綱)
「ジャポニカの学習帖がひしめいてサファリパークのごとき教室」
(伊波真人)
「ショートケーキを箸もて食し生誕というささやかなエラーを祝う」
(内山晶太)
「ショッカーの時給を知ったライダーが力を抜いて繰り出すキック」
(木下龍也)
「ショッピングモールの中の駄菓子屋は親切な郷愁でおなじみ」
(松木秀)
「すきな原曲のカバーがいいときのしっぽがあればふりたい気持ち」
(岡野大嗣)
「すきまなくしげれる蓮の葉の池にぬきいでて立ちひらく蓮の花」
(岡麓)
「すごい雨とすごい風だよ 魂は口にくわえてきみに追いつく」
(平岡直子)
「スニーカーの親指のとこやぶれてて親指さわればおもしろい夏」
(陣崎草子)
「すれちがつた今の女が眼の前で血まみれになる白昼の幻想」
(夢野久作)
「セーターを洗って干せば風が来てほそくかがやくかひなを通す」
(永井陽子)
「ゼラチンの菓子をすくえば今満ちる雨の匂いに包まれてひとり」
(穂村弘)
「そこはだめあけてはならぬ芽キャベツの親戚一同が待ち伏せているから」
(肉球)
「そのマスクいいね いんかんここ まいど ひかりをとどけたひとのせなか」
(坂口涼太郎)
「その子二十 櫛にながるる黒髪のおごりの春のうつくしきかな」
(与謝野晶子)
「ダアリヤは黒し笑ひて去りゆける狂人は終にかへり見ずけり」
(斎藤茂吉)
「ただひとつ惜しみて置きし白桃のゆたけきを吾は食ひをはりけり」
(斎藤茂吉)
「ただ頼めたのむ八幡の神風に浜松が枝はたふれざらめや」
(武田信玄)
「たっぷりと真水を抱きてしづもれる昏き器を近江と言へり」
(河野裕子)
「たとうれば留守番電話のやさしさにキリンは立てり秋草を踏み」
(吉川宏志)
「たほたほと移される春の小麦粉の粉にはなれぬあたりが飛べり」
(田中濯)
「タマネギは芯からだめになってゆく取りのぞけない場所から腐る」
(天野慶)
「ため息をどうするわけでもないけれど少し厚めにハム切ってみる」
(俵万智)
「だらしなく花おわらせるチューリップ女というのが面倒になる」
(黒﨑聡美)
「ダリアは黒し笑ひて去りゆける狂人は終にかへり見ずけり」
(斎藤茂吉)
「ダリア畑でダリア焼き来し弟とすれちがうとき火の匂うなり」
(佐藤通雅)
「だんじょかれよしの 歌声の響き 見送る笑顔 目に留まる」
(今上天皇)
「タンポポの綿毛のようにフワフワと42キロの旅に出る」
(高橋尚子)
「たんぽぽはまぶたの裏に咲きながら坐れり列車のなかの日溜まり」
(内山晶太)
「チェンバロの音色にきみのお喋りも織り込まれつつ薄暮のカフェは」
(加藤治郎)
「チューリップを幾百種類咲かしめて朝明るき公園の道」
(細川謙三)
「つくづくと春のながめの寂しきはしのぶに伝ふ軒の玉水」
(大僧正行慶)
「つつましき花火打たれて照らさるる水のおもてにみづあふれたり」
(小池光)
「つばくろよ翻るたびにくらくらと雲がひっくり反るならずや」
(杉崎恒夫)
「つゆくさで色水つくって遊んだよ明け方の空の涙みたいな」
(鶯まなみ)
「つよすぎる西日を浴びてポケットというポケットに鍵を探す手」
(岡野大嗣)
「てのひらに卵をうけたところからひずみはじめる星の重力」
(佐藤弓生)
「テレビからタモリが消えたあの日から並行世界を僕ら生きてる」
(岡本真帆 )
「どこまでが空かと思い結局は地上スレスレまで空である」
(奥村晃作)
「どこまでも二人のままで沈むよう耳のかたちをくらべる夜は」
(黒崎聡美)
「どのやうな手もやはらかにしてくれるクリームください焚火の色の」
(多田愛弓)
「どの家も紫陽花ばかりが生き生きと貧しき軒を突き上げて咲く」
(長谷川愛子)
「トマトの皮を湯剥きしながらチチカカ湖まで行きたしと思うゆうぐれ」
(生沼義朗)
「トマトの葉ちぎればトマトのにほひして昨日よりふかき空ふり仰ぐ」
(春野りりん)
「ドラえもん無しでここまで生きてきた自分をもっと褒めてあげたい」
(志井一)
「ト音記号を最後に書きしはいつなりしか広げし白紙に雨音ひびく」
(河野裕子)
「なくなれば美しくなる でもぼくは電線越しの空が好きです」
(寺井奈緒美)
「なげやりに暮らしているとおさいふの一円玉が増えてくるのよ」
(本多真弓)
「なにがあつたかわからないけど樅茸もみたけがいぢけて傘をつぼめてゐたよ」
(石川美南)
「なにか思ふなにかは嘆く世の中はただあさがほの花の上のつゆ」
(詠み人知らず)
「なにとなく君に待たるるここちして出でし花野の夕月夜かな」
(与謝野晶子)
「なにもかも決めかねている日々ののち ぱしゅっとあける三ツ矢サイダー」
(野口あや子)
「なんという青空シャツも肉体も裏っかえしに乾いてみたい」
(佐藤弓生)
「ぬばたまの黒髪変かはり白髪(しらけ)ても痛き恋には逢ふ時ありけり」
(沙弥満誓)
「ネコかわいいよ まず大きさからしてかわいい っていうか大きさがかわいい」
(宇都宮敦)
「ねむいねむい廊下がねむい風がねむいねむいねむいと肺がつぶやく」
(永田和宏)
「ねむくなりしひとが乗りこむ真夜中の電車は地下のみづうみへゆく」
(松平修文)
「ねるまえに奥歯の奥で今朝食べたうどんの七味息ふきかえす」
(岡野大嗣)
「ノンシャランと夢を貌かおよりふりおとすとおいユラ紀の銀杏のカノン」
(水原紫苑)
「パトラッシュが百匹ゐたら百匹につかれたよつていひたい気分」
(本多真弓)
「パブロンでなんとかなると信じたい 春なのにダウン着てねむります」
(阿波野巧也)
「パンケーキショップの甘い蜂蜜の香りがしたら右に曲がって」
(鈴木晴香)
「パンセパンセパン屋のパンセ にんげんはアンパンをかじる葦である」
(杉崎恒夫)
「ピーマンの青い空洞には夭折の詩人の住んだ痕跡がある」
(杉崎恒夫)
「ひたすらにドレミの歌を繰り返す サンドバッグを蹴り上げながら」
(龍翔)
「ひとり識る春のさきぶれ鋼よりあかるく寒く降る杉の雨」
(三枝昴之)
「ひと匙のマーマレードの安らかさ少し焦げ目を与えたパンに」
(東直子)
「ひと束の水菜のみどり柔らかくいつしかわれに茂りたる思慕」
(横山未来子)
「ヒメジオンとハルジオンの違いをさりげなく聞けばたちまち機嫌をなおす」
(永田和宏)
「ふかづめの手をポケットにづんといれみづのしたたるやうなゆふぐれ」
(村木道彦)
「ふくろうの置物吾の宝物ふくろうの目は哲学をする」
(大島史洋)
「ふと見れば大文字の火ははかなげに映りてありき君が瞳に」
(吉井勇)
「ふるさとの右左口郷(うばぐちむら)は骨壺の底にゆられてわがかえる村」
(山崎方代)
「ふる雨にこころ打たるるよろこびを知らぬみずうみ皮膚をもたねば」
(佐藤弓生)
「ぼくらが明日海に出たとしても王宮の喫茶室では黒い紅茶が」
(正岡豊)
「ポケットの中で紙片の手触りを小さく固く折りたたんでゆく」
(相原かろ)
「ほととぎす鳴くや五月のあやめぐさあやめも知らぬ恋もするかな」
(詠み人知らず)
「ほのぐらき意識の奥に地獄門立てり逆巻く阿鼻叫喚のこゑ」
(森山晴美)
「ほほえみの裾がめくれて退屈な紫陽花が見ゆ陽にふくれつつ」
(吉川宏志)
「ほろほろと肝臓(レバー)食みつつふと思う扱いにくき人の二、三を」
(村上きわみ)
「ほんとうにおれのもんかよ冷蔵庫の卵置き場に落ちる涙は」
(穂村弘)
「ほんとうはまだ好きだよとエイプリルフールに君は言うんだ ずるい」
(佐々木あらら)
「マーラー忌さすらふ若人手のひらに塊根黒し五月のダリア」
(藤村益弘)
「まだ何もしていないのに時代といふ牙が優しくわれ噛み殺す」
(萩原裕幸)
「マフラーに顔をうづめて大寒の街を急げり風に向かひて」
(喜夛隆子)
「みかん型トイレ、牛型トイレあり天竜浜名湖鉄道の駅」
(小島ゆかり)
「みずうみのあおいこおりをふみぬいた獣がしずむ角(つの)をほこって」
(小林久美子)
「みづいろのあぢさゐに淡き紅さして雨ふれり雨のかなたの死者よ」
(高野公彦)
「むこう側の世界に何か降れるごとひえびえと自動販売機の硬貨は」
(小高賢)
「むらさきの指よりこの世の人となりこの世に残す指のむらさき」
(有賀眞澄)
「もういやだ死にたい そしてほとぼりが冷めたあたりで生き返りたい」
(岡野大嗣)
「ものぐらく花塊(かたま)れるあぢさゐを過りて杳(とほ)し死までの歩み」
(小島ゆかり)
「もののふの八十(やそ)娘子(をとめ)らが汲み乱ふ(まが)寺井の上の堅香子(かたかご)の花」
(大伴家持)
「もののふの矢橋の舟は速けれど急がば回れ瀬田の長橋」
(宗長)
「もの思へば沢の蛍もわが身よりあくがれ出づる魂(たま)かとぞ見る」
(和泉式部)
「もの書きてひと日を過ごし雨もまたその文章の中に書き込む」
(浜田康敬)
「やがてわれ解けては水に還らむと思ふまどろみは水の如かれ」
(高橋睦郎)
「やどりせし人のかたみか藤袴わすられがたき香ににほいつつ」
(紀貫之)
「やはらかい水を降ろしてまづ春は山毛欅の林のわたしを濡らす」
(谷とも子)
「やはらかき手のあらはれて思ふさま入れる鋏のひびきは空に」
(鳴海宥)
「やはらかき生身の四肢を湯に浸しボタンひとつで追ひ焚きもする」
(寺尾登志子)
「ゆるきやらの群るるをみれば暗き世の百鬼夜行のあはれ滲める」
(馬場あき子)
「ゆるやかに死にゆくものと卵もつものありて明るき朝の水槽」
(横山未来子)
「よもの山に木の芽はるさめふりぬればかぞいろはとや花のたのまむ」
(大江匡房)
「ライナスの毛布になって包む夜のしんしん積もる二月のひかり」
(高田ほのか)
「リニアモーターカーの飛び込み第一号狙ってその朝までは生きろ」
(穂村弘)
「レタスからレタス生まれているような心地で剝がす朝のレタスを」
(中畑智江)
「わがうたにわれの紋章いまだあらずたそがれのごとくかなしみきたる」
(葛原妙子)
「わがごとく柿の萼(うてな)を見下ろすか熾天使は酸きなみだに濡れて」
(大辻隆弘)
「わがままな貴婦人に似た紅のパノラマカーよ歌いつつ去る」
(加藤治郎)
「わが胸にぶつかりざまにJeとないた蝉はだれかのたましいかしら」
(杉崎恒夫)
「わが国のたちなほり来し年々にあけぼのすぎの木はのびにけり」
(昭和天皇)
「わが恋は虹にもまして美しきいなづまとこそ似むと願ひむ」
(与謝野晶子)
「わたくしはけふも会社へまゐります一匹たりとも猫は踏まずに」
(本田真弓)
「わたつみの神にたむくる山姫の幣をぞ人は紅葉といひける」
(作者不詳)
「われらかつて魚なりし頃かたらひし藻の蔭に似るゆふぐれ来たる」
(水原紫苑)
「をさなさははたかりそめの老いに似て春雪かづきゐたるわが髪」
(大塚寅彦)
「愛を言う舌はかすかに反りながらいま遠火事へなだれるこころ」
(服部真里子)
「逢うことは雲居はるかになる神の音に聞きつつ恋ひわたるかな」
(紀貫之)
「安倍首相嫌ひなれどもテレビ見る激しく嫌ふ元気出るゆゑ」
(岩田正)
「一とせの暦を奥にまきよせてのこる日数のかずぞすくなき」
(藤原知家)
「一瞬をひかりとなりてひるがへりツバメはわが身抜けてゆきたり」
(永井陽子)
「一年は円卓にしてどの席も主賓席なり二月に座る」
(石川美南)
「一匹のナメクジが紙の政治家を泣き顔に変えてゆくを見ており」
(佐佐木定綱)
「一輪の直情として切花は立ち盡くすなり莖を焼かれて」
(佐々木六戈)
「芋の葉にこぼるる玉のこぼれこぼれ子芋は白く凝りつつあらむ」
(長塚節)
「飲食[おんじき]の最後にぬぐう白き布汚されてなお白鮮[あたら]しき」
(錦見映理子)
「雨に濡れあぢさゐを剪(き)りてゐる女(ひと)の素足にほそく静脈浮けり」
(小島ゆかり)
「雨の降り始めた街にひらきだす傘の数だけあるスピンオフ」
(近江瞬)
「雨の日のさくらはうすき花びらを傘に置き地に置き記憶にも置く」
(尾崎左永子)
「雨の日も考えている、君のこと遠き星のごと近き樹のごと」
(佐々木幸綱)
「雨降れば色去りやすき花桜薄き心も我思はなくに」
(紀貫之)
「嘘いくついいわけいくつ吐きて来しくちびるに花花は紫陽花」
(藤原龍一郎)
「影の濃い木と薄い木と見あたらぬ木があるひるの梅園をゆく」
(荻原裕幸)
「影もたぬ妖(あやかし)われは歩み来て雨中に昏きあぢさゐ覗く」
(小島ゆかり)
「永遠と思いこんでた「青春」の二文字の中に「月日」があった 」
(逢)
「永遠にきしみつづける蝶番 無精卵抱く鳥は眠れり」
(錦見映理子)
「炎天に白薔薇(はくそうび)断つのちふかきしづけさありて刃(やいば)傷めり」
(水原紫苑)
「遠くその夜に触れたい一通のメールで君の画面を灯す」
(近江瞬)
「奥山のいはがきもみぢちりぬべし てる日の光みる時なくて」
(藤原関雄)
「牡丹花は咲き定まりて静かなり花の占めたる位置のたしかさ」
(木下利玄)
「音だけがもう春の雨パジャマからいったんぜんぶぬいできがえる」
(上澄眠)
「何処までもデモにつきまとうポリスカーなかに無電に話す口みゆ」
(清原日出夫)
「夏の夜はまだ宵ながら明けぬるを雲のいづこに月宿るらむ」
(清原深養父)
「夏空の飛び込み台に立つひとの膝には永遠のカサブタありき」
(穂村弘)
「夏至の日のながき日暮にゆく道の額紫陽花は雨に鮮(あたら)し」
(上田三四二)
「夏至の日の夕餉をはりぬ魚の血にほのかに汚るる皿をのこして」
(小池光)
「夏晴れのさ庭の木かげ梅の實のつぶらの影もさゆらぎて居り」
(斎藤茂吉)
「嫁として帰省をすれば待ってゐる西瓜に塩を振らぬ一族」
(本田真弓)
「家ならば妹が手まかむ草枕旅に臥やせるこの旅人あはれ」
(聖徳太子)
「家のうち机のうへの紫陽花のうすら青みのつのる真昼日」
(若山牧水)
「家ひとつ取り毀されて夕べにはちひさき土地に春雨くだる」
(小池光)
「家々に釘の芽しずみ神御衣(かむみそ)のごとくひろがる桜花かな」
(大滝和子)
「箇条書きで述ぶる心よ書き出しの一行はほそく初雪のこと」
(大口玲子)
「花の香を風のたよりにたぐへてぞ鶯さそふしるべにはやる」
(紀友則)
「花の名に定家は残り小さなるスクリュー型がいくつも散りぬ」
(前田康子)
「花見にと群れつつ人の来るのみぞあたら桜のとがにはありける」
(西行)
「花散らふこの向つ峰の乎那の峰の州につくまで君が齢もがも」
(作者未詳)
「過ぎゆくは紺の歳月 紫陽花のめぐりの闇のなまあたたかし」
(小野興二郎)
「我が姿たとへ翁と見ゆるとも心はいつも花の真盛り」
(牧野富太郎)
「我こそは新じま守よ沖の海のあらき浪かぜ心してふけ」
(後鳥羽院)
「画家が絵を手放すように春は暮れ林のなかの坂をのぼりぬ」
(吉川宏志)
「芽キャベツはつやめきながら湯にうかぶ<生まれる前のことを話して>」
(東直子)
「芽きゃべつも靄でしっとり緑色おやすみなさいいつも寂しい」
(吉野朔実)
「会えぬものばかり愛した眼球の終のすみかであれアンタレス」
(佐藤弓生)
「解剖台のうえのミシンと女郎蜘蛛 出糸腺からあふれだす歌」
(小林久美子)
「改札に君現はるるまでを待つそのまま死後の出会ひのかたち」
(大津仁昭)
「海を知らぬ少女の前に麦藁帽のわれは手をひろげていたり」
(寺山修司)
「開花まであと二か月というところ雲の流れに置かれる花芽」
(小川佳世子)
「街あかりのなかに薄れしさそり座の心臓の赤い熱帯夜です」
(杉崎恒夫)
「街路樹の若葉わがこころの若葉ふれあひていま春過ぎむとす」
(荻原裕幸)
「柿の実が柿の甘さに辿り着く時間(とき)の豊かさよ日当たりながら」
(武下奈々子)
「柿の皮剥きてしまへば茶を入れぬ夜の長きこそうれしかりけれ」
(島木赤彦)
「殻うすき鶏卵を陽に透かし内より吾を責むるもの何」
(松田さえ子)
「覚えたての道を行くとき曲がりたいのをこらえれば目印に着く」
(山階基)
「角砂糖みたいに職場に溶け込んできたり入社後二ケ月経ちて」
(萩原慎一郎)
「角砂糖角[かど]ほろほろに悲しき日窓硝子唾[つ]もて濡らせしはいつ」
(山尾悠子)
「葛の花踏みしだかれて色あたらしこの山道を行きし人あり」
(釈迢空)
「寒鮒の肉を乏しみ箸をもて梳きつつ食らふ楽しかりけり」
(島木赤彦)
「干涸びた赤い蠍をその髪にかざり土曜日のゆふぐれに来る」
(松平修文)
「感情の置き場所だけは奪われぬ言葉はずっとずっと一緒だ」
(東直子)
「漢数字の一を茹でるとひらがなのしになる人の初めから終わり」
(九螺ささら)
「看護師の手の甲のメモ三桁の数字見ながら血を採られおり」
(馬淵のり子)
「観る人のまなざし青みあぢさゐのまへうしろなきうすあゐの球(たま)」
(高野公彦)
「眼球にチョコの目薬さしたなら生前最後の甘い風景」
(又吉直樹)
「喜びは森にあふれてニンフらの踊りに山羊まで踊り出したり」
(藤岡武雄)
「帰ったら上着も脱がずうつ伏せで浜辺に打ち上げられた設定」
(原田彩加)
「菊の花若ゆばかりに袖ふれて花のあるじに千代はゆずらむ」
(紫式部)
「久方の光のどけき春の日にしづ心なく花の散るらむ」
(紀友則)
「泣き濡れているのはわたし高いビル全部沈めて立つのはわたし」
(花山周子)
「球形(たまがた)のまとまりくれば梅雨の花あぢさゐは移る群青の色に」
(宇都野研)
「巨大なる会いたさのことを東京と思うあたしはわたしと暮らす」
(北山あさひ)
「拒まれて帰るゆうぐれチャック状の傷跡のあるトマトを選ぶ」
(中沢直人)
「胸びれのはつか重たき秋の日や橋の上にて逢はな おとうと」
(水原紫苑)
「仰向けで空想すればなかぞらの飛び込み台から落ちてくるきみ」
(小島なお)
「極楽へ行く人の乗る紫の雲の色なるあじさいの花」
(行其)
「玉に貫く楝(あふち)を宅に植ゑたらば山霍公鳥離れず来むかも」
(大伴書持)
「玉虫の羽をもて厨子を貼りし者の不穏のこころひと日見えゐつ」
(稲葉京子)
「九つの人九つの場をしめてベースボールの始まらんとす」
(正岡子規)
「九月のしぐれの雨の山霧のいぶせき我が胸誰を見ばやまむ」
(作者不詳)
「空間に手を触れながら春を待つちいさな虫の飛んでいる部屋」
(内山晶太)
「靴紐を結ぶべく身を屈めれば全ての場所がスタートライン」
(山田航)
「君をおきてあだし心を我がもたば末の松山浪も越えなむ」
(詠み人知らず)
「傾きし緋牡丹の花思ひきり崩れはてよといふこころあり」
(齋藤史)
「蛍光ペンかすれはじめて逢えぬ日のそれぞれに日没の刻あり」
(大森静佳)
「血管の中に住みたいからだじゅう隅から隅まで知りたくなって」
(千原こはぎ)
「月月に月見る月は多けれど月見る月はこの月の月」
(詠み人知らず)
「月光の夜ふけをつんと雪に立つ蓬(よもぎ)のこゑを聴きし者なし」
(柏崎驍二)
「牽牛(ひこほし)の思ひますらむこころより見るわれ苦し夜のふけゆけば」
(湯原王)
「言祝ぎを 海から海へ発ってゆく鳥それぞれが持つ二本足」
(阿部圭吾)
「限りなくやさしい君に添寝するタプタプタップ海のようだね」
(奥村晃作)
「湖うみのほとり青の光につつまれて神はしだいに遠のきたまふ」
(加藤克巳)
「湖代に逢ふこころ揺らぎて身じろぎし足首白きに鳴る鈴の音」
(古谷智子)
「虎杖のわかきをひと夜塩につけてあくる朝食ふ熱き飯にそえて」
(若山牧水)
「交(あざ)わらず愛遂ぐるてふいろくずの累卵のせて今朝の白米(しらいひ)」
(高橋睦郎)
「光なき玻璃窓一めんにあぢさゐの青のうつろふ夕ぐれを居り」
(五味保義)
「口中に一粒の葡萄を潰したりすなはちわが目ふと暗きかも」
(葛原妙子)
「甲虫の肢(あし)内側に折るように眼鏡を畳むきょうの終わりは」
(小島なお)
「紅つばき爛漫たれば思ひ出づ舌を出すアインシュタインの顔」
(小島ゆかり)
「紅に深くにほへる桜花雨さへ降りて色を染めける」
(詠み人知らず)
「香の高き薔薇の名はケアレス・ラブといふ二つくらゐは誰にもあらむ」
(米川千嘉子)
「国人ととつ国人と打ちきそふベースボールを見ればゆゝしも」
(正岡子規)
「黒きだりあの日光をふくみ咲くなやましさ我が憂鬱の烟る六月」
(前田夕暮)
「黒き鞭とすれちがひたり女人(をんなびと)の髪毛でありて顔さへ見ざりし」
(森岡貞香)
「骨なしのチキンに骨が残っててそれを混入事象と呼ぶ日」
(岡野大嗣)
「今年より春しりそむる桜花ちるといふことは習はざらなん」
(紀貫之)
「昆蟲は日日にことばや文字を知り辭書から花の名をつづりだす」
(塚本邦雄)
「歳月の中にそよげる向日葵の幾万本に子を忘れゆく」
(秋山律子)
「菜種梅雨やさしき言葉持つ国を歩む一人のスローモーション」
(俵万智)
「作用の/仕天は/作極の/しずみを/焦す/いざつむえ」
(友原康博)
「昨日なし明日またしらぬ人はただ今日のうちこそ命なりけれ」
(今川義元)
「昨日より色のかはれる紫陽花の瓶をへだてて二人かたらず」
(石川啄木)
「鮭の死を米で包んでまたさらに海苔で包んだあれが食べたい」
(木下龍也)
「殺してもしづかに堪ふる石たちの中へ中へと赤蜻蛉(あきつ) 行け」
(水原紫苑)
「山笑う、とさいしょに喩えた人がいてその生涯で出遭うほほえみ」
(加藤はる)
「山水に萌えいづる青は早くして蕗の花いくつか立ちあがり咲く」
(土屋文明)
「山蕗のまだやはいうちを摘みとつてうれしいこんなに指がよごれて」
(谷とも子)
「仕事にてひとつに束ねゆく髪のそれぞれ深き毛根をもつ」
(小島ゆかり)
「四年前グアムで買った星型のにこにこシールを使い始める」
(仲田有里)
「思いきり愛されたくて駆けてゆく六月、サンダル、あじさいの花」
(俵万智)
「思い通り咲けぬさくらも混じれるか雨に散りたるあとを踏まれて」
(千々和久幸)
「思へどもなほ飽かざりし桜だに忘るばかりの深見草かな」
(後水尾院)
「思惟をことばにするかなしみの水草をみづよりひとつかみ引きいだす」
(川野芽生)
「止まったら強制的に電源を切って再び入れれば直る」
(相原かろ)
「死にともな嗚呼死にともな死にともな深きご恩の君を思えば」
(本多忠勝)
「死ぬるまで愛しあふ鳥死を越えて愛しあふ鳥白深きいづれ」
(水原紫苑)
「死者一切近づくなかれ哄笑しわれらかがやく葡萄呑みたり」
(小池光)
「死神はてのひらに赤き球置きて人間と人間のあひを走れり」
(葛原妙子)
「私は、と書き出すときにもういない私こうして夏に踏み出す」
(小島なお)
「私は日本狼アレルギーかもしれないがもう分からない」
(田中有芽子)
「紫のひともとゆゑに武蔵野の草はみながらあはれとぞ見る」
(詠み人知らず)
「紫陽花といふ名は誰が名づけけむ雨季を彩る三字の名詩」
(熊沢雅晴)
「紫陽花にひねもす眠りゆふまぐれ猫は水色の眸(まなこ)を瞠く」
(小島ゆかり)
「紫陽花のはな傾きて降る雨によごれし笊(ざる)をうたせつつをり」
(津田治子)
「紫陽花のまだとゝのはぬうてなに、花の紫は色立ちにけり 」
(釈迢空)
「紫陽花のむらがる窓に重なり大き地球儀の球は冷えゐつ」
(葛原妙子)
「紫陽花の首をはねつつこれがかの男ならばと思うてならじ」
(大下一真)
「紫陽花の木(ぼく)のうへなる藍いろとみどりまじはりがたく明るむ」
(小中英之)
「紫陽花も花櫛したる頭をばうち傾けてなげくゆふぐれ」
(与謝野晶子)
「持つものも持たざるものもやがてやってくる花粉で汚れた草の姫の靴」
(フラワーしげる)
「時過ぎて色の褪せたるもみぢ葉のそのありのまま水面に映る」
(来嶋靖生)
「次にやる曲のさわりを鳴らすようにつつじが咲きかけの並木道」
(岡野大嗣)
「耳ふかく気圧は変わりトンネルを抜ければ夏の空だけがある」
(後藤由紀恵)
「執拗に水切りしたる豆腐もて白和えつくる二月の厨」
(後藤由紀恵)
「捨てゼリフ残し飛び出すねえちゃんはけれどもドアを優しく閉める」
(松田わこ)
「煮込みゐるカレーの背筋がぴんとたつガラムマサラのこのひと振りに」
(竹浦道子)
「若竹の伸びゆくごとくこども達よ真直に伸ばせ身をたましひを」
(若山牧水)
「取り落とし床に割れたる鶏卵を拭きつつなぜか湧く涙あり」
(道浦母都子)
「守るべき女の誇りに奪らむ首 夜の牢獄黄の薔薇かおる」
(佐藤洋子)
「樹枝状のブロッコリーを囓るときぼくは気弱な恐竜である」
(杉崎恒夫)
「秋くれて深き紅葉は山ひめのそめける色のかざりなりけり」
(藤原定家)
「秋茄子を両手に乗せて光らせてどうして死ぬんだろう僕たちは」
(堂園昌彦)
「秋日ざし明るき町のこころよし何れの路に曲りて行かむ」
(窪田空穂)
「秋風にたなびく雲のたえ間より漏れ出づる月の影のさやけさ」
(左京大夫顕輔)
「秋来きぬと目にはさやかに見えねども風の音にぞおどろかれぬる」
(藤原敏行)
「十余年わが書きためし草稿の跡あるべしや学院の灰」
(与謝野晶子)
「柔肌の熱き血潮に触れもみで寂しからずや道を説く君」
(与謝野晶子)
「春のあとに夏の来るこそあはれなれアガパンサスの茎拉(ひし)ぎつつ」
(岡井隆)
「春の土もたげて青むものの芽よをさなき物の育つはたのし」
(窪田空穂)
「春の日の麒麟のような山のかげに僕の生まれた村が見える」
(中野嘉一)
「春を練りシナモンロールに焼き上げる仕方ないことを仕方なく思う」
(九螺ささら)
「春分の日のねむごろにあたたかき光をあびて木草そよげり」
(石黒清介)
「初雪になりにけるかな神な月朝くもりかと眺めつるまに」
(源経信)
「女学生 卵を抱けりその殻のうすくれなゐの悲劇を忘れ」
(黒瀬珂瀾)
「小さめにきざんでおいてくれないか口を大きく開ける気はない」
(中澤系)
「床下に水たくはへて鰐を飼ふ少女の相手夜ごと異なる」
(松平修文)
「消息のわからない雲わからない猫わからないさいごのてがみ」
(やすたけまり)
「焦点の合わぬレンズの輝きのようなあなたに会いにゆきます」
(野口あや子)
「色変えてゆく紫陽花の開花期に触れながら触れがたきもの確かめる」
(岸上大作)
「心臓が透明な男ヴィオロンをひきつつ冬の角を曲がりたり」
(井辻朱美)
「新しき年のはじめにおもふことひとつ心につとめて行かな」
(斎藤茂吉)
「真中の小さき黄色のさかづきに甘き香もれる水仙の花」
(木下利玄)
「真昼 紅鮭の一片腹中にしてしばし人を叱りたり」
(高瀬一誌)
「神は死んだニーチェも死んだ髭をとったサンタクロースはパパだったんだ」
(穂村弘)
「人おのおの生きて苦しむさもあればあれ絢爛として生きんとぞ思ふ」
(尾崎左永子)
「人の子の恋をもとむる唇に毒ある蜜をわれぬらむ願い」
(与謝野晶子)
「人生に付箋をはさむやうに逢ひまた次に逢ふまでの草の葉」
(大口玲子)
「人類はほとんど水でできておりやがては霧となる資料集」
(小野田光)
「人恋ふる夜明けの部屋にみづみづと春の花木となりし手袋」
(秋山佐和子)
「水の音つねにきこゆる小卓に恍惚として乾酪黴びたり」
(葛原妙子)
「水の上にかがやくをとめ。水底にともなふ翳をしらず漂ふ」
(岡野弘彦)
「水苑のあやめの群れは真しづかに我を癒して我を拒めり」
(高野公彦)
「水含み重なりあへる吸殻に涼しき君の初夏の霊」
(小林久美子)
「水漬ける柱朽ちたる桟橋にいのちいとほし月の漣波」
(宇佐見英治)
「水面に垂らした糸の先端が跳ねた気がして携帯摑む」
(野村まさこ)
「睡魔乗る車輪かがやき顕在のわれと昆虫轢かれてゆけり」
(佐竹彌生)
「睡蓮は水の恋人、くれなゐのまぶた明るく閉ぢてひらきて」
(岡井隆)
「雛飾る部屋の暗さよ人形の白き顔にはほくろのなくて」
(栗木京子)
「世の中に蚊ほどうるさきものは無しぶんぶといふて夜も寝られず」
(作者不詳)
「世の中に麻は跡なくなりにけり心のままの蓬のみして」
(北条泰時)
「瀬をはやみ岩にせかかる瀧川のわれても末に逢はむとぞ思ふ」
(崇徳院)
「星という小人の中に美しき肘のみ見せて寝たる夕月」
(与謝野晶子)
「晴れた日は虹を作ろう たくさんの水でこころを洗っておこう」
(天野慶)
「清らかに 身をひく友が 進む道 何があっても 共にする未知」
(ウド鈴木)
「生(あ)るることなくて腐(く)えなん鴨卵(かりのこ)の無言の白のほの明りかも」
(馬場あき子)
「生れは甲州鶯宿峠に立っているなんじゃもんじゃの股からですよ」
(山崎方代)
「生者なるわれにまだまだ幾人(いくたり)も生者は絡み お墓を洗ふ」
(片岡絢)
「西洋細密画よりまなこを転じみるものは境もあらぬ大和の桜」
(小池光)
「青き菊の主題をおきて待つわれにかへり来よ海の底まで秋」
(塚本邦雄)
「青海波 かがやく部位をひとつずつ指さしてゆく春の午餐よ」
(丸山るい)
「青玉のしだれ花火のちりかかり消ゆる途上を君よいそがむ」
(北原白秋)
「青春の鬼に再び守らるる禁獄の身となるよしもがな」
(与謝野晶子)
「静かなる雨に散りたる山茶花の踏まれやすきを踏むなりわれも」
(伊藤一彦)
「赤ちゃんの靴と輪投げと月光の散らばる路面電車にひとり」
(穂村弘)
「切り株は幻肢の幹に枝に葉に風を受けおり静けさの中」
(島本ちひろ)
「雪になりきれぬ弱さを真剣に地上へぶちまけろよみぞれ」
(松木秀)
「雪晴れて格子の雫星のごと輝きくるる吾に一瞬」
(坂口弘)
「舌先で口内炎をさわってるその眼差しにひかれたのです」
(戸田響子)
「舌打ちの音でマッチに火が灯るようなやさしい手品がしたい」
(寺井奈緒美)
「先まくりいま二夜をば満てずしてくまなきものは長月の月」
(藤原俊成)
「戦争が(どの戦争が?)終わつたら紫陽花を見にゆくつもりです」
(荻原裕幸)
「鮮麗なわが朝のため甃(いしみち)にながれてゐたる卵黄ひとつ」
(小池光)
「窓口に恐怖映画の切符さし出す女人の屍蝋の手首」
(江畑實)
「他界より眺めてあらばしづかなる的となるべきゆうぐれの水」
(葛原妙子)
「体重をかけながら刃を圧してゆく受け入れられて息の漏れたり」
(駒田晶子)
「大いなる空振りありてこれならばまだ好いていよう五月の男」
(梅内美華子)
「大玉のキャベツざくざく切るときに窓に近づく春の雲あり」
(関谷啓子)
「大銀杏ひと葉動かず秋雲の晴れたる下に黄なるしづけさ」
(金子薫園)
「大熊座から降りてきた妖精ニンフひと夜 若草いろにカーディガン手に」
(石川美南)
「大粒の雨降り出して気付きたり空間はああ隙間だらけと」
(栗木京子)
「第二波の予感の中に暮らせどもサーフボードを持たぬ人類」
(俵万智)
「茸きのこたちに月見の宴に招かれぬほのかに毒を持つものとして」
(石川美南)
「炭酸が沁み込むように体中弾けるような蟬時雨受く」
(野村まさこ)
「団栗はまあるい実だよ樫の実は帽子があるよ大事なことだよ」
(小島ゆかり)
「暖炉には森の小枝が組まれゐてほそき炎がそれを嘗めるよ」
(池田はるみ)
「男前ばっか集めてうふふふふうふふふふうふふふふうふふふふ」
(谷じゃこ)
「地下鉄の前方後方指す指に白き流星をともす駅員」
(梅内未華子)
「地獄ではフードコートの呼び出しのブザーがずっと鳴ってるらしい」
(岡野大嗣)
「筑波嶺の新桑繭の衣はあれど君が御衣しあやに着欲しも」
(作者不詳)
「筑摩江や芦間に灯すかがり火とともに消えゆくわが身なりけり」
(石田三成)
「茶にまさる物なしといふは我ならず声そろへ言ふわが舌わが喉」
(窪田空穂)
「茶碗など黙って洗う涙とはたまれば自然におちる液体」
(畑彩子)
「中空を皿が割れてすべり落ちてくる白い白い音もなく白い」
(花山多佳子)
「長時間露光のなかに咲きいづるだらりの帯の金糸の刺繍」
(穂崎円)
「鳥の卵ひとつのみほすあけぼのへ冷え冷えと立つをとこののみど」
(小池光)
「追儺の豆外には打たじ戸もたてじ召されし護国の鬼の兄来よ」
(大島かづ子)
「通院は二度で終わってアルベルト・アインシュタイン戦争の途中」
(工藤吉生)
「定型は無人島かな 生き残りたくばみずから森を拓(ひら)けと」
(柳澤美晴)
「天ふかく陽(ひ)の道ありぬあぢさゐの露けき青の花群(はなむら)のうへ」
(高野公彦)
「天雲に近く光りて鳴る神の見れば畏し見ねば悲しも」
(詠み人知らず)
「天球に薔薇座あるべしかがやきにはつかおくれて匂ひはとどく」
(水原紫苑)
「転調をくりかえしつつ生活は譜面に眠るまだ見ぬ音符」
(伊波真人)
「冬ごもる蜂のごとくにある時は一塊の糖にすがらんとする」
(佐藤佐太郎)
「冬と春まじわりあって少しずつ暮らしの中で捨ててゆく紙」
(阿波野巧也)
「冬ながら空より花の散りくるは雲のあなたは春にやあるらむ」
(清原深養父)
「冬ばれのひかりの中をひとり行くときに甲冑は鳴りひびきたり」
(玉城徹)
「東京はエレベーターでも電車でも横目でモノを見る人の街」
(カン・ハンナ)
「灯の下にとりどりのパン集まりて神の十指のごとく黄昏」
(楠誓英)
「藤波の咲く春の野に延ふ葛の下よし恋ひば久しくもあらむ」
(詠み人知らず)
「踏むたびに水と落ち葉はめくれつつ水と落葉のふかさを見せる」
(谷とも子)
「透きとほる肌と妖しく光る眼と遠き記憶の海に漂ふ」
(来嶋靖生)
「同棲をしたいと切り出す妹の納豆の糸光る食卓」
(鯨井可菜子)
「童貞のするどき指に房もげば葡萄のみどりしたたるばかり」
(春日井建)
「突風に生卵割れ、かつてかく撃ちぬかれたる兵士の眼」
(塚本邦雄)
「南極に宇宙に渋谷駅前にわたしはきみをひとりにしない」
(岡本真帆)
「南極のとけなくなった雪たちへ捧ぐトロイメライの連弾」
(笹井宏之)
「肉体の思想激しく叫ばんに十九世紀夢の波濤よ」
(福島泰樹)
「虹色の能力と音に満ちているやがてすべてが叶えられてく」
(加藤知恵)
「日中を風通りつつ時折にむらさきそよぐ堅香子の花」
(宮柊二)
「日本語の「行けたら行く」は「待たないで」の意味だったのか 飴を舐めつつ」
(カン・ハンナ)
「熱たかき夜半に想へばかの日見し麒麟の舌は何か黒かりき」
(中城ふみ子)
「熱つ熱つのじゃがいも剥けば冬眠からさめたばかりのムーミントロール」
(杉崎恒夫)
「年たけてまた越ゆべしと思ひきやいのちなりけり佐夜の中山」
(西行法師)
「馬鈴薯が青き芽伸ばし好きなことそろそろしてもいいころと言ふ」
(佐藤慶子)
「廃駅をくさあぢさゐの花占めてただ歳月はまぶしかりけり」
(小池光)
「背後にて斬首まつヨハネを意識してサロメはうつむき眼線およがす」
(松坂弘)
「肺魚へと進化してゆく一瞬が湯にとじこもるわたしにはある」
(江戸雪)
「梅の花紅の色にも似たるかな阿呼がほほにつけたくぞある」
(菅原道真)
「梅の実は緑の中に色わきて紅にほふさみだれのころ」
(松平定信)
「梅雨ぐもりただに物うきのみならず紫陽花の花は色濃かりけり」
(岡麓)
「梅雨くればふかきみどりに揺れやまぬ肌のひかりがこの国のひかり」
(早川志織)
「梅雨に入りしその日駄洒落ハピバスデイ梅雨(ツーユー)と言ふ窓に向かいて」
(菊池孝彦)
「梅雨晴れの白き陽のさす柵のなか夢遊病者のキリンがあゆむ」
(吉川宏志)
「白き馬うまに非ざるかなしみに卵生の皇子みこは行きてかへらぬ」
(水原紫苑)
「白き餅われは呑み込む愛染も私ならずと今しおもはむ」
(斎藤茂吉)
「白玉の憂いをつつむ恋人がただうやうやし物もいはなく」
(伊藤佐千夫)
「白昼の星のひかりにのみ開く扉(ドア)、天使住居街に夏こもるかな」
(浜田到)
「白鳥はおのれが白き墓ならむ空ゆく群れに生者死者あり」
(水原紫苑)
「白湯気のなかの豆腐をすくふとき豆腐か湯気かふふとわらへり」
(小島ゆかり)
「白藤のせつなきまでに重き房かかる力に人恋へといふ」
(米川千嘉子)
「爆発に注意しましょう玉ねぎには春の信管が仕組まれている」
(杉崎恒夫)
「箸先に生きて身をそる白魚をのみこみし夜半ひとりするどし」
(松坂弘)
「発音で出自が知れるイギリスの階級社会を強く憎めり」
(渡辺幸一)
「半夏生 わたくしは今日頭上より雨かんむりをしづかにはづす」
(永井陽子)
「斑らなるひかり散りゐて紫陽花はつめたき熱の嚢とぞなる」
(葛原妙子)
「悲しみのほむら燃ゆると思ふまで色たちてくるかたかごの花」
(岡野弘彦)
「悲しみをもちて夕餉に加はれば心孤りに白き独活食む」
(松田さえ子)
「飛べ!愛と勇気だけしか友達がいないアンパンマンの孤独よ」
(枡野浩一)
「枇杷の木に黄なる枇杷の実かがやくとわれ驚きて飛びくつがへる」
(北原白秋)
「美しき球の透視をゆめむべくあぢさゐの花あまた咲きたり」
(葛原妙子)
「美女裸女に/かこまれ魂も/蕩けなむ/聖者は天見る/天の神見る」
(岩田正)
「百年じゃあ答えが出ない人間は樹木は生きて何をしている」
(小島ゆかり)
「百年の受容ののちの夕微光ここ出でて春の橋わたるべし」
(谷岡亜紀)
「病監の窓の下びに紫陽花が咲き、折をり風は吹きに行きにけり」
(斎藤茂吉)
「不思議なり千の音符のただ一つ弾きちがへてもへんな音がす」
(奥村晃作)
「封筒に書類を詰めてかなしみを詰めないやうに封をなしたり」
(佐藤りえ)
「風景に横縞あはく引かれゐるごときすずしさ 秋がもう来る」
(栗木京子)
「蕗の薹ひっこり湧きて自尊心いら立ち腹立ち知らぬさみどり」
(大下一真)
「蕗の薹ほこと涌きたる地の温さ人は知らざりもの履きしより」
(大下一真)
「平泳ぎのようにすべてがゆっくりと流れゆくのみ秋の浮力に」
(小島なお)
「平成をカカカカカカっとピンヒール駆け抜けていった安室奈美恵」
(池田典恵)
「壁ぎわに影は澄みゆく芽キャベツがこころこころと煮えるゆうべを」
(佐藤弓生)
「片恋よ 春の愁いの一日をティッシュペーパーほぐして過ごす」
(服部真里子)
「方舟はこぶねのとほき世黒き蝙蝠傘かうもりの一人見つらむ雨の地球を」
(水原紫苑)
「蜂蜜のうごきの鈍ささへ冬のよろこびとして眺めてをりぬ」
(笹井宏之)
「僕たちが今進んでいる方向の未来にドラえもんはいますか 」
(仁尾智)
「奔馬ひとつ冬のかすみの奥に消ゆわれのみが累々と子をもてりけり」
(葛原妙子)
「本棚に戻されたなら本としてあらゆるゆびを待つのでしょうね」
(笹井宏之)
「盆の様な満月今は皆既して黒きひょろ玉山超えんとす」
(村瀬広)
「満月は半分欠けたが地獄の門はまだ見えるなり」
(高瀬一誌)
「味噌汁尊かりけりうつせみのこの世の限り飲まむとおもへば」
(斎藤茂吉)
「夢の汗よりもどればきみは陽のにおう朝をさしだすようにスープを」
(加藤英彦)
「無理矢理に肥大させたる肝臓を抗ひがたく生きて味わふ」
(本多稜)
「明日よりは春の初めと祝うべし今日ばかりこそ今年なりけれ」
(藤原公実)
「迷ひたる賢治に道を教へきと大法螺吹きの万年茸は」
(石川美南)
「鳴く蝉の命の限り鳴く声は夏のみそらにひびき沁みけり」
(岡本かの子)
「姪っ子がEXILEの絵を描いている こげ茶と黒がなくなりそうです」
(二葉吾郎)
「木には木の訛言葉があるのだろう影まわしつつ銀杏葉は落つ」
(平山繁美)
「木犀のかをりほのかにただよふと見まはせど秋の光のみなる」
(窪田空穂)
「目と鼻の奥の力を抜けというヨガの最後の死体のポーズ」
(久山倫代)
「目覚めたら息まっしろで、これはもう、ほんかくてきよ、ほんかくてき」
(穂村弘)
「問十二 夜空の青を微分せよ 街の明りは無視してもよい」
(川北天華)
「門松は冥土の旅の一里塚めでたくもありめでたくもなし」
(一休宗純)
「夜と昼のあはひ杳かに照らしつつひるがほの上に月はありたり」
(河野裕子)
「夜の机われのにほひを嗅ぐごとく黒きダリアを手にとりてみる」
(若山牧水)
「夜の更くるお茶の水橋の下びには人面(じんめん)なして葛の葉が吹く」
(河野愛子)
「夜の耳しんと立てれば流れ込む遠い呼び声樹下のささやき」
(松村由利子)
「宥されてわれは生みたし 硝子・貝・時計のやうに響きあふ子ら」
(水原紫苑)
「柚子の実の皮をしむきて歯にかみぬさみしき心やらはむがため」
(石黒清介)
「夕闇に溶けゆくネーブル・オレンジと蠅をみていたあのまなざしは」
(穂村弘)
「夕雲の輝くごとき菊の花その比喩ひとつ抱いてねむる」
(佐藤佐太郎)
「夕暮れのゼブラゾーンをビートルズみたいに歩くたったひとりで」
(木下龍也)
「浴槽を磨いて今日がおとといやきのうのなかへ沈みゆくころ」
(大森静佳)
「羅(うすもの)の女ささめくカジノの夜 “oui, oui,, “mais, non”,, 恋も賭けるの」
(松平盟子)
「落ちてきた雨を見上げてそのままの形でふいに、唇が欲し」
(俵万智)
「卵ひとつありき恐怖(おそれ)につつまれて光冷たき小皿のなかに」
(前田夕暮)
「卵もて食卓を打つ朝の音ひそやかに我はわがいのち継ぐ」
(高野公彦)
「卵黄吸ひし孔ほの白し死はかかるやさしきひとみもてわれを視む」
(塚本邦雄)
「欄外の人物として生きてきた夏は酢蛸を召し上がれ」
(山崎方代)
「裏山の径をのぼりて木犀の香を嗅ぐころぞ秋はれわたる」
(斎藤茂吉)
「裏庭に日向ぼこする狐おり教師に銃を持てという国」
(西岡徳江)
「立てるかい 君が背負っているものを君ごと背負うこともできるよ」
(木下龍也)
「流れくる水泡のごとき虚(こ)のごときいかに花降るわれのみなかみ」
(今野寿美)
「留まらむとして紫陽花の球に触りし蝶逸れつつ月の光に上る」
(北原白秋)
「留守と言へ/こゝには誰も居らぬと言へ/五億年経つたら帰つて来る」
(高橋新吉)
「竜田姫たむくる神のあらばこそ秋の木の葉のぬさと散るらめ」
(兼覧王)
「緑濃き曼珠沙華の葉に屈まりてどこにも往かぬ人も旅人」
(伊藤一彦)
「林床の落葉や小石押しのけて節分草の芽は出るという」
(前田康子)
「涙吸うレンズをつるんと眼に入れる 泣かなくなったわたくしの眼に」
(佐伯裕子)
「冷蔵庫にほのかに明かき鶏卵の、だまされて来し一生(ひとよ)のごとし」
(岡井隆)
「冷蔵庫ひらきてみれば鶏卵は墓のしずけさもちて並べり」
(大滝和子)
「冷蔵庫内に霜ふり錐形の死の眠りもて熟るる苔桃」
(塚本邦雄)
「恋ひ恋ひて逢へる時だに愛しき言尽してよ長くと思はば」
(大伴坂上郎女)
「蓮葉のにごりに染まぬ心もてなにかは露を玉とあざむく」
(僧正遍照)
「六月は酒を注ぐや香を撒くや春にまさりて心ときめく」
(与謝野晶子)
「曼珠沙華一むら燃えて秋陽つよしそこ過ぎてゐるしづかなる径」
(木下利玄)
「鬱の字一画ごとに摘まみ抜き息吹きかけて飛ばしてみたし」
(遠藤由季)
「毬のごと打てば跳ねくる心もて幸を求めん山のかなた江」
(寺山修司)
「當方は二十五、銃器ブローカー、祕書求む。――桃色の踵の」
(塚本邦雄)
「筍の穂先はつかに出でてゐて見つけらるるまで見つからずあり」
(入部英明)
「薔薇は薔薇の悲しみのために花となり青き枝葉のかげに悩める」
(若山牧水)
「蟷螂が蟷螂を食べ春先はみどりあふれる子蟷螂がおり」
(佐藤華保理)
「騙されたとおもっていっぺん騙されて新潮文庫の紐は甘いよ」
(西村曜)
「鵞肝羹(フォワグラ)のかをりの膜にわが舌は盲(し)ひゆめかよふみちさへ絶えぬ」
(塚本邦雄)
【おまけ】「夏」を含む百人一首
「卑しきことおもひしならずたふときことおもひしならず白き夏至の日」
(葛原妙子『鷹の井戸』より)
「わたしたち夏から冬がすぐ来ても曇天を今日の服で飾って」
(柳原恵津子『水張田の季節』より)
「風鈴に指紋ありたり夏は疾く遠くなりゆく季節と思ふ」
(𠮷澤ゆう子『緑を揺らす』より)
「この夏に失ったもの 手洗いの藍の服から藍が流れる」
(岡本幸緒『ちいさな襟』より)
「ひと夏の夏百日の一日の金赤のダリア黒赤のダリア」
(朝井さとる『羽音』より)
「生徒らと読みすすめゆく『夏の花』題名はさう平凡がいい」
(本田一弘『眉月集』より)
「舌赤く染めて硝子を食べているわたしが夏に産みし生きもの」
(藤田千鶴『貿易風(トレードウインド)より)
「夏の窓 磨いてゆけばゆくほどにあなたが閉じた世界があった」
(笹川諒『水の聖歌隊』より)
「ハードルをつぎつぎ越ゆる若き脚(あし)のむかうに暗き夏のくさむら」
(柏崎驍二『四月の鷲』より)
「夏山をつぎつぎに行く雲の影どの雲というかげではなくて」
(池本一郎『樟葉』より)
「夏きざすやうに勇気はきざすのか飲酒ののちの蕎麦のつめたさ」
(大口玲子『東北』より)
「睡蓮が水面をおほふ夏の午後こんなに明るい失明がある」
(千葉優作『あるはなく』より)
「彼らは夏を逝きたり若き日の写真の顔をこの世に遺し」
(糸川雅子『ひかりの伽藍』より)
「夏青葉しげる木下をゆくときに傘打つあめの音とほざかる」
(山中律雄『淡黄』より)
「死なばまた夏にかへらむ卓上に薄氷のごとき皿並べゐつ」
(高橋淑子『うゐ』より)
「弱いもの順に腐ってゆくことの正しさ 夏はあまりにも夏」
(上坂あゆ美「生きるブーム」『短歌研究』2022.08より)
「初夏愕然として心にはわが祖國すでに無し。このおびただしき蛾」
(塚本邦雄『日本人靈歌』より)
「夏休みまだだいぶあり風を浴びてこれから出来ることのいろいろ」
(大辻󠄀隆弘『樟の窓』より)
「眠るだけ眠りなさいな夕立にあゆみを止める夏の日時計」
(萩野なつみ『遠葬』より)
「スイミングスクール通わされていた夏の道路の明るさのこと」
(鈴木ちはね『予言』より)
「夏衣の母のあゆみの衰へて来しあのころが晩年なりしか」
(古川登貴男『篠懸の木蔭』より)
「みりん甘くて泣きたくなつた銀鱈の皮をゆつくり噛む夏の夜」
(山下翔『温泉』より)
「くちぶえは背中にぬけてぼくたちにもうふらふらと夏がきたんだ」
(東直子『青卵』より)
「おとうとが春服をドラムバッグから出して夏服詰め込んでゆく」
(高橋千恵『ホタルがいるよ』より)
「桜をはり松の林に来てゐたり潮の香いまだ夏の香ならず」
(伊藤一彦『微笑の空』より)
「さきにいた熱とけんかをする熱だゆっくり夏のお粥をすする」
(山階基『風にあたる』より)
「夏の大セールで買った妹はセーター厚地のヒツジの柄の」
(椛沢知世「ノウゼンカズラ」ねむらない樹vol.8より)
「虹の余光身に浴びながら雫するタワービル群 夏の林よ」
(佐伯裕子「短歌研究」2021年10月号より)
「「夏苦しい」たった一言そう書かれたアルバム評を手に走り出す」
(盛田志保子『木曜日』より)
「僕たちのドレッシングは決まってた窓の向こうに夏の陸橋」
(穂村弘『水中翼船炎上中』より)
「もう次の芥川賞が来るらしい 夏の帰宅をくりかえしたら」
(左沢森「VとR」より)
「逆光の鴉のからだがくっきりと見えた日、君を夏空と呼ぶ」
(澤村斉美『夏鴉』より)
「まなぶたのくぼみ激しくなりし夏蝶も鳥らもさりげなくゆけ」
(百々登美子 『荒地野菊』 より)
「町をゆくすべての人は使者として夏の日暮れを音もなくゆく」
(阪森郁代 『歳月の気化』より)
「あの雲のすそをつまんで岸辺までぐいと引き寄せられないか、夏」
(加藤英彦『プレシピス』より)
「大らかに夏雲はしる野の森の泉に足を洗ひてゆきぬ」
(山川登美子「山川登美子全集・上巻」より)
「玉藻刈る敏馬を過ぎて夏草の野島の﨑に舟近づきぬ」
(柿本人麻呂 万葉集 巻三 350より)
「魂は人にむくろは我に露ながら夏野の夢のなごり碎くる」
(萩原朔太郎/初出『文庫』第23巻第6号より)
「檜の香部屋に吹きみち切出しの刃先に夏の雨ひかりたり」
(高村光太郎 『高村光太郎選集 第2巻』より)
「夏ははや生いきの労いたづき苦しむか交つがひたる蝶むなしきに舞ふ」
(遠藤麟一朗/引用は粕谷一希『二十歳にして心朽ちたり』洋泉社MC新書より)
「仰ぎ見て我が天才を疑わず天地ひれ伏せ十六の夏」
(榎本ナリコ『センチメントの季節7 二度目の夏の章』より)
「さらば夏アトランティスを見て来たと誰か電話をかけてこないか」
(久木田真紀「時間(クロノス)の矢に始めはあるか」『短歌研究』1989年9月号より)
「あんたはなあどうも甘いと言はれてる烈夏の下を通つてゐたが」
(池田はるみ『正座』より)
「あまたなる死刑と雨の影のこし平成最後の夏は終はりぬ」
(住谷眞『遁世はベンツのやうに』より)
「数寄屋橋の夏の歩道に漂ふは水牛の乳のけもののくささ」
(知花くらら『はじまりは、恋』より)
「夏草の一茎にありてしづみゐし蟷螂(かまきり)の眼の碧きこゑのす」
(前川佐重郎『彗星紀』より)
「三時草の爆ぜたるのちのさびしかる錆色の実を真夏に見おり」
(花山周子『林立』より)
「無言になり原爆資料館を出できたる生徒を夏の光に放つ」
(重藤洋子/2019年宮中歌会始の儀入選歌より)
「時計より出(い)で来て踊る人形の目線は遠き夏木立かも」
(中川佐和子『海に向く椅子』より)
「水銀の鈍きひかりに夏がゆきしまわれてゆく女のかかと」
(広坂早苗『未明の窓』より)
「喫茶より夏を見やれば木の札は「準備中」とふ面をむけをり」
(光森裕樹『鈴を産むひばり』より)
「腕時計ひかりをかへしいつのまにか半袖ばかり着てをれば初夏」
(栗原寛『Terrarium テラリウム ~僕たちは半永久のかなしさとなる~』より)
「あらくさにしんしん死んでゆける夏黄のフリスビーと毛深き地蜂」
(米川千嘉子『夏空の櫂』より)
「足裏より夏来て床に滴りしすいかの匂いまばゆい午後だ」
(天道なお『NR』より)
「春の船、それからひかり溜め込んでゆっくり出航する夏の船」
(堂園昌彦『やがて秋茄子へと到る』より)
「レスラーはシャツを破りて瞳孔をひらいてみせる夏の終わりに」
(内山晶太『窓、その他』より)
「恋愛が恥ずかしかった夏 海を見るためだけに海に出かけた」
(千葉聡『そこにある光と傷と忘れもの』より)
「逝きかけの蟬を励ますこの夏にとくに未練はないはずなのに」
(北島洋「夏の終わり」『外大短歌』第7号より)
「やがて海へ出る夏の川あかるくてわれは映されながら沿いゆく」
(寺山修司『空には本』より)
「夏なのに咲かない向日葵 泣いていた記憶ばかりが鮮明、ずっと」
(岩崎恵『手紙の森』より)
「6月の2日の朝に夏が来てあなたに会うので夏バテしそう」
(仲田有里『マヨネーズ』より)
「なにげなく摑んだ指に冷たくて手すりを夏の骨と思えり」
(服部真里子『行け広野へと』より)
「雨宿りせし駄菓子屋にインベーダーゲーム機ありき あの夏のこと」
(笹公人『念力姫』より)
「「斎藤さん」より少しだけ美しい「真夏の夜の夢の斎藤さん」」
(原詩夏至『ワルキューレ』より)
「ビル街のよぞらに雨後の月あかしむかし御油[ごゆ]より出でし夏の月」
(小島ゆかり『折からの雨』より)
「ゆびあはせ小窓つくれば三角のあはひをよぎるあの夏の雲」
(紀水章生『風のむすびめ』より)
「野菜たち官能的な蕊匂わせ生殖している夏の菜園」
(角田利隆『〈無〉の習作』より)
「きたぐにの夏空白く抉り取りグライダーわが頭上飛び越ゆ」
(月岡道晴『とりよろへ山河』より)
「真夏、還つて来たのは小さな石だつた。小石のままの母のおとうと」
(高尾文子『約束の地まで』より)
「夏帽子振るこどもらよ遺影なる伯父とことはに戦闘帽かぶる」
(栗木京子『夏のうしろ』より)
「教科書は絶対と思つてゐた夏のしづかな教師の頸太かりき」
(池谷しげみ『二百箇の柚子』より)
「2040年の夏休みぼくらは懐かしいグーグルで祝祭を呼びだした」
(フラワーしげる『ビットとデシベル』より)
「半夏生しらじら昏れて降る梅雨に母は病みこもる父と老いつつ」
(近藤芳美『近藤芳美集 第三巻』より)
「全速の自転車に脅え日日あゆむこの街に来てはじめての夏」
(島田修二『草木国土』より)
「一日が過ぎれば一日減つてゆくきみとの時間 もうすぐ夏至だ」
(永田和宏『夏・二〇一〇』より)
「夏にみる大天地(おおあめつち)はあをき皿われはこぼれて閃く雫」
(窪田空穂『まひる野』より)
「どうしても抜けぬ最後のディフェンスは塩の色した夏だとおもえ」
(正岡豊『四月の魚』より)
「夏帽のへこみやすきを膝にのせてわが放浪はバスになじみき」
(寺山修司『空には本』より)
「在りやうをわれに咎めに朱夏来たる容赦なし<蝉時雨>浴びせて」
(村木道彦『存在の夏』より)
「この口は夏の蝉よりくりかえすどんなにあなたにみにくいだろう」
(今橋愛『O脚の膝』より)
「幽霊とは、夏の夜に散る病葉(わくらば)のことです」とその街路樹の病葉が言ふ」
(松平修文『蓬(ノヤ)』より)
「ひるがほのかなたから来る風鳴りが銀の車輛となる夏の駅」
(小島ゆかり『憂春』より)
「どこへも届かぬ言葉のやうに自転車は夏の反射の中にまぎれつ」
(阪森郁代『ボーラといふ北風』より)
「初夏の陽に青みてうかぶ種痘あとわれをつくりし父母かなし」
(日高堯子『野の扉』より)
「夏の雲ふくれゆく空にんげんはこゑ出して泣くすべを持ちたり」
(都築直子『淡緑湖』より)
「熱帯の蛇展の硝子つぎつぎと指紋殖えゆく春より夏へ」
(林和清『ゆるがるれ』より)
「ながめつつながめ尽くせず夏暮るる樹樹の繁りのやどす表情」
(大塚寅彦『声』より)
「YEN再びマッチョになる日を夢みむか夏の喉(のみど)を降るバーボン」
(山田富士郎『羚羊譚』より)
「それからはただひたすらにたかなりて轟く夏の雲となりしが」
(福島泰樹『無聊庵日誌』より)
「いつさいを告げたくきみと逢ふ街に初夏の陽ざしの匂ひうづまく」
(外塚喬『喬木』より)
「このキスはすでに思い出くらくらと夏の野菜の熟れる夕ぐれ」
(伴風花『イチゴフェア』より)
「遠いドアひらけば真夏 沈みゆく思ひのためにする黙秘あり」
(澤村斉美『夏鴉』より)
「いまだ日は長きに夏至の過ぎたるを繰り返し言う追われるごとく」
(松村正直『やさしい鮫』より)
「次の夏いっしょに行きたかった場所 あした言おうとしてたひとこと」
(谷村はるか『ドームの骨の隙間の空に』より)
「カナリアの羽ぬけかはる夏となりとまり木の上にひと日黙せり」
(有沢螢『朱を奪ふ』より)
「女生徒がふたり笑えば雲よりもはるかに白い夏のセーター」
(山田恵理『秋の助動詞』より)
「足もとに影を集めて立ちつくす昏き歩哨と夏の木立は」
(楠誓英『薄明穹』より)
「ひしひしと夏空あをし煙突掃除のひとりの影ののぼりゆくとき」
(川本浩美『起伏と遠景』より)
「夏至の日の夕餉をはりぬ魚の血にほのか汚るる皿をのこして」
(鈴木美紀子『廃駅』より)
「在りやうをわれに咎めに朱夏来たる容赦なし<蝉時雨>浴びせて」
(村木道彦『存在の夏』より)
「黒人の蜂起近づく真夏かも池は電柱逆さに吊りて」
(新城貞夫『朱夏』より)
「生ビールもわれの心も「冷えてます」朱夏革命の兆しなければ」
(小泉史昭『ミラクル・ボイス』より)
<夏そのものの異称>
「夏」そのものを指す別の言葉です。
夏月【かげつ】(夏場の3カ月のこと。)
三夏【さんか】(陰暦4~6月の夏の3カ月を指す言葉。)
朱夏【しゅか】(五行説では夏を「朱」で表すことから。)
暑月【しょげつ】
この記事が参加している募集
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
