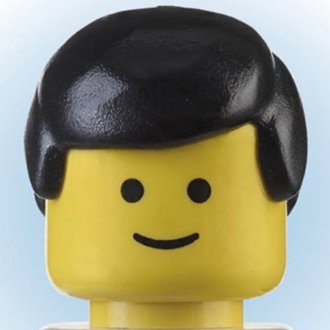2022年8月の記事一覧
アイドルは歌が下手だからダメ?—否、それでいいのだ
よく、アイドルの歌が下手だという批判をする人がいる。
昔の少年隊が踊りながら歌っていたのを引き合いに出し、
最近のアイドルは踊りもしないのに歌が下手だとの指摘がある。
確かに、多くのアイドルの歌は下手である。
だから多くのアイドルがCD音源とうり二つの口パクでテレビ番組に出ている。
多くのファンは「口パクじゃない!」と強弁するが、もはやそれは信仰の世界である。
信じたい人だけが口パクではない
「FACTFULNESS」を読んでの雑感
いまさらではあるが、かつて話題だった本である。
筆者のハンス・ロスリング氏はTEDというオンライン講義にも何度か登場している。"The best stats you've ever seen"と題した講座を行っている。開始から間もなく始まる、競馬実況のような迫真の演説には誰もが心惹かれるだろう。"And we have a completely new world..."というところで自然に拍手
本嫌いが本好きになるまで②
しかしそうであっても、自己内部の世界(=不可視の世界)を完全に言語化することはできない。
だから読み進める。こうなると読んでいる最中も先が気になって仕方がない。「こいつが何を考えるのだろう」――そればかりが気になるのである。
この「遮光」はなかなか衝撃的なエンドを迎えるのだが、何にせよ初めての読後感だった。
作品を読んでいるときに、その読書という経験が自分を他の世界にでも連れて行ってくれるような