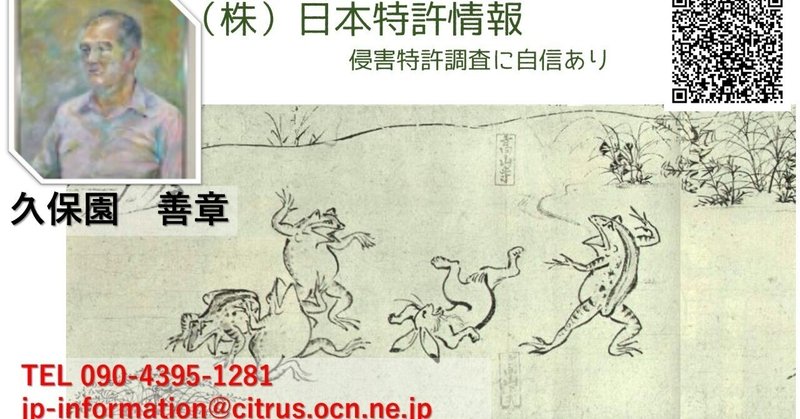
どうする特許庁! 目覚めよ審査官!! いつまで続く、散漫で、お粗末な「審査」(サーチ)による特許付与を、です。
知的財産高等裁判所により、「要旨変更」と断定され、「権利無効」とされたものの28件目です。
https://drive.google.com/file/d/1juJuxOx6XE707F0_a7aNjViDDxJLs699/view?usp=drive_link
特許権者である原告の古河電気工業㈱は、自分が保有する特許第2,898,643号(量子井戸半導体レーザ素子)について、その特許の「有効性」を検証したか不明です。
「有効性」とは、例えばその特許についての「無効資料調査」等を行うことで、たとえ利害関係者などの第三者からの「無効審判」を起こされても、その特許は盤石であると確信することです。
それにも拘らず、特許庁より与えられた特許を有効と信じて、日本オプネクスト㈱を特許侵害している、と提訴しました。
先ず、東京地方裁判所により、「本件発明は,旧特許法29条1項3号に該当するものとして,特許無効審判により無効にされるべきものと認められる。よって,特許法104条の3第1項の規定により,原告は,被告に対し,本件特許権につき権利を行使することはできない。」とされました。
そして、知的財産高等裁判所は、「特許法29条1項3号の適用により本件特許は特許無効審判により無効とされるべきもので本件請求は理由がないとした原判決は,無効とされるべきものとする点で,結論において相当であるから,控訴人のなした本件控は,その余について判断するまでもなく,理由がない。」とし、東京地方裁判所所の判断を支持し、結局、控訴人は敗訴し、損害賠償金を得ることができませんでした。
その中身は、「平成9年8月11日付けでなされた本件第2回補正は平成5年法律第26号による改正前の特許法40条にいう「要旨の変更」に該当するから本件特許の出願日は補正時たる平成9年8月11日まで繰り下がり,平成2年5月18になされた本件公開公報により新規性を失ったから,・・・」とあります。
その根拠は「本件発明と本件公開公報に記載された発明とは,「・・・・・」の範囲で共通する(この範囲については,本件発明が本件当初明細書に記載された発明に含まれる。)と認められる。すると,本件発明は,旧特許法29条1項3号に該当するものとして,特許無効審判により無効にされるべきものと認められる。」としています。
「特許法29条1項3号」とは、「特許出願前に日本国内又は外国において、頒布された刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となつた発明」です。
そして、結論は「よって,特許法104条の3第1項の規定により,原告は,被告に対し,本件特許権につき権利を行使することはできない。」となりました。
なお、特許庁の審査と審判における情報が非開示であるため、その内容は知る由もありません。
特許庁の「出願情報」によれば、出願人は、審判にて「特許査定」を勝ち取り特許権を得ました。
しかしながら、特許権利者は東京地方裁判所と知的財産高等裁判所において、上記のように敗訴しました。
本件の根本原因は、本件特許出願は「特許法29条1項3号」に該当するものとのことです。
従って、本来なら、古河電気工業㈱の出願に対して、特許庁は特許を与えるべきでなかったと考えます。
特許庁の審判官のズサンな判断に基づいての、特許付与は許されません。
「行政」(特許庁)としては、「司法」(裁判所)により誤りを指摘されたことを謙虚に反省し、その誤りを正すことを心掛けるべきです。
ここで、本件特許公開の「出願情報」のうち「FI」と「Fターム」を、本エクセル資料の2シート目以降に挙げておきました。
( Google Translation )
What should the Patent Office do? Wake up, examiner! !
How long will patents be granted based on messy and poor "examination" (search)?
This is the 28th case in which the Intellectual Property High Court has determined that the subject matter has been changed and the rights have been invalidated.
It is unclear whether the plaintiff, Furukawa Electric Co., Ltd., which is the patentee, has verified the "validity" of its patent No. 2,898,643 (quantum well semiconductor laser device).
``Validity'' means, for example, that by conducting an ``invalidation document search'' on a patent, even if an ``invalidation trial'' is filed by a third party such as an interested party, the patent is solid. It's about being sure.
Despite this, the company believed that the patent granted by the Japan Patent Office was valid and filed a lawsuit against Nippon Opnext Co., Ltd., accusing it of infringing the patent.
First, the Tokyo District Court ruled that ``This invention is recognized as falling under Article 29, Paragraph 1, Item 3 of the old Patent Act and should be invalidated in a patent invalidation trial.
Pursuant to the provisions of paragraph 1, the plaintiff cannot enforce the patent right against the defendant.''
The Intellectual Property High Court held that, ``By applying Article 29, Paragraph 1, Item 3 of the Patent Act, the original judgment that the patent should be invalidated by a patent invalidation trial and that the claim is groundless is invalidated. ``The appellant's submission is without merit, as there is no need to make a judgment on the rest.'', upholding the judgment of the Tokyo District Court.
In the end, the appellant lost the case and was unable to obtain any damages.
The content is that ``The second amendment in this case made on August 11, 1997 corresponds to a ``change in the gist'' of Article 40 of the Patent Act before the amendment by Act No. 26 of 1993, so the patent in question is The filing date of the patent was pushed back to August 11, 1997 at the time of the amendment, and the patent lost its novelty due to the publication of the patent on May 18, 1990.
The basis for this is that ``The present invention and the invention described in the present publication are common within the scope of ``...'' (with respect to this range, the present invention is included in the invention described in the original specification ).
Therefore, it is recognized that the invention falls under Article 29, Paragraph 1, Item 3 of the old Patent Act and should be invalidated by a patent invalidation trial. ”.
"Article 29, Paragraph 1, Item 3 of the Patent Act" refers to "inventions that have been described in publications distributed in Japan or abroad or that have become available to the public through telecommunications lines in Japan or abroad before the patent application is filed."
The conclusion was, ``Therefore, pursuant to the provisions of Article 104-3, Paragraph 1 of the Patent Act, the plaintiff cannot enforce the patent right against the defendant.''
Please note that there is no way to know the contents of the examinations and trials conducted by the Patent Office, as the information is not disclosed.
According to the Japan Patent Office's "Application Information," the applicant won a "grant of patent" in the trial and obtained the patent right.
However, the patentee lost the case at the Tokyo District Court and the Intellectual Property High Court as described above.
The root cause of this case is that the patent application in question falls under "Article 29, Paragraph 1, Item 3 of the Patent Act."
Therefore, we believe that originally the Patent Office should not have granted a patent to Furukawa Electric Co., Ltd.'s application.
It is not permissible to grant a patent based on the sloppy judgment of a patent office examiner.
The ``administration'' (patent office) should humbly reflect on the fact that the ``judiciary'' (courts) pointed out an error, and strive to correct the error.
Here, the "FI" and "F-term" of the "application information" of the patent publication are listed in the second sheet and subsequent sheets of this Excel document.
(Google 翻译)
专利局应该做什么? 醒醒吧,考官! !
基于混乱且糟糕的“审查”(检索),专利会被授予多长时间?
这是知识产权高等法院认定标的物变更、权利无效的第28起案件。
目前尚不清楚作为专利权人的原告古河电气工业株式会社是否验证了其第2,898,643号专利(量子阱半导体激光装置)的“有效性”。
“有效性”是指,例如,通过对专利进行“无效宣告文件检索”,即使利害关系人等第三方提出“无效宣告审判”,该专利也是可靠的.这是为了确定。
尽管如此,该公司仍认为日本专利局授予的专利有效,并对Nippon Opnext Co., Ltd.提起诉讼,指控其侵犯该专利。
首先,东京地方法院裁定:“本发明被认定属于旧专利法第29条第1款第3项的范围,应在专利无效审判中宣告该发明无效。
根据第1款的规定,原告不能对被告强制执行专利权。
” 知识产权高等法院认为:“适用专利法第二十九条第一项第三项规定,经专利无效宣告审理应宣告该专利无效且权利要求无根据的原判决无效。
”上诉人的主张没有法律依据,其余部分无需作出判决。”,维持东京地方法院的判决。
最终上诉人败诉,也无法获得任何损害赔偿。
其内容是“本案1997年8月11日的第二次修改,相当于1993年第26号法修改前的专利法第40条的‘主旨变更’”,因此该专利问题在于,该专利的申请日在修改时被推迟到了1997年8月11日,并且该专利因1990年5月18日公布的专利而失去了新颖性。
其依据是“本发明和本公开中描述的发明在‘……’的范围内是共同的(就该范围而言,本发明包括在本公开中描述的发明中)原始规格)。
因此,认定该发明属于旧专利法第二十九条第一项第三项规定的情形,应当通过专利无效审理宣告该发明无效。 ”。
“专利法第29条第1项第3项”是指“在提交专利申请之前已在日本或国外发行的出版物中描述的或通过日本或国外的电信线路向公众公开的发明” ”。
结论是:“故依专利法第一百零四条之三第一项之规定,原告不能向被告主张专利权。” 请注意,由于信息未公开,因此无法了解专利局进行的审查和审判的内容。
根据日本特许厅的《申请信息》,申请人在审理中获得了“专利授权”,获得了专利权。
然而,如上所述,专利权人在东京地方法院和知识产权高等法院败诉。
本案的根本原因是涉案专利申请属于《专利法第二十九条第一项第三项规定》。
因此,我们认为专利局原本不应对古河电气工业株式会社的申请授予专利权。
不允许根据专利局审查员的草率判断来授予专利。
“行政部门”(专利局)应该虚心反省“司法部门”(法院)指出的错误,并努力纠正错误。
这里,该专利公开的“申请信息”的“FI”和“F项”列在该Excel文档的第二页和后续页中。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
