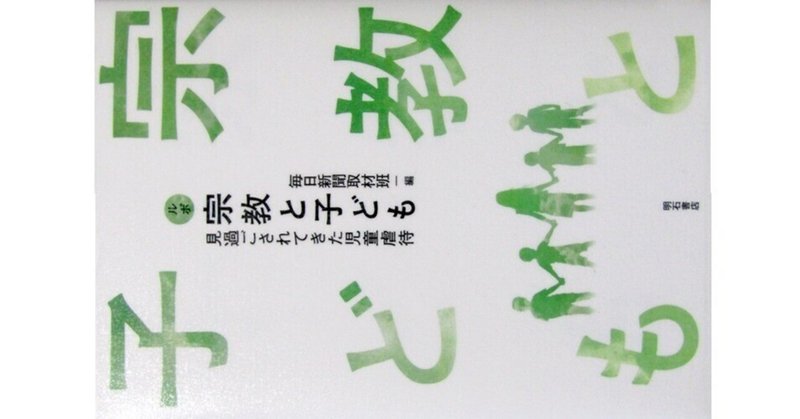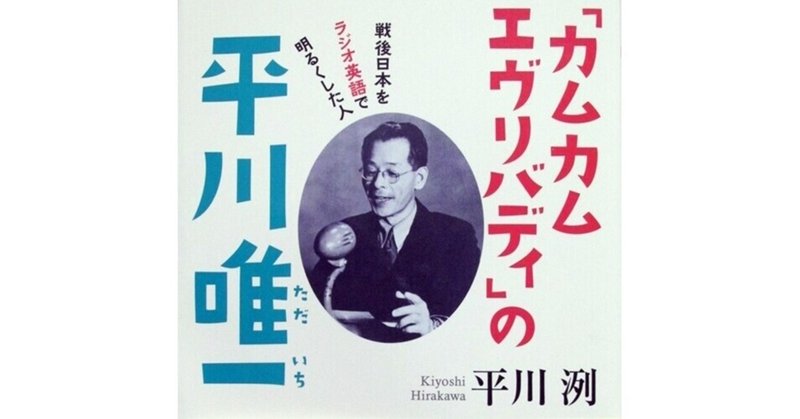- 運営しているクリエイター
#信仰
『生かされて。』(イマキュレー・イリバギザ スティーヴ・アーウィン 堤江実訳)
私は偶々続編としての『ゆるしへの道』から読んだ。そこでは、虐殺を乗り越えた話も書かれてあったが、少し端折った形で、その後の国連での働きの過程のほうに重きが置かれていた。そこでも嫌なことがあり、「ゆるし」というものが突きつけられたのだ。
本書は、いわば本編である。助け出されるまでの過程が、一つひとつ丁寧に描かれる。
これは、1994年、アフリカのルワンダで起こった虐殺事件の生き証人の報告であ