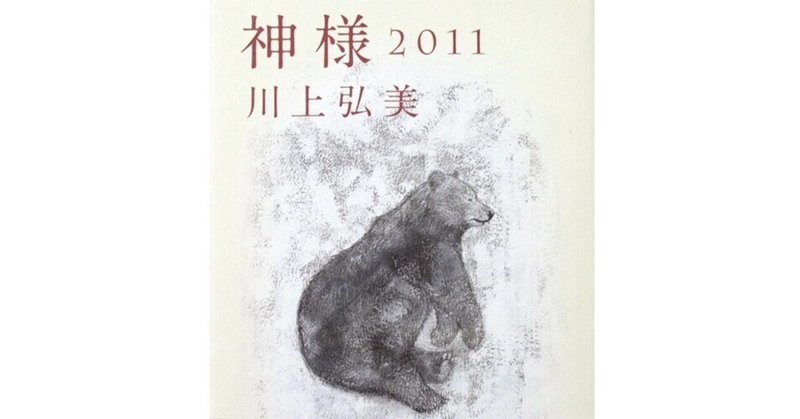ひとのこころ、見つめてみます。自分のこころから、誰かのこころへ。こころからこころへ伝わるものがあり、こころにあるものが、その人をつくり、世界をつくる。そんな素朴な思いに胸を躍らせ…
- 運営しているクリエイター
2022年3月の記事一覧
「私たちと一緒に その先の光を見に行こう。」
コロナ禍での受験は、まことに歯を食いしばるような営みだった。もともと受験勉強というものはストイックなイメージがあるが、束縛の大きさから考えても、全くゆとりのない生活を強いられていた受験生である。
兵庫県立大学の広報チームが教えてくれた。受験生へのエールである。最初の言葉は、そこで呼びかけられたものである。
https://www.u-hyogo.ac.jp/message2021/index